
「わたしはできる」と思うこと - バンデューラ
前回「職業選択は、自己概念の実現の手段を選ぶということ」というスーパーの理論を紹介しました。
「正しい選択をすれば肯定的自己概念が持てる。肯定的自己概念があれば正しい選択ができる。」という。セットらしいことは分かるけどニワトリタマゴですよね。何が”正しい選択”になるかの未来の結果が分からないから私たちは悩むわけなので、まずは"肯定的自己概念"を切り口に考えます。
肯定的自己概念=①自己効力感+②自己肯定感
肯定的自己概念に従うというのは、言い換えれば「自分で良いと思える心と直観に従う」ということ。シンプルなようですが、実は”勇気”が必要な行為です。私たちは、外部からのノイズで簡単に自信が揺らぐので。
「肯定的自己概念」は、より直観的な言葉で「自尊心」と言い換えることもできます。その自尊心は「自己効力感(Self-efficacy)」と「自己肯定感(Self-esteem)」に要素分解することができます。
①自己効力感(Self-efficacy)は、自分の能力に対する自信。「わたしは”できる”、だから素晴らしい」。直截でわかりやすい。
②自己肯定感(Self-esteem)は、「わたしは"できてもできなくても”素晴らしい」。いわば、命への自信。こちらも大事。
両方あっての自尊心。今回はまず「自己効力感」に踏み込みます。
バンデューラの社会学習理論
キャリコン学者陣の中で、一番最初(1950年代)にその言葉をハイライトしたのは、カナダ生まれ・スタンフォード大学教授のアルバート・バンデューラ博士。
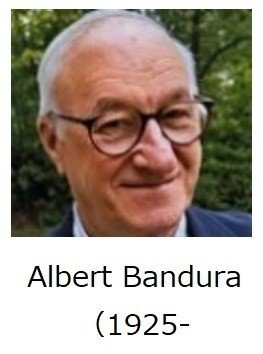
バンデューラは「自分はうまくやれそうだと思うことが人の行動を変える」そして、「モデリング(観察)学習によってその自己効力感を鍛える」という、社会的学習理論を展開しました。
1986年の論文で「社会的認知理論」(Social Cognitive Theory)と改名されていますが、キャリコン養成講座の教科書も試験も旧名「社会的学習理論」(Social Learning Theory)が使われています。
確かに「自分は、できない…」と肩を落とすことは、未来に対して百害あって一利なし。生きていればそういう日もあるかもしれないけれど、無力感に苛まれ続けていると、何かを「やってみよう」という力を失います。
疑問符つきでも「できるかも?」と思えることが、人の行動を促し、チャンスが開けるのです。
バンデューラが曰く、自己効力感をあげる方法は、主に4つ。
1.遂行行動の達成:実際に成功体験を積むこと
2.代理経験:出来ている人の観察をすること(モデリング)
3.言語的説得:「君はできる!」という言語的励ましを得ること
4.情動的喚起:リラックスして「できそう」な気になること
網羅的で納得感あります。キャリコン試験では特に#2のモデリングについてその詳細が出題される傾向が強いようですが、私は子育てのためにこの四項目を頭に入れておきたいです。
クルンボルツの理論との違い
なお、以前紹介したクルンボルツの「機会遭遇理論(Chance Encounter Theory)」も、行動主義・社会的学習理論の系譜で、自己効用感を重視する論旨です。また、予想不可能な偶然とのつきあいかたを説いている点も似ています。試験ではクルンボルツのほうが頻出ですが、先に「自己効用感」を取り上げたのは3歳年上のバンデューラ。クルンボルツは、その影響を受けて、計画された偶発性理論を展開したのです。
両者の違いは、バンデューラのそれが「偶然は予測されずに起こるが、一旦起こってしまえば予定されていたことと変わりない。それは通常の意思決定の連鎖の中に組み込まれ、人間の選択行動に影響を与える」とフラットな印象なのに対して、
クルンボルツは「キャリアは予想不可能な偶然で左右されるから、目標がセットできなくてもどんどん行動して行こう!」と積極的に、「偶然(まだ見ぬ不確実性)を恐れるな」という方向に踏み込んだ感じですね。
モデリング理論は心理学を超えて大活躍
バンデューラの自己効用感やモデリングに関する理論は、実は、心理学の領域にとどまらず、社会学や教育学にも広範な影響を及ぼしています。2002年の「世に最も影響を及ぼした心理学者」ランキングで、スキナー、ピアジェ、フロイトに続いて第4位に輝いているんです。凄い!しかもまだご存命!!(御年94歳@2020年現在)…握手したーい。
世間には本当にいろんな自己啓発セミナーやコーチング協会がありますが、それらのハウツーの根本を辿ると、だいたいバンデューラがいます。
向上心ゆえのセミナー・ジプシーで、溢れるポジティブに飽きた人、アゲアゲされることに疲れた人は、一旦立ち止まって、バンデューラ博士の書籍を一度読んでみると何か気付きがあるかもしれないよ…と、お勧めできそうな本を調べてみたら、どれもお高くて目玉が飛び出ました…(英語版ならResearch Gate等で原文PDFが無料ダウンロードできます)
とにかく、バンデューラの整理を足掛かりに、「①自己効力感」については、その鍛え方のハウツーが花咲いているんですね。
でも、一筋縄ではいかないのが「肯定的自己概念(自尊心)」。
次回はそのもう一つの構成要素、「②自己肯定感」について、フランクルの論旨を紹介しながらわたしなりにアプローチを試みます。
どなたさまも、ハッピーなライフ・キャリアを。
