
読書感想譚📚📚(本の「使い方」)

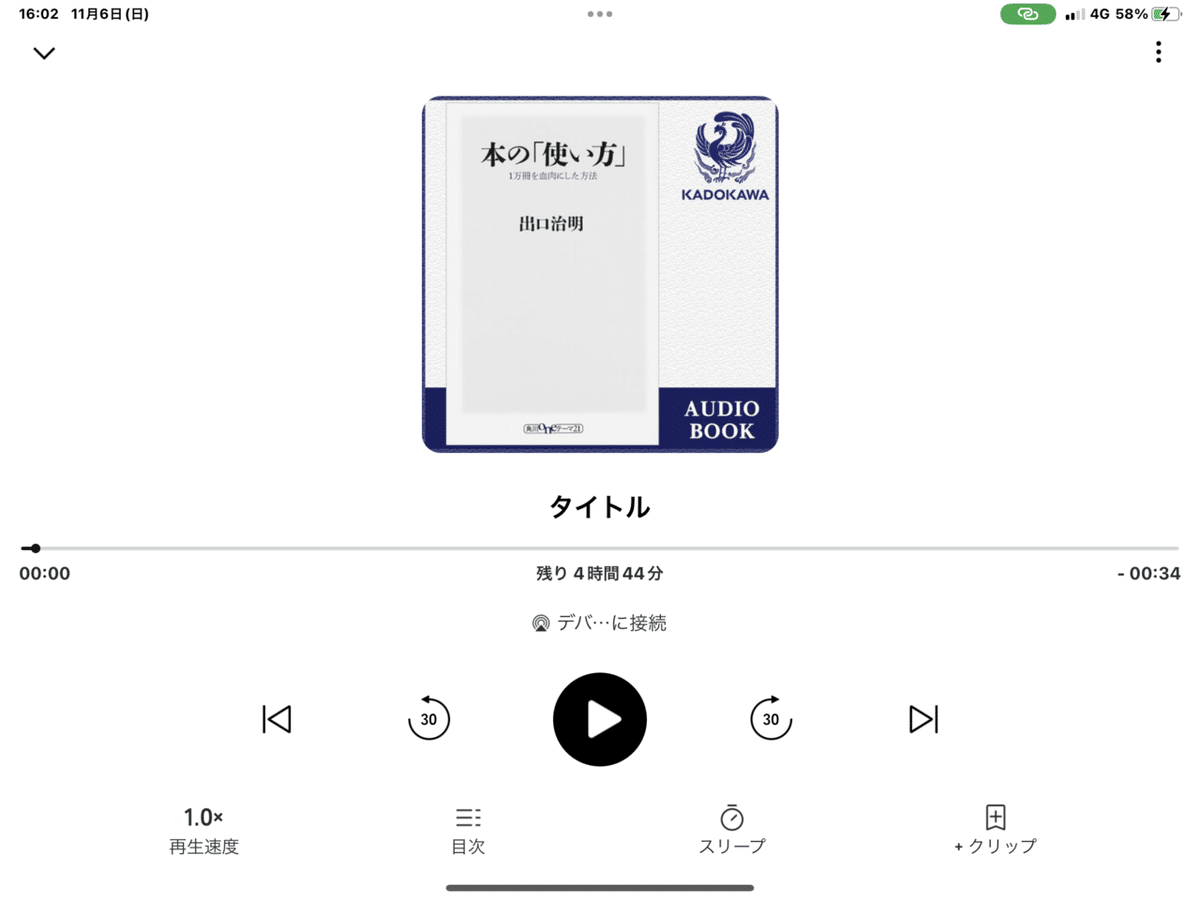
著者 出口 治明、237ページ・角川oneテーマ21(2014/09/11)刊。
(加筆の新版:256ページ、KADOKAWA(2019/06/21)刊)
オーディオブック版:4時間43分、朗読 白川 周作。
・参考リンク(著者・朗読)・
✏️今回、「世界システム理論」本編をしたかったのだけれど、『正義論』には及ばないまでも、あんなゴツい本2冊も持ち歩けませ〜ん。💦
(蔵書予定の本なので痛むのやだし⋯)
という訳で、今回のテーマはズバリ「本」です。
独学ノート📝
『本の使い方━1万冊を血肉にした方法』
出口 治明 著・角川oneテーマ
はじめに
目次
1章 本とは「何か」━━教養について考える
1「教養」と「教育」の違い
・ 坂本龍一はなぜ、自分のことを「才能がない」と言い切るのか
・ 教育+教養=より良い生活
・「知」は、それだけで力になる
・ 大切なのは「読書量」よりも、精神のあり方
2 教養を得るための効率的なツール
・教養を身に付けるための「三智」
・「世界を正しく理解する」ために
・ 本が持つ5つの優位性
① 何百年も読み継がれたもの(古典)は当たりはずれが少ない
② コストと時間がかからない
③ 場所を選ばず、どこでも情報が手に入る
④ 時間軸と空間軸が圧倒的に広くて深い
⑤ 実体験にも勝るイメージが得られる
・ 人生の5割は、本から学ぶ
3 どのジャンルで学んだらいいか
・ 好きなものから学べばいい
・ 仕事で必要な知識は、無条件で勉強する
4 リベラルアーツの必要性
・ 日本では、教養を学ぶ環境が整っていない
・ 日本のリーダーは、世界的に見ると教養が浅い
・「青田買い」が大学生をスポイルしている
・ 僕が大企業病にかからなかった理由
5 本、新聞、インターネットの違い
・ 新聞は、価値の序列を伝えるツール
・ インターネットは、速報性と検索性に優れたツール
・ 本は、全体的な知識をコンパクトにまとめたツール
・ 新聞、インターネット、本を、特性ごとに使い分ける
6 本を読まない人が増えると、どんな影響があるのか
・ 大学生の活字離れを防ぐ方法
・ 教養なき社会は、政治と経済を不安定にする
・ 不当広告に騙されてはいけない
2章 本を「選ぶ」━━「おもしろうそうな本」という鉄則
1 未知の分野の勉強のしかた
・ 新しい知識を整合的に学ぶには、7~8冊の本が必要
・ 新しい知識を得るときは、「厚い本」を最初に読んでみる
・ 学んだ知識を実際に試してみる
・ 自分で咀嚼して腹落ちしたことが教養になる
・ マイルールを決めたら、あとは淡々と従う
2 どうして古典が難しく感じるのか
・ 古典を読んでわからないのは、自分がアホだから
3 古典を読む意義
・古典が「優れている」理由
① 時代を超えて残ったものは、無条件に正しい
② 人間の基本的、普遍的な喜怒哀楽が学べる
③ ケーススタディとして勉強になる
④ 自分の頭で考える力を鍛錬できる
4 古典の選び方
・『(よりぬき)サザエさん』や『いじわるばあさん』も立派な古典
・ 古典を読み慣れていない人は「薄い本」から読む
・ 解説書よりも「原典」を選ぶ
5 現代の本の選び方
・ 現代の本を選ぶときのマイルール
① 興味のあるジャンルの本を選ぶ
②「目に飛び込んだ来た本」を手に取る
③ 立ち読みをして、「最新の10ページ」で決める
④ 新聞3誌の「書評欄」を見て、ムラムラした本を選ぶ
⑤ 基本的に「作者」は気にしない
⑥「SNS」を使って、人に聞く方法もあるある
⑦「ベストセラー本」は読まない
6 図書館を活用する
・ 読みたい本は、図書館にリクエストする
7 ラーニング・コモンズとして機能するAPUのライブラリー
・ 利用者同士が活発に学び合える図書館
・ APUのライブラリーは、人と出会い、交流ための場
8 本の薦め方
・ 本が好きか、長編でも平気か、どの分野が好きか
3章 本と「向き合う」━━1行たりとも読み飛ばさない
1 読書の作法
・ ネクタイを締め、正座をするぐらいの気持ちで本を読む
・ 歯を磨くように習慣化する
2 本は、人
・ 読書は、著者との真剣勝負
・ 線を引いたり、付箋を貼ったりしない
3 歴史書の読み方
・ ストーリーで覚えると、忘れにくい
・ 歴史書は、「同時代を扱った本」を複数冊読む
4 速読より「熟読」
・ 本は、素直に頭から読む
・ 目次や見出しを拾っても、本を読んだことにはならない
・ たくさん読んでも、何も残らなければ意味がない
・ 本は、食べるように読む
5 ビジネス書との距離の取り方
・ 成功体験に、どれほどの意味があるのか?
①ビジネス書は、後出しジャンケンである
② ビジネス書は、抽象化されすぎている
・ ビジネス書にも良書はある
4章 本を「使う」━━著者に左右される人、されない人
1 数字・ファクト(事実)・ロジック(論理)
・ 思い込みは捨て、客観的に判断する
・ 本の内容に左右される人、されない人
・ 自分と著者の考えが違うとき
2 本に即効性を求めない
・即効性を謳う本は、疑わしい
3 本の再読
・ 大人になるとは、可能性を捨てること
・ 年を取れば、人生への認識が変化する
4 考えるとは、言語化すること
・ 人間は、言語化する動物である
・ アウトプットするから、インプットされる
・ 母国語で考える
5 目的別のお薦め本
・「新社会人」の心構えについて考えるための本
(20代ビジネスパーソン向け)
・「人間と社会」についてさらに掘り下げて考えるための本
(30代ビジネスパーソン向け)
・「リーダー」について考えるための本
(40代ビジネスパーソン向け)
・「老いや死」について考えるための本
(50代以降のビジネスパーソン向け)
・「女性の生き方」について考えるための本
・「恋愛」について考えるための本
・「子育て」について考えるための本
・「子ども」に読ませたい本(読んで聞かせたい本)
・「心を落ち着けたい」ときに読む本
・「人間の原始の感情」について考えるための本
5章 本を「愛する」━━自分の滋養、他者への架け橋
1 本との出会い
・どうして太陽は落ちてこないのか
2 小学生時代
・図書館にあった文学全集を読破
3 中学生時代
・戦記物に興味を持つ
4 高校生時代
・長編小説、大河小説を読みふける
5 大学生時代
・マルクスを知らずに、恥をかく
・高橋和己と高坂正堯
・宗教、中国古典、生物学、都市論など、あらゆるジャンルを乱読
6 社会人時代
・歴史は総合科学。通説とは異なる
・現代世界のしくみを知る名著
・自伝・伝記の最高傑作
・キリスト教は、おもしろい
7 読書が与えてくれるもの
・皇后陛下の『橋をかける』は、世界最高の読書論
おわりに
編集後記
本書内での紹介書籍一覧
・参考リンク・
✏️あとがき(独学ノート📝)
本書2章で原作漫画『サザエさん』と『いじわるばあさん』が出てくるが、著者 出口氏は、ジャンルとしての「漫画(マンガ)」を否定はしていない。
自身も小学生の頃に少年サンデーとマガジンを読んでいたとし、
『基礎的な教養を身につけた上で読む分には良いだろう』
とのこと、うーむ耳が⋯。😅
私自身は19~20歳ごろに一端ジャンルとしての「漫画(マンガ)」を半ば卒業して、小説・ベストセラー本・テクノスリラーなどに夢中になり、20代後半━諸事情でジャンルとしての「漫画(マンガ)」に戻ってきた。(1番の理由は懐事情)
本邦🇯🇵では、全年齢で「本離れ」が嘆かれているが、高齢化だけでなく、前述の私の事情と似た理由じゃないのかなぁ⋯と。(ボソッ
参考リンク)
~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・
−おまけ(本の使い方:番外編)−
個人的にとても気になった、「本の使い方」番外編。
◯1位🥇「六法全書」を投げる
👆実際に事件もおきてます、「本」を人に投げるのはやめよう。😅
◯2位🥈「本でドミノチャレンジ」賛否両論
👆あゝ私の思い出の本(寄贈した本)が~、気持ちはわかります。💦
3位🥉「本棚」倒壊による圧死事件
👆これがまったく他人事ではなく、本📚の収納スペースとともに一大関心事。
実際に以前の漫画メイン本棚が地震により倒れて埋もれて目が覚めた。
その後、なんやかんやで漫画卒して新しい本棚新設したけど、最初は辞書・事典系を中心に50冊ほどの蔵書数で、あとは電子書籍にしようと考えていた。🤔
本好きのみなさんもくれぐれも地震対策は万全に。⛑<ご安全に〜
追記(2022/11/08)
どこに書こうか迷った挙句、テーマ的にもここが相応しかろうで追記として。
某思想家氏のキレ動画が拡散されているけど、個人的には『だから、「動画」はや』なのと。😓
20世紀は映像の世紀といわれるように、「映像」は前世紀の最大の発明かも知れない⋯が、現在私はゲーム卒・テレ卒した。
マネタイズの観点では、「映像」はもの凄く“文字〟の何十倍もの情報量があるのは確かだ。
テレ卒はしたが、「映画」は未だに観るし円盤も購入している。
どちらも一長一短があり、優劣をつけるものではないのだろうが、あのキレ動画を見て彼の書籍(電子書籍含む)を一切合切処分してよかった━と思う。🤔
本の内容は素晴らしさは、著者の人柄を保証するものではない━という無名の人の格言が胸に染み入る。
もう彼は好きに生きればいいと思うけど、「映像」の世界で生きるつもりの人は肝に銘じていてほしい、なぜテレビ界📺をいわゆる芸人さん達が制したのかを。
そのうち、「文字と映像(仮)」をテーマにして感想譚やりたいなぁ⋯と。🔚
追記(2022/11/08)
以下の記事👇によれば、「映像」は文字の5000倍の情報量だそうです。💦(映像作品鑑賞後、えらく疲れる訳だ)
よく巨匠の大作(いわゆる鈍器本)を過去の偉人の引用や抽象的表現で水増しされてt、あまり中身がない━という批判があるが、その意味では「映像」作品は書籍の比ではなく、無駄な(関係薄い)情報がメインの娯楽作品だ━ということも言えてしまう。
やはり一度「文字と映像」編はやらないとなあ。(書籍探さないと)🧐
