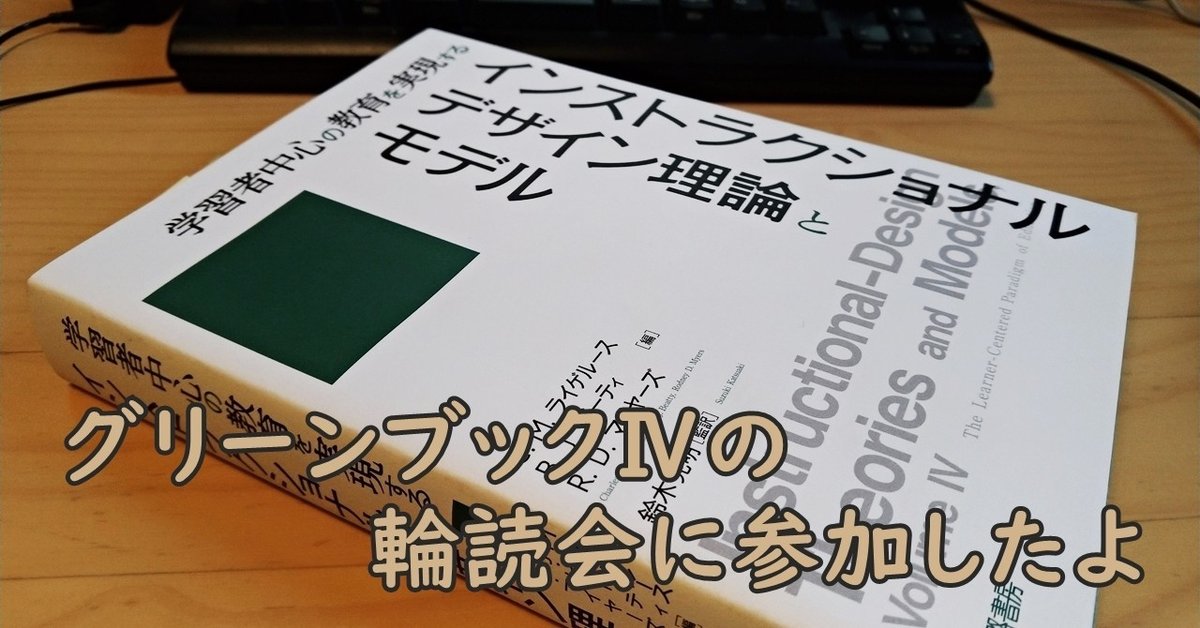
輪読会 書籍「インストラクショナルデザイ理論とモデル」第1章 後半
前回は、1章の基礎理論として取り上げられている
認知主義
構成主義
人間中心主義
や達成基盤型インストラクションと成果基盤型の違い
などを取り上げてつれづれと記載しました。
今回は第1章の後半です。
輪読会の対象書籍です。
後半では、インストラクショナルデザインでは、太刀打ちできない領域もあるよねという話題もあがりました。
キーワードとしては、ホーリスティク vs マスタリーといった事や、ブルームの完全習得批判(全人的・総合的な経験学習への道のり)
以下のような書籍の紹介もなされました。
1.達成度基盤型のインストラクション
経験学習に関しては、統合、省察(リフレクション)がキーワードとして出てきました。
IDが出てきた背景(操作や決められた動作を、いかに効率的に効果的に身に着けさせるか)や文化 と 儒教的で年長者を敬う文化的側面の異なりも話題にあがりました。
日本のようなハイコンテクスト文化では、学習者に空気をよませることを暗に押したり、師弟文化もあったりする。
日本は精神的なことで語られる事がある。欧米では理論的なアプローチがある。例えばコーチングなどはよい例で、日本的コーチは、大声で指示を出す。欧米ではメソッドとして体系化され、対象者に寄り添い語りかけ、相手に内在する思いを表層化させるアプローチ方法が示されている。
インストラクショナルデザインは万能ではなく、使い方を間違えたり、適用する箇所・分野を間違えないようにしなくてはならない。
学校寄りの視点かビジネス寄りの視点かで考え方も異なってくる。
2.課題中心型のインストラクション
足場かけをして、対象者を上手く導き(教えすぎず上手く導き)を行うのが PBL との違い。
自己調整学習ではあるが、講師側はファシリテーターやメンターの役割を担う。今までのようなテーチング中心ではない。そのため、講師には、ジャストインタイムでフィードバック(対象者がうまく進めているのか、なにか直さなければことは何か)することが求められる。
講師からのフィードバックがスキャフォールディングになる。内発的動機づけにもつながる。
フィードバックは、タイミングと頻度を十分に考慮する必要がある。
ジャストインタイムでフィードバックし、介入しすぎない。
今回もつれずれメモ的に書きました。
次回は2章を取り上げます
いいなと思ったら応援しよう!

