
グリーン・デイのCGの風船(前編)
私が今文章を書いているこのnoteというサイトには「応募する」というコーナーがあり、そこでは一般者からの投稿による、何らかのお題を元にしたエッセイが随時募集されている。3月7日現在だと「♯このお店が好きなわけ」「♯ハマった沼を語らせて」、等…
その中に「♯どこでも住めるとしたら」というお題を見つけた。大企業が運営するライフスタイルメディアとnoteが合同で開催した投稿コンテストであり、"居住区"という概念において、物理的・経済的な制約を度外視した生活を送れるとすれば何ができるのか、について書かれた文章を大勢の人達から集い「自分にとって心地よい、街やコミュニティとの関わり方」等を模索していく試みらしい。見事グランプリに選出されると、なんと10万円分のギフトカードが貰えるそうだ。これはもうやるしかない。とにかく10万円だ。コミュニティ云々については適当な美辞麗句を連ねればいい。そもそも、お互いの信頼関係に基づいて既存のコミュニティと心地よく関わりたいと思うようなまともな人間は、わざわざnoteに長文とか書かないだろう。そんなもん書く暇があったら黙ってコミュニティと関わってるよ。これは、大して何にも関わって無い、どこに住んでもこうならざるを得なかった地域の奇人達が手製の文章を持ち寄って10万円を奪い合うネット上の熱い祭りなのだ。下がれ。その10万円、私が貰う。
しかし一つ問題が有る。締切が3月5日までなのだ。もう終わっていた。
私は考えを改めた。本来、この様な地域社会を活性化させる為の催しは、その共同体を構成している各々が自発的に参加すべきであり、その際如何なるリターンが発生するのかをあさましく訝しむ等もっての他であると。
以下に書く文章は「♯どこでも住めるとしたら」を私なりに考えた、グリーン・デイのメジャー4枚目のアルバム、それは「アメリカに住んでいる事」をテーマにした「アメリカン・イディオット」の一つ前の作品でもある、「ウォーニング」についてのエッセイになる。もしも、この文章が読まれる事で、どなたかとコミュニティとの関わり方が活性化するのであれば、それに勝る喜びはない。

先日、講談社選書メチエから山川偉也の「パルメニデス 錯乱の女神の頭上を越えて」が刊行された。紀元前5世紀に存在していた哲学者についての本だ。だが、私がこの本に関して書ける事は現時点で何も無い。何故なら内容が難しくて数回読んだだけでは理解できないからだ。しかし、私がこの本を手に取るきっかけになった同氏の「ゼノン 四つの逆理 アキレスは何故亀に追いつけないか」(講談社学術文庫、1996年刊行、2017年に復刊)についてであれば、稚拙ながら書ける事がある。
ゼノンはやはり紀元前5世紀の哲学者であり、パルメニデスの弟子であった。「ゼノン 四つの逆理〜」は、アリストテレスの「自然学」第六巻第九章に書き残されている「解こうとする人々を困惑させる、運動に関するゼノンの四つの議論」、並びにゼノン自らが綴ったとされる文を含む「断片一、二、三」、それらを読み解く事で、ゼノンが一体何を我々に伝えようとしていたのかを考察した本だ。
「四つの議論(逆理)」のうちの一つは、同書の副題から察せられる通り、「アキレスと亀」として後世に伝えられる様になったものである。「第二逆理『アキレス』」:足の遅いAが走っており、その後ろをAより足の速いBが走りながらAを追いかけている。そして、「Aがかつて走っていた地点(a)」にBが辿り着いた時、Aはそこよりはいくらか先んじた地点(a')を走っている。Bがa'に到達した時、Aはまたそこよりかはいくらか先(a'')を走っている。この事は無限に繰り返される為、BがAに追い付く事は決して無い。

また第三逆理の『矢』は「飛んでいる矢は、その瞬間瞬間に矢自体がある地点と等しい場所において静止している。なので飛んでいる矢は動いていない」というものだ。残り二つの逆理も、現代の私達が共有する運動に対しての概念に根底から揺さぶりをかけるものである。だが、いかんせん紀元前五世紀という古い時代に立てられ、かつ有名なこれらのパラドックスは、解決法もまた広く知れ渡っている。これら逆理のどの点が現代常識に反し、どこを矯正すれば正しく見えるのか、それについて書かれた記事は現在ネット上を検索するだけでも数多く見付かる事だろう。しかし、この「ゼノン 四つの逆理」は、「これらの逆理は何処が間違っているのか」についての本ではない。「これらの逆理に論理的な破綻が無いとすれば、その事は何を意味するのか」について書かれている。
ゼノンの師であるパルメニデスは「万物は一である」と考えた。全ての物は「一」であり「多」として分ける事は出来ないのだと。しかし、当時のギリシアにおいてもこの考えは異様な物であり(アリストテレスは「生成消滅論」にて彼の考え方を「狂気の沙汰に近いもの」だと述懐している)、多くの論敵を呼んだ。そこで師の思想を継承したゼノンは、仮に「有る物(時間や距離)」が「一」でなく「多」であれば、その時いかなる不都合が起こるのかを示す事によって師の正しさを証明したのだ。もし「有る物」が「多」であるとすればという仮定、作り話、それが先程の四つの逆理となる。なのでゼノンのこれらの奇妙な主張の目的は、「運動」の否定で無く「多」を否定するものであった。
時間や距離といった「有る物」が「多」である場合、その「有る物」はいたる所が一様に分割が可能である筈だ。その「有る物」の両端をA、Bとし、その中心に点Oを置いてみる。OとBの間もまた一様であり分割可能なので、OとBの中心に点O'を置く事が出来る。O'とBの間にもまたO"を置ける。この作業が終了する時とは、AB間に分割されうるべき「有」が無くなり、これ以上分割され得ない「無」のみによってAB間が構成された時である。しかし「無」から「有」が構成される事は不合理であり、よって「有る物」は「多」ではなく「一」なのだ。これがゼノンの逆理に隠された主張であった。
これに対し、当時パルメニデスの最大の論敵であったピュタゴラス派の徒達は、「有る物」を分割していった際に「もうこれ以上は分割しきれ得ない」最小の単位が残り、「有る物」とはその最小の単位の連続によって構成される「多」なのだ、と反論した。哲学にも化学にもなんら専門知識を持たない私が考えるなら、「原子」が後々発見された事からピュタゴラス派の主張の方が正しいように思える。しかしゼノンはやはりこの説をも否定した。分割行為の果てに何かが残る事は論理的にありえないと。
この議論から膨大な時が経った現代、科学技術がその発展の為に採択した思想は、ヨーロッパにおいての「形」と「数」をめぐる形而上学的思想になる。そして、その思想の強力な基盤となったユークリッドの「原論」において、「点」とは「部分をもたぬもの」として定義されており、この「部分をもたぬ点」という概念が何から生まれたのかというと、それは、ピュタゴラス派の徒が有していた「万物はそれ以上の分割が不可能な最小単位の連続から成る「多」である」という思想に、パルメニデスが加えた批判を契機として形成されたものだと考えられている。
そして、現代科学の眼を持って見る「運動」とは、さながらAB間に無数の「部分をもたない点」、実際には存在しない思惟的な点を敷き詰める行為になる。だが、その行為は、その瞬間その瞬間に、飛んでいる矢が空間上に占めているべき位置に静止した矢のイメージを置いていく様なものになり、矢と矢の間の運動を捉える事は出来ないだろう。何故なら、矢と矢の間にあるのは「部分をもたない点」の集まり、つまり集合した「無」であるからだ。その様な認識に依拠しながら生きるという事は、私達に一体どの様な影響を及ぼすだろうか?
というような事がこの本に書かれているのだと私は思っている。まだ読んでいない方は是非お手に取ってみて下さい。
私がこの本について批評出来る事は何も無い。ギリシア哲学について何の知識も持っていないので。よく読んで「勉強になりました」と言う事が精一杯である。なので代わりに「現代社会が無数の思惟的な点の集合体として運動を還元している、その為に私達は運動の本質を捉える事は出来ない」という状況について思った事を簡単に書こうと思う。
運動が分割される際、当たり前だがその運動を分割する為に「見ている」者が居ないといけない。その運動の一瞬一瞬をその観察者が居る「今」自体に対応付ける存在としての眼、それを「ゼノン 四つの逆理」はデカルトの「コギト」(ワレ思ウ)そのものであると断言している。そこで、仮に私が「今」という一点から運動を「多」として見るとき、その運動は私が居る「今」自体には決して届かず、それが私の観察と同時間に起こった運動だとしても、常にその間に「部分をもたぬ点」が挟まっている為に、私が居る「今」よりも過去の出来事になり、その時に私と運動が観察する者/される者の関係から抜け出して仲間意識を共有する事はとても難しいだろう。同じ時間域に生きていないので。また、運動がイメージとして思惟的な点の羅列と成る時、その点と点との間の相関関係からその運動の未来を計算する事が出来る。それが当たるかどうかは別だが。乱暴に言えば、イメージとは未来(もしくは過去)に関する妄想を誘発しやすい存在であるとは言えるだろう。そもそも「運動の本質を捉える事が出来ない」とはどういう状態なのかというと、多分「運動のエネルギーやダイナミクス、それ自体を体験する事が出来ない」という事になるだろう。私自身はそれをもう仕方が無い事だと思っている。実際の友人と会って居酒屋で飲む行為も、Vtuberのゲーム実況配信を自宅で見る行為も、後々に振り返ればどちらもバカバカしい時間であった事に変わりは無いだろう。各々が好きな方のバカさを選べばいい。多分人類はもう二十数年に及ぶインターネットの台頭において、運動のエネルギー自体から切り離されている虚しさに完全に麻痺してしまったのだ。それが100%悪い事だとは思わない。その状況だからこそ生まれる希望だってあるんだろう。
そんな私の意見はさておき、「現代社会において、運動とはイメージの連続体であるに過ぎず、それは本当の運動自体を捉えているとは言い難い」、という問題をロック界に提示したレコード(のうちの一つ)だと私が考えているものがある。それはヴェルヴェット・アンダーグラウンドのファーストだ。
"THE VELVET UNDERGROUND&NICO"中の殆どの曲で、その歌われる対象は、何かを待つ、何かを繰り返す、何かに耐えているといった、ひとつの静的な状況へと限定されている。麻薬の売人を通りで待っている"I'm waiting for my man"では「まず学ぶべきは、お前はいつでも待たされるって事だ」とはっきり歌われる。"venus in furs"において「彼」は、1000年間も眠り続けられる程に疲れながらも、「彼」を待っている女王様から打擲される事で癒やされたいと望む。これらのシチュエーションに何らかの発展性は見受けられない。"there she goes again(また始まった)"の言葉通りに「彼女」は通りに出る事を繰り返し、歌い手はそれに対して「あの女を殴った方がいい」と吐き捨てる。別の曲の中で「彼女」は明日のパーティーを待っている。恐らく歌い手に近しいのであろう様々な人物の状況についての曲、"run run run"では"You gotta run run run…(お前は走らないといけない(Runがドラッグに依る高揚感を表しているという説もある))"と歌われる。つまり、まだ走っていないという事だ。"VELVET〜''において、抽象的な歌詞である最後の二曲を除き、曲中の登場人物達は何らかの静的な状態にあり、激しい運動、荒れ狂うエネルギーの奔流は全てそれら人物の思惟の中で起こっている。その事を一番良く表しているのが"heroin"だろう。
ヘロインを打った際の感覚について歌われるこの曲でルー・リードは「王国の為に挑戦して自らの男性性を感じたい」「千年前に生まれたかった」とそんな事言ってもどうにもならない事を言いながらヘロインを打ち、次第に「多分俺は知らないんだろう」「何もかもがどうでもいい」という酩酊状態へ突入していく。その行為が繰り返される。
ルー・リードの体内に入ったヘロインは(身体に重大な損傷を与えながらも)やがては体外へと排出される。なのでルー・リードは再びヘロインを自らへ注入する。それは「死ぬよりもいい気分」へと彼の精神を誘った後に再び彼から出て行く。彼はまたヘロインを打つ。
この行為を「前を進んでいるヘロインを、後ろから走っているルー・リードが追い掛ける」行為だと考えてみる。
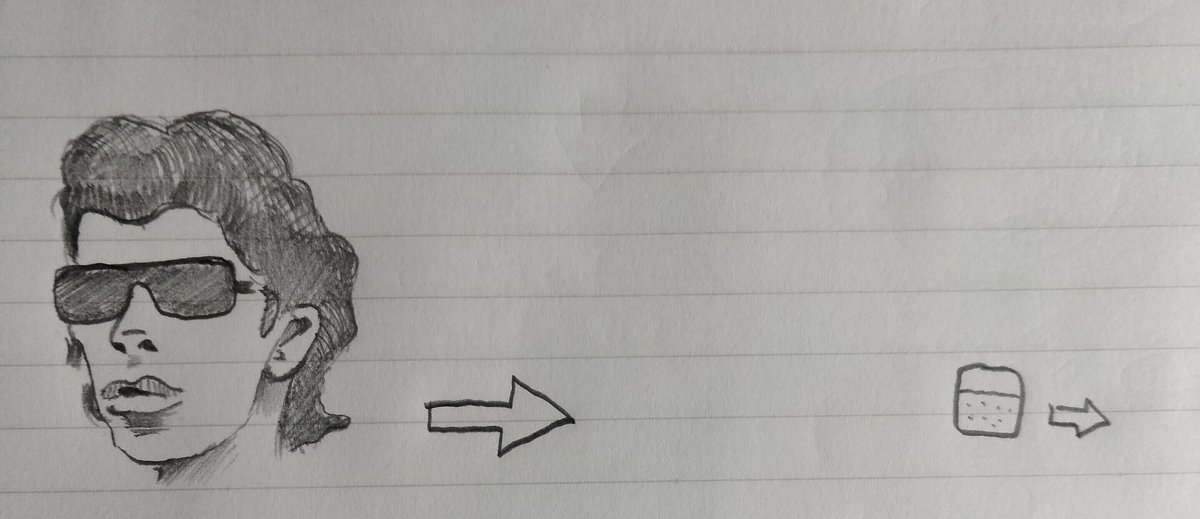
ルー・リードがヘロインを打つ時、それはルー・リードとヘロインが一点に重なる時であり、「後ろを走っていたルー・リードが、ヘロインに追い付く瞬間」の事だ。それは思惟的な点の羅列によって静的に還元されていた運動がその軛を外されて運動本来のエネルギーを取り戻した瞬間、ルー・リードが運動そのものの中に没入して目標へと辿り着いた瞬間である。そこは現代の科学技術を用いての理解や説明が出来ない、ルー・リードが「知らない」空間である。その事を最もよく表しているのが次の箇所になる。
「なぜならヘロインが流れ始めたら/俺は本当に何もかもどうでもよくなるんだ/山の様に積まれた死体の事ですらも」
ここでのジョン・ケイルによる電気ヴィオラの躁鬱的なノイズは、それ自体が「山の様に積まれた死体」の如き迫力を伴い、聴き手の眼前にその荒涼とした光景を現前せしめる。しかしその狂った奔流は同時にルー・リードによって「どうでもいい」ものだと断言されている。凄まじいエネルギーそのものでありながらも「どうでもいい」、つまり「無」であるもの。"heroin"はこの箇所において、ルー・リードの精神を叙述する事をも止め、現代の科学では「無」であるとしか認識出来ない「運動の本質」を音楽で表したものになった。そして、それはルー・リードの思惟によって生まれたものなのだ。
この爆発的なエネルギーの濁流を、アルバムのプロデューサーであるアンディ・ウォーホルは「バナナのシールを剥がす事が出来るジャケット」という、極めてニヒリスティックな手法でビジュアルへと翻訳した。
ウォーホルはこのアルバムのプロデューサーではあるが、実際の音像を決定する様な役割ではなかったと伝えられている。彼の実際の役割は何であったか?それはヴェルヴェット・アンダーグラウンドというバンドのイメージをわかりやすく世間に伝える事であっただろう。彼による"VELVET〜"のアルバムのジャケットはバナナの絵であった。この皮のついたバナナの絵はシールになっており、それを剥がすとその下から皮を剝かれたピンク色のバナナの絵が現れる仕様である。多くの人が知っている通り、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドを語る際、このバナナのジャケットはほぼ切り離せないものとなっている。しかし、なぜこのイメージは必ずと言っていいほどこのバンドとと共に語られるのであろうか?
ここで、あなたが道端でヴェルヴェット・アンダーグラウンドの、バナナの皮が剝かれた状態のジャケットを見つけたと考えてほしい。あなたは、そのジャケットに貼り付いていたバナナのシールが、どの様にして剥がされていったのか分かるだろうか?ゆっくりと剥がされたのか?それとも一気に剥がされたのか?どれほどの力で?
分かるわけが無い。これは何を意味するのか。つまり、皮のついたバナナのイメージがあり、皮を剝かれたバナナのイメージがあり、そしてその間にある「運動」を捉える事は出来ない、「運動」は存在しない、なぜなら知覚できないので、という事だ。これがウォーホルが"VELVET〜"のジャケットに込めた主張であった。麻薬の売人を待っている男は居る、パーティーを待っている彼女も居る、しかし、ヘロインで高揚している男の精神が生み出すエネルギーは、目に見えないので、無い。もしそれが有るのだとすれば、それはイメージとして視認できるもの、すなわち思惟的な点の連続体としてこの世に翻訳された物なのだ。それが、ただビルが映っているだけの数時間に及ぶ映画を撮る位に「像」に固執する男がいってのけた主張であり、それはつまり、このアルバムに、さながらヘロインの様に流れるエネルギーそれ自体を「過激なイメージ」としてパッケージングして売り出すという戦略であり、それはバンドと聴衆を「見られる物/見る物」へと完全に区別する行為であった。それがどのくらい成功したのかは知らない。だが未だにヴェルヴェット・アンダーグラウンドはこのバナナのイメージと共に語られているのだ。そして、このウォーホルの考え方に顕著な「ロックとは、過激な"イメージ"である」というテーゼは、それからロック自体を縛る枷になっていったのだと私は思う。
(↓中編につづく)
いいなと思ったら応援しよう!

