続IT書紀 基礎資料(3)
「汎用プログラム・モジュール流通情報センター」構想は、『続IT書紀』の重要なキーファクターです。これがのちの「ソフトウェア生産工業化システム」ないし「シグマセンター」につながっていきます。
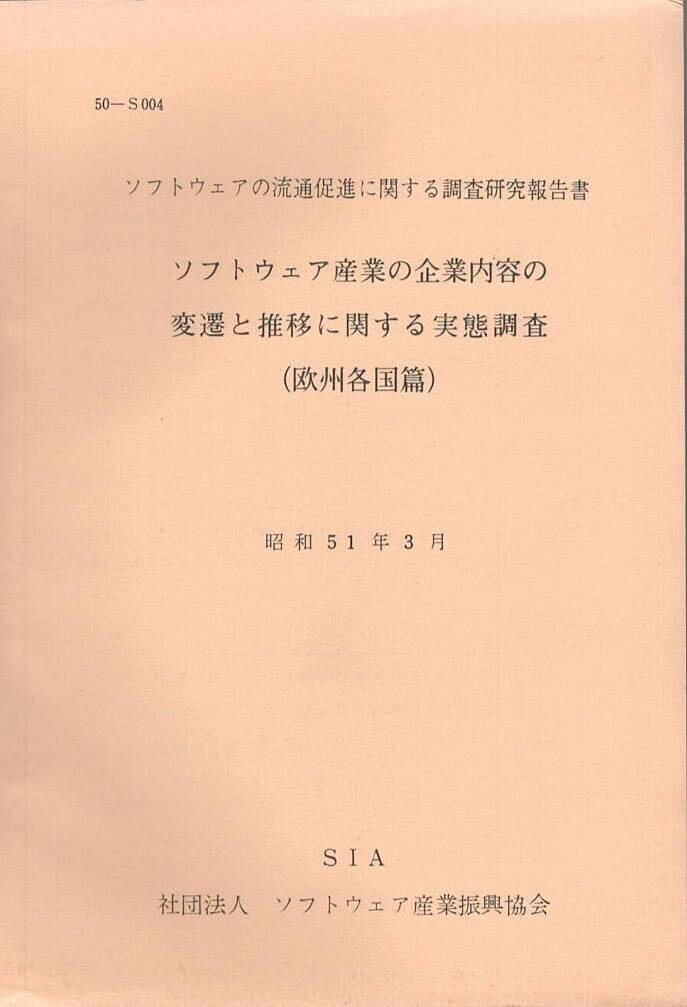
ソフトウェアの流通促進に関する調査報告書 ソフトウェア産業の企業内容の変遷と推移に関する実態調査(欧州各国編)
発 行:1976年3月
発行者:社団法人ソフトウェア産業振興協会
判 型:B5/260ページ
1976年4月1日から、コンピュータ・ソフトウェアが貿易自由化品目に指定されました。背景には汎用電子計算機(特にIBM汎用機)のハードウェア/ソフトウェアのアンバンドリング、国産電算機産業振興をねらったメーカー6社の3グループ化がありました。
海外からの圧力に国内ソフトウェア事業者がどう対応すべきか、事業の高度化方策を探るために、1975年10月24日〜11月10日に実施した欧州ソフト企業視察の報告。

経営情報データベース化のための計量的分析に関する調査研究
発 行:1984年3月
発行者:社団法人日本情報センター協会
経済文献研究会
判 型:B5/156ページ
序に「本書は、当社団が経済文献研究会に委託した報告書である」とある。経済文献件研究会の詳細は不明。
企業経営や景況・経済分析に資するデータベースの一つとして、コンピュータによる日本語処理技術を援用した書誌データが注目されていた。データファイルの構成、採録・インデキシングの手法、分類コード・キーワードのあり方などを、海外の事例を参照しつつまとめている。
https://itlibrary.hatenablog.jp/entry/2021/03/31/085829

ソフトウェア価格問題に関する調査研究報告
発行:1980年4月
発行者:社団法人ソフトウェア産業振興協会 ソフトウェア価格問題調査研究専門部会(部会長=丸森隆吾:ソフトウェアリサーチアソシエイツ社長)
判型:B5/50ページ
表紙に発行年月がなく、前書きや奥付もないため、一目では発行年が分からない。中扉に「昭和55年4月」とあるので、発行は1980年4月とした。
ソフトウェアの受託開発における価格の設定は、古くて新しいテーマであることが分かる。人件費を基準としたり要員のランクに付随するマンパワー型でなく、工程別単価をベースに工数と諸経費を勘案して積算する「工程別価格体系」を提案している。
提案した工程別標準月額は以下のようだった(単位:千円)。
システム設計のための調査分析:1049〜1260
システム設計:840〜1260
プログラム設計:700〜840
プログラミング:560〜672
総合テスト:840〜1008
マニュアル作成:560〜672

ソフトウェア流通促進に関する調査報告書 汎用プログラム・モジュール流通センター構想調査研究(ソフトウェア流通情報センター構想)
昭和53年3月
B5判262ページ
社団法人 ソフトウェア産業振興協会
会長・服部正(はっとり・まこと:構造計画研究所所長)の「序にかえて」によると、同調査は昭和49年(1974)「基礎的調査」、50年(1975)「技術調査」、51年(1976)「ソフトウェア流通情報センター構想」を受けて、「ソフトウェア流通情報センター」設立・運営の前提となるセンターの機能や政策を探ることを目的として報告書がまとめられました。
100ページ未満の報告書が多かった当時、262ページという規模は当時のソフトウェア産業振興協会、なかんずく服部正氏が「ソフトウェア流通情報センター」構想にいかに力を注いでいたかを物語ります。
