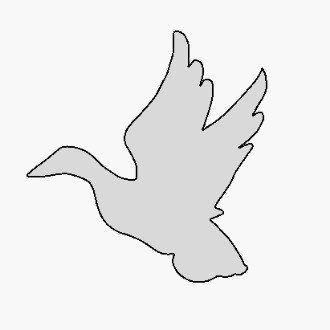Blenderで疑似・簡易ポーザブル・シンメトリができる記事を執筆中
色々あってBlenderでリグポージング中のモデル、主にフィギュア原型用のモデル編集用途のお話。Blenderの編集モードでならばZbrushのポーザブル・シンメトリ相当の編集ができることが分かった😍なので駆け足でその第1弾のブログ記事を執筆した。
(約 2,400文字の記事です。)
小出しに成果物を公開する作戦
まだ一部は未執筆なので(執筆中)の箇所が何カ所かあるが、寝かせていてもしょうがないので公開することにした。
ブログ記事は基本的には「アジャイル開発」みたいなもので、ただしOKを出してくれるクライアントは自分自身。なので途中でも書きかけでも、寝かしておいて価値が上がることはないのでどんどん出す。後から修正して更新履歴を書き換える。そもそもクライアントが自分なので、自分がOKを出すならば公開も公開後の修正も自由自在だ。
文句を言ってくるクライアントはいないw
一方で、読者は読者。ファンかもしれないが、記事執筆のクライアントではない。もちろん読者の視点やメリットなどを考慮して記事を書いてはいるが、直接的に「誰からどんな指示があって」「誰がOKを出せば執筆終了か」は定まっていない。なのでアジャイル開発でのクライアントではないことになる。
なので書きかけでも、とりあえず1つのテーマの記事が仕上がったら、後は「後に続く」的な書き方で少しずつ書き足していこうと思う。
ブログ記事は「大きな固まり」にしないこと
全部完成してから堂々の公開!は、実はあまりメリットがない。よほどの超大作でない限り、意外と読者からのレスポンスは「冷めたもの」だったりする。そうやって落差が大きすぎるとやる気に関わる。なのでハイリスク・ローリターンになり得る。
だからこそ、今日完成した分は今日公開しても何も問題はない。誰も不利益を被らないならば、成果物は小出しでいいのだ。WIP公開という。Work In Progress、進行中だよ&途中だよ、の略字。
また実は記事として完成型に仕様とすると1投稿の文字数が凄く増える。そうなると読者も読みづらいだろう。なのでシリーズ物にして数本構成にし、1本を3,000文字程度で区切るほうが読みやすい。その点でも、ある程度記事にボリュームが出てしまったら、記事を区切ることを考えてもいいだろう。そこら辺の塩梅が、大体1日1記事のWIP公開区切りが丁度いい気がしている。
折衷案をとるならば、その日書いた記事を翌日に推敲して公開、というのがいいかもしれない。たいていの場合、書き上げた直後よりも翌日の「別の頭」で冷静に成果物を評価してみると、色々分かることも多い。即日公開にこだわらず、翌日の自己点検後の公開でもいいだろう。後は自分次第w
専門ブログ記事はエネルギー消費量が多い
ここにnoteでつらつらとストレス発散を兼ねて文字を書くのは簡単だ。ここまでで10分少々だw 気ままにスラスラとは楽ちん。
だが専門ブログで専門的な内容を正確に表現しつつ、ソフトを触りながら裏取り作業をし、スクショを作り、説明が分かりやすい構成を考えての書くステップのスクショ撮影と加工、話の流れと分かりやすさの再検証、などなど、どんどん時間が奪われる。予定では1.5時間作業が倍の3時間になってしまった。それだけ専門ブログの執筆コストは高い。
そして疲れる。脳の疲弊を感じる。
なのでストレス発散を兼ねてここに書き散らかす😅
理解した後に「分かりやすく再構成」が大変
内容を理解してしまうと、それを人に分かりやすく説明することのほうが大変。理解までに要した時間が15分なのに、それをブログ記事にすれば2~3時間もかかってしまう。だるい、というのが本音😖脳みそが知的好奇心を失って、100%わかりきったことを再構成することに「めんどぅくせぇ感」を送りつけてくる。
脳内では一瞬で3次元的なイメージや、解説の流れ、必要な3DCGモデルや解説ポイントの図が湧き出す。だがそれを具現化するためにはいちいちモデルを作ったり操作したり、スクショを撮っては矢印だったり①②だったりを付けて、文章の説明では箇条書だったり段落構成、章構成を作ったりと、1次元の作業を時間軸方向に貫いて、という「2次元作業」でしか処理できない。3次元的な並列作業ができない。だから結果として時間がかかってしまう。
自分には動画よりも画像+文字が合っている
動画で説明したほうが楽か?とも考えたが、私がビデオ会議で知人に説明するならそれでもいいが、それをYouTube公開などとなると色々編集やカットが必要。結果として動画編集のほうがさらに倍くらい時間がかかる。15分の説明動画に編集6時間とかザラだし。
動画になってもポイントとなる箇所への視線誘導のための矢印や囲みを入れる必要がある。それをカットすると視聴者が「どこに着目すれば?」が分からないまま、ダラダラと声で解説を聞かなければならないので苦痛だ。結局動画になれば「視線誘導のための仕込み」が増えるだけなのだ。静止画ならば矢印1つで済む。タイムラインの制御という1次元を省略できるわけ。
またブログ記事だと図の差し替えで済むところ、動画だと部分的な撮影し直しか、PinP的な静止画の図の差し替え&再エンコードだろう。
時間軸のある作品には向いていない。
やはり自分には動画での解説は向かない。
というストレス発散日記で今日も終了。
noteみたいにサクサクと専門ブログ記事が書けたらなぁ、と思うが、もしそうやると「不正確」「あいまい」「ようするに何がポイントか?」「どこをどう活用できるの?」などがよく分からない、謎日記になってしまうのだ。だから手間暇かけて仕上げるしかない。
Udemyのセールが来た。ライノ関連の動画も1,500円になっていた。どうしようかなぁ?12/19までなので、今日1日検討することにしよう。
今回の創作活動は約45分(累積 約4,061時間)
(1,203回目のnote更新)
いいなと思ったら応援しよう!