
Web3ビジネスとは?
Web3ビジネスに本格的に取り組み始めてから3か月くらいですが、現時点での僕の見えているWeb3ビジネスについての解釈を記しておこうと思います。
まず、Web3の定義から
Web3(ウェブスリー)とは、次世代のワールド・ワイド・ウェブとして提唱されている概念である。分散化・ブロックチェーン・トークンベース経済などの要素が取り入れられており、一部の技術者やジャーナリストは、「ビッグ・テック」と呼ばれる大手IT企業にデータやコンテンツが集中しているとされるWeb 2.0とこれを対比させている。
ちなみに僕は下記の様に形で解釈しています。
Web3=分散型のインターネット
Web2→ 特定のサーバーに保存される。
Web3→ サーバーが分散されているので、特定のサーバーに依存しない。
ブロックチェーン技術を用いることで、特定の誰かが何かを管理するのではなく、みんなで管理するんだよ、というのが、一番しっくりくる考え方なんだと思います。
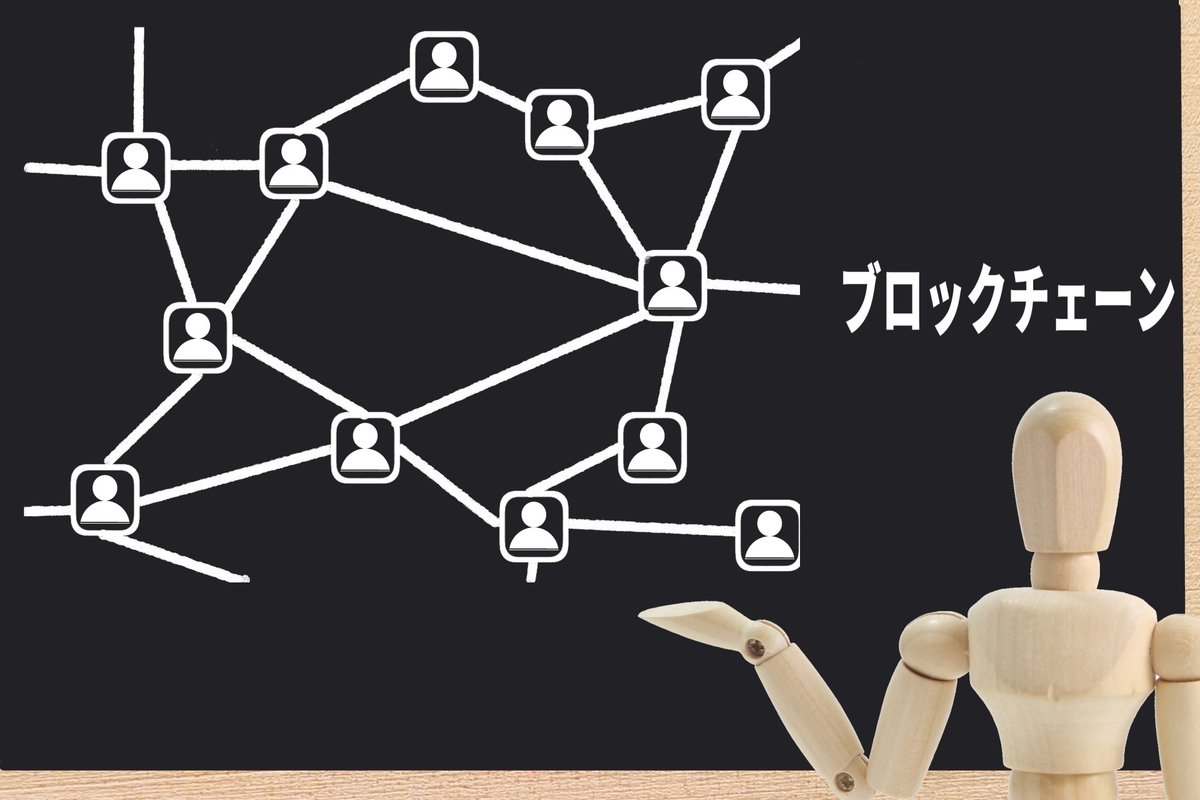
Web3ビジネスとは何か?
Web3ビジネスの定義については、しっかりとしたものがなかったのですが、「Web3的な要素を取り入れたビジネス」とするのが一番近いなと僕は感じています。
ただそれだとNFTを作って売るのもWeb3ビジネスになり、ちょっと違和感あるので、Web3ビジネスの定義を、2つの観点に分けて考えてみました。
1.プロダクトの観点
2.ビジネスモデルの観点
1.プロダクトの観点
プロダクトの観点でいうと、分散技術(多くの場合はブロックチェーン技術)を使ったビジネスは全てWeb3的と言える、ということです。
この観点からすると、NFTを作って売るのももちろんWeb3的です。
NFTの販売に関しては、OpenSeaなどのプラットフォームを通すことで2時販売手数料の一部を製作者が得られるので、今までのビジネスと全く同じではないですが、それでも極めてWeb2的なビジネスモデルです。
そういった点から、こういったWeb3的な技術を使ったWeb2ビジネスのことをWeb2.5ビジネス、と言われています。
※NFTの販売とかで言うとWeb2.2とか言われたりします。
2.ビジネスモデルの観点
ビジネスモデルの観点がWeb3というのは、自分たちで新しいコインを発行して、その価値を上げていく、というビジネスです。
特定の誰かが売上や利益を管理するのではなく、それもみんなで管理する、ということです。
プロダクトの観点も、ビジネスモデルの観点もWeb3的なビジネスこそ、いわゆる世間でWeb3ビジネスと言われているものだと思います。僕が最初の記事や、コインの価値ってどうやって上げるのか?という記事で書いてきたのも、まさにそれです。

なぜWeb3ビジネスがわかりにくいのか?
Web3ビジネスの定義は何となくわかったけど、いまいち掴みにくい理由、僕もずっとしっくりこなかった理由。
それは、成立しているWeb3ビジネスがほとんどないからです。
この事実が、あまり知られていないと感じています。
Web3ビジネスの具体例
成立しているWeb3ビジネスの数少ない具体例をあげると、やはりBTC(ビットコイン)とETH(イーサリアム)です。
この2つを正しく理解することがWeb3ビジネスへの理解の最短だと僕は思っています。
BTCについて
BTCは、世界で初めて誰にも管理されていない通貨という価値を持ったプロダクトである。(プロダクトの観点)
BTCというビジネスは、BTCというプロダクトの価値を担保している分散された複数のPC(バリデータと呼ばれる)が、働きに応じて報酬としてBTCを得る、というまさにWeb3ビジネスです。(ビジネスモデルの観点)
ちなみにBTCに関しては、創業者も謎に包まれており、本当に特定の誰かが主導している訳ではないもの、と言われています(イーサリアムは創業者がまだ、主導しています)。
それゆえ、BTCはプロジェクトとして完璧、美しい、まさに本当に意味でのDAOを体現している唯一のプロジェクトです。

ETHについて
イーサリアムはヴィタリック・ブテリン氏によって開発されたプラットフォームの名称です。 このプラットフォーム内で使用される仮想通貨をイーサ(英: Ether、単位: ETH )といいます。
イーサリアムチェーンというプロダクトは、ブロックチェーン技術を使いやすくする基盤です。(プロダクトの観点)
例えばNFTを1つ発行するのに、毎回複数の分散されたPCを用意したりするのは、現実的ではありません。
イーサリアムチェーンを使うことで、誰でも簡単にブロックチェーン技術を使ったプロダクトを作ることができます。
イーサリアムというビジネスは、イーサリアムチェーンというプロダクトの価値を担保している分散された複数のPC(バリデータと呼ばれる)が、働きに応じて報酬としてETHを得る、というまさにWeb3ビジネスです。(ビジネスモデルの観点)

成立しているWeb3ビジネスとは?
BTCとETHは有名なので知っている。その他に、成立しているWeb3ビジネスって何があるのか?
その話の前提として、そもそもWeb3ビジネスにある、チェーンビジネスとアプリケーションビジネスという分類から触れたいと思います。
チェーンビジネス
これは先ほど話したまさにイーサリアムチェーンが代表例です。
チェーンとは、ブロックチェーン技術を使いやすくする基盤です。
イーサリアムチェーンが世界初のチェーンで、その後、イーサリアムとは違うアプローチ(例えば開発言語が違う、など)で、いくつものチェーンが展開されています。
コインの時価総額の上位には、チェーンに紐づくコインが多くランクインしています。例えば下記です。
BNB → BSC(バイナンススマートチェーン)で使われる
SOL → Solana(ソラナチェーン)で使われる
チェーンビジネスは、Web2でいうプラットフォーム的なビジネスであり、大きなお金が動いていますが、大事なことは、チェーンはアプリケーションがのって初めて価値がある、ということです。
当たり前の話ですが、アプリケーションがユーザーの手に届き、それにユーザーが価値を感じて初めてチェーンに価値が生まれます。

アプリケーションビジネス
チェーンの上に乗っているWeb3プロダクト、実際にユーザーの手に触れるものです。色々なアプリケーションが広がることが、Web3ビジネスが広がる、ということになります。
ですが実は今のところ大きなものは2種類しかアプリケーションビジネスは発明されていません。
1.NFT
インターネット上で、このデータは誰が保有しているのか、というのを明らかにしたもの。特定のサーバーが保証するのではなく、分散されたサーバー上で保証したもの。ビジネスモデルとしては全くWeb3ではない。
2.DeFi
ユーザー間で勝手にお金の貸し借りや通貨の両替ができる銀行的な仕組み。レンディングとDEXがある。これも実はビジネスモデルとして運営が手数料をもらっている、極めてWeb2的なビジネスです。
ちなみにNFTとDeFiの両方の仕組みを使ったビジネスが、ブロックチェーンゲーム(BCG)だったりしますが、全てビジネスモデルの観点ではWeb3ではありません。
※ブロックチェーンゲームについてはまた次回以降で書きたいです。

成立しているWeb3アプリケーションビジネスはない
ここは僕も驚いたのですが、コインを発行しているDeFiもBCGも、実はビジネスモデルはWeb3ではないのです。コインに価値や権限が集中している訳ではなく、手数料収入があり、運営はそれを得ています。
「アプリケーションビジネスで、現在Web3ビジネスは存在していません」
小さく成立しているものや成立に向かっているものはあるかもしれませんが、チャレンジ中、といったところだと思います。
Web3ビジネスは今後、成立するのか?
繰り返しになりますが、Web3ビジネスがわかりにくいと言われているのは当然で、成立しているものが極めて少ないのです(BTC及び一部のチェーンビジネスのみ)。
なぜWeb3ビジネスが成立してないのか?
Web3ビジネスが成立していない理由は、ビジネスとしてリスクリターンがプロダクトがチェーン以外にないからだと思っています。
リスク:本来運営が得る収益をユーザーに還元し、ユーザー主導(DAO)で運営していける様な体制を長期的には作らないといけない。
リターン:ユーザーに本質的で新しい価値体験を提供でき、長い目で見るとサービスが反映する。
リターンの部分に書いている本質的で新しい価値を理解しているユーザーが少ない点と、まだWeb3ビジネスの歴史が浅く、長い目でサービスを見ることができないのが、成立しているWeb3ビジネスが少ない理由です。
「Web3的な考え方がもっと浸透して、誰かが管理しているプラットフォームってダサいよね、リスクだよね。」
「ブロックチェーンを使って分散的に情報を持って分散的に管理されてるコミュニティの方がクールだよね、安全だよね。」
といった考え方が一般的になっている世の中では、Web3ビジネスが当たり前になっていると思います。

僕はもちろん、長い目で見るとWeb3ビジネスはニーズがあると思ってます。誰かが管理しているYoutubeやTwitterではなく、誰も管理していない動画プラットフォームやSNSの方が、時代に合ってそうという感覚です。
ただし、そこまでいくのはいつになるのか。
Web3ビジネスが一般的になるのは、もう少しだけ先な気がしてます。
だからWeb3の業界の人は、Web2.5くらいがちょうどいい、と言っているのです。
Web3のWikipediaには、下記の様にも書かれています。
イーロン・マスクやジャック・ドーシーなど、Web3は単なるバズワードやマーケティング用語でしかないと主張する者もいる。
純粋な意味でのWeb3はまだ先の未来なのかもしれませんし、理想なのかもしれません。
ただし、Web3的な考え方や技術は、ゲームの分野とは非常に親和性が高いと感じており、今までにないユーザー体験を持つ、面白いゲームを作れると感じています。

何回もぐるぐる回りましたが、やっと方向性と体制が決まったので、9月頃にはプレスリリースを出したいなと思っております。
今回も読んでいただいた方はありがとうございます。
