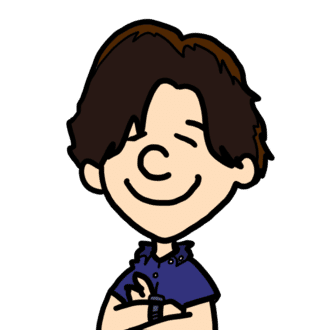BYARDがあって良かったこと
BYARDは2024年12月にサービスの終了を発表しましたが、これまでのnoteにはBYARDがなくなったとしても有益な情報があるものも多いと思いますので、あえてnoteの各記事はそのまま掲載しております。
こんにちは、BYARDの武内です。
今回のnoteはいつもと趣旨を少し変えて、社内から出た「BYARDがあって良かったこと」とその解説をお届けします。
こちらの話は、セールス側が「BYARDを導入することのメリットをもっと言語化したい」という意図で開いた座談会で、主にバックオフィスの担当者と、マネージャーから出た意見を集約したものです。
まとめるにあたって、多少は言葉の修正はしておりますが、一切のヤラセはございませんww
BYARDが解決しようとしている課題はまだまだ抽象度が高く、マーケ・セールスともにその解像度を上げることに必死になっていますが、今回はBYARD社内でも最もプロダクトとしてのBYARDを使っているメンバーからの素直な意見をご紹介することで、BYARDの存在意義を少しでも感じてもらえれば幸いです。
1.バックオフィス目線
まずはBYARDのバックオフィス担当者目線です。
入社1年未満、首都圏外に在住、子育てのために時短勤務(&フレックス)なので、入社初日からずっと「BYARDをフル活用して業務をしている」状態です。「BYARDがあったらうれしい(nice to have)」、ではなく「BYARDがないと困る(must have)」目線でのコメントになります。
(1)休みやすい
・事前に休みわかってるとき:仕事のタスク割上で担当者を変更するだけ。
・突然の場合:休んだ人でソートかけて、フォローしてあげる。
BYARDは「“人”と“業務”を切り離すことで、属人化を解消する」ことを意図して開発されたプロダクトです。
「○○さんの仕事」ではなく、「××という仕事を○○さんが担当している」と考え、BYARD上には「○○さんじゃなくても対応できるような情報を書きましょう(代替性)」ということを意識してもらうように日頃から社内やお客様にもご案内しています。
これは言うは易く行うは難しなのですが、お子さんがいらっしゃる方はイメージしやすいと思いますが、「いつ保育園(or幼稚園)から呼び出しがあるか分からない」という状態が日常茶飯事だと、嫌でもできるようになる(やるしかない)という側面もあります。
プロダクトの機能というよりも、「私以外の人が見ても分かるようにBYARDの状態を保っておこう」と常日頃からどれぐらい意識しているかの差です。
そして、それができている状態だと、突然お休みする事態になったとしても、周囲とコミュニケーションを取った上で「担当者を変更する」だけで引き継ぎは完了してしまうのです。
タスク管理ツールやExcelでのチェックリストは「私が分かればいい」という状態になりがちです。「“人”と“業務”を切り離す」ことができることがBYARDの最大の特徴です。
(2)周知がラク
仕事のやり方とか変更するときはいちいち人に周知しなくてもBYARD上でえいって変えるだけで、皆の仕事のやり方を誘導できると言うか。後は勝手に皆BYARDの流れに沿った動きをしてくれるようになるので、やり取りのコストがすごくが低い。
「“人”と“業務”を切り離す」ことの延長線上ですが、可能な限り代替性が高い状態を保つことで、社内のメンバーが「BYARDに沿って業務をやれば大丈夫」という認識になっていきます。
BYARDでは「最初から完成度の高いストリームを作らなくてもOK」ということはお客様も含めて何度もお伝えしております。
粗くてもいいので、「業務の流れ」を作った状態で、まずは回してみる。その過程で詰まったところやトラブルが起こったところについては、即座にテンプレートを修正する、ということの繰り返しで精度は自然と上がっていきます。
完璧なストリーム(業務プロセス)を作ろうとして、最初から頓挫してしまう人が結構いるのですが、完成度が高くなくても「見れるもの」があることで「もっとこうだったらいいのに」「ここが分かりにくかった」というフィードバックを受けられて、一人で悶々としながら作るよりも早く完成に近づきます。
「誰が見ても分かりやすく書く」というのは簡単なことではないのですが、自分が考える「必要十分」と、その業務を熟知していない人が考える「必要な情報」はどうせ一致しないので、それであれば不十分な状態でも出してみることに意義があります。
そして、業務の手順は「BYARDに書いてある通りにやる」という認識にみんながなってくれればこっちのものです。業務の変更の周知などは全体会議で口頭で説明し、社内の掲示板やチャットツールなどで流したとしても、ほとんどの人はいざ自分がやるときになったらそんなことは覚えていませんw
業務のやり方を周知するのではなく、みんなの仕事のやり方をBYARD上で誘導していく。そういう観点でストリームを作っていくと、結構楽しくできるかもしれません。
(3)業務を覚えなくていい
・BYARD使っていると、いい意味で仕事を覚えようとしなくなる。
・「BYARD見て、そこに書いてあることをシンプルにやるだけ」という認識に変わる。
・その分脳のリソースが浮くのが良いなと思ってるけど、この感じをBYARD使っていない人に伝えるのが難しい。
・逆に覚えちゃうと改善されなくなる気がする。
「“人”と“業務”を切り離す」ためには、「仕事の内容を覚えていなければできない」という風にしてはいけない、ということになります。
かといって、すべての情報が書かれている超詳細なマニュアルを作るべきか、と言われると、それは絶対に違います。分厚い説明書など多くの人が読みたくないのと同じです。
テキストだけでマニュアルを作っていくと、どうしても詳しくなりすぎてしまって、逆に分かり難くなる上に、分量が増えるとそのメンテナンスも大変になります。
結局、そうなるとベテランの人しか業務ができなくなる(他の人はマニュアル見てもできない)、ベテランの人はマニュアルを見なくてもできるので更新されなくなる、○○さんしかできない業務になる、という負のスパイラルに一直線です。
BYARDのストリームという概念は、そうならないようにワークカード単位でちょうどいい粒度で業務を分割していけるように構築しています。
新しく仕事を始めた際は「早く仕事を覚えなきゃ」という風に考えてしまうのですが、理想は仕事をガッチリ覚えなくても業務が進められる状態だと思っています。
また、いい意味で「覚えていない」ので常にフラットな目線で業務プロセスを見て、改善ポイントに気付きやすくなるというメリットもあります。
(4)キャッチアップが早くなる
・新しい人のキャッチアップが、BYARD上にあった方が圧倒的に早い。
・余分なことを聞かなくていいので、聞く方にもストレスがない。
・BYARD上に業務プロセスがないと、聞くとことから始まってしまう。
・共通認識を探すところからだと、考える幅がどっと広がってしまう
新しく仕事をする人の目線からすると、「早く戦力になりたい(役に立ちたい)」と思うのが普通ですよね。そういう観点からも「“人”と“業務”を切り離す」の概念は非常に有効に機能します。
一番最悪なのは、引き継ぎ(業務説明)は、マニュアルやフロー図もなく、すべて口頭で行われるやつだと思いますが、マニュアルやフロー図があったとしても、「それが最新じゃない(正しくない)」という場合は結構困ると思います。
こうやって書くとかなりダメな職場っぽいのですが、私がこれまで見てきた企業の業務の半分以上は、このどちらかに当てはまっていました。つまり、新しいメンバーにちゃんと引き継ぎをする準備は、ほとんどの企業がまともにできていないということです。
「“人”と“業務”を切り離す」観点で、再現性(何度やっても同じ成果がでる)や代替性(誰がやっても同じ成果がでる)が高い状態をずっとキープし続けること。これがBYARDの存在意義だと思っています。
新しい概念なので、商談の中で「業務フロー図だけでいい。タスク管理や進捗管理の機能はいらない」と言われることも結構あるのですが、業務プロセスだけをどんなにキレイに書き出したところで、それを常に見ながら業務を遂行する状態を維持しなければ、あっという間にフロー図は形骸化します。
休みやすくなる、周知しなくていい、いい意味で仕事を覚えなくていい、という状態が作れていると、新しいメンバーが入ってきた時の仕事のキャッチアップもめちゃくちゃ早くなります。
「忙しくて教えている暇がない」という話はよく聞きますが、「教えないと業務ができない状態」を作ってしまっていることが本来はダメなのです。
2.マネージャー目線
こちらはBYARD社内のマネージャーからの意見です。
マネージャーといっても、すべての業務を事細かに把握していることは不可能ですが、最終的な責任を負っているので、進捗状況はどうしても気になります。
だからといって、マイクロマネジメントをしてしまうとメンバーも疲弊しますし、マネージャー自身もすぐにパンクしてしまうでしょう。
BYARD社内では特に複数人が関わる業務(承認フローなども含む)についてはBYARD上でストリームを作って管理するようにしています。その結果、マネージャーとしてもストレスがない状態が保てるようになっています。
(1)進捗状況が分かる
・「あれ?この進捗、今どこまでできるんだっけ?明日までだけどもう夜だし…」みたいなときもBYARDを見れば、いちいち人に聞かなくてもすぐに分かる
・定例会議でそれぞれ聞いて把握するようなスタイルだと、なんていうか…結構公開処刑みたいな。詰めてる感じになっちゃうけど、BYARDだと期限切れが明確なので、そうはならない
この感覚は、Salesforceをちゃんと活用できるようになったセールスチームのマネージャーが感じるやつに、非常に近いと思っています。セールスメンバーがSalesforce上で業務をするようになればなるほど、レポートの精度も上がって、マネージャーはレポート・ダッシュボードを見ることで状況が把握できるようになるやつです。
間接部門の業務の進捗は担当者任せのことが多くて、進捗状況は定例会議で共有するだけみたいなスタイルも未だに多くあります。
また、メンバーにとっても重要なのは「進捗状況を報告するための作業がない」ことです。当たり前のように日々の業務を進めていくだけで、マネージャーが進捗状況を把握できるからこそ意味があるのです。
Salesforceとその他のSalesforceっぽいものの大きな差はここにあると私は考えていて、レポート・ダッシュボードの機能も大事なのですが、それよりも重要なのはいかに日常的にSalesforceを当たり前に更新する状態を作れるかだと思っています。
BYARDはここを非常に意識して機能を設計してきました。正直、現時点ではSalesforceにはまだまだ及ばないところばかりですが、わざわざチェックを付けにいくタスク管理ツールではなく、いかに「BYARD上で業務をする」という状態を実現できるかを重視して、開発と改善を続けています。
それが実現できていると、マネージャーも安心してレポート・ダッシュボードを見るだけで状況を把握できるようになるのです。
(2)成果が数値化できる
今月何をどれだけしたのか。どういう成果物が何件あったか、すぐに出せるようになった。
セールス部門や開発部門の人からすると驚くべきことなのかもしれませんが、間接部門では「どのような業務が何件ぐらい発生しているのか」を数値で把握している企業はほとんどありません。
数値管理が徹底された製造業では別だと思いますが、ほとんどの企業はなんか忙しい、最近ミスやトラブルが多い、ということを(なんとなく)感じて、そこからようやく実態を把握しにいくというのがスタンダードです。
リーガルチェックや契約書の締結は月に何件実施されているのか、請求書は何件発行されていて、現場とのやり取りで差し戻しが発生するケースがどれぐらいあるのか等、こういうデータが即座に確認できるダッシュボードを持っている間接部門は希少です。
多くの間接部門はベルトコンベアに流れてくる作業を処理しているわけではないため、様々な種類の仕事をそれぞれの持ち場で対応していますが、かなり専門的だったり細かいものが少なくないので、マネージャーもその詳細な中身については把握していないことがほとんどです。
マネージャーが全てを把握することは無理ですし、そんなことを求めていたら誰もマネージャーにはなれません。ただ、詳細は把握していなくても、ある程度の定量的な数値で状況を把握する必要は、間接部門のマネージャーにもあります。
ここでも重要なのは「現場がわざわざ報告のために何かを作成・記入する必要がないこと」です。BYARDを使って業務プロセスを構築し、運用すると自然とBYARD上で状況を把握できるようになります。
フロー図を描くだけでは決して実現しない世界を、BYARDは実現したいと考えています。
3.CS目線(お客様と接しながら感じること)
最後は、常日頃からお客様と向き合い業務設計や改善を伴走しているCSメンバーからの目線です。
BYARD導入に当たっては、「まずは現在の業務を可視化しましょう」というところから入ることが多いですが、では可視化の先に何があるのかをどれぐらい意識できるか、が重要だとそのメンバーは語ります。
業務を標準化する、無駄をなくす、という目標は一見良さそうですが、抽象度が高くて上滑りをしがちです。可視化をして、まずは組織の中での業務に対しての共通認識を作ることが重要です。個々人の目標だけではずれが生じますし、土台が整っていなければその上に新しいものを構築することはできません。
BYARDは業務のど真ん中にあって、関係者間の共通認識を作るものなのです。
(1)共通認識が作れる
・よく見る職場の状態は、「実際仕事の内容とあってるのかな?間違ってるのかなって」という風に、正しいものとそうじゃないものが混ざっている状態。マニュアルの精査が必要だったりして、どのマニュアルを信じていいかわからないことがある。
・BYARDだと絶対生きたマニュアルになってる(最新化されている)って確信できるので、マニュアルを選ぶところから迷いがない
・情報がたくさんあることが正義ではない(間違った情報があることで逆に混乱する)
・マニュアルだけで業務は進められない
BYARDを導入いただく企業には、すでにマニュアルやチェックリストが整備されていることも少なくありません。ただそれらはほとんど機能していません。なぜなら、内容が古くなっていて、業務の実態と乖離してしまっているからです。
新しい職場に配属されて、先輩社員から「この通りのやってみて」と言って渡されたマニュアルの内容が古くて、システムの画面なんかも大きく変わっていたら、困りますよね。
マニュアルやチェックリストは業務を落とし込む手段としては一般的ですが、作って満足してしまっては意味がありません。
本来目指すべきは「それを見て確実に業務が回せる状態」を作ることにあるはずです。
会社の規模が大きくなるほど、業務の担当範囲は細分化されていき、業務の全体像に対して共通認識を作ることが難しくなっていきます。マニュアルやチェックリストでは共通認識までは持つことができません。
BYARDのストリームは業務の全体像という抽象的なレイヤーと、具体的な各業務の手順を行き来することができる仕組みです。
(2)役割分担が明確になる
・業務に明るくない人でも全体と個別を理解できる。
・複数人での進捗の把握ができる。(Excelだと不可能)
・どこで問題が起きて、なんで起きたのか、要因の把握と改善が早くなる。
・インシデントの発生を未然に防ぐことができる
タスク管理ツールやプロジェクト管理ツールにも、担当者欄はあります。ただ、その目的が「担当者自身が業務をやったかどうかをチェックする」ことに主眼が置かれているため、業務の全体像や役割分担ということに目が向きにくい構造になっています。
セールスや開発であれば、「その担当者が最初から最後まで対応を行う」前提なので問題はありませんが、間接部門の業務は複数の部門や担当者にまたがって行われることが少なくありません。
例えば、労務関連の業務である入退社や休職の対応について、主幹部門は労務ですが、アカウントの発行や停止は情シスが担当しますし、端末や名刺などの手配は総務が担当する、といった感じで労務担当者がすべてを処理することはできません。
業務の性質や粒度も担当領域毎に違うので、多くの企業では部門毎にタスクやプロジェクトの管理方法がバラバラなことはよくあります。業務の全体の進捗状況は誰も把握しておらず、各部門が自分の役割をきちんと果たすことで成り立っている状態です。
自分の担当タスクが終わったら、社内のチャットなどで次の担当者に連携して、手元のタスク管理としてそれで完了です。
それで問題なく回っているうちはいいのですが、こういう状態だと全体の業務プロセスを構成する担当者の誰か1人でも退職や異動で変わってしまうと、トラブルが頻発したりします。
フロー図やマニュアルがあったとしても、実際には担当者同士の阿吽の呼吸で業務プロセス全体が回っているため、その部分をちゃんと引き継ぐことは容易ではないのです。
SmartHRの労務もそういう状態だった中でBYARDを導入いただき、部門をまたいだ業務の役割分担や共通認識を持った状態を作ることができました。
マニュアルやフロー図があったとしても、慣れてくると自分の頭の中にある手順で業務を進めてしまうため、記載内容と実際の業務内容に乖離が生じてきます。そうなってくると、何か問題が生じたときにも原因を特定したり、再発防止策を立てる前に、現状把握に時間がかかってしまいます。
BYARDが目指しているのは「常にBYARD上で業務を進めていく状態を作ること」です。まだ他のシステムとの連携も不十分なので機能として未熟な部分も多いですが、そういう世界観で開発を今後も進めていきます。
まとめ
わずか30分の座談会だったのですが、BYARDのコンセプトとしてお伝えしたいことがたくさんあったので、noteを書いてみると結構な長文になってしまいました。
創業当初から言っているとおり、既存のタスク管理ツールやプロジェクト管理ツールを進化させたプロダクトを開発しているつもりはありません。SalesforceやGitHubのように、業務のやり方や管理手法そのものを大きくアップデートすることができるプラットフォームを目指して開発しています。
まだ抽象的で概念的な話も多いのですが、その中で「休みやすい状態を作る」というのは具体的に目指す状態の一つではあります。「○○さんの業務」ではなく、「××という業務を○○さんが担当している」状態、つまり「“人”と”業務”を切り離せた」状態をBYARDで作ることができれば、きっと休みやすい職場・業務になるだろうという風に考えています。
今回、座談会の冒頭でBYARDのバックオフィスメンバーが「休みやすい」という風に話してくれたことは非常に嬉しかったですし、自分達が作ってきたBYARDというプロダクトの方向性が肯定された気がしました。
マニュアルやチェックリストという100年以上も前からあるツールの使い勝手をあげるのではなく、間接業務というものを根本からアップデートしたい。それがBYARDの存在意義であり、目標なのです。
BYARDのご紹介
BYARDはツールを提供するだけでなく、初期の業務設計コンサルティングをしっかり伴走させていただきますので、自社の業務プロセスが確実に可視化され、業務改善をするための土台を早期に整えることができます。
BYARDはマニュアルやフロー図を作るのではなく、「業務を可視化し、業務設計ができる状態を維持する」という価値を提供するツールです。この辺りに課題を抱える皆様、ぜひお気軽にご連絡ください。
いいなと思ったら応援しよう!