
ホームページ制作でやってはいけないこと24個!#2【構築編】プロが教える最適解|TRASP株式会社 制作部
「ホームページ制作で失敗したくない」と悩んでいませんか?
ホームページ制作では
ユーザーや検索エンジンから嫌われてしまうNG施策があります。
最悪の場合にはホームページが検索結果に表示されなくなることも…
このシリーズでは、数多くのホームページ制作実績のあるTRASPが、
「知らないとやばい!」24個のNG施策を紹介します。
まずは【構築編】として6つをご紹介。
構築は、ホームページ制作会社に対応してもらえますが、自分でも知識を持っておくことでトラブルを避けられますよ。
【企画・SEO編】【コンテンツ編】【デザイン編】はこちら。
1.無料サーバーを選んでしまう

ホームページを「家」とする場合、サーバーは「土地」、ドメインは「住所」にあたります。
土地が不安定であれば頑丈な家は建てられませんし、住所が不明だとだれも訪れませんよね。
同様にホームページにおいても、サーバーとドメインの選び方はとても重要です。
結論として、無料のサービスを選ばないようにしましょう。
なぜなら、無料サーバーにはさまざまなデメリットがあるからです。
無料サーバーのデメリット
容量が小さくて、すぐにサーバーダウンする
1個のドメインしか使えない
サポートがない
大手CMSが使えないなど
そのため、大手レンタルサーバーを利用するのがおすすめです。
2.ドメインがわかりにくい…
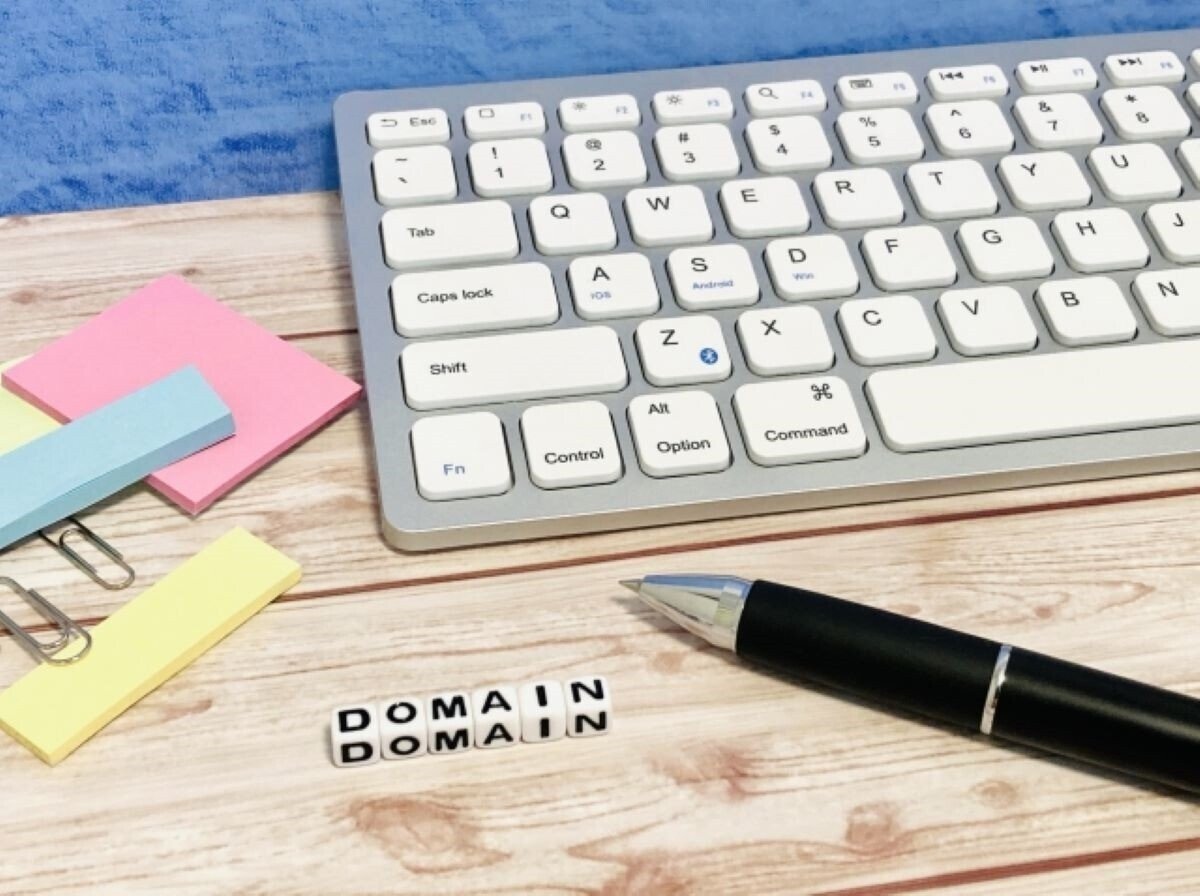
前述したように、ドメインとは、いわば「インターネット上の住所」です。
住所がなければ、どこに自社が存在しているのかわからないのと同様に、固有ドメインがあることで、自社のWebサイトにユーザーがアクセスできるようになります。
ドメインの構成要素
それでは、ドメインについてわかりやすく解説します。
【当社TRASPのサイトhttps://trasp-inc.comの場合】
・「https://」スキーム:
WebサーバーがWebサイトのページにアクセスする際に利用するプロトコル
・「trasp-inc」セカンドレベルドメイン(2LD):
自社で決められるWebサイト住所にあたる部分
・「.com」トップレベルドメイン(TLD):
インターネット上で定められている組織の種別
ドメインの種類
ドメインには、「独自ドメイン」と「共有ドメイン」があります。
【独自ドメイン】
独自ドメインとは、自社だけで所有しているドメインのことです。有料ではあるものの、自社で自由にドメイン名を決められます。自社で所有できるドメインとなっているため、サーバーを変えても同じドメインを使用でき、オリジナルドメインとして対外的な信頼度を高められるでしょう。
また、検索エンジンに評価されやすいため、SEO対策に適しています。そのため、企業が新しくWebサイトを運用する場合には、独自ドメインの取得がおすすめです。
【共有ドメイン】
共有ドメインとは、多数の利用者が共有で利用できるドメインのことです。ブログサービスやサーバー会社が所有していることが一般的で、契約すると、無料で利用できるようになります。
ただし、自社で所有できるわけではないので、例えばドメインが「trasp-inc.webblog.jp」だとすると、「.webblog.jp」の部分はサービスの運用会社ごとに決められたものを使用しなければなりません。
共有ドメインでは、自社で広告を設定できないため、自社とは関係のない広告が表示されたり、サーバーを変えるとドメインも変わってしまったりなどのデメリットがあります。
また、共有ドメインを所有しているサーバー会社などの都合でサービス提供がなくなるおそれも考慮しなければならず、自社のWebサイトを作成するには不安が残るでしょう。
ドメインは独自ドメインがおすすめです。
またドメインは、ひと目でサイト名や会社名がわかるものにしましょう。
ランダムな文字列のようなドメインでは、「詐欺サイトかな?」といった不信感を抱かれてしまいます。
OK:trasp-inc.com
NG:sptratrspa.com
ドメイン販売サイトでは、「.net」や「.blog」などが扱われています。しかし基本的には、ユーザーが見慣れている「.co.jp」「.com」「.jp」を選ぶのがおすすめです。
ドメインは、「インターネット上の住所」であるため、オンライン上の名刺として、ユーザーとのタッチポイントとしての役割をもっています。
会社が長期間存在するなかで、経営方針や事業活動が変化していったとしても、ドメインは変わることなく使用するものなのです。
同じドメインを使用し続けることで、ブランド認知度の向上や社会的な信頼の獲得につながる一方、半永久的に使用するものであることを意識してドメイン名を決める必要がありますね。
3.パンくずリストが設置されていない

パンくずリストがないサイトは、ユーザーや検索エンジンに理解されにくくなってしまいます。
そもそもパンくずリストとは、
閲覧しているページの位置を視覚的に表すリストのこと。
主にページ上部に、リンク形式で記載します。TRASPのサイトでは以下のように表示されています。
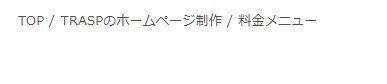
【パンくずリストの例】
TOP>大カテゴリ>少カテゴリ>ページ
TOP>アウター>Tシャツ>商品A
パンくずリストがあると、ユーザーが前のページや同カテゴリの別記事を訪れやすくなり、サイト回遊率を向上可能です。
また、検索エンジンのクローラーが巡回しやすくなるため、SEOへの効果も期待できます。
【パンくずリストの設置方法】
・HTMLを編集する
・構造化データマークアップ
・CMSの設定やプラグイン
4.セキュリティ対策をしていない

「サイバー攻撃なんて大企業だけの話でしょ?」
「うちみたいな小さい会社は関係ない」
このように考えている、中小企業の方も多いのではないでしょうか?
ところが現在、大企業のセキュリティが強固になっていくなかで、サイバー攻撃・不正アクセスのターゲットが中小企業へとシフトしてきているのです。
大企業を狙うための踏み台として中小企業がターゲットにされるケースもあります。
個人情報の漏洩やページの改ざんなどが起きないように、下記の施策を中心にしっかり備えておきましょう。
編集画面へのログインURL・ID・パスワードの管理
WordPressのプラグインの活用
怪しいプラグインなどは使用しない
セキュリティ対策のあるサーバーを選ぶ
SSL化など
特にSSL化は、欠かさず行いましょう。
SSL化とは、URLの「http」を「https」に変更し、データの送受信を暗号化すること。基本的にはレンタルサーバーの設定で実行できます。
HTTPとは「シンプルな通信」
HTTPとは、「Hyper Text Transfer Protocol(ハイパーテキスト・トランスファー・プロトコル)」というホームページを表示するための通信規格(プロトコル)のことです。
HTTPSとは「暗号化された通信」
HTTPSとは、「Hypertext Transfer Protocol Secure(ハイパーテキスト・トランスファー・プロトコル・セキュア)」という、SSL(暗号化通信)によりデータを暗号化しているHTTP通信のことです。
HTTPとHTTPSの違い
HTTPとHTTPSの違いは、ユーザーの使用しているブラウザとサーバーの間で情報をやり取りする際の通信が暗号化されているかどうかにあります。
HTTPの場合には、「Webブラウザからサーバーにリクエストが送られる→サーバーがそのリクエストに応答する→Webサイトの情報が表示される」という通信の内容が丸見えになっています。
そこで、第三者に通信データを傍受された際にも、通信を暗号化することで、通信内容がわからないようにするSSLが導入されるようになりました。
SSL化は、ホームページで入力された顧客情報の保護などに役立ちます。
SSL化しておらず、個人情報流出などのトラブルが起こると、会社の信頼を失ってしまうので注意しましょう。
5.ページ速度が遅い

ページ全体が表示されるまでに時間がかかると、ユーザーの離脱につながります。
Googleはユーザーの利便性を重視しているため、SEOの観点でみても不利になります。
そのため、定期的に「PageSpeed Insights」でページ速度を確認しましょう。
PageSpeed Insightsは、ページ速度を表すスコアとともに、改善方法も提案してくれます。
圧縮を有効にする
ブラウザのキャッシュを活用する
画像を最適化するなど
一つひとつ改善して、ユーザーが閲覧しやすいホームページを維持しましょう。
6.モバイル(レスポンシブ)対応していない

スマートフォン・パソコン・タブレットなどの媒体に合ったデザインで表示するには、レスポンシブ対応が必要です。
【レスポンシブWebデザインとは】
スマートフォン・タブレット・パソコンなど、異なる画面サイズに応じ、レイアウトを最適化する機能を指します。
従来はスマートフォン用・タブレット用・パソコン用といったように、デバイスごとに複数のHTMLファイルを用意する必要がありました。
しかしレスポンシブデザインは、ひとつのHTMLファイルでOK。それぞれの画面サイズに合うようにレイアウトやデザインを自在に調整できます。
そのため、デスクトップパソコンの大型画面からスマートフォンの小さな画面まで、同じWebサイトが各デバイスの画面サイズに適したレイアウトに自動で切り替えられます。
レスポンシブ対応していないホームページは、媒体によって文字が小さくなったり、ページが切れたりするため、ユーザーの満足度が低下してしまいます。
どの媒体でも見やすい「レスポンシブ対応」することが大切です。
レスポンシブ対応の実装方法例
HTML・CSSを編集
変換ツールを使用
レスポンシブ対応しているCMSを使用
WordPressのプラグインを使用など
さいごに
ホームページ制作でやってはいけないこと24個のうち、【構築編】として6つを紹介しました。
ホームページ制作会社に依頼する場合は、大部分は制作会社が担うことになります。そのため、制作会社選びがとても重要です。
どこに依頼すれば良いかわからない場合は、ぜひTRASPにご相談ください。
もし合わないと感じたら遠慮なくお断りください。料金は無料です。
TRASPでは、「ホームページ制作でやってはいけないこと」に配慮したうえで、ターゲットや目標に合わせたやるべきことを実行いたします。
Webの知識がない方でも一から丁寧にサポートしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
