
■【歴史を超えた東西の共鳴とバカの壁】[西]市場原理主義(スミス自由放任の極致)と[東]無為自然(ケネーlaissez-faireの淵源)の意外な共鳴!?故に、米中“自己利益”中心主義(自閉概念硬化)の<解除→再構築の努力>こそが必須!
■【歴史を超えた東西の共鳴とバカの壁】[西]市場原理主義(スミス自由放任の極致)と[東]無為自然(ケネーlaissez-faireの淵源)の意外な共鳴!?故に、米中“自己利益”中心主義(自閉概念硬化)の<解除→再構築の努力>こそが必須!


・・・宇沢弘文『経済学の考え方』(岩波新書)によると、1763年にアダム・スミス(Adam Smith/1723-1790/↑画像@wiki)は3年近くにおよぶ欧州見分の旅に出向いたが、フランスではフランソワ・ケネー(Francois Quesnay/1694 -1774/↓画像@wiki/『経済表』の業績で近代以降の循環経済論の基礎を創った)と会って大きな影響を受けている。医者でもあったケネーは、経済を自然の一環である人間の肉体にたとえて、その循環のメカニズムを図式化し『経済表』を完成させた訳だが、このようにケネーら当時のフランスの経済学者たちは、自然の一環として経済を位置付けていたため、彼らの経済学は農業経済(重農主義)と呼ばれている。

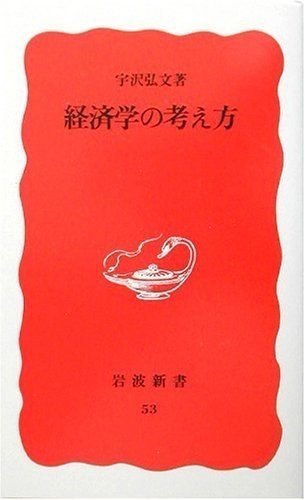
・・・また、根井雅弘『経済学はいかに衰退するのか』(NHK出版)によれば、オーストリアンの世界を取り込みつつ、経済「発展」の根本を解明しようとしていたシュンペーターは、肝心の「経済発展」への観察が可能な現象についての契機が欠落していることに気付き、一般均衡理論のワルラスと異なる観点から、リアル経済のモデルである『動態』と、そのベースとなる『静態』の思考実験を構想したとされる。
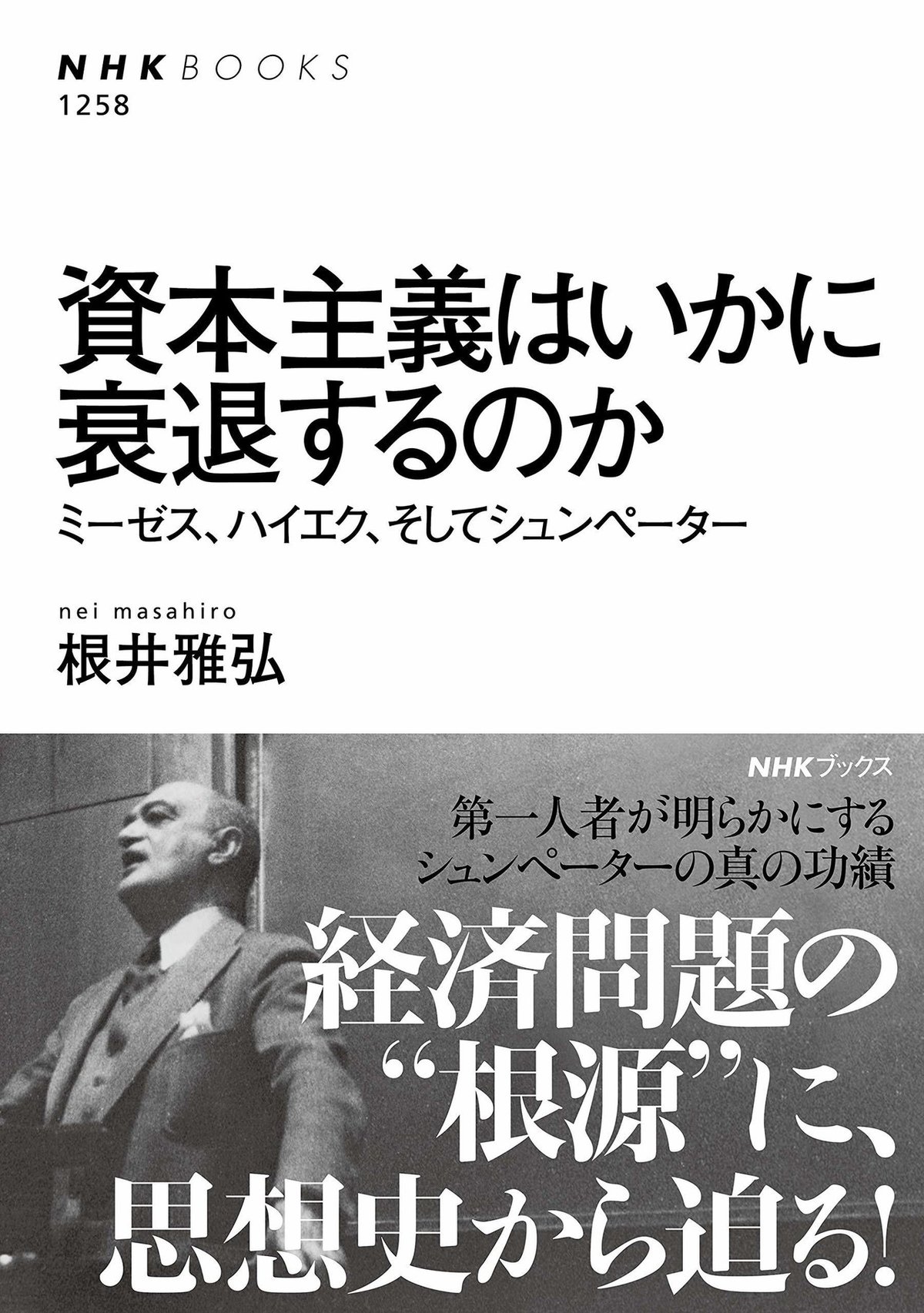
・・・因みに、ケネーに始まる「重農主義」(通商・交易(市場経済)の利潤ストックを重視する重商主義の対語)は、日本語で無理に「重農主義」と訳さず、そもそもの用語である「physeos kratesis(physiocracy/ギリシア語由来で、自然の秩序により統治する経済の意味)」で表記した方が、より正しくその意味が理解できるのではないか?それを現代的に表現すれば「エトノス自然環境を重視する経済学」(内外の“潜性イノヴェーション”の世界をも視野に入れた経済学)ということに他ならないからだ。
・・・また、アダム・スミスの「自由放任主義」(つまり、laissez-faire)が、このフランスのケネーらによる重農主義(自然循環の影響を重視する経済学の視点)の思想から大きな影響を受けていたことは今や論を待たない。そして、興味深いのは、このような視点に立つと、スミス‘自由放任’の極致ともされてきた「市場原理主義」(ハイエク、ミルトン・フリードマンらによる超抽象的な概念硬化のジャンル)については、更に『国富論、1776』と、もう一つのスミスの業績である『道徳感情論、1759』を合わせ見ることによって、そもそもそれ(市場原理主義)が一種のボタンの掛違いの賜物だったのでは?ということが、次第に明らかとなりつつあることだ。
・・・それだけではない、近年の研究(↓The Eastern Origins of Western Civilization, John M.Hobsonら)によれば、中国の古代思想(老荘思想)と概念がケネーに大きな影響を与えた可能性が高いことが明らかとなりつつある。つまり、[西]市場原理主義(スミス自由放任の極致)と[東]無為自然(ケネーlaissez-faireの淵源)の意外な共鳴!?が聞こえつつある(自省も含めて?)という訳だ。哲学・思想・イデオローグをはさむ対立激化(今でいえば、米-中対立)の覇権を争う構図が↓◆、必然的にゼロサムの「赤の女王」に凱歌を謳わせてきたという恐るべき歴史(トウキディディスのわな/覇権を争う国家どうしは戦争を免れることが難しいという歴史上の教訓/Cf.↓(参考))を、今こそ、特に多数派の人々(われわれ凡人、人類)が真剣に直視すべき時であるのかも知れない。
◆覇権対立の“激化”(Ex.米トラ-中習の対立)こそがゼロサム「赤の女王」に凱歌を謳わせてきた!という歴史上の教訓(トウキディディスの罠)を、今こそ多数派の我われ凡人が真剣に直視すべき鴨神社!? →今は冷戦期以上の核危機だ ペリー元米国防長官らに聞く724朝日 https://twitter.com/tadanoossan2/status/1286469495834329089
・・・トランプ政権は、201802に核体制見直し(NPR)を公表しており、通常兵器による攻撃に対しても低出力の核兵器で報復する選択肢を増やすとした。現在も、核の先制使用方針は放棄していない。/保有核弾頭数:米国5800、ロシア6370、中国320、北朝鮮35、英国195、フランス290、パキスタン160、インド150、イスラエル80~90(724朝日)

https://twitter.com/tadanoossan2/status/1286469495834329089
(参考)アメリカの国際政治の底流に流れる「トゥキディデスの罠」とは何か/The Libety‐Web、https://the-liberty.com/article.php?item_id=14115
・・・
●協調無視ではゼロサムの“赤の女王”↓<注>が歓喜するのみ!トランプの損失などドウでもだがw、全人類の没落は回避すべき! →コロナ危機と世界秩序(上)対中戦略 協調体制再構築を/トランプ再選なら協調困難に!717日経A.オロス、WCカレッジ教授
https://twitter.com/tadanoossan2/status/1286229063019843584

https://twitter.com/tadanoossan2/status/1286229063019843584
<注>ゼロサム「赤の女王」・・・「赤の女王」は、ホッブス・リヴァイアサンを「自然・政治・経済・社会・文化」の全般にわたり作用する不可避の共通原理と見なす考え方https://twitter.com/tadanoossan2/status/1283584860313882624

https://twitter.com/tadanoossan2/status/1283584860313882624
(追記)赤の女王、https://toxandoria.hatenadiary.jp/entry/2020/06/04/155449
・・・そもそも、「赤の女王」とはルイス・キャロルの小説『鏡の国のアリス』に登場する人物であり、彼女が作中で発した「その場にとどまるためには全力で走り続けなければならない(It takes all the running you can do, to keep in the same place.)」という台詞から、種・個体・遺伝子が生き残るためには進化し続けなければならないことの比喩として用いられている。

・・・「赤の女王」は、ホッブス・リヴァイアサンを「自然・政治・経済・社会・文化」の全般にわたり作用する不可避の共通原理と見なす考え方(『自由の命運 上、下: 国家、社会、そして狭い回廊』(早川書房)の著者、ダロン・アセモグルと ジェイムズ ・A. ロビンソンによる)。それを放置すればゼロサム化するのが必然なので、これに薄皮一枚で必死に抗いつつ生き続ける全生命の一環たるヒト(の社会)でも、必然的に永続的な薄皮一枚の「この意味での努力」の持続が厳しく求めらている。
●The Eastern Origins of Western Civilization, John M.Hobson,(Cambridge U P)によれば、中国の思想と概念がケネーに影響を与えた可能性が高い。ケネーは欧州での孔子・老子ら研究の第一人者でもあったので レッセ・フェール、laissez-faire(仏ケネー → 英アダム・スミス)の命名が、この老荘の「無為自然」に啓発されたとも考えられる。https://books.google.co.jp/books/about/The_Eastern_Origins_of_Western_Civilisat.html?id=KQN85hrJyT4C&redir_esc=y

●無為自然・・・儒教の仁義(人徳)中心主義や形式主義に対して唱えられた老荘思想の対立的な概念をいう。《老子》の無をもって天地万物の根幹たるものとする思想からすれば、無為自然こそが万物の本体となる。出典:平凡社百科事典マイペディア、https://kotobank.jp/word/%E7%84%A1%E7%82%BA%E8%87%AA%E7%84%B6-640764

(参考)
●異論は与党から出たのが米国だった!とは、バカアベ日本と同じくバカトラに圧倒!の無様なだけのことでは?w →米、対中は議論なき総意!米の究極の強みは危機においてこそ侃侃諤諤の議論アリだったこと!中国マターでは其の静けさに不安を感じる!ジャン・ガネシュ722日経、https://twitter.com/tadanoossan2/status/1286385897777164290

https://twitter.com/tadanoossan2/status/1286385897777164290
・・・
The Eastern Origins of Western Civilisation
https://books.google.co.jp/books/about/The_Eastern_Origins_of_Western_Civilisat.html?id=KQN85hrJyT4C&redir_esc=y
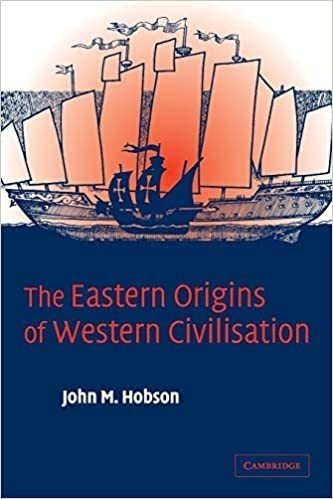
John M. Hobson, Professor John M Hobson
Cambridge University Press, 2004/06/03 - 376 ページ
4 レビュー
This book challenges the ethnocentric bias of mainstream accounts of the 'Rise of the West'. John Hobson argues that these accounts assume that Europeans have pioneered their own development, and that the East has been a passive by-stander. In contrast Hobson describes the rise of what he calls the 'Oriental West'. He argues that Europe first assimilated many Eastern inventions, and then appropriated Eastern resources through imperialism. Hobson's book thus propels the hitherto marginalised Eastern peoples to the forefront of the story of progressive world history.
・・・
著者について (2004)
John M. Hobson is a Senior Lecturer in Government and International Relations at the University of Sydney. He is the author of The State and International Relations (2000), The Wealth of States: A Comparative Sociology of International Economic and Political Change (1997), and co-author (with Linda Weiss) of States and Economic Development: A Comparative Historical Analysis (1995).
John M. Hobson is a Senior Lecturer in Government and International Relations at the University of Sydney. He is the author of The State and International Relations (2000), The Wealth of States: A Comparative Sociology of International Economic and Political Change (1997), and co-author (with Linda Weiss) of States and Economic Development: A Comparative Historical Analysis (1995).
書誌情報

書籍名
The Eastern Origins of Western Civilisation
ACLS Humanities E-Book
著者 John M. Hobson, Professor John M Hobson
版 イラスト付き, 再版
出版社 Cambridge University Press, 2004
ISBN 0521547245, 9780521547246
ページ数 376 ページ
