
襖がギシギシして動かない問題を解決しよう!スムーズな開閉のための簡単対処法を紹介
襖がギシギシして動かなくて困った経験はありませんか?「開け閉めが重くてイライラ」「家族みんなが使うから、なんとかしたい!」そんな声をよく聞きます。
実は、襖がスムーズに動かなくなるのは、経年劣化や鴨居の歪み、戸車の摩耗などが原因で起こることが多いんです。でも安心してください!この記事では、誰でも簡単に試せる方法から、長持ちする解決策まで詳しくお伝えします。ぜひ一緒に、スムーズな開閉を取り戻しましょう!
※最終更新日2025年1月

この記事のポイント
襖が動かなくなる原因をわかりやすく解説
湿気やゴミ、鴨居の歪みなど、よくあるトラブルの原因がスッキリ理解できます。家庭でできる簡単な対処法を紹介
ロウソクやスプレーを使った改善法から、鴨居ジャッキの使い方まで詳しく解説します。プロを頼るべきタイミングと選び方を解説
自分で直せない場合の相談ポイントや、信頼できる業者の見極め方をお伝えします。再び襖が動かなくならないための予防策もバッチリ
定期的なお手入れ方法や、トラブルを未然に防ぐアイデアをまとめました。

▼Amazonのアソシエイトとして前田畳店は適格販売により収入を得ています。
■襖がぎしぎし動かない原因とは?
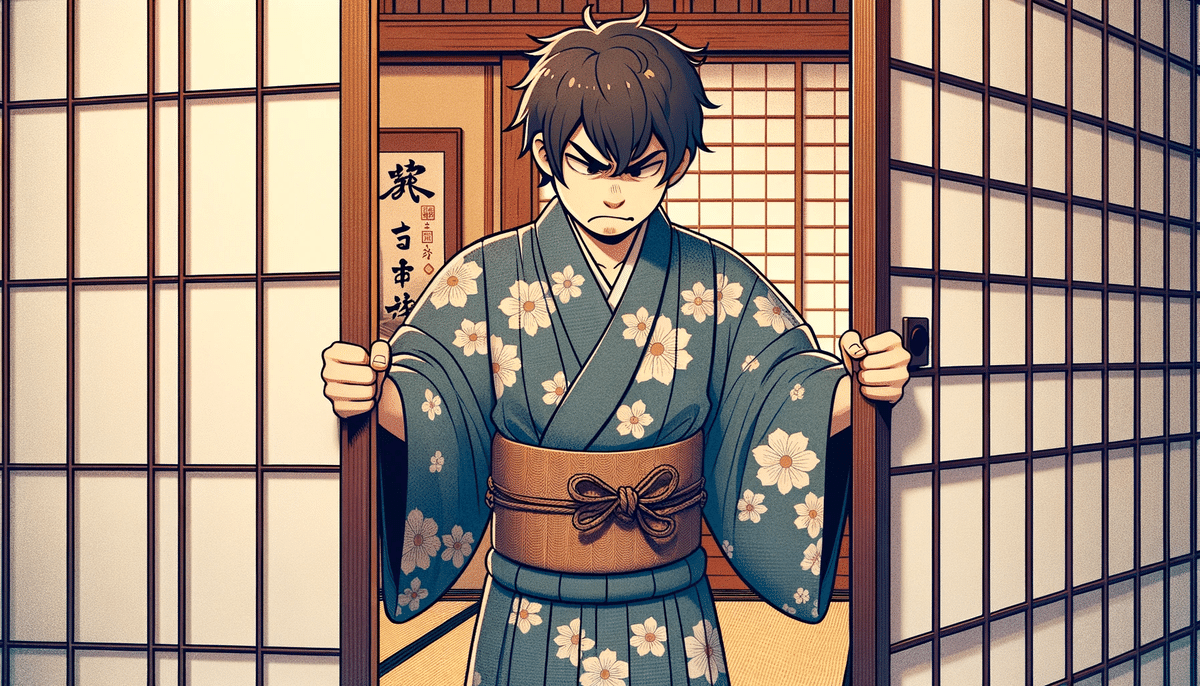
まず結論から言います、襖がぎしぎしと動かなくなる主な原因は、敷居や鴨居が下がってきたり、くるってきたり、溜まったゴミやホコリ、そして時間とともに進行する部材の劣化にあります。
主に、敷居や鴨居が下がるのがほとんどの原因と考えてください。
問題が解決しない場合は、専門家による修理や、場合によっては戸車など部品の交換が必要になることもあります。
襖が動かない問題は、多くの和室を持つ家庭でよく見られます。その主な原因をもう少し解説します。
ふすまの滑りが悪くなる一般的な原因

まず、襖の滑りが悪くなる最も一般的な原因は、敷居や鴨居が下がったり、くるったり、溜まったゴミやホコリなどです。
ゴミが襖と敷居の間に挟まり、滑りを悪化させます。ゴミなどで建付けが悪い場合には、定期的な掃除でこの問題は簡単に解決できます。
お掃除をする暇もない方がいるかと思います。そんな時はプロのハウスクリーニング業者に頼むのもひとつの方法です。私の書いた記事があります。リンクを下記に貼っておきますので、よろしければご覧ください。
▼前田畳店ライブドアブログ
■襖が動かない!鴨居の垂れ下がりについての詳しい説明
鴨居が垂れ下がる理由は、建物の構造的な要因や経年劣化による影響が大きいです。鴨居とは、和室の建具を支える上部の溝付き木材のことで、通常は敷居と組み合わせて建具の滑りを助けます。しかし、鴨居は天井下に設置されており、年月が経つにつれて重さや外的要因によって徐々に下がることがあります。
例えば、障子2枚分の幅(約180㎝)程度であれば、鴨居が下がる影響は比較的小さいですが、障子4枚分(約3.6m)の幅になると、中央部分が自重によって下がりやすくなります。このような状況を防ぐために、大工は鴨居の中央に「吊り束」という角材を設置することがあります。
吊り束は鴨居を支える役割を果たし、垂れ下がりを防ぎます。しかし、吊り束が設置されていない場合や、設置されていても建物の劣化が進んでいる場合には、鴨居は次第に下がってしまうことがあります。
さらに、鴨居が下がる原因として以下のような要因が挙げられます。
木材の特性による影響
木材は湿気や乾燥などの環境変化により、収縮や膨張を繰り返します。この過程で木材に歪みやたるみが生じ、鴨居が下がる原因となります。特に、日本のような四季のある気候では、湿気が多い夏や乾燥する冬が木材にストレスを与え、変形を加速させることがあります。地盤沈下や建物の傾き
建物が建てられている土地の地盤が軟弱だった場合、時間の経過とともに地盤沈下が起こり、建物全体が傾くことがあります。この影響が鴨居にも及び、ゆがみや垂れ下がりを引き起こします。施工時の不備や設計の問題
家の建築時に、大工が鴨居の設置に適切な処置を施さなかった場合、長期間にわたる使用で鴨居が下がりやすくなります。たとえば、吊り束の強度が十分でなかったり、鴨居を支える部材が不足していたりすると、時間とともに負荷に耐えられなくなることがあります。建物の老朽化
建物が古くなると、木材が腐食したりシロアリの被害を受けたりして、鴨居を支える力が低下します。この結果、鴨居が下がりやすくなり、建具の動きにも影響を与えます。

このように、鴨居が下がる現象はさまざまな要因が重なって起きるため、早めの点検や修理が重要です。また、問題が発生した場合には、鴨居や建具の調整で対応できる場合と、大掛かりな修繕が必要な場合があるため、状況に応じた対処が求められます。
時間と使用による劣化の影響

また、襖紙の劣化や戸車の摩耗も原因です。長年の使用により、戸車もスムーズな動きを失います。これらの部品の交換や修理が必要になることがあります。
これらの原因を把握することで、襖がぎしぎし動かない問題に対処するための第一歩を踏み出せます。次の章では、これらの問題に対する簡単な対処法を見ていきましょう。
▼こちらの有料記事が好評を得ています
■襖が動かない場合の簡単な対処法

襖がぎしぎしと動かない時、いくつかの簡単な対処法があります。これらの方法は、特別な工具や高度な技術を必要とせず、ご自宅で試すことができます。
まず、襖や障子を外そう!
襖が外れなくなった場合、専用の鴨居ジャッキを使って安全かつ効率的に外す方法があります。ただしジャッキがない方がほとんどだと思うのでない時にはどうしたら良いのか先に解説します。
まず、作業を始める前に、作業スペースを確保し、周囲の障害物を片付けます。そして、襖の周囲を確認して、外れない原因を特定します。多くの場合、木材の変形や収縮が原因です。
建具の引っかかっているところは主に、建具の上部です。左右どちらかにスライドして外せれば外しましょう。外せなければ、鴨居ジャッキを使うと言う事になります。

専用の鴨居ジャッキはいくつか種類がありますが、おおむね使い方は皆同じですので、それほど迷う事なく使えるかと思います。
注意点は外れない襖はどちらか左右に寄せて、ジャッキを衝立てましょう。
ハンドルを回して徐々にゆっくりと回しましょう。いきなり力強く回すと鴨居や敷居が壊れる時があります。
目安としては少しだけ、ピキっとかミシッとか音が鳴ったところでいったんストップして外してみましょう。左右どちらかによせて具合の悪い方では外せないので、それでも外れない場合には、今度は逆に寄せてジャッキを衝立て同じように繰り返します。
それでも外せない場合には、再度ジャッキのハンドルを回して圧力をかけると言う事になりますが、少しづつジャッキアップして様子見ながら外す作業を繰り返します。
私の経験上、ジャッキアップで外れない事はほとんどありません。もし外せない場合にはジャッキが悪いのではなしに、やり方が悪いので再度チャレンジしてみてください。
ただし!回し過ぎ、力の入れ過ぎには注意です。適度な力加減を保ちましょう。
▼Amazonのアソシエイトとして前田畳店は適格販売により収入を得ています。
鴨居ジャッキはこれでなければいけない!と言う事はありませんが、一般的に安くてレビューも良い商品です。ご検討してみてください。
■襖が動かない!ジャッキ以外で鴨居の持ち上げよう
専用の鴨居ジャッキがない場合でも、家庭にあるもので工夫して鴨居を持ち上げる方法があります。ここでは、木材やかまぼこ板などの身近な道具を使った代替手段について詳しく説明します。この方法は、鴨居が軽度に垂れ下がっている場合に特に有効です。
まず、使用する道具として太めの木材を準備します。この木材は、敷居から鴨居までの距離よりやや短い長さに切る必要があります。長すぎると設置が難しく、短すぎると力が十分に伝わりません。木材が直接鴨居や敷居に当たると傷がつく可能性があるため、その保護のために「かまぼこ板」や厚みのある古本などを緩衝材として使います。
作業を始める前に、鴨居と敷居を清掃し、木材や板をしっかり固定するためのスペースを確保してください。次に、準備した木材を鴨居の中央部分の真下に設置します。この際、木材の上下にかまぼこ板や古本を挟み、木材が鴨居や敷居に直接触れないようにします。これにより、傷つくことを防ぎながら、適切に力を分散させることができます。
木材を設置したら、トンカチやハンマーを使って木材を少しずつ斜めに立てかけるように固定します。この角度調整が重要で、木材が垂直に近い状態だと十分な力を発揮できず、逆に斜めすぎると滑ってしまう可能性があります。最初は垂直に近い角度から始め、徐々に調整して木材が鴨居を持ち上げる力を発揮するようにします。
鴨居が少しでも持ち上がったら、障子や襖が動くか確認してください。もし動きが改善されなければ、木材の位置を微調整するか、別の箇所で再度試してみます。この方法は専用ジャッキほどの強い力は期待できませんが、軽度の垂れ下がりには効果的です。

また、この方法を試す際には無理に力を入れず、壁や鴨居自体に過剰な負荷がかからないよう注意してください。特に、木材やかまぼこ板が割れる恐れがある場合は、別の代替材料(ゴムマットやカーペットの切れ端など)を検討してください。安全を確保しながら、少しずつ作業を進めることが重要です。
この代替手段は、専用の道具を使わずに手軽に試せる方法ですが、大きく垂れ下がった鴨居や古い建物では効果が薄い場合もあります。その際は、プロに相談することを検討してください。
さて、建具を外した!次は削ってみよう!

ここまでおそらく建具は外せた?かと思います。次は鋸やカンナで削ってみようという章となります。
まず大前提として、賃貸の場合には必ず大家さんと相談してから行うようにしましょう。
下記の画像、こちらは押入れの戸襖の裏側から見たもので、上下が逆になっていますのでご注意ください。見えているのが上部の上桟です。
襖や障子がスライドできずにきつい場合、襖の上桟(うわざん)の赤い部分がひっかかっている状況がほとんどです。ゆえに赤線のようにきつい所をカンナで削ってあげればそれで大丈夫です。
カンナは日曜大工の物や学校の授業で習った本当に簡単なカンナで大丈夫です。

▼Amazonのアソシエイトとして前田畳店は適格販売により収入を得ています。
高いカンナや電動系の奴は必要ありません。この2つで十分すぎるので、大丈夫です。これも別にこのカンナ!と言う事はないので、似たようなもので十分です。
ただし安すぎるカンナは気を付けましょう!
ケズリ方は分かるかと思います。
注意するのはケズリ過ぎない事です。1mm、2mmくらい削っても十分すぎるほど建付けは良くなりますので、センチ単位では絶対に削らないでください。
■襖が動かない時!削り作業のポイントと注意点
鴨居が下がり、障子や襖がスムーズに動かない場合、建具の上桟を削ることで改善することがよくあります。
この作業は、障子や襖が鴨居の溝に適切に収まるようにするもので、削る厚さや手順をしっかり把握して行えば効果的です。ただし、削りすぎや不適切な工具の使用には注意が必要です。以下に、削り作業の具体的なポイントや注意点を詳しく説明します。
削り作業を始める前に、どの部分を削る必要があるかを確認することが重要です。基本的には建具の上桟(うわざん)の上側が鴨居に引っ掛かるため、この部分を削ることが一般的です。削る前に障子や襖を外し、鴨居の溝と建具の上桟をよく観察してください。特にどこが引っ掛かっているのか、どのくらい削れば良いかを視覚的に把握するために、鉛筆で削るべき部分に印をつけておくと作業がスムーズに進みます。
削る厚さは慎重に設定する必要があります。いきなり大きく削るのではなく、まずは1~2㎜程度から始めるのが基本です。一度削りすぎると元に戻すことはできません。そのため、少しずつ様子を見ながら調整するのが失敗しないコツです。もし隙間がほとんどない場合や鴨居の垂れ下がりが大きい場合でも、一度に削る厚さは3㎜程度にとどめ、必要に応じて作業を繰り返してください。

削る際には、適切な工具を使用することが大切です。最も基本的な工具はカンナです。カンナは木材を均一に削るための工具で、初心者でも扱いやすい替え刃式のカンナを使用すると良いでしょう。
また、小型のミニカンナや「脇キワカンナ」など、細かい部分を削るための工具も便利です。さらに、ノコギリは上桟の両端や角の出っ張りを切る際に役立ちます。特に引き切りタイプのノコギリは初心者でも使いやすく、正確なカットが可能です。削った後の仕上げには木工用の細目ヤスリを使用すると、表面が滑らかに整います。
作業中は、削る部分がまっすぐになるよう注意を払います。削る範囲を鉛筆でマーキングしたら、定規を当てて平らかどうかを確認しながら削っていきます。削りすぎを防ぐために、削りたい部分を鉛筆で塗りつぶしておくのも効果的です。削りながら何度も鴨居にはめて確認し、必要以上に削らないよう慎重に作業を進めます。
さらに、削った部分の角を滑らかに仕上げる「面取り」作業も忘れてはいけません。削った角が鋭いままだと、障子や襖を動かす際に引っ掛かりやすくなるだけでなく、木材が欠ける原因にもなります。面取りは、ノミやヤスリを使って削った部分の角を45度の角度で削り、滑らかに整える作業です。この工程を行うことで、建具の耐久性が向上し、滑らかな動きが確保できます。

また、作業環境の整備も重要です。削りカスが大量に出るため、掃除しやすい場所で作業を行いましょう。必要に応じてマスクやゴーグルを着用し、木屑の吸い込みや目への飛散を防ぐようにします。作業台や建具をしっかり固定し、不安定な状態で削らないよう注意してください。
最後に、削り作業が終わったら削り残しがないかを確認し、建具を鴨居にはめて動作をチェックします。動きがスムーズになれば作業完了ですが、まだ引っ掛かる場合は再度少しずつ調整してください。削り作業は一見難しそうに思えますが、慎重に進めれば初心者でも十分に実施可能です。正確な作業と適切な道具の使用を心がけ、必要に応じてプロに相談することも視野に入れておきましょう。
ここまでは、かなりきつく、襖や障子がスライドできないと言った比較的に重症レベルの時の完治法でしたが、そんな事せずとも、軽症の場合にはもっと簡単に直す方法がありまのでこれから解説します。
▼あわせて見たい
■襖が動かない時!ロウソクとスプレーを使った滑り改善法
ロウソクを使った方法は、非常に古典的でありながら効果的です。敷居や鴨居にロウソクの蝋を塗ることで、襖の滑りを改善できます。また、専用のスプレーを使用して、滑りをよくすることも可能です。これらの方法は、襖と敷居の間の摩擦を減らし、スムーズな開閉を実現します。
▼Amazonのアソシエイトとして前田畳店は適格販売により収入を得ています。
敷居と鴨居の掃除と修理
敷居や鴨居に溜まったゴミやホコリを定期的に掃除することも、襖の動きを改善する重要な方法です。また、歪みが原因である場合は、専門家による修理が必要になることもあります。しかし、軽度の歪みであれば、先ほども解説しましたが、自宅で簡単な調整を行うことも可能です。
戸車の交換方法
戸車が摩耗している場合は、新しいものに交換することで襖の動きが大幅に改善されます。戸車の交換は比較的簡単で、DIYが可能なレベルです。交換に必要な工具や部品は、ホームセンターや専門店で手に入れることができます。
これらの対処法を試すことで、多くの場合、襖がぎしぎしと動かない問題を解決することができます。しかし、これらの方法でも改善されない場合は、長期的な解決策を考える必要があります。次の章では、そういった場合の対応について解説します。
▼前田畳店 ブロガーブログ
■襖が動かないのを直した後の再設方法
障子や襖を削る作業が完了した後、建具を鴨居と敷居に再設置する必要があります。この再設置は、単に元に戻すだけでなく、正しい手順とルールに従うことで、建具がスムーズに動き、見た目も美しく仕上がります。ここでは、再設置の具体的な手順や注意点について詳しく説明します。
まず、再設置を始める前に、鴨居と敷居の溝を清掃します。削り作業や経年で溝にたまった埃や木屑は、建具の滑りを妨げる原因となります。乾いた布や掃除機を使って、しっかりと溝をきれいにしましょう。特に敷居にはゴミが溜まりやすいため、重点的に掃除します。
清掃が終わったら、建具を持ち上げて再設置に取り掛かります。この際、障子や襖の重さを分散するため、両手を使って水平に持ち上げることが重要です。建具を斜めに持つと、鴨居や敷居に傷をつけたり、建具が溝にはまりにくくなる原因になります。
再設置の基本ルールとして、障子や襖を「上から下へ」とはめ込むことを守りましょう。まず、建具の上桟を鴨居の溝に入れます。建具を少し傾けると、上桟が溝にスムーズに収まります。次に、建具の下桟を敷居の溝に軽く押し込むようにして設置します。このとき、力を入れすぎないよう注意してください。強引に押し込むと、建具や溝を傷める可能性があります。
再設置する際は、障子や襖の順序にも気を付ける必要があります。一般的なルールとして、2枚引き戸の場合、右側が手前に来るように設置します。たとえば、押し入れの2枚引き戸なら、左側の襖を奥に、右側の襖を手前に納めます。これにより、開閉がスムーズになり、建具同士のぶつかりや傾きを防ぐことができます。

4枚引き戸の場合は、中央の2枚が手前に来るように設置するのが基本です。両端の襖は奥に配置します。この配置は、見た目の整然さだけでなく、建具同士が引っ掛かりにくくなるメリットもあります。
また、4枚引き戸で中央に柱がある場合は、柱を基準に左右それぞれ2枚ずつ設置し、右側が手前に来るようにします。これにより、左右のバランスが保たれ、開閉時の安定感が向上します。
建具をはめ込んだ後は、しっかりと動作確認を行います。障子や襖をゆっくりと左右に動かし、スムーズに滑るかを確認します。もし途中で引っ掛かる箇所があれば、鴨居や敷居の溝にゴミが残っていないか再度確認してください。それでも改善しない場合は、削りが足りない可能性があるため、もう一度建具を外して調整します。

最後に、建具の位置や高さを微調整します。襖や障子は、設置後に左右の高さが揃っていないと見た目が悪くなるだけでなく、動きが悪くなる原因にもなります。特に襖の場合、左右の引き手が一直線になるよう高さを調整してください。この作業は、建具を鴨居の溝で少し上下に動かすだけで簡単にできます。
再設置作業は、正しい手順と慎重な作業を心がけることで、建具が美しく機能的に仕上がります。また、正しい順序で設置することで、和室全体の見栄えや使いやすさも向上します。建具が滑らかに動き、部屋の雰囲気が整うことで、より快適な空間が作り出せるでしょう。
■プロに依頼するタイミングと選び方
障子や襖の問題を自力で解決しようとしても、解決が難しい場合があります。このようなとき、無理に対処せずプロに依頼することで、問題をスムーズに解決できる可能性が高まります。以下では、プロに頼るべきタイミング、費用感(あくまで目安)、そして信頼できる依頼先の選び方について詳しく説明します。
プロに依頼するタイミング
建具が外れない、動かない場合
鴨居や敷居に建具が完全に引っ掛かり、自力で外せないときはプロに相談するのが最適です。特に、鴨居の垂れ下がりが大きい場合や、専用工具(鴨居ジャッキなど)が必要な場合には専門家の介入が必要です。鴨居や敷居が大きく歪んでいる場合
鴨居や敷居自体に歪みが生じ、建具の調整だけでは解決しない場合には、木材の修繕や補強が必要です。これには専門的な技術が必要になるため、プロに依頼するべきタイミングです。削りや調整がうまくいかない場合
自分で削ったり調整しても効果が見られない、もしくは削りすぎてしまった場合にはプロに相談してください。プロは適切な工具と技術を駆使して問題を修正します。建具が古く、全体的に劣化している場合
障子や襖の木枠が反っていたり、戸車が壊れていたりするなど、建具自体が劣化している場合には、修理だけでなく張り替えや交換が必要になることがあります。プロに相談することで適切な判断が可能です。建物全体に問題がある場合
鴨居や敷居だけでなく、建物の傾きや地盤沈下が影響している場合には、建具職人に加え、大工や建築業者の力が必要になるケースもあります。
プロに依頼する際の費用感(目安)
障子や襖の削り・調整
1枚あたり 4,000~12,000円程度。作業の複雑さや地域によって異なります。障子や襖の張り替え
1枚あたり 3,500~16,000円程度。使用する素材(和紙、ビニール障子紙など)やデザインによって価格に幅があります。鴨居や敷居の補修
8,000~55,000円程度。歪みの程度や補修範囲が広いほど高額になります。建具の新調
1枚あたり 18,000~60,000円程度。特注の場合や高級素材を使用する場合はさらに高額になることがあります。
費用を抑えるためには、複数の業者から見積もりを取り、作業内容や価格を比較するのがおすすめです。また、見積もりが無料であるかを確認することも重要です。
信頼できる依頼先の選び方
経験と専門知識のある業者を選ぶ
障子や襖の調整、鴨居や敷居の修繕は専門的な技術が必要です。建具や和室の修理に特化した職人や業者を選ぶことで、仕上がりの満足度が向上します。公式ウェブサイトやレビューを参考にすると、実績を把握しやすくなります。地元の業者を優先する
地元密着型の業者は迅速な対応が期待できるだけでなく、交通費や出張費を抑えられる場合があります。また、その地域特有の建築様式に詳しいため、適切な提案を受けられる可能性が高いです。口コミや紹介を参考にする
実際に利用した人の口コミや評価を確認するのは、信頼できる業者を選ぶ際に役立ちます。また、知人や家族の紹介を受けると、事前に業者の評判を知ることができ、安心して依頼できます。明確な見積もりを取る
作業内容や費用について、事前に詳細な見積もりを出してもらうことが重要です。見積もり内容が不明瞭な業者や、追加費用が発生しやすい業者は避けたほうが良いでしょう。アフターサービスの有無を確認する
修理後に問題が発生した場合に対応してくれるか、アフターサービスがあるかを確認してください。信頼できる業者は、作業後のフォローにも力を入れています。対応のスピードを重視する
すぐに解決が必要な場合、緊急対応が可能な業者を選ぶのもポイントです。特に地元密着型の業者は、迅速な対応が期待できます。
プロに依頼するメリット
プロに依頼することで、自分では対応できない難しい作業を確実に解決してもらえます。また、見た目の仕上がりや耐久性も向上し、今後のトラブルを防ぐことができます。さらに、プロは状況を適切に判断し、必要に応じて建具の調整だけでなく建物全体の修繕も提案してくれるため、長期的な安心感が得られます。
自力での修理が難しい場合は、無理をせずにプロに相談しましょう。適切なタイミングで信頼できる業者に依頼することで、スムーズに問題が解決し、快適な和室環境を取り戻すことができます。
■襖が長期的に動かない時の解決策とプロへの依頼
襖がぎしぎし動かない問題に対して、短期的な対処法では解決しない場合、長期的な解決策を検討する必要があります。特に、大きな歪みがある場合や、部品の劣化が激しい場合は、プロの力を借りることが賢明です。
▼前田畳店ライブドアブログ
リフォームと張り替えの選択
襖や和室全体のリフォームを検討することで、根本的な問題解決に繋がります。また、襖紙の張り替えも、部屋の雰囲気を一新し、襖の動きを改善する効果があります。張り替えは、見た目の美しさだけでなく、機能的な面でも大きなメリットがあります。
当店での支援とサービス
私たち前田畳店では、襖のリフォームや張り替えをはじめ、敷居や鴨居の修理、戸車の交換など、幅広いサービスを提供しています。プロとしての豊富な経験と知識を活かし、お客様の悩みを解決します。
継続的なメンテナンスの重要性
また、襖の問題を長期的に防ぐためには、定期的なメンテナンスが不可欠です。当店では、定期的な点検やメンテナンスサービスも行っており、襖の問題を未然に防ぎます。
長期的な解決策を検討する際は、自分でできる範囲と、プロに依頼するべき範囲を見極めることが大切です。襖がぎしぎしと動かない問題にお悩みの方は、ぜひ当店までご相談ください。
襖がぎしぎしと動かない問題は、多くの日本家屋で見られる一般的な悩みです。この記事では、その原因として、敷居や鴨居の汚れ、戸車の摩耗、部品の劣化などを挙げ、それぞれに対する簡単な対処法から、長期的な解決策、プロへの依頼に至るまでを解説しました。
日常的なメンテナンスと適切な対処法を実践することで、多くの場合、襖の問題は改善されます。しかし、問題が解決しない場合や、より根本的な改善を求める場合は、リフォームや張り替えなどの長期的な解決策を検討し、必要であればプロの力を借りることが大切です。
私たち前田畳店は、襖のリフォームやメンテナンス、張り替えなど、和室に関するあらゆる問題に対応しています。襖の問題でお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。長年の経験と専門知識を持つプロフェッショナルが、あなたの悩みを解決へと導きます。
そして、快適な和室での生活を取り戻しましょう。襖がスムーズに開閉することで、毎日の生活がより快適になること間違いありません。
■襖がギシギシして動かない問題を解決しよう!スムーズな開閉のための簡単対処法を紹介の総括
✅ 鴨居の垂れ下がりは、湿気や乾燥、地盤沈下、施工不備、老朽化など複数の要因が重なって発生する。
✅ 鴨居ジャッキを使用すると、障子や襖の取り外しがスムーズになることが多い。
✅ ジャッキがない場合は、木材やかまぼこ板などを使って鴨居を持ち上げる方法が有効である。
✅ 障子や襖の上桟を削ることで、スムーズに動くよう調整が可能。削り作業は少しずつ進めることが大切。
✅ カンナやノコギリを使った削り作業では、適切な工具の選択と安全対策が必要。
✅ 削った部分の角を滑らかに仕上げる「面取り」作業が、建具の耐久性と動きを向上させる。
✅ 再設置時は、溝を清掃し、建具を「上から下へ」と正しい手順で取り付けることが重要。
✅ 2枚引き戸や4枚引き戸では、襖の設置順序にルールがあり、順守することで動作が安定する。
✅ ロウソクや専用スプレーを使うと、摩擦が減り襖がスムーズに動くようになる。
✅ 敷居や鴨居の掃除や戸車の交換も、建具の動きを改善するための効果的な方法である。
✅ プロに依頼するタイミングは、鴨居の歪みが大きい場合や、自力で調整できないとき。
✅ 専門業者を選ぶ際は、経験、口コミ、明確な見積もり、アフターサービスの有無を確認することが大切。
✅ 日常的なメンテナンスを行うことで、襖や障子のトラブルを未然に防ぐことができる。
✅ 問題が解決しない場合は、リフォームや張り替えといった根本的な解決策を検討すべきである。
---------------------------------
【前田畳店の紹介】
盛岡で創業60年の信頼と実績!
たたみ、ふすま、しょうじ、カベ紙、アミ戸の張替えリフォームは
畳製作技能士一級・畳訓練指導員、壁装技能士1級、2級在籍の
前田畳店・インテリアマエダ
【お問い合わせ】
岩手県盛岡市天昌寺町9-16
019-647-3555
営業時間:9時~17時
(土曜日は15時頃まで)
定休日:日曜日
m.masa.tatami@gmail.com
お急ぎの方はメールかLINEでどうぞ
★お仕事のご相談ご依頼はLINEお友達登録からがお得で便利!
初回5%OFF↓↓ 前田畳店公式LINE

https://lin.ee/iZMItdH
スマホから「アプリで開く」を押してください。
ホームページ http://www.eins.rnac.ne.jp/~maeda-t
▼リフォーム価格表はこちら
・ライブドアブログ
https://www.tota100.com
・noteブログ
https://note.com/tota100
・インスタグラム
https://www.instagram.com/totalinterior_m/
・ほぼ毎日更新 スタンドエフエム
https://stand.fm/channels/5ff42a521f63b1cf68803d8e
★壁紙の張り替えご検討中の方はこちら
https://o6b1m.hp.peraichi.com
★襖・障子の張り替えご検討中の方はこちら
https://6k6k5.hp.peraichi.com
★畳替えをご検討中の方はこちら
https://77yvg.hp.peraichi.com
▼あわせて読みたい当店のライブドアブログ
