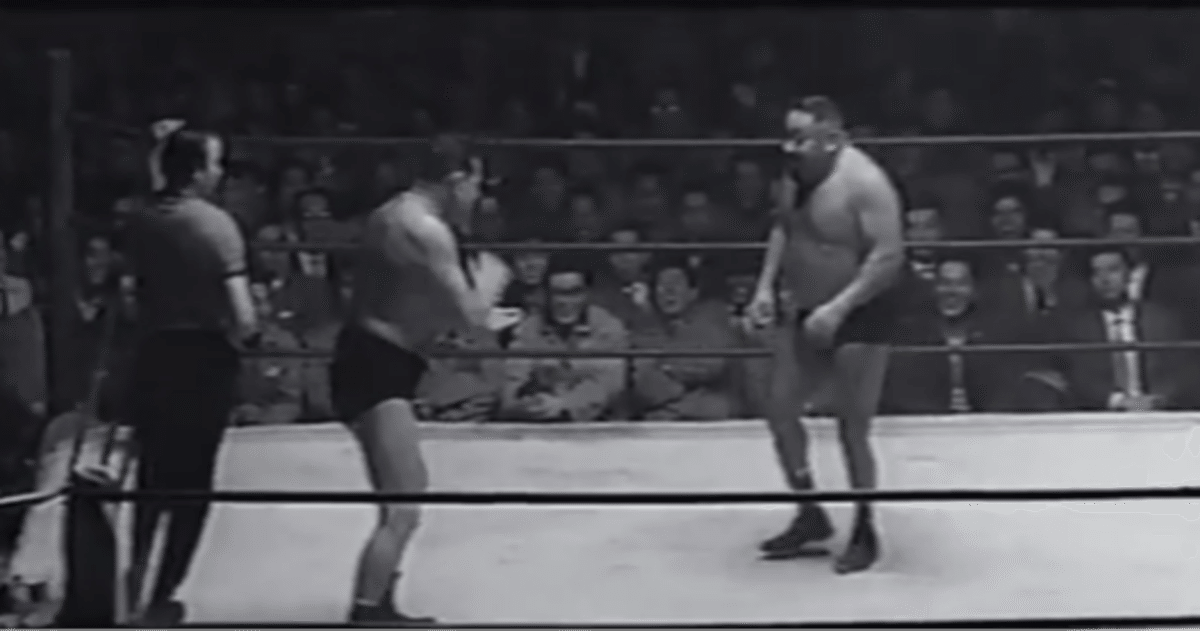
プロレス・スーパーヒーロー列伝 デューク・ケウェセキ編 【短編小説】
のちにデューク・ケウェセキ(川崎)として知られるワン・タオソンが生まれたのは1916年4月のハワイ、オアフ島のことであった。父親は中国からの移民で、サトウキビ畑で働く労働者であり、母親は日系一世の女性だった。当時のハワイには日本や中国などアジアからやって来た移民が数多く暮らし、最下層の仕事をこなして生計を立てていた。タオソンの父親も中国の香港近郊の小さな村からアメリカ本土に渡ったが、サンフランシスコ一帯での中国人排斥運動に身の危険を感じてハワイに移った。そこで沖縄から来ていた日本人女性と恋に落ち、周囲の大反対にも関わらず二人は結婚した。
「子供の頃の家には様々な言語が飛び交っていた」とデューク・ケウェセキは子供時代を回想してこう語っている。「中国系の移民は同郷の者だけで固まって他の民族とは混じり合わないイメージがあるが、僕の家族はそんなことはなかった。父は日本語が、母は広東語が話せなかったので、家の中は基本的には英語が公用語だった。でも僕は中国系とも日系の子供とも遊んだから、自然に三つの言葉を覚えたんだ」
十歳の頃まで、彼の家族はとても裕福とは言えない暮らしぶりだったが、父親の兄がはじめた食堂が忙しくなり、タオソンの父親も農場での仕事をやめて兄の食堂を手伝うことになった。父親に料理の経験はなかったので、給仕としての仕事が主だった。タオソンと二人の妹が成長し、子育てが一段落ついた母親も夫と一緒に働くことになったが、このことが一家の運命を大きく変えることになる。
食堂はオアフ島ホノルルのチャイナタウンの中にあり、客層ももっぱら中国系の移民たちであった。良心的な値段とオーダーした料理が出てくる早さが売りの、労務者向けの食堂だった。タオソンの母親は広東語がほとんど話せなかった。簡単な挨拶やメニューは覚えたものの、容姿だけでは中国系と見分けがつかない彼女は、一日の仕事を終えて腹を満たしにやって来た中国系の人々から掛けられる声にすっかり参ってしまった。母親は英語を身につけるのにも苦労したほどに語学のセンスがなかったので、騒がしく喋り合っている華人の中に身を置いているとそれだけで寂しさを抱いた。また兄の息子たちも成人して食堂の手伝いを始めたこともあり、タオソンの両親は自分たちの店を構えることにした。しかし今度はチャイナタウンの安食堂ではない。オアフ島のメインストリートの外れ、ワイキキビーチの近くに少し高級感を漂わせたチャイナレストランをオープンさせたのだ。スタッフや料理人は中国系だったものの、開店資金のほとんどは母親の一族から出資を受けたので、母親が新しい店のオーナーになった。この「ドラゴンナイト」は中華風ナイトクラブ的な佇まいが受けて繁盛した。客は主に白人の裕福層であり、彼らの中国趣味を満足させるには充分の料理とナイトライフを提供したことにより、三年後には二号店を出すまでにヒットした。こうしてタオソンが高校生になる頃には一家は事業に成功した金持ちアジア人としてホノルルで認知されるまでになった。
高校生になったタオソンも両親が若かった頃とは大違いの、恵まれた青春を謳歌していた。高校には自家用車を自ら運転して通い、勉強はそこそこだったもののレスリングとフットボールに熱中した。彼は父親に似た大きく壮健な身体つきであり、喧嘩も強かった。当時のハワイは人種の混じり合いが顕著で、アジア系も大きなボリュームを占め、アメリカ本土よりはるかに人種差別は少なかった。しかし、まったくなかったわけではない。金持ちであり、スポーツも優秀だったタオソンはそれだけで目をつけられやすく、ドイツ系白人のガールフレンドと付き合い出したこともなおさら悪目立ちさせた。タオソンが18歳の時、学校の駐車場で事件は起きた。以前からタオソンを快く思っていなかったガールフレンドの兄のグループから私刑を受けた。きっかけも、理由も、映画のような勇ましい切り口上もなく、いきなり七、八人の若者に取り囲まれて殴りつけられた。
タオソンは殴り返さなかった。しかし地面にしっかりと立ち、決して倒れなかった。ガールフレンドの悲鳴が響き、業を煮やした一人がナイフを取り出して切りつけた。キラリと太陽光を反射する刀身を目にしてタオソンはとっさに避けたが、彼の頬からこめかみにかけての皮膚が切り裂かれ、血が噴き出した。出血の多さに驚いた白人たちは逃げ出したが、タオソンは自分で車を運転して病院に向かった。後の彼の記事にはデューク・ケウェセキの頬に残る傷は、彼のリングでの残虐非道ぶりに怒った観客に斬り付けられたもの、と紹介する記述が多いが、それは間違いである。
高校を卒業したタオソンは母のレストランで給仕として働きつつも、経営の一端を任されるようになる。調理場で働くコックの中には広東語しか話せない者も多かったので、彼のようなバイリンガル(実際にはトライリンガル)は必要不可欠だった。一方でまだ若く力の余っていたタオソンはボディビルに熱中した。当時は現在のようなトレーニング理論も栄養学も確立されていなかったが、ヘラクレスのような肉体美を求めて鍛錬に励む男性は少なくなかった。またドラゴンナイトの二つ隣のビルで営業していたジムは深夜遅くまで開いており、タオソンも同じビルの五階に部屋を借りて住むことにしたので不便はなかった。そんな若きタオソンが23歳の時に運命的な出会いがあり、彼の人生の歯車は狂い出していく。
ドラゴンナイトの常連客の一人にホノルルでの興業を取り仕切る大物プロモーターのポール・キーナンという男がいた。彼は以前から自分の興業で取り扱うスターたち、歌手やサーカス団員を持てなすのにタオソンの店を利用しており、若きタオソンとはすっかり顔馴染みであった。
「ようボーイ、相変わらず鍛えているかね?」その夜もレストランの一番奥の席に陣取ったキーナンは料理を運んできたタオソンに声をかけた。
「いらっしゃいませ、キーナンさん」とタオソンは言った。「ええ、鍛えてますよ。僕はこの店の用心棒でもあるんです」
「ひゃひゃ、用心棒かい、そりゃあいい」突き出た腹をダブルの背広で包んだキーナンは葉巻を手に、楽しそうに笑った。「しかしだボーイ、君は残念ながら田舎の小さな島の力自慢に過ぎないことを知るだろう、このボディ・マスターのショーを見ればわかる」
「ボディ・マスター?」タオソンはキーナンの向かいの席に座る男に目をやった。見たところ何の変哲もない中年男がポロシャツを着て腕を組み、椅子に浅く座っていた。ピンと伸びた背筋は力を漲らせた雰囲気があったが、決して鍛えられているようには見えない。腕の太さも自分の方があるぞ、とタオソンは思った。
「あまり若い人をからかうものではないよ、ミスター」男は口を開き、プロモーターに言った。
「彼のショーはホノルルでは初めてだ」とキーナンは言った。「何年も前からラブコールを送っていたんだが、やっと招聘に成功して私はご機嫌というわけだ」
「それよりもミスター、ジムの手配をお願いできないだろうか。飛行艇の中ではほとんど身体を動かせなかったんだ」
「ジムならこのすぐ近くにありますよ。夜中もずっと開いてます」
「そうか、それはよかった」と中年男は言った。「食事の後、利用させてもらおう」
デービー"ボディ・マスター"ホッジは現在のプロレスの世界からは完全に忘れ去られている。そもそも彼はプロレスラーではない。デューク・ケウェセキ、ブルーノ・カルネラといったレスラーにトレーニングを施したトレーナーであり、自身はPEショーの主役として全米を回っていた。PE(体育)ショーとはサーカスと見世物小屋の中間にあるような興業形態で、20世紀初頭から1950年代にかけて人気を博した旅回りのショーだった。屈強な男たちによる怪力自慢とアクロバットが主体の興業であり、ホッジは人間離れした力技で観客たちを魅了していた。全盛期の彼が行っていた技を写した写真が残っている。横に渡した二メートルの鉄骨の両端に椅子を載せてそこに二人ずつ女性が座り、そんな計四人の重量にも関わらず、ホッジが鉄骨の真ん中を片手で差し上げて支えている、というものだ。写真だけ見た人はおそらく何かのトリックがあると疑うだろうが、彼は実際にやってのけるほどの怪力の持ち主だった。その夜、ドラゴンナイトが閉店した後、ジムでホッジの技を目にしたタオソンも言葉を失った。ホッジはタオソンがいつも脚を鍛えるために肩に担いでいるバーベルを軽々と頭上に差し上げ、なおかつ片手でバランスを取って上下に動かした。自分よりはるかに大きな男が行うならまだしも、ホッジの体重はせいぜいミドル級だ。一時間に渡ってホッジのトレーニングを目の当たりにしたタオソンは思わず「僕を弟子にして下さい」と頼み込んでいた。
「いいだろう、若いの」とホッジはにやりと笑った。
ホッジのトレーニングは彼が独自に編み出した変則的なものだった。彼の理論の中核をなすのが「筋肉を鍛える前に骨と関節の強度をあげろ」というもので、そのためにとても動かせない高重量の負荷をかけて骨そのものにダメージを与えた。なおかつ一週間毎日激しく鍛えると、次の一週間は回復のためにトレーニングを休む、というメニューも考案していた。全米を興行して回るホッジがホノルルにやって来るのは数ヶ月に一度だったが、その間、タオソンは彼から授かったトレーニングメニューを一人もくもくとこなした。二年を過ぎる頃にはタオソンも自分の肉体が以前とまったく変わっているのに気づいた。体重は少し減り、身体つきも細くなったが、その肉体からほとばしり出るパワーは桁違いだった。太った酔っ払いは片手で担いで店の外に放り投げ、中華鍋を紙のように丸めた。またホノルルでのホッジのショーにはアシスタントとして出演し、ホッジの胸板に丸太をぶつけて折る役目も任されていた。(しかし素性を知られたくなかったので顔にはマスクを被った)。「彼との関係を一言でいうなら」とタオソンは後に語った。「トレーナーではないね。ホッジは日本語で言うセンセイだったよ」
しかし時代は1941年12月を迎えていた。日本軍がホノルルの軍港、パールハーバーに奇襲攻撃を仕掛けた朝、タオソンの人生の歯車はさらに狂う。アメリカ本土と違い、ハワイの日系人がキャンプに収容されることはなかった。しかし彼ら日系人はハワイにおいても二級市民として扱われることになる。半分は日本人の血が流れ、日系人のコミュニティとも繋がりがあったタオソンだが、彼らの方が気を遣ってタオソンから離れて行った。日系人の友人の一人は言った。「僕等に関わらないほうがいい。君を巻き込んでしまうから」
戦時下ということもありドラゴンナイトの営業も縮小された。確認できる限り、ドラゴンナイトはあたり一帯の区画が再開発される1975年まで営業を続けていた。しかしそこにタオソンの姿はなかった。太平洋戦争がはじまってしばらく彼はドラゴンナイトの給仕、そして経営者としてホノルルで暮らしていた。しかし1942年頃から消息が途絶え、次に彼が姿を現すのは1948年のセントルイスである。この間、彼はどこで何をしていたのか? 後のインタビューでも決して語ることはなく謎に包まれているが、一つの仮説としてアメリカ軍に関わっていた、というものがある。日系人でもないのに日本語が話せた彼は当局からすれば使い勝手がよかった。そのため通訳、もしくは暗号解読に関わる情報技官として軍務についていたのではないか、とまことしやかに囁かれているが、現時点では裏付けの取れない憶測である。しかし終戦後にセントルイスにやって来た彼の素性ははっきりしている。プロレスラー、ミスター・ワンとして人々の前に姿を現したのだ。
セントルイスにはホッジが本拠地としていたトレーニングジムがあり、彼のショーの団員たちが住み込みで鍛えることのできる設備が整っていた。戦後、早いうちにタオソンはこの地にやって来て、PEショーに出ていたようだ。またホッジはセントルイスでプロレス興業を取り仕切るプロモーターのドン・レオ・ブラッドショーと親交があり、デビューを目指す新米レスラーたちのトレーニングも請け負っていた。PEショー自体がテレビの普及とともに下火になったこともあり、タオソンもプロレスのリングに上がることになった。中国人レスラー、ミスター・ワンとして。
ここに当時のセントルイスの地方新聞であるセントルイス・クロニクル紙がある。スポーツ欄には市内で開かれていたプロレス興業の様子も短く残っている。『第三試合、カール・ベネット対ミスター・ワン。場内に響くキル・ザ・ジャップの大歓声の中、ベネットが勝利』この短い文章からでも当時の会場の様子がどのようだったか、手に取るように解る。タオソンは日本人そのものではないし、そのように名乗ってもいないが、ハワイや西海岸とは違い、セントルイスにアジア系の移民はもともと少なく、アジア人の顔をしたタオソンがリングに上がっただけで人々は憎き日本人と誤認して最大級のブーイングを送ったようだ。太平洋戦争が終結してから四年も経っていない。人々の胸には反日感情がまだ強く残っていた。面白いことに日を追うごとにタオソンの試合は後ろへずり下がって組まれるようになり、そしてついに二ヶ月後の大会で彼はメーンイベントのリングに上がった。もちろん、それまでの試合で勝利は一つもなかった。その後一年間、ミスター・ワンはブラッドショーのテリトリーであるセントルイス、カンサスシティ、スプリングフィールド、コロンビアといった各都市で開かれた大会に出場しているが、1950年になると彼の消息は突然プツリと途絶える。そのかわりに姿を現したのが、デューク・ケウェセキである。ミスター・ワンの写真は試合中のリングの遠景を写したものが一枚残っているだけだが、デューク・ケウェセキになった頃から宣伝用の写真も用意され、はっきりと日本人レスラーを名乗るようになる。ヨコハマ出身、スモウレスラーを経てレスリングデビューし、全米を転戦中。写真の中でも股引スタイルにちょび髭を生やし、戦時中のプロパガンダに使われた日本人そのものの姿でリングに登場した。当然だが彼の試合はブーイングと野次、怒号によって包まれ、会場全体が揺れるような熱狂だった。試合が始まるとデューク・ケウェセキが対戦相手(ほとんどが白人レスラー)を攻撃し、汚い反則で痛めつけているとブーイングが響き、一転、相手に攻撃を受けると跪いて両手を前に突き出した卑屈なポーズで許しを請う。それでもレフリーや相手の一瞬の隙をついて目潰しや急所への反則をくり出す。するとブーイング、そしてついに形勢が逆転して相手の白人からたっぷりと痛めつけられる。時には額から流血し、マットに倒れてスリーカウント、白人レスラーの勝利、場内は大歓声。ほとんどの試合がこれと同じパターンの繰り返しだった。
観客の多くが彼を憎み、実際に空き缶を投げつけられたり、唾を吐かれることも多かったが、プロモーターや対戦相手のレスラーからは愛されることになる。プロレス興業は勝利者やヒーローだけでは成り立たない。ヒーローの影に隠れがちだが、引き立て役、汚れ役、プロモーターが売り出したいと考えるスター候補の噛ませ犬となってくれるレスラーは不可欠だった。また多くの白人レスラーもデューク・ケウェセキとの対戦を熱望した。自分のレスリング技術がどれだけ未熟だろうと、大勢のレスラーに埋もれてパッとしない存在だろうと、デューク・ケウェセキと戦えば大歓声を受けて皆から讃えられる一夜のヒーローになれる。実際、デューク・ケウェセキには全米のプロモーターから引き合いが殺到した。1952年から1957年にかけてが彼の全盛期と言えるだろう。この間、彼はハワイを除く全米をサーキットして回った。アラスカにさえ行った。彼のレスラーとしてのハイライトは1957年11月7日、ニューヨークのマジソン・スクウェア・ガーデンで行われた対アントニオ・ルッキーニ戦で間違いないだろう。当時のルッキーニはNYで絶大な人気を誇るレスラーであり、前年の大統領選挙では民主、共和両党の間で、彼に応援を請わないと密約が交わされたほどだった。この対戦を会場後方の五ドルの席で見ていた当時のファンはこう証言している。「俺はそれまでも何度かケウェセキの試合は見たことがあったよ。その日ははじめてルッキーニとの対戦だったけど、あまり期待はしていなかった。ケウェセキの試合はいつも同じようだったからね。でも、その日は違ったんだ。何がって、ケウェセキはほとんど反則をしなかったんだ。そして会場の反応を楽しんでいる風でもあった。 お前ら、俺が反則をしなくて不思議だろ、って言っているような顔だったな。だからあの日の試合は本当に二人の技の応酬が凄かったよ。それで会場も盛り上がったんだ。ルッキーニと言えば代名詞は高くジャンプしたドロップキックだけど、ケウェセキも同じ技をしたんだ。もしかしたら、ルッキーニより高かったかもしれない。まあでも、最後はルッキーニの勝利だったんだけど、あまりにも意外な展開だったんで、今でも昨日のことのように思い出せるよ」
この証言からもデューク・ケウェセキが本来持っていたレスリング技術の高さが窺い知れる。彼は高校時代もレスリング選手としてハワイでは鳴らしていたし、ホッジのトレーニングにより見た目からは分かり辛いが屈強な肉体を持っていた。シカゴで長年トップレスラーの座にあったバーン・クロステルマンとの間でも何試合か好勝負を繰り広げており、デューク・ケウェセキは決して観客の日本人憎しを利用しただけのギミックレスラーでないのは間違いない。一流のレスラーには一流のレスリングで応えるだけの技術は持っていた。ではなぜ彼はアメリカ人に憎まれる日本人の役を長く続けたのだろうか?
ここで取り沙汰されるのが戦争中の彼の仕事だ。もし彼がアメリカ軍に手を貸していたのなら、ワン・タオソンの働きにより多くの日本人兵士が死んでいったのは間違いない。暗号解読に携わっていたとしたら、部隊が全滅したこともあったろう。そんな戦争に関わってしまった贖罪の思いから彼は醜い日本人を演じ、自身にヘイトを集めることで罪滅ぼしをしたかったのではないか、というものだ。しかしこの論理でも「日本人を多く死に追いやったから自分がアメリカ人に憎まれる」というのが理解し辛いし、軍に関わっていた証拠もない。ただ日本人を演じれば金になったからやったのだ、とする証言も多い。特に日本人のプロレス関係者の口からはよく聞かれる。
1958年からデューク・ケウェセキは体調を崩し、リングに立つ回数がめっきりと減った。流血を繰り返した傷口から黴菌が入ったことによる敗血症だった。この間、以前ほどの旺盛なサーキットに出ることはなく、居を構えたロサンゼルス近郊での試合にスポット的に出場するのみであった。LA出身の日系人レスラーであるハロルド・サカモトと組んだチームでカリフォルニア州タッグ選手権ベルトを腰に巻いた時期もあったが、それも一人よりも負担の少ないタッグ戦に活路を見出した結果である。一方で設立されたばかりの日本のプロレス界に関わることになる。日本人がまだ目にしたことのなかったプロレスを広めるために、プロレス全般のアドバイザー、日本からやって来る新米レスラーの育成係、アメリカ人レスラーを日本に送るブッキングの仕事に携わった。日本での試合もこなした。デューク・カワサキの名前でリングに上がったが、大相撲出身の日本人レスラーである力王山を引き立てるための汚れ役を自らに任じた。日本国内の興業で、デューク・カワサキは白人レスラーに簡単に負けてしまう、みじめな日系人レスラーだった。その後の試合で力王山が白人レスラーに復讐を果たして大盛況となるわけだが、当時の日本ではプロレスが始まったばかりであり、観客はレスラーそれぞれに役割があることなど理解していなかった。また敗血症のダメージから全快していたとはいえず、精彩を欠いたものだったのも間違いない。アメリカで大いに受けた醜い日本人を演じるわけにもいかず、彼の日本での試合は15回に留まった。
以降はアメリカ人レスラーを日本に送り込むブッカーとしての仕事が主なものになる。この時に彼と関わった日本人がデューク・ケウェセキの金への執着ぶりを話し、金に汚かった、守銭奴だった、との証言が多く残っている。だがそれとは逆に、彼は多くの金を要求したが、それだけの金額に似合う仕事を残している、と擁護する意見もある。確かに1961年に東京で開かれたチャンピオン・カーニバルに出場したレスラーの名前を見ると、いずれもアメリカ各地で興業のトップを張っていた本当のチャンピオンが集結しており、アメリカ国内では絶対にありえなかったカードも組まれている。もちろんこれはデューク・ケウェセキの仕事だ。50年代に全米をサーキットして回り、各地のプロモーターに恩を売った彼でなければ成し遂げられない偉業と言っていいだろう。
60年代になると盟友だった力王山の急死(酔っ払って眠りこけ、吐瀉物が喉に詰まっての窒息死だった)もあり、日本との関わりも減っていく。LAで新人レスラーを相手にしたトレーナーやマネージメント業などがメインとなり、半リタイア状態になっていたデューク・ケウェセキのもとに意外なところからオファーがあった。独立したばかりのシンガポールだった。当時、設立されたばかりの民間テレビ局のチャンネル5が視聴者獲得の目玉として毎週土曜夜七時からのプロレス中継を企画し、デューク・ケウェセキにアドバイザーとして協力が要請されたのだ。彼は現地に飛び、又はプロデューサーがLAにやって来て何度も打ち合わせをしているうちに、今回の企画には決定的に欠けているものが浮き彫りになった。
「プロレスに絶対に必要なのが地元のヒーローです」とデューク・ケウェセキは説明した。「よそからやってきた悪役を地元のヒーローが撃退する、これがプロレスの主軸です」
「しかし放送は三ヶ月後に迫ってるし、今からシンガポールの力自慢をレスラーに仕立て上げるのは遅すぎるでしょう。やはり、その役はあなたに頼むしかないですね」
「え?」とデューク・ケウェセキは目を丸くした。「私ですか?」
デューク・ケウェセキことワン・タオソンは翌月に五十歳の誕生日を控えていたが、白いものが増えていた髪を黒く染め、何年かぶりのホッジ式トレーニングで身体を作り上げ、シンガポールのリングに上がった。当然、リングネームはミスター・ワンだった。アメリカでのプロレスを熟知し、なおかつ広東語が流暢に喋れるタオソンにしか務まらない役回りだった。試合前のインタビューでは早口の広東語でまくし立て、相手(アメリカの白人、もしくは黒人レスラー)を人種差別ギリギリの言葉でこき下ろし、試合に勝つと再びインタビューに答え、観客の声援に感謝した。本格的なプロレス興業に接したことのなかったシンガポールの視聴者はタオソンのプロレスに熱狂した。土曜日の夜七時は街の人通りが減り、犯罪の発生率も下がった。タオソンが街を歩くとファンに取り囲まれてサイン攻めに合い、彼のネクタイやシャツが剥ぎ取られるほどだった。しかしそんなプロレス中継も半年で中止を余儀なくされた。シンガポール当局により、タオソンの興業ビザが停止されたのである。シンガポールは政治や経済の中心を中国系が占め、権力の大部分を抑えている社会だが、人口の何割かはマレー系やインド系の住人も含んでいる。そのため民族問題には敏感であり、多文化主義を標榜している政府にとって、タオソンの中華系の民族主義を煽った一連の発言が問題視されたのだ。また彼の母親は実は日本人で、彼自身も戦争中のシンガポール占領の際に日本軍に手を貸した、といった根も葉もないデマが飛び交い、ミスター・ワンの活動は閉ざされてしまった。
晩年、ワン・タオソンは生まれ故郷であるハワイに戻って静かな余生を送った。二十歳年下のハワイ系の女性と53歳で結婚し、子供こそ作らなかったものの、仲睦まじい夫婦の姿を近所の住人は記憶している。ホノルル郊外の住宅地にかなり大きな邸宅を構え、庭造りとボウリングと油絵描きにいそしむ彼のことを、多くの人がワンおじさんと親しみを込めて呼んでいたが、血にまみれた前半生のことを知る人など皆無だった。62歳の時、胃がんが発覚し、数度に渡る手術に耐えたものの、64歳でホノルルの病院のベッドで息を引き取った。美しい妻と、二人の妹、そして五人の姪と甥に看取られた静かな死だった。
彼の亡骸はホノルルの墓地の一画に埋葬された。墓標にはただ一文「アメリカ人に憎まれ、日本人に無視され、シンガポール人に愛されたハワイ人、ここに眠る」と刻まれている。
(了)
