
三浦雅士――人間の遠い彼方へ その3第2章 人間の方へ――『この本がいい』を読む
三浦雅士――人間の遠い彼方へ その3
鳥の事務所

第2章 人間の方へ――『この本がいい』を読む
1 前置き その①――いささか苦言を……
それでは第2章です。
本章では、相当以前に、1993年ですね、わたしが書きました書評のようなものをお読み頂きます。
『この本がいい』、これですね。やたら分厚いですね。こちらは1989年から92年まで、足掛け4年に渡って、講談社の今は亡き、――「今は亡き」が結構ありますね、つまり廃刊になったんですが、PR誌の『本』に連載されていたものが元になっています。
コラム ☕tea for one
~『この本がいい』~
■三浦雅士編『この本がいい――対談による「知」のブックガイド』1993年3月1日・講談社。
■対談集。
■初出 「対談によるブックガイド」/『本』1989年6月号~1992年11月号・講談社。
■3,200円(税込み・発売当時)。
■687ページ。
■装丁 山岸義明。
■編集担当 鷲尾賢也(『本』編集長)・木村妙子・丸本忠之・横山建城。
📓
【コラム 3 『この本がいい』】
コラム ☕tea for one
~『この本がいい』目次~
(最後のあとがきを除いて題名の前は対話者)
・竹中平蔵「科学のふりすることもない――経済学の本」 ・杉浦日向子「垣根越しからの江戸――「江戸」の本」 ・岡田英弘「世界史はモンゴルの賜――「歴史」の本」 ・樺山紘一「自分の過去をよく見れば――ヨーロッパ像の再検討」 ・大室幹雄「細部を読み込む楽しみ――中世史」 ・青木保「もっともっときわどく――新しい世界の文学」 ・今福龍太「あらゆる人間は亡命者――ラテンアメリカ文学」 ・沼野充義 「ペレストロイカ以後――ロシア文学」 ・柴田元幸「生半可じゃない小説――新しいアメリカ文学」 ・黒井千次「極めつきはこれだ――翻訳ミステリー」 ・日野啓三「「現実」は溶けていく――文学としてのSF」 ・養老孟司「脳のパラドックス――科学論と脳」 ・西垣通「生命と第三の性――機械と人間」 ・岸田秀「解釈は無限に続く――フロイト」 ・福島章「壮大なホラ話一歩手前――病跡学の本」 ・市川雅「ダンスこそ芸術の根源――舞踊の本」 ・諸井誠 「アマチュアにはご用心――オペラの本」 ・若桑みどり「フェミニズム自由自在――女性と芸術」
・巌谷國士「芸術の未来を予感する――少女漫画そとから」 ・萩尾望都「創作の最前線――少女漫画うちから」 ・三浦雅士「やっぱり本は面白い――あとがきのようなもの」・「すべての本好きに捧げるブックリスト」・「人名索引」
📓
で、問題は、と言うほど問題ではないのですが、そもそもブックガイドという建前ですから、気軽に読めるのが理想なんだと思います。雑誌連載中は、それぞれの項目が前後2回に分載されていて、というか、そもそもタダですから、それは気軽に読めたのですが、この厚さとこの価格ですから、――まあ、価格は仕方ないとしても、気軽に手に取って読める形にはなっていません。理想を言うと新書か、いきなり文庫化ですね。講談社の新書は結構分厚いのが出ていますから、新書で2,000円以内の価格に抑えると、もっと読者が確保できたのではと愚考する次第です。つまり、辞典ではありませんが、ある特定の問題、領域について、全体的な見通しが立つ、大変優れた本なのです。
【コラム 4『この本がいい』目次】
コラム ☕tea for one
~『この本がいい』目次~
(最後のあとがきを除いて題名の前は対話者)
・竹中平蔵「科学のふりすることもない――経済学の本」 ・杉浦日向子「垣根越しからの江戸――「江戸」の本」 ・岡田英弘「世界史はモンゴルの賜――「歴史」の本」 ・樺山紘一「自分の過去をよく見れば――ヨーロッパ像の再検討」 ・大室幹雄「細部を読み込む楽しみ――中世史」 ・青木保「もっともっときわどく――新しい世界の文学」 ・今福龍太「あらゆる人間は亡命者――ラテンアメリカ文学」 ・沼野充義 「ペレストロイカ以後――ロシア文学」 ・柴田元幸「生半可じゃない小説――新しいアメリカ文学」 ・黒井千次「極めつきはこれだ――翻訳ミステリー」 ・日野啓三「「現実」は溶けていく――文学としてのSF」 ・養老孟司「脳のパラドックス――科学論と脳」 ・西垣通「生命と第三の性――機械と人間」 ・岸田秀「解釈は無限に続く――フロイト」 ・福島章「壮大なホラ話一歩手前――病跡学の本」 ・市川雅「ダンスこそ芸術の根源――舞踊の本」 ・諸井誠 「アマチュアにはご用心――オペラの本」 ・若桑みどり「フェミニズム自由自在――女性と芸術」
・巌谷國士「芸術の未来を予感する――少女漫画そとから」 ・萩尾望都「創作の最前線――少女漫画うちから」 ・三浦雅士「やっぱり本は面白い――あとがきのようなもの」・「すべての本好きに捧げるブックリスト」・「人名索引」
📓
ちなみに、この本の題名『この本がいい』という書題は、連載元の『本』編集長の鷲尾賢也の命名、というか企画そのものも鷲尾の提案だったそうですが、うーーん、まー、連載段階の「対談によるブックガイド」の方が内容に誠実だったかも知れない。
ついでに、言い難いことを付け加えておくと、わたしはこの対談を連載中からずっと楽しみに読んでいて、単行本化を楽しみにしていました。ところが、書店に行って一目見るといささか残念に思ったことを覚えています。――分かりますか?
そう、装幀なんです。担当の方には申し訳ないですが、なんというか、野暮ったい感じがしますね。
【コラム 5 PR誌】
コラム ☕tea for one
~PR誌~
PR誌も次々と廃刊になっていますが、PR誌って分かりますか。PRって「public relations」の略ですが、要するに広告・宣伝のことです。今はもうネット社会ですから、出版社もSNSや自社のホウム・ペイジなどを通じて宣伝しますが、従来はそれぞれのPR用の雑誌形態の小冊子を発刊して、一部100円とかで売ってることになってましたが、大抵の本屋ではただで置いてあるんです。
どうでもいいですが、昔から、これとか、全集とかの内容見本のリーフレットを集めるのがわたしは好きでした。趣味、PR誌、内容見本の収拾って変態ですね。これを中学生の時からやってます(笑)。
今生き残っているのは岩波書店の『図書』、新潮社の『波』、筑摩書房の『ちくま』とか、こちらは書店ですが、紀伊國屋書店の『SCRIPTA』とかが有名ですが、実はこれがなかなか侮れない代物で、新刊に関するインタヴューやエッセイなども、あとあと重要にはなってきますが、それとはまったく無関係に連載されているものがとても重要です。惜しむらくは、講談社の『本』はその手の連載がかなり目白押しだったので、かなり残念です。例えば、社会学者の大澤真幸さんの「社会性の起源」(2013年12月号~2020年3月号)は超長期連載半ばでweb版に連載が移行しました。大澤さんと言えば、かの大著『ナショナリズムの由来』(2007年・講談社)もこの『本』の連載が元になっていました。
📓
というのは、今まで、少なくとも単著に限って言うと、装幀は原則、菊地信義さんがされていました。例の超売れっ子ですよね。あれも、これも、どれも菊地さんの装幀ばかりになってしまって嫌う方もいますが、例えば、作家の丸谷才一は嫌っていたのだと思います。作者名の下、とか横にイタリック、斜字体のローマ字で、その読みを書くのも菊地さんの特徴ですが、講談社文芸文庫は菊地さんの統一フォーマットですが、丸谷は生前そのローマ字を入れさせないようにしていました。よっぽど嫌だったんでしょうね。亡くなってからのはきちんと入っているので、ちょっと笑っちゃいましたが。
それはともかく、とにかく一目で菊地信義の装幀だと字体だけで分っちゃいます。一言で言うとクールな感じがします。強い装幀家の意志を感じます。
ところが、これですから。ちょっとこれはどうなのと言わざるを得ません。
レコードとかCD、って言っても、もう歴史的遺物ですが、「ジャケ買い」って言葉があります。内容とかよりも、レコードとかのジャケットのデザインがかっこいいので思わず買っちゃうことですが、これは本でもそういうことがあると思うんですよ。もちろん、ちゃんと聞いたり、読んだりするのは、まー当然としても、手元に置いて、手でさすったり、匂いを嗅いだり、眺めたりするという(笑)、てことってしませんか。丁度、村上春樹さんが同じことを、これはレコードですが言ってました(村上『古くて素敵なクラシック・レコードたち』2021年・文藝春秋・p.p.13-14)。
うーーん、ま、立派な変態ですね。
だから、音楽のストリーミング配信とか、本の電子書籍とかも、或る一定の比率で存在するのは、確かに便利だと思いますが、全部がそれだけになってしまうとすると、なんだか味気ないというか、人間の文化の中のこだわり? がなくなっちゃう気がするなー。
どう思いますか。
話を戻しますが、『身体の零度』は講談社選書メチエの中の一冊ですし、『漱石』は岩波新書ですから、統一のフォーマットがありますから除外するとして、1995年の『バレエの現代』までは菊地さんの装幀です。少し開いて、1999年『考える身体』から、原則、最新作『石坂洋次郎の逆襲』に至るまで近藤一弥さんの担当です。要はあの長篇三部作の真っ白い装丁が特徴のあれですね。
近藤一弥さんは、例の、と言ってもなんですが、『安部公房全集』(1997年~2009年)が新潮社から出たときのデザイナーの方です。あの、ですね、見たことがある人は分かりますが、当たり前ですが。全集なので箱に入っているんですが、タイトルのところが金属のプレイトになっていて、そこから本を引き出すと、そこに穴が開いているんです。こんな感じ。ほらね。
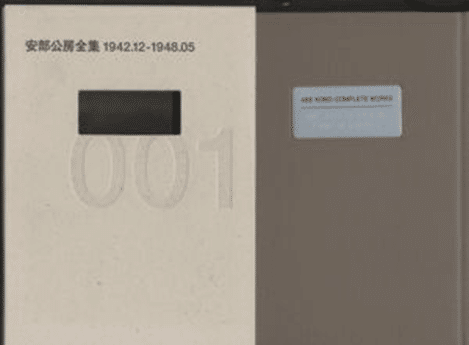
【図 3 『安部公房全集001』書影】
それだけでもかっこいいんですが、――安部公房は写真が好きで、自分のカメラでたくさん写真を撮ってるんですが、

【図 4 『安部公房全集』の函の中】
さっきのこの穴から覗くと、その写真が見えるようになってるんですね。つまり、箱の内側一面にその写真が印刷されているんですが、これはもちろん、安部公房の、主人公が巨大な段ボール箱に入ってしまう『箱男』(1973年・新潮社)をモチーフにしている訳です。凄いですね。これで、1998年に東京ADC原弘賞を受賞されているそうです。
で、三浦さんは安部公房の長女に当たる安部ネリさんに近藤さんを紹介されたと書いてます*。
*三浦「私の文芸文庫 ⑥ 安部ヨリミ『スフィンクスは笑う』――安部公房の母の威力」/『群像』2020年6月号。
いずれにしても、自著のデザインについてもそれ相応の見識を持っているということだと思います。その意味での? です。
2 前置き その②――返信
しばらく、余談が続きます。すいません。
単純なわたくし事ですが。
それで、今から読むのは30年近く前に書いた文章です。後にはネットにも上げましたが、そもそもは紙ベイスの同人紙に載せたものです。200部だか300部ぐらいコピーをして、文章中に言及させて頂いた方と友人たちに配布しました。
すると、恐るべきことに、まず、しばらくすると、講談社の編集部の横山建城さんという方からお礼の葉書が来ました。ちょっと驚いていると、本文中にお名前を挙げさせて頂いた詩人の大岡信さんからも「気持ちのいい紹介」云々、「三浦君も喜んでいるだろう」とのお葉書を頂きました。
更にしばらくすると三浦さんご本人からもお葉書を頂戴いたしました。
というような訳で、そんなことあるのかなーと、前代未聞の出来事ですから、大変驚き、また感銘した次第です。
まだ、言いたいことがあるのですが、前置きが長過ぎるので、一旦、本文に入って、その後、追加したいと思います。
それでは、お手元のレジュメをご覧ください。
行きます。原題は「〈知〉の地中海の方へ――三浦雅士編『この本がいい』を読む」でした。若干の字句の訂正と注釈を変えました。
3 人間の方へ――三浦雅士試論Ⅰ
三浦雅士は地中海ではないか。 現代日本における「知」の地中海であると言えないか。
1 地 中 海 と は 何 か
では地中海とは何か。彼はあるところで「地中海はひとつの劇場である。」*としている。しかし、それは「ただたんにそこでさまざまな事件が継起したからというのではない。」*と続けて、以下次のように述べる。
劇場という比喩にあくまでも固執しなければならないのは、そこではつねに、 異質な文化や文明の接触が、すなわち人間と人間の精神的また物質的な交換が行われつづけてきたからである。地中海とはまさに巨大な交通そのものであるといってよい。そしてこの交通こそが劇場を劇場たらしめるものなのだ。(*三浦「地中海」/『夢の明るい鏡』p.p.198-199・傍線引用者)
2 異質な知性と感性の交通
三浦雅士が地中海であるというこの比喩は、いうまでもなく彼が70年代をすっぽりと包む形で編集者として様々な異質な知性や感性の接触や交通の役割を果たしたからである。例えば柄谷行人はあるところで次のように述べている。
柄谷 (前略)ぼくは、七〇年代後半以後グループをつくったのは三浦雅士だという感じがする(笑)。
三浦 ぼくはつくらないよ。だいたい入れてくれないよ。
柄谷 つくるというより、 つなげてしまったわけだね。
三浦 つなげるのは異質な人をですよ。仲間同士、仲良くなんてのはない。
柄谷 ただ、八〇年代において顕著になる編集者的なもの、 エディターシップの優位を先駆的に示したのが三浦さんだね。
(柄谷行人編『近代日本の批評』昭和篇〔下〕p.169)
3 編集者としての三浦雅士
若干揶揄の気味がないでもないが、三浦雅士の仕事の一端はあるいはここに尽きているかと思う。
彼は1970年の7月から75年の1月まで青土社から刊行されている詩誌『ユリイカ』の編集長を務め、その後引き続き同じ出版社から刊行されている思想誌『現代思想』の編集長を1981年の12月まで務めている。
この二つの雑誌で活躍した人々を列挙してみれば、彼の編集者としての手腕の一端が分かるというものだ。
彼自身あるインタヴューで次の人々を挙げている。大岡信・山口昌男・柄谷行人・中村雄二郎・高階秀爾・市川浩・多木浩二・村上陽一郎・生松敬三・木田元・高橋康也・青木保・澁澤龍彦・種村季弘・蓮實重彦・武満徹・加納光於・磯崎新・原広司などそうそうたるメンバーだ(『夢の明るい鏡』p.29)。もちろんこれだけではなく他にも数多くの知識人が参加している。
浅田影が『現代思想』の「ラカン」特集でデビューしているのは有名な話だ(浅田彰「ラカン――構造主義のリミットとしての」/『現代思想』1981年7月臨時増刊号)。ちなみに浅田彰の最初の著書『構造と力――記号論を超えて』 (1983年・勁草書房) 所収論文の大部分が掲載されたのも『現代思想』である。そう考えてくると1983年から84 年を中心としたニュー・アカデミズムのブームを準備したのは70年代の三浦雅士の仕事だったのではないかとも言い得るわけだ。
これも有名な話だが、 いまでこそ誰しもが知っている大江健三郎と山口昌男の親近性にしても、まだ二人がお互いに知らなかった頃、「神話的世界」という観点で二人は通底するとして結びつけようとしたのは三浦である。しかし、時期尚早でそのときはうまくいかす、後に互いに対応し合うようになったという(『夢の明るい鏡』p.18)。
まさに編集とは交通なのである(『夢の明るい鏡』p.104)。
4 読 書 の 熱 気
それにしても、 いかにしてこのような仕事が達成されたのであろうか。
例えば彼は「著者の必然性」 (『夢の明るい鏡』p.14) という視点を挙げている。「この著者はこういうものを書かなければならないんじゃないかということを著者の立場に立って考えなきゃいけないということね。」(『夢の明るい鏡』p.14)。数多くの著作家の内的必然性にまで思いを致して、彼は原稿を依頼したり、インタヴューをしていたのである。
しかし、 これはとてつもなく大変な勉強を要求される。例えば、誰かの特集をするとすれば、当然のようにその人の作品や著作のほとんどに目を通すという(『夢の明るい鏡』p.p.32‐33)。そんなことは当たり前と言えば当たり前なのだが、それを持続するのにどれくらいのエネルギーが必要とされるであろうか。
三浦は編集というものは「無色透明であるべき」*だとして次のように述べている。
それでもどうしても残るものがその雑誌の個性であり、それはおそらく編集者という読者が、雑誌を作りあげる段階での懸命な読書によって発散する一種の読書の熱気のようなものと思われます。 (*『夢の明るい鏡』p.108)
まさに彼自身の内側においても読書という激烈な交通が行われていたのである。
「情熱がすべてだ」 (『夢の明るい鏡』p.34)と語る三浦雅士の情熱は凡百のそれではない。彼は当時の編集部を「海賊船団」 (『夢の明るい鏡』p.12 ) にたとえているが、まさに地中海の強い日差しに日焼けした海賊が持つ情熱なのである。
5 た だ の ブ ッ クガ イ ド で は な い
さて、前置きが長くなった。本書は「対談によるブックガイド」との題で、講談社のPR誌『本』での連載(1991年6月号-1992年11月号)をまとめたものである。しかし、これは単に書目を並べて解説をつけただけのブックガイドではない。目次を一覧すれは分かるだろう、まさにこれこそ「知」の地中海である。これだけの幅広い領域にわたって、 その道の専門家や読巧者と渡り合えるだけの読書を準備し、なおかつそのジャンルにおけるポイントを押さえて、対談を展開するというのはただごとではない。
そればかりでなく三浦自身の鋭い仮説がちらほらと織り込まれる。例えば推理小説は19世紀のものだが、サイエンス・フィクションは20世紀のものだという。何故なら、前者は犯人を探すという形である人間をアイデンティファイするものだが、それに対して後者はむしろ誰が誰だか分からなくなっていくものが多いからだとか(本書・p.286頁、p.318)、吉本ばななや小川洋子などは少女漫画の視線で小説を書いているとか(本書・p.576)。
6 科学とは文学である?
あるいは単発的に触れられるものばかりではなく、一貫して論じられているものもある。 一つには論文にもなっている、小説という形式は植民地支配が生んだものだという仮説や植民地の問題そのもの*。二つには科学の無根拠性の問題である。ここでは後者の問題を考えてみよう。
*三浦「小説という植民地」/『小説という植民地』。「世界史はモンゴルの賜」・「もっともっときわどく」・「あらゆる人間は亡命者」・「ペレストロイカ以後」・「生半可じゃない小説」 ・ 「極めつきはこれだ」/本書 。
経済学者・竹中平蔵との対談では冒頭、経済学は科学とは言えないのではないか(本書・p.8)、という点から話し始めているが同じ趣旨の発言は他の対談においてもしばしば繰り返される。いわく、歴史は文学だ(本書・p.70)、精神分析、あるいは精神病理学は文学だ(本書・p.424、 p.453)、はては実は科学そのものが文学なのだという発言にまで至る(本書・p.341 、p.352)。
三浦雅士のこの懐疑は決して単に思いつきで述べられているものではない。彼は「二十世紀に発生した重要な学間のほとんどすべてが、解釈学的なものを含んでしまっている」と述べ、例として、現象学、イコノロジー、文化人類学、あるいは動物行動学を挙げる。「それらのコアの部分に解釈学としての精神分析があって、そのまた底にユダヤ人のカバラ的神秘主義」すなわち「ユダヤ教における聖書解釈学の伝統がある」としている(本書・p.p.430-431)。
これだけでも充分に重要な問題なのだが、 ヨーロッパの根本に聖書解釈学の伝統があるとすれば、それは20世紀の学問だけではなく、ヨーロッパの学問全体が実は解釈の問題に帰着することは言うまでもない。 つまり解釈があるだけたということになる。それが何故文学になるかと言えば、少々くどいが、引用を重ねると「解釈学的な要素とは、要するに意味論でしょう。意味というのは関係ですから、関係が入ってきちゃうと、その関係性を記述する人、解釈する人の主観が入るのはいかんともしがたい宿命でしょう。それはまったく文学的ですよ。」ということになるからだ(本書・p.453)。したがってヨーロッパの生み出したあらゆる学問、 つまり科学にひたすら近づこうとした諸学は実は文学だったということになる。
7 相 対 主 義 の 問 題
だが、何故それが問題なのか。科学が文学であって何故いけないのか。別にいいではないか。
だが、やはり問題なのだ。
別の角度から考えてみよう。従来科学と文学は対立するものだと思われて来た。 この二元論はあるいは理性と感性、あるいは〈絶対〉と〈相対〉という言葉で置き換えることができるだろう。科学は絶対的な真理を追求するものだという具合に。 つまりいつかは確かな答えか出るものだと考えられてきた。三浦の言っていることはそれに対してそうではない、答えなど出ないではないか、と言っているのである。心理学者の岸田秀は次のように述べる。
岸田 決定的な言説になり得なかったら、なぜいけないんですか。相対的でいいんじゃないですか。
三浦 世の中には相対的では死んでも死にきれないという人もいるんですよ。 (本書・p.441)
8 神 の 空 席
なんだか冗談めかして答えているが三浦自身にとっては、この絶対 と相対の問題は過去の著作において何度も触れられている極めて重要な問題なのである。
例えば、人は自らを狂人ではないと述べることはできる。しかしその真偽のほどは定かではない。それを判定するためには精神科医が要請される。しかし、その医者も狂人かも知れない。それを判定するために第2の医者が要請され、そしてまたさらに第3の医者が要請され……、論理的には無限にこの連鎖が続いていく。おそらくその後に招来されるべき問題はひとえに絶対の問題、神の問題に他ならない。神こそがこの連鎖を断ち切るのである。 だが、もし神が存在しないとすればどうなるか。もちろん、ほとんどの人はそんなことは考えない。しかし考えなくても「人類は恐るべき気違いの集団である可能性をつねに秘めている」とは確かに言い得る(三浦『メランコリーの水脈』p.p.63-64)。
そしてそのことに気づいてしまった人間は、 ニーチェやマックス・ヴェーバーあるいは柄谷行人らのようにひたすらそれを宙づりにして引き受けたうえで思考を続けるか、または全く逆に神の空席に様々な代置物を設定するようになるだろう。
例を挙ければ小林秀雄や江藤淳、あるいは大江健三郎などの日本の文学の主流が、 そのように動いていることは言うまでもない。もちろん、それを批判することは容易である。
だが結局人間とはそのようにしか生きないのではないのか。何かを信ずることによってしか生きられないのではないのか。
あるいはこう言ってもいいだろう、生きるに値する人生が、あるいはその意味が解体しているにも関わらず、やはり人間は生き続けるものなのであると。
三浦はあるところで批評の基準に触れて、次のように述べている。「批評は絶対を狙わねばならない。」と (『死の視線』p.10)。だが批評の絶対的な基準などはない。存在するのは単なる相対主義的なそれでしかない。一般的なのは一流に接することで自らの批評眼を磨くという経験主義。しかしこれは新しい経験には無効である。 であれば相対的であるしかないということ自体を認めてしまうという考え方もある。しかしそれも一種の経験主義なのだ。そこで三浦は次のようにまとめる。
おそらく、 これまでのところ、批評が絶対を狙う過程で導き出した最大の基準は自己意識である。作者の、あるいは作品の自己意識の強度が作品の価値を形成するという考え方だ。/(……)これを要するに文学作品は人間ということにかかわることによって読者を感動させるといって誤りではない。あたりまえのことだ。だが、あたりまえだからこそ重要なのだ。/作品の善し悪しを決めるのは、その作品がどれだけ深く、また強く人間ということにかかわっているかである。(『死の視線』p.p.11-12 ・傍線評者)
9 人 間 の 方 へ
三浦雅士が1991年、突如として『ダンスマガジン』 (新書館)の編集長になったのには驚かされた。しかし、舞踊こそあらゆる芸術の根源であるという発言*もこのように考えてくれば得心がいく。三浦雅士は人間に帰ったのだ。舞踊を通じて人間というまさに絶対的なものに帰っていったのである。
*「ダンスこそ芸術の根源」/本書。三浦「ダンスに魅せられて」/『毎日新聞』1991年5月17日夕刊。
だが注意しておくが、これは保守回帰ではない。三浦がそのような根源的な場所に身を置いて決して安心してはいないことは、彼の著作に明らかである。むしろそのような場所から歴史や文学あるいは芸術そして人間に至るまでの様々な領域に絶えず疑問を投げかけているのである。それは何をおいても本書に明らかだろう。
三浦雅士という「知」の地中海にはあまたの航跡図が書き込まれている。「疑問の網状組織」という航跡図が書き込まれている。そこでは今日も波しぶきを上げながら激しく「交通」が生起しているのである。
(初出 『鳥』1995年1月号・鳥の事務所)
4 補講 その①――ソクラテスとプロタゴラスの間で――相対主義を巡って
という訳で、ま、若気の至りというか、途中途中でおかしなことを言っていたり、文章が言葉足らずだったりしますが、大目に見てあげてください。しかしながら、おおよそ、わたしの言いたいことの主要な論点は今も変わりません。
ちょっと今手元に本がないので、うろ覚えで話しますが、ソクラテスの話です。専門的な見地からは多分不正確で、なおかつ間違ってもいるとは思いますが、個人的な解釈、感想だとお考え下さい。
アテナイ、今のアテネですね、そこにプロタゴラスというソフィスト、今風に言うと、評論家とか、思想家でしょうか、そういう人がいた。
彼は「人間尺度論」という考えを説きました。要は、この世に絶対的な考え方などない、――もう、この時代からそんなことを言ってる人がいたんですね、絶対がないということは、じゃあ、何が基準になるかと言うと、人間だというんですが、これは人間一般と言うことではなくて、要するに人間一人一人と言うことですから、人間が尺度と言うよりも、自分自身がそれを評価するかどうかということですから、「人間尺度論」ではなくて「自分尺度論」ですね。自分がこれはいいと思ったら、それでいいという考え方です。――うん、今風ですね。
で、それに対して、ソクラテスが言うのは例の如く、ああでもない、こうでもないと言って、結論が出ないんですが、要は、人間には生きるに足る価値、つまり、出来るだけ善く生きることが大切なんだ、と言うことが言いたいようですが、今からするとソクラテスの方が古めかしい説教爺のように聞こえます。実際、けっこううっとうしいじーさんだったんじゃないかとは思いますけど、ま、それはともかく、今の日本の状況からすると、何となくプロタゴラスに軍配に上げたくなりますよね。
でも、彼の言ってることをまともに実践すると、本当に何でもOK になっちゃいます。もちろん、戦争が、――戦争中であればということですが、OKならば、たいていの犯罪もOKですよね。
『罪と罰』って読んだことありますか。ドストエフスキーの。
あれとおんなじですよね、主人公のラスコーリニコフはエリートである自分が生き残るためには、――つーのは彼は食うや食わずの超貧乏だったんですが、その為には他人を殺害しても構わないという論理で、金貸しのお婆さんをハンマーで、――嘘です、斧で叩き殺してしまう、っていう話なんですが、ま、だからこうなっちゃってもいいよな、お互い様だから、ということになります。
こうなっちゃうのは、普遍的な善とか、神様、仏様が存在しないとなると、必然的な帰結ではないでしょうか。それも、経済的に厳しい状況、つまり、ラスコーリニコフがそうだったようにご飯が食べられなければ、生きるためには何でもしますよね。
そうでもないですか。
わたしは学生の頃、ま、今も学生のようなものですが、電話はもちろんのこと、電気は止まる、ガスは止まる、流石に水道は結構待ってもらいましたが、そういう謎のような超貧乏を経験したことがあります。幸いなことに、近所のパン屋のお婆さんを殺したりはせず、近所のパン屋で格安、30円ぐらい? で売られていた食パンの耳ですね、それを買って飢えをしのいだりとか、ビールとかの空き瓶、リターナブル瓶ですね、それを集めて酒屋さんに持っていって換金したりとかしていました。流石に路上での生活にまでは至りませんでしたが、事情があって、「追っ手」から逃れるために、下宿に帰れず、冬の寒い街を彷徨い歩いたこともありました。「追っ手」というと、抜け忍みたいですが、――抜け忍というのは、忍者の組織というのは終身雇用制なので、――知ってましたか、忍者って就職したら途中で辞められないんです。で、課長、今月いっぱいで辞めますとか言うと、基本、殺されます、って超ウルトラ・ブラック企業じゃないですか。ま、だから、殺されないためには、なんかミッションの途中かなんかでそっと姿を消すんですね。それでもそういうのは生かしおけないので「追っ手」が来て殺害されちゃうんですが。これは皆さん知らないと思いますが、白土三平さんの書かれた『カムイ伝』(現43巻・1964年-2000年・ゴールデンコミックス(小学館))とか『カムイ外伝』(現22巻・1965年-1987年・ゴールデンコミックス(小学館))とかはそういう話です。
話が逸れました。それ過ぎたかも知れません。
いずれにしてもこの生きる意味なんかないじゃん、というのは切実な問題ではあったのです。
ま、ここは一考の余地があります。
5 補講 その②――文体の問題
1 常体か敬体か、それが問題だ
では、本日最後のお話です。順番的に、果たしてここで話すのが妥当なのかはちょっと分かりませんが、一旦話してみます。
文体、の問題です。この文体の問題、いわゆる、常体か敬体か、つまり「だ・である」調か「です・ます」調かという問題に聞こえます。
実は、本書の文体とも関わる問題です。
【コラム 6「話体」は文学なのか?】
コラム ☕tea for one
~「話体」は文学なのか?~
常体か敬体かという問題は、これすなわち、本来、文・言葉の芸、文・言葉の芸術であるべき文学作品における「会話体」をどう捉えるのかという問題に近接しています。例えば吉本隆明は、その著『言語にとって美とは何か』(全2巻・1965年・勁草書房/2001年・角川ソフィア文庫)、『言語美』って略します。ヴェーバーの「プロ倫」(「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の「精神」」/『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』1905年/大塚久雄訳・1989年・岩波文庫)と似てるか。似てねーな。その『言語美』で「話体」という表現を使っていたと思いますが、そのことです。つまり、文学作品に、どれくらい「話体」をぶっ込めるのか、あるいは「話体」そのものをどれくらい文学作品として遇したらいいのか、という問題です。例えば、最近の例では詩人の最果タヒさんの口語詩は、果たして「詩」なのか、という批判があるようですが、わたし個人の意見は本人が「詩」といったら「詩」なのです。それをどのように遇するかは読者、というよりもマス・メディア側の問題のようにも思います。それをもう少し拡張すると、ちなみにわたしは「拡張」という言葉と概念が好きです、本人が、全く「詩」であるという意識を持ってないものでも、実は「視線の変更」によって「詩」になるのだ、と示したのが、編集者(と言ってよいのか?)都築響一さんの編集による『夜露死苦現代詩』(2006年・新潮社/2010年・ちくま文庫)です。要は通常文学作品とな見なされない言葉の数々を「現代詩」として読みなおしたものです。あの、コピーとか街の看板とか、暴走族の特攻服の言葉とかね。ただ、あいだみつをの作品をここに入れるのはどうかな。そこんとこ、夜露死苦!
つまり、これは文学に留まらず、芸術って何なの? という問題と隣接している訳です。美術で言えば、例のトイレの便器を「泉」(1917年)という名前を付けて芸術としたマルセル・デュシャンとか、音楽で言えば、演奏家が4分33秒間何も演奏せず、その間、聴衆は「沈黙の音」を聴き続けるという、ジョン・ケイジの「4分33秒」(1952年)などがあるね。
「商品としての芸術」という問題を考えるのであれば、結局そこにあるのはマス・メディア、マス・コミュニケイションの問題に帰着する、つまり「芸術」は「人為的に作られる」、当たり前ですが、もうちょっと言うと「捏造される」訳ですから、芸術もファッションもポップ・ミュージックも同じです。
ですが、そうではないような、つまり「商品」として「消費」されないような「芸術的創造」というものが、実際には存在しないけれども、理念的に想像されるべきではなかろうかと愚考する次第です。
なんの話だったかというと話体、会話体ですね。結論は、他人がどう思おうと、本人が芸術だ、文学だ、と思えばそれは芸術であり、文学なのです。そこんとこ、夜露死苦!
📓
ことは、そう単純ではなくて、もしそうであれば、単に文末処理の問題に過ぎなくなります。これだと、内容なり視点なりはほとんど変化がありません。
従来の日本の近代以降の文芸評論家はいわゆる常体で書いてきました。常体が常態だったのです。ほぼ唯一の例外は中村光夫です*。彼のみは敬体で書いていましたが、正直に言うと、単に文末がただそうなっているだけなのです。三浦さんは、「だから花がない」のだと断じています。つまり、文芸、文の芸になってない、人をその文章でアトラクトしない、というようなことかとは思いますが、まー、同感です。
*一部敬体で書いているのが、三浦さんも指摘しているように劇作家・批評家の福田恆存(三浦『青春の終焉』p.212)。「つねあり」と訓みますが、一般的には「フクダ・コウゾン」と呼ばれます。近年では文芸評論家の加藤典洋が一部の著書を敬体で書いています。また、新書など一般向けの論著を敬体で書く人も増えてきました。
2 『この本がいい』の「あとがき」の文体――「読者の召喚性」
三浦さんの文体は或る種の散文詩を思わせるような緊密な表現で知られています。
ところが、この「あとがき」はどう書かれているのか分かりませんが、奇妙な文体で書かれています。
比較のために、ほぼ同時期に書かれた『身体の零度』の「あとがき」の冒頭を引用してみます。
本書はいうまでもなく端緒にすぎない。あるいは試行錯誤の一過程にすぎない。調べなければならないことは膨大であり、考えなければならないことはさらに多い。
にもかかわらず上梓するのは、かりに端緒であれ、また過程であれ、個人的な思索にとどまってよいとは思えなかったからだ。この、さまざまな領域を横断する主題を、やはりさまざまな領域の方々に考えていただきたいと思った。とりわけ、私などよりはるかにふさわしい場にいる若い研究者の方方ママにぜひ考えていただきたいと願っている。(三浦「あとがき」/『身体の零度』p.278)
これでもまだ実務的なことが書かれているが、――、つまり「あとがき」と言いながら、本文と同じテンションというケイスもあるが、この緊張感が本来の三浦さんの文体です。なにやら空中に浮かんでいて、或る種の非日常的な空間で話されている気がします。三浦さんの理論で言えば、「あの世」、「彼岸」に接続する、連続する文体です。
ところがこれです。元々、対談集への「あとがき」ですから、いつもとは違って、いささかテンション低めというと、なんですが、比較的日常に近い感じで書かれています。
書き出しはこうです。
講談社のPR誌「本」の編集長の鷲尾賢也さんから、対談でブックガイドのようなものをやらないかと言われた。もちろんすぐに引き受けた。まず、彼からの申し出である。よほどのことでもないかぎり断るわけにはいかということも、むろんあった。けれど、ホンネを言えば、本をめぐって自由に話をするという企画そのものが嬉しかったし、ありがたかったのである。(三浦『この本がいい』 p.641)
全く違いますよね。要するに文末がどうということではなくて、先の例と比べると地上に降りてきたような感じがします。「この世」、「此岸」、言葉的に妥当かどうか分かりませんが、地に足が着いている文体ですが、ただ、文・芸と言えるかどうかは別の問題です。
対談の文体に引っ張られたのか、意図的だったのか、ちょっと分かりません。
ま、こんな風な出だしだったのも呼び水になっていたかも知れませんが、段々書いているうちに興が乗ったのでしょう、文章の途中で、文体がさらに変わります。年表について論じていて、レヴィ=ストロースが『野生の思考』の中でサルトルを批判しているという下りです。サルトルは分かっとらん、という訳ですが、そこでこうなる。
ちょっと本を持ってきてみる①。
ええと②、確か 『野生の思考』の最後のほうの、「歴史と弁証法」の一節でした③。あれあれ②、「これはほとんど歴史の不可能性についての言及で、明らかにゲーデルを意識している」なんて書きこみまである①けれど、これも考えはじめると面白い問題なんだけど、それはともかく、例えばこんな一節だ。(三浦『この本がいい』 p.648。傍線部と番号は引用者)
という具合にレヴィストロースの引用が始まる訳だが、これは一体どういうことでしょうか?
いやー、ただ、フランクに書いてるだけじゃん、と言えば、そりゃそうなんだけど、もうちょっと突っ込んでみます。
① 具体的な行為についての記述がある。
② 感動詞を伴った会話表現になっている。
③ 「確か~でした」、これも会話表現ではあるが、自分が自分に確認することによる表現。ひいては読者に対する確認にもなっている。
といったところですが、要はここから浮かび上がってくるのは具体的に筆者が書斎で原稿用紙を前にして、呻吟(しんぎん)しながら、呻吟というのは苦しみながらってことね、singingしながらじゃないよ、どうして鼻歌を歌いながらになるんだ、で、呻吟しながら原稿を書き進めている様子が目に浮かぶ、つまり、現在性、今まさに書いてるよ、考えてるよ、という状況を浮かび上がらせる視線に他ならないわけだ。
もう少し言うと、今そこに三浦さんがいて書庫からレヴィ=ストロースの『野生の思考』を持ってきて、われわれ読者に、「ほらここだよ、こう書いてあるね」と言って語りだす、そんな印象を与える。これを一旦、「読者との対話性」とか、その場に読者が呼び出されるので「読者の召喚性」、召喚ていうのは召喚獣と同じで、「あの世」? 「この世」? どっちだ、いずれにしても別世界、別次元にいた読者をモンスターみたいに呼び出す効果があるってことなんだけど。
ちょっと無理があるかな?
でも、この表現は、突然やってきた、降ってきた表現だと思うんだけど、つまり、突然ここで文体が変わって、またすぐ戻ってしまうんです。普通なら、ここは直すところだけど、直さなくて正解だと思いますね。
あと数回、この文体と通常の文体が入り混じることになるんですが、最初に偶然やってきた後は意図的にこの文体を採用することにして、修正の必要なしとしたんだと思います。
というのは、この文体には先例があるからです。
3 丸谷才一の独特の文体
言うまでもなく、丸谷才一の独特の文体です。丸谷さんは旧仮名遣い、一部旧字という変則的な表記法で有名ですが、それとは別に、先ほど触れた点で言えば、基本的には常体ですが、要所要所で敬体やら、会話体を入れてくる、まさに緩急自在とはこのことです。適切な引用箇所とは思えませんが、ちょっと読んでみましょう。敬体、です・ます調、会話体の箇所に傍線を引きます。
小説論で厄介なのは筋の紹介ですね。適当にあれを入れないとわからなくなる。もちろん専門家向けならそんなことは気にしなくてすむけれど、しかし批評家や学者だつて誰でも筋を覚えてゐるわけぢやないし、それどころか、読んでない場合だつてかなりある。そしてわたしは、なるべくなら大勢の人を相手にして、わかりやすく、小説の楽しさについて語りたい。
でも、その点、『坊つちやん』なら大丈夫です。みんなが知つてゐる。説明する必要がない。第一、夏目漱石の……なんて作者名を言ひ添へたらをかしいくらゐでせう。読んでない人はゐないし、みんながよく覚えてゐる。あれは忘れられない小説なんです。(丸谷才一「忘れられない小説のために」/丸谷『闊歩する漱石』2000年・講談社・p.7。傍線引用者)
恐らく、筆者名を隠して、この本文を出して、さあ、誰の文ですか、とやっても、或る程度の読書をしている人なら間違えようがない、独特の文体です。丸谷さん自身が、ここで述べているように「なるべくなら大勢の人を相手にし」たい、その為に入念に準備された文体です。
ここは丸谷才一について語る場ではないので、詳しい分析は省きますが、引用例は2000年に出された「漱石論」、つまり評論ですが、この文体はどこから来ているかというと、もう一回言うと詳しい分析は省きますが、随筆ですね。これもまー、引用が適当になってしまう、つまり、開いたところを、とりあえず読んでみる、ということだけど、読んでみる。先ほどと同様に、敬体、です・ます調、会話体の箇所に傍線を引きます。
昔、電報といふものがあつた。正確を期して言へば、いまでもあることはある。
しかし、電話が普及したせいで、慶弔用にしか使はれなくなつたんですね。慶弔用以外には、大学入試の速報と、それからサラ金の催促に使ふんださうです。後者は、何月何日たしかに催促しましたよといふ證拠になるから。内容證明だの、配達證明だのでやったんぢや、高くつくのである。やはり、サラ金業者なんてのは、かういふことにかけては頭がいいなあ。(丸谷才一「電報譚」/丸谷『軽いつづら』1993年・新潮社/1996年・新潮文庫・p.22。傍線引用者)
どうです。続きが読みたいでしょ。こういう随筆は、落ちが大切ですから、それをお話するわけにはいきません。落ちって落語じゃあるまいし、って思いますが、近代日本語の文体の問題は、当然明治になって突然、覚醒する訳ではなくて、江戸からの流れが脈々と流れているのは言うまでもありませんが、当然、落語、あるいはその台本、というか口述筆記の文体が明治仕初期の、いわゆる言文一致の問題と関わってくるんですが、それもここでは省略。要は落語の文体や発想は結構大きいぞ、とご理解頂ければとりあえずOKです。
つまり、この、或る意味孤高と言ってもよい丸谷さんの文体は相当大きな意味を、三浦さんにとっても、現代文学の作家、批評家たちにとっても、あるいはそれらを享受するわれわれ読者にとっても、大きな意味を持っているとわたしは思っていますが、とりあえず三浦さんに絞ります。
いずれにしても、三浦さん自身はこの種の随筆、エッセイの類は全くと言っていいほど書いていませんが、この丸谷さんの出世作と言ってもよい『たった一人の反乱』の講談社文芸文庫版、前章でお話したように、やはりローマ字の著者名がありませんね、これに三浦さんが解説を書いています。
丸谷才一の『たった一人の反乱』というのは、じつは日本の文壇に対する「たった一人の反乱」だったのです。
などというと、これはまことに穏当を欠く発言になるかもしれないが、しかし、確かにそういう面があるのである。もっとも、反乱の相手は必ずしも日本の文壇とは限らないかもしれない。もう少し広く、日本の小説、 いや日本の文学と言ったっていいかもしれない。あるいは世界の小説、世界の文学と言ったっていい。だけど、そうなると、もっと穏当を欠くことになりかねない。ここは、小さく、日本の文壇、すなわち日本の小説界ということにしておいたほうが無難だろう。 つまり、明治以降の日本の、小説を中心にした文学の流れに対する反乱ということである。(三浦雅士「解説 たった一人の小説家の反乱」/丸谷才一『たった一人の反乱』(原著1972年・講談社)1997年・講談社文芸文庫・p.620。傍線引用者)
なんだ、少ないじゃないか、と仰るかも知れませんが、そもそも、この書き出しから既に丸谷節で、一読三浦雅士の文だと誰も思いません。で、まだ、調子が出てなくて、途中から徐々にこの傾向が強くなっていきます。
無論、これは先輩作家・批評家に対する、文体模写による敬意の表れと見るべきだが、何故にくどくどと、この文体の話をしているかというと、後に、2008年ですが、突如文体の変更を一度だけしていて、また元に戻しているからです。というか、そういう意図がご本人にあったかどうかは分かりませんが、見た目上はそうなってます。
『漱石――母に愛されなかった子』がそれです。この内容そのものはまた別途触れますが、ここでは、大変読み辛い文体のことです。
4 『漱石』の独特過ぎる文体――あの世とこの世の往還運動
読み辛さは一点なんですが、今までお話ししてきた常体・敬体の混在が今一つ形になってない気がする。
もう一つは、読み辛さというよりも、これはOKなのか、ということですが、引用文を地の文に地続きに入れてしまうことです。ちょっと読んでみます。例のごとく敬体・会話体には傍線を引き、本来カギカッコなどの引用符で括るべき箇所はゴシック(太字)で示しました。
漱石は母に愛されなかった子だった。少なくとも漱石はそう思っていた。そのことはたとえば『坊っちゃん』を読めばすぐに分かります。
【コラム 7 岩波新書の漱石論】
コラム ☕tea for one
~岩波新書の漱石論~
漱石といったら岩波書店だが、とりあえず岩波新書に限って、漱石論がどれくらい出されているか調べてみました。すると意外なことに気づきました。1967年の吉川幸次郎のものは文字通り、漱石の漢詩を注釈したもので、これはこれでないと困る必須アイテムですが、いわゆるガチの漱石論ではないですね。それ以降、相当月日が経ち、2002年になって、ようやく作家の島田さんが書きます。およそ30年ぶりです。
その後、ガチ目のものは④の三浦さんのと⑤の十川さんのものでしょう。
この理由は比較的簡単で、岩波新書で、という括りをしてしまったわたしが悪いのですが、いわゆる定番の漱石論っちゅーやつがあるからですね。
つまり、漱石の直弟子であるところの小宮豊隆の『夏目漱石』(1938年・岩波書店)が1953年に上中下の3巻本で岩波新書ではないが、装幀がそっくりの新書判の形で発行されていたからだと思います。
2016年~17年にかけて多くの漱石論が刊行されていますが、これは岩波が2016年から全集の新版『定本 漱石全集』の刊行を始めたからです。つまり、言葉は良くないが宣伝の一環ですね。まー、仕方がない。
①吉川幸次郎(中国文学研究者)『漱石詩注』1967年。
②島田雅彦(作家)『漱石を書く』2002年。
③坪内稔典(俳人・日本近代文学研究者)『俳人漱石』2003年。
④三浦雅士(文芸評論家)『漱石――母に愛されなかった子』2008年。
⑤十川信介(日本近代文学研究者)『夏目漱石』2016年。
⑥赤木昭夫(科学史家)『漱石のこころ――その哲学と文学』2016年。
⑦小林敏明(哲学・精神病理学・日本近代思想史研究者)『夏目漱石と西田幾多郎――共鳴する明治の精神』2017年。
以下は岩波ジュニア新書。ジュニア新書を侮ることなかれ。
⑧姜尚中(政治学者)『姜尚中と読む 夏目漱石』2016年。
⑨小山慶太(物理学者)『漱石先生の手紙が教えてくれたこと』2017年。📓
親譲りの無鉄砲で子供のときから損ばかりしている、というのが『坊っちゃん』の語り出しです。以下、歯切れのいい口調で腕白時代の話が続く。どんなに負けん気の強いいたずら者だつたか、とても説得力のある例を四つほど挙げたあとで、まるでその無鉄砲の理由であるかのうに、おやじはちっともおれを可愛がってくれなかった、母は兄ばかり贔屓ひいきにしていた、という有名な台詞が出てくる。
おやじはちっともおれを可愛がってくれなかった、母は兄ばかり贔屓にしていたというのは、兄弟姉妹があれば、たいていはそんなふうに思えるときがあるものです。そうだ、自分もそうだよ、と思う読者は少なくないだろう。『坊っちゃん』が多くの読者を獲得した理由のひとつだと思われる。子供は、幼年時代のあるとき、自分だけが親に、とりわけ母親に愛されていないのではないかと、少なくとも一度は疑う。ルナールの『にんじん』とか、下村湖人の『次郎物語』とか、同じように母に愛されなかった子を主題にした小説が、ひと頃よく読まれたものです。(三浦『漱石――母に愛されなかった子』p.2。傍線、ゴシック変換引用者)
どうですか。読み辛いでしょう。そんなことを誇っても仕方ないんですが、でも、内容はとてもいいんです。
引用符の問題は後で論じますが、この常体/敬体・会話体の混用が読みずらい原因ですね。残念ながら人をいらいらさせますね。
ところが、三浦さんの最初の新書であるにも関わらず、あまり評判にならなかったと思います。印象ですが。
恐らく、視点が不安定というか、どちら側に批評家の主体を置くのか、ということなんじゃないかな、と思います。どいうことかというと、敬体・常体混用と言っても、基本はどちらかが主軸になって、もう一方が補完的に使われる、という具合ですね。
例えば、常体が基本で書いていて、要所要所で敬体・会話体が入るというのは、あたかも途中で合いの手が入るような感じです。
逆のケイスは、多分、講演の速記なんかがそれに当たると思いますが、ずっと敬体、会話体で話して来て、ここだ! という大切な箇所に来ると常体で言い切るという具合でしょうか。
常体
だ・である調
永遠
あの世
彼岸
敬体・会話体
です・ます調
現在・一瞬
この世
此岸
【表 1 常体と敬体・会話体の比較】
つまり、通常の常体で書かれている文章は、筆者は「あの世」にいて「永遠」の時間に属するものとして、批評の言葉を繰り出す。そこに敬体・会話体が混用されるということは、その瞬間だけ、筆者が「この世」に「降臨」して、読者に問いかけるのだ。言うなれば、神様が今まで、あれはよい、それは駄目とかの御託宣を降ろしていたのが、敬体・会話体を使うことによって、いわゆる「人の子」として、――あ、この辺ちょっとやばいかも、その辺を歩いているおっさんとか、JKとかに「ですよね?」とか言って話しかける訳だ。突然、「ですよね?」とか言われても、言われた方は結構困るな。
逆は、――さあ、いよいよやばいぞ、普通は、人間として「この世」で活動してるんだが、ときどき、不図我に返ったかのごとく、天国のことを思い出すわけだ、あ、まじやべ、オレ神ジャン、とか言って。
だから、そういう意味合いにおいて、この常体/敬体・会話体の混用はあの世とこの世の往還運動とも言えるわけですが、話を戻して、三浦さんの『漱石』の、この文体は先ほど述べたようにどちらかに軸足が立っておらず、あたかも彷徨える浮遊霊のごとくあの世とこの世のどちらにも所属しないが故に、不安定な、あるいは不気味な印象を与えたと言えます。
さて、なぜ三浦さんはこんなことをしたのでしょうか。内容はともかくとして、この文体については相当人を選ぶというか、チャレンジングな文体であることは確かです。少なくとも、入門書、啓蒙書であるところの新書という枠ですべきではなかったかもしれない。いや、むしろ逆に入門書だからこそ、こうなったのかもしれません。三浦さんはこの『漱石』論の表記の問題について、その「あとがき」でこう述べています。目的に当たるところをゴシック(太字)で、実際になされた方法に傍線を引きました。カッコ内の文言は勝手に書き加えたものです。
漱石像をくっきりさせるために(目的①)、引用をすべて地の文に流し込んでしまいました(方法①)。したがつて旧字旧仮名はすべて新字新仮名になってしまった。また、漱石独特の文字遣いを一般的な文字遣いにし、地の文とのつながりを分かりやすくするために前後を置き換えたりするなど、一字一句をそのまま引用しているわけではない(方法②)。漢詩、漢文、また漢文的な文章にいたっては、意訳してしまっている。漱石を敬愛する人々の顰蹙を買うとは思いますが、本書を手にとってくださった方に、短い紙数のなかで、とにかくこれだけは伝えたいという、その目的のため(目的②)にはやむをえない方法でした。ぜんぶ、話しかけるように書かなければならなかった(方法③)のです。拙いながらも、とにかく説得したかったから(目的③)です。漱石ファンの海容を乞います。(三浦「あとがき」/『漱石』p.p.246-247。ゴシック変換・傍線・カッコ内引用者)
くだくだしく、註記を書き加えましたが、まとめる以下のようになります。
【目的】
①漱石像をくっきりさせる
②短い紙数のなかで、とにかくこれだけは伝えたい
③とにかく説得したい
②と③は同じことですね。だから「漱石像をくっきりさせて、それをとにかく伝えたい」ということでしょうか。
【方法】
①引用をすべて地の文に流し込む
②一字一句をそのまま引用しているわけではない
③ぜんぶ、話しかけるように書かなければならなかった
①は引用符を使わないということで、であるなら表現が変わってしまうこともあるということ。で、ここには直接は常体/敬体・会話体混用の問題は触れられていないが、それすなわち③の「話しかけるように書く」という点に①②も統合されると思います。
でも、そういう印象が感じられなかったのは先に申し上げたように視点がどっちつかずの印象を与えるからだとわたしは思います。
さて、一体これはどこから来たのでしょうか?
5 講演体
恐らく、ここで三浦さん自身が言っているように実際に人前で話した講義なり講演なり、あるいは編集者を前に話すやり方もありますが、それを文章の形にすればよかったかもしれません。
例えば、三浦さん自身がその文庫解説を書いている、哲学者・木田元さんの『反哲学入門』(2007年・新潮社/2010年・新潮文庫)は、木田さんが編集者を前に話したことを文章に起こしているもので、したがって文体は完全敬体です。ちなみに、三浦さんの、その文庫の解説「名演奏家・木田元の秘密」は混在型で書かれています。
個人的な判断にはなりますが、この文体で成功しているのは、やはり講演の内容を文章に起こしたものです。残念ながら、三浦さんはあちこちで講演をされているようですが、講演集のような形ではまとめられていません。
が、例外的にそれが残っているものがあります。後に述べるように、東京の世田谷文学館での連続講演会の記録がそれです。三浦さんが参加しているのは3冊です。
①『村上春樹の読みかた』2012年・平凡社。
②『辻井喬=堤清二――文化を創造する文学者』2016年・平凡社。
③『大岡信の詩と真実』2016年・岩波書店。
このうち③に収録された「詩人ふたり」は詩人・谷川俊太郎さんとの対談なので、一旦措くとして、①に収録された「言葉と死」と、②に収録された「二つの名前を持つこと」はいずれも三浦さんにとっても極めて重要かつ大変濃度の、高密度の講演の記録になっています。とりわけ、②の辻井喬論「二つの名前を持つこと」は日本語で書かれた文芸批評の中でも内容は無論のこと、今までお話ししてきた常体/敬体・会話体の融合というのが期せずして、つまり、類稀なる偶然によって現出したものと考えていますが、それが高いレヴェルで達成されています。①についても、②についてもいずれお話しいたしますが、ちょっとこのことを記憶の片隅に留めておいていただけると幸いです。
で、さっきの問題に戻ります。
さて、一体これはどこから来たのでしょうか?
6 小林秀雄の文体
1 小林秀雄の講演
これは、今お話ししたように講演と関わりがあります。講演の起こしなど誰でもやってるじゃん、と言われれば、確かにそうです。偶々三浦さんに講演集がないだけで、他の名立たる評論家たちは自身の講演集を刊行しています。
とりわけ、ここで重視せねばならぬのが、他ならぬ小林秀雄その人です。
小林秀雄については後に詳しくお話しいたしますが、――ってか、そんなんばっかやん、仕方がない、同時に100ぐらいのことを話すことができないのが難点ですが、三浦さん自身も、憑依かれたかのごとく、小林を論じています。
一旦ここでは、小林の後期から晩期にかけて見られた、講演の書き起こしについてです。
小林の講演のいくつかは今でもCDなどで視聴できますし、やはり複数の代表的な講演のテキストは文庫や全集、全作品などで読むことができます。
これは大変有名な話ですが、小林は講演をしたあと、その速記を元に徹底的に手を入れて発表の文章としたとのことですが、その例を実際に見ることができます。先に触れたCDの講演は学生を対象としたもので、そのあと学生の質問に答えているのがCDにも入っています。その学生の質問に答えた部分が、『学生との対話』(2014年・新潮社)との書籍になっています。
小林の著名な講演は複数ありますが、「信ずることと知ること」というのが嚆矢になるかとは思います。
そもそもは「信ずることと考えること」の題目で、1974年8月に学生を対象に講義されて、翌75年に現行題に改定されて『日本への回帰』第10集(国民文化研究会)に収録されました。その後、76年に、改稿、その決定稿を雑誌『諸君!』7月号に掲載され、各書籍に収録され、今に至ります。
で、そこに元の講演、というか講義に近いとは思いますが、元の形、話したままに近いものと、事後的に手を入れたものの2つのヴァージョンが収録されているのです。
大変興味深いので比べてみましょう。最初がオリジナルに近いもの、二つ目が、現行の改稿決定版です。これらは敬体・会話体が元になっているので、常体の箇所に傍線を引いてみましょう。
この間、ユリ・ゲラーという青年が念力の実験というのをやりまして、大騒ぎになったことがありますね。私の友達の今日出海君のお父さんというのが、今は亡くなりましたが、日本郵船の一番古い船長さんでした。その人が船長をやめてから、心霊学というものに凝って、インドの有名な神秘家、クルシナムルテという人の会の会員になりました。だから僕はああいうことは学生の頃からよく知っていました。ただ念力というような超自然的現象についての話が、世間を騒がすという事は、時々ある。私は、そういう現象は常にあるが、これが世間の大きな話題となるという事には、いろいろな条件が必要だ、そう考えています。ああいう不思議がいつもある、いつも私達の生活には随伴している事を疑いません。ところが、これを扱う新聞や雑誌を注意して見ていますと、その批評は実に浅薄なのですね。世間には、不思議はいくらもあるのですが、現代のインテリは、不思議を不思議とする素直な心を失っています。テレビで不思議を見せられると、これに対し嘲笑的態度をとるか、スポーツでも見るような面白がる態度をとるか、どちらかでしょう。今の知識人の中で、一人くらいは、念力というようなものに対してどういう態度をとるのが正しいかを考える人がいてもいいでしょう。ところがいない。彼等にとって、理解出来ない声は、みんな不正常なのです。知識人は本当に堕落していますね。皆おしゃべりばかりしていますが、そういうことに対する正しい態度がないのです。(小林秀雄「講義 信ずることと知ること」/小林『学生との対話』2014年・新潮社・p.p.30-31)
一段落がめっちゃ長いね(笑)。改稿版です。
この間テレビで、 ユリ・ゲラーという人が念力の実験というのをやりまして、大騒ぎになったことがありましたね。私の友達の今日出海(こんひでみ)君のお父さんは、もうとうに亡くなったが、心霊学の研究家だった。インドの有名な神秘家、クルシナムルテという人の会の日本でただ一人の会員でした。私はああいう問題には学生の頃から親しかったと言ってもいい。念力というような超自然的現象を頭から否定する考えは、私にはありませんでした。今度のユリ・ゲラーの実験にしても、これを扱う新聞や雑誌を見ていますと、事実を事実として受けとる素直な心が、何と少いか、そちらの方が、むしろ私を驚かす。テレビでああいう事を見せられると、これに対し嘲笑的態度をとるか、スポーツでも見て面白がるのと同じ態度をとるか、どちらかだ。念力というようなものに対して、どういう態度をとるのがいいかという問題を考える人は、恐らく極めて少いのではないかと思う。今日の知識人達にとって、己れの頭脳によって、と言うのは、現代の通念に従ってだが、 理解出来ない声は、みんな調子が外れているのです。その点で、彼等は根柢こんてい的な反省を欠いている、と言っていいでしょう。(小林秀雄「信ずることと知ること」/小林『学生との対話』2014年・新潮社・p.p.159-160)
後半かなり表現に手が入っているが、それよりも、全体のトーンがかなり違う、オリジナルのいささか間延びした印象が、強い緊張感に支えられているのが分かります。適切な常体の混在させ方です。まさにこれこそ、文章の達人の為せる技だと感心せざるを得ませんね。つまり、ずーっと敬体・会話体で書いていくと間延びしてしまうんですね。
2 「小林の文章を入試問題に出すな」
さて、問題はこの小林の文体です。
コラム ☕tea for one
~日本語にうるさい人たち㊤~
丸谷さんがどれくらい日本語にうるさかったかは、今ここで全てを挙げきれないくらい数多くの日本語に関する著書を出していることでも分かりますが、――少しだけ例を挙げると、手に入りやすいものは、新潮文庫から出ている『完本 日本語のために』(2011年・新潮文庫)と、これはいささか入手が難しいでしょうが、――古書店か図書館で探してみてください、盟友である国語学者・大野晋(すすむ)さんとの共編になる叢書『日本語の世界』(全16巻・1980年~86年・中央公論社)の中の一冊『国語改革を批判する』(丸谷編著・第16巻・1983年・中央公論社。これに書き下ろした論文「言葉と文字と精神と」は先に挙げた『完本 日本語のために』にも収録されている)を上梓しています。まーこれが極めつけでしょうか。
わたしが3億年前に大学に入ったとき、教養ゼミ、つまり一般教養なんだけどゼミ形式でやる授業があって、作文、――文章作法だったかな、の授業があって、そこに新聞社の記者の方が担当していました。そういう変な大学。で、その先生が言うには、まず日本語の文章作法ということでは、まず、当時『朝日新聞』の記者だった本多勝一の『日本語の作文技術』(1976年・朝日新聞社/1982年・朝日文庫/新版・2015年・朝日文庫)と、丸谷才一の『文章読本』(1977年・中央公論社/1980年・中公文庫/新版・1995年・中公文庫)を読め、と仰ったんです。まー、一応、初年兵に対しては妥当な指示でしょうね。(㊦に続く)
【コラム 8日本語にうるさい人たち㊤】
実は、わたしは数えたのですが、恐らく他の方ともさほどぶれないはずですが、大学の入試問題に、或る時期から最もよく出題されるようになったのは、イギリス文学者、というかエッセイストの外山滋比古ですが、――例の、東大生と京大生が最もよく読んだという嘘か真実か分かりませんが『思考の整理学』の著者なんですが、それ以前は小林秀雄がその長期政権を担っていました。ところが、これもしばしば言われることですが、小林の、特に初期から中期にかけての文章は、悪文、つまり、飛躍や、論理の逸脱、言葉の十分な定義なしに自己の用法で文章が進んでいく、過剰なレトリック、ためにするための反語的用法など、数え上げればきりがないですが、要は普通の人が普通に読むとさっぱり分からない、ということになるのが普通なのです。――そう思いません?
日本語にうるさいことで知られた作家・批評家の丸谷才一さんも同じようなことを言っている。あ、すいません、わたしの方が後ですから、これはちょっと失礼ですね、最初から丸谷さんを引用すればいいんでした。
【コラム 9 日本語にうるさい人たち㊦】
コラム ☕tea for one
~日本語にうるさい人たち㊦~
参考になったかどうかというのははなはだ疑問ですが、――つまりこれは普通に考えれば分かることですが、この手の文章作法の本は、あくまでもオレハコウ書イテルヨナ、という自己確認のものであって、技術論そのものには対しては、さほど影響を受けないものです。文章というものは、やはり、自分が気に入った作品を多読することによってしか手に入れられないものだとは思いますが、でも、この種の本は買って読んじゃいますよね。自己啓発書と同じで、読んで満足して、結局何も変わらない、というやつね。あ、別に批判してる訳じゃないですよ。要は自分の問題だということです。
ただ、この作文界、――いやこれだと丸谷さんの逆鱗に触れるか、文章作法界の二巨頭に共通するのは、――恐らくそれ以外は水と油ぐらいに接点がなさそうですが、両者とも自著に、原則として自らの表記法を掲げていることです。本多さんは「凡例」として(本多『日本語の作文技術』p.8)。丸谷さんは「わたしの表記法について」。それがなくても旧仮名遣いで一目瞭然ではありますが。漢字は旧字ではなくて、原則新字ですが、一部気に入らない(そんな勝手な!)ものは旧字を使っていることもつとに知られています。例えば、昼は晝、蔵は藏、という具合(丸谷『桜もさよならも日本語』新潮文庫・p.262)。まー、これぐらいのこだわりを自らの母語には持ちたいものですね。
📓
で、丸谷さんはどう言ってるかというと、多くの大学で小林の文章が出題されていることについて触れたあとこう述べています。
しかし、小林はたしかに偉大な文藝評論家ではあるにしても(そのことをわたしは認める)、彼の文章は飛躍が多く、語の指し示す概念は曖昧あいまいで、論理の進行はしばしば乱れがちである。それは人試問題の出典となるには最も不適当なものだらう。(丸谷「小林秀雄の文章は出題するな」/丸谷『桜もさよならも日本語』1986年・新潮社/1989年・新潮文庫・p.243)
念のために、若手(でもなかった、失礼)、文体が若手の、で、なおかつ、『文章読本さん江』(2002年・筑摩書房/2007年・ちくま文庫)で栄えある第1回小林秀雄賞受賞評論家・斎藤美奈子さんに聞いてみよう。
もっとも小林秀雄はかつて「試験に出る評論文」の代表選手だったのだ。試験に出る評論文の条件は名文であることではない。「論旨がわかりにくいこと」だ。論旨がすぐわかったら試験にならないからね(その点は試験によく出る「天声人語」も同じ)。(斎藤美奈子「15 小林秀雄『モオツァルト・無常という事』――試験に出るアンタッチャブルな評論家」/斎藤『文庫解説ワンダーランド』2017年・岩波新書・p.148。傍線引用者)
つまり、小林の文章は分かりづらい、というよりも端的に言って分からんのだ。
ただし、これは初期から中期にかけて、まー人によっては後期の『本居宣長』も分からん、という方もいらっしゃるやも知れぬが、比べてみれば、その難易度、というか悪文度の差は歴然としているとは思うけどね。
個人的な話になりますが、ちょっと記憶が曖昧ですが、最初わたしが小林を読んだのは、多分、中公文庫から出ていた『人生について』だったと思います。今手元にないので、うろ覚えで話しますが、これには、名講演として評判の「私の人生観」や「信ずることと知ること」などが入っていて、今から考えるとベストの入門の仕方だったのではないかと思います。だって意味が分かったのだから。そのあと『新訂全集』の終わりの方の巻、これも大変良かったが、例の「本居宣長 補記」が入っていました。これも講演ですね。若いながら、分かってないにも関わらず、感銘を受けたわたしは単行本になっていた薄い上製の『本居宣長 補記』を読み、『本居宣長』の本編に行き、同時並行で、『考へるヒント』などの後期を文章をよんでからーの、初期の文章に突撃して、あ、これはデビュー作の「様々なる意匠」に尽きているやんけ、と思った次第にございます。
という訳で、小林の大変有名な言葉に「或る著作家に就いてはその全集を読め」というのがありますが、小林の場合、その全集を順番に読んでいくと、まず間違いなくたいていの人は即死します。ショック死します。即身成仏します。おめでとう! という事ですが、ですが、後期から晩期にかけての文章は相当次元が異なるレヴェルで、流石、批評界のラスボスはこうあるべきものか、と感慨にふけっちゃうぐらいです。
で、三浦さんと小林との関りは根深いものがあります、というよりも三浦さんの小林に対する執着は、――恐らく意図せざる執着はいささか常軌を逸したところがある気がする。これは後ほど詳しくお話しいたしますが、例えば、『小林秀雄論』という大上段に振りかぶった論著はありませんが、――確かに「小林秀雄論」という短篇の評論はありますが、三浦さんの論著の要所要所で小林が姿を現す。あたかも亡霊のように。――ちょっと怖いですね。三浦さんは必ずしも小林のことを論じている訳ではない、と断り書きを入れるが、例えば『青春の終焉』のおよそ3分の1ほどの流さでその主役を演ずるのは小林その人です。未刊行のままになっている「孤独の発明」本篇に至ってはおよそその半分の主役をも小林が演じているのです。
ここには何かがあると考えなければなりませんが、先を急がず、ゆっくり考えていきましょう。なにせ、わたしにも分かってないからね。
3 小林秀雄の講演から来ている文体
で、まず文体の問題です。三浦さんは先ほどお話しした、この後期以降の小林の文体について『青春の終焉』の中で、小林を太宰治と並べ、その文体に落語、――笑いを伴う話芸を持つものとしてまとめています。確かに、わたしの記憶が確かであれば、小林の講演の録音がLPレコードとして発売された時、新聞では、少し甲高い声音で、名高い落語家の師匠の口演を思わせる云々という紹介があり、早速買って聞いてみた記憶がある。もちろん、落語との関連は無論考慮にいれねばなりませんが、一旦ここでは、講演の問題から考えても見ましょう。
三浦さんはこう述べています。
小林秀雄が講演をはじめるのは戦時下である。「事変の新しさ」「文学と自分」は一九四〇年、「文学者の提携について」は四三年の講演である。同じく講演を思わせる「歴史と文学」は一九四一年。そして、これらの講演の体験から生まれたのが「無常といふ事」の文体である。『一言芳談抄』の一節を引いた後に、次の文がつづく。(三浦「十九世紀日本文学」/『青春の終焉』p.210)
と、この後に小林の「無情といふ事」の一節が引用されていますが、そこは端折ります。と言っても気になる方もいると思うので、そこは註に回します*。巨匠、すいません。
* 「先日、比叡山に行き、山王権現の辺りの青葉やら石垣やらを眺めて、ぼんやりとうろついてゐると、突然、この短文が、当時の絵巻物の残欠でも見る様な風に心に浮び、文の節々が、まるで古びた絵の細勁な描線を辿る様に心に滲みわたった。そんな経験は、はじめてなので、ひどく心が動き、坂本で蕎麦を喰ってゐる間も、あやしい思ひがしつづけた。あの時、自分は何を感じ、何を考へてゐたのだらうか、今になってそれがしきりに気にかかる。無論、取るに足らぬある幻覚が起ったに過ぎまい。さう考へて済ますのは便利であるが、どうもさういふ便利な考へを信用する気になれないのは、どうしたものだらうか。実は、何を書くのか判然しないままに書き始めてゐるのである。」(小林秀雄「無常といふ事」/『文學界』1942年6月号/三浦『青春の終焉』p.210から援引)
長くなりますが、引用を続けます。
「である」調、「ですます」調を綯いまぜにしているわけではないが、文に潜む強弱緩急は、講演から穫得した技術である。そしてその強弱緩急は、文語の雰囲気と口語の雰囲気を巧みに取り混ぜているところから生じている。『一言芳談抄』はむろん文語である。その引用の後につづく体験は文語に接し、その体験を考えようとしている現在は口語に接している。この文体がそのまま『モオツァルト』の中心に据えられたことは指摘するまでもない。小林秀雄は、講演を重ねることによって、体験の語り方を、そして体験の書き方を学んだのである。
戦後、講演が増えるのは、書く余裕がないほど忙しかったからではおそらくない。語りの文体そのものに関心を持ったからである。あるいは話芸を磨くことに惹かれた。(三浦『青春の終焉』p.p.210-211。傍線引用者)
果たして「無常といふ事」に、三浦さんが言うような「講演から穫得した技術」が表れているかというと、にわかには判断できかねますが、この「講演から穫得した技術」というものが「語りの文体」となり、後年の小林の文体を変えていったことは明らかだと思います。それは、むしろ、続けて三浦さんが引用している「私の人生観」に明らかだと思います。
引用を続けます。小林の「私の人生観」です。例のごとく、常体に傍線を引きます。
美しい自然を眺めてまるで絵の様だと言ふ、美しい絵を見てまるで本当の様だと言ひます。これは、私達の極く普通な感嘆の言葉であるが、私達は、われ知らず大変大事な事を言つてゐる様だ。要するに、美は夢ではないと言つてゐるのであります。併し、この事を反省してみる人はまことに少い。それは又かういふ事にもなると思ふ。海が光ったり、薔薇が咲いたりするのは、誰の眼にも一応美しい。だが、人間と生れてそんな事が一番気にかかるとは、一体どうした事なのか。現に、会場に絵を並べた二人の画家は、四十何年間も海や薔薇を見て未だ見足りない。何といふ不思議だらう。さういふ疑問が、この沢山な鑑賞者のうちの誰の心に本当に起こっているだろうか。そういう疑問こそ、絵が一つの精神として諸君に語りかけて来る糸口なのであり、絵はそういう糸口を通じて、諸君に、諸君は未だいっぺんも海や薔薇をほんとうに見た事もないのだ、と断言している筈なのであります。(小林秀雄「私の人生観」/『批評』1949年9月号/三浦『青春の終焉』p.211から援引。傍線部引用者)
いや、全く余計な言葉は要りませんね。目の前に鎌倉の(多分?)海がきらきら光って見えますね。こういう文章を読むと、あーほんとに小林は詩人だな、と思わされます。ただ味わってください、としか言いようがないのですが、まさにこれこそ「語りの文体」と言うべきものでしょう。三浦さんはこれに続けて、更に考察を深めます。
『私の人生観』の有名な一節。一九四八年*。
講演速記そのままではもちろんない。徹底的に手を入れているのだ。 つまり、口語を書いているのである。口語を書いたこの一節の、強弱緩急のその呼吸が、「無常といふ事」に酷似していることは、当然といえば当然だが、驚くほどである。口語と文語の往還を巧みに用いた例である。(三浦『青春の終焉』p.p.211-212。傍線引用者)
*引用者註。「一九四八年」は講演が行われた年。翌年1949年に雑誌発表の後、単行本『私の人生観』として創元社より刊行されました(吉田凞生編「年譜」/『小林秀雄 百年のヒント――生誕百年記念「新潮」四月臨時増刊』2001年・新潮社・p.p.334-335)。
わたしの用語では、一般の用語法に合わせて、「常体/敬体・会話体」としているものを、三浦さんは「文語/口語」としているが、言わんとしていることは同じだと思います。まさに文章で「口語を書く」ことで、「口語と文語の往還」が可能になる訳です。
まとめましょう。三浦さんのまとめです。
小林秀雄の初期評論は、ときに美文と賞されるが、悪文である。枝葉が削がれすぎて、論理が独断に、熟慮が韜晦に見えてしまう。読むものの心に意味がまっすぐに入ってくるようになるのは、おそらく『考へるヒント』からだろう。 かつて大岡昇平は、小林秀雄に入るには『考へるヒント』からがいいいと述べたが、要するに、人が素直に読める文章を小林秀雄が書くようになったのはこの頃からなのだ。文体のこの変容が、数多くの講演を体験したことによってはぐくまれたことは疑いない。(三浦『青春の終焉』p.212)
もともとこの下りは、落語の問題、笑いの問題からこの講演による文体の創造の話になっていたので、この後、三浦さんは、その小林の書き直された講演には笑いがないとして、そこに小林の「限界」として、エッセイの文体の創造という観点で丸谷才一さんの話題に移っているが、丸谷さんについては先にもご紹介したので、よいでしょう。
問題はやはり、同じ常体/敬体混用文でも、ユーモア、というか落ちを付けずには落ち着かない丸谷さんよりも、より一層小林の文体こそ、この文脈、三浦さんの文脈ではより重視されねばならないはずです。
この文体の問題は単に文体という表面的なことに留まらず、批評家がどこにいるのか、どのように読者と対しているのかという問題と直面しているからです。それは当然、何を語るのかという思想の問題をも内包しているのは言うまでもありません。
この問題は、小林秀雄の問題として、後ほど論じていきたいと考えています。
では、本日はここまで。長時間ご清聴ありがとうございました。
🐤
202405142032
