
12月21日 ちょっとだけ映画感想文
個人的に忙しすぎて長い感想文が書けないので、観た映画の軽めの感想を書いていきます。

1917 命をかけた伝令
Amazon Prime Videoにて視聴。
要するに監督サム・メンデスのお爺ちゃんが実際に体験したできごとを映画にしたもの。
ウィリアム・スコフィールドとトム・ブレイクは突如将軍に呼び出され、ある伝令をデヴォンシャー連隊に送ることを命じられる。それは敵陣地のまっただ中を突っ切って行く、という超絶的に危険な任務だった……。
全編ワンショットで撮影された映画。カットで割れないわけだから、あらゆるところでごまかしが効かない。通常の映画では、セットはごく一部だけを作り、カメラ位置を変えながら、あたかも広大なセットがそこにあるかのようにみせかけるわけだけど、ワンカット撮影だからその手が使えない。
冒頭から塹壕の入り口から始まり、その後ずーっと塹壕の中を進んでいき、その中の様子をじっくり見せながら、えんえん主人公2人をカメラが追いかけていく。見ていると「え?どこまで作ったの、これ?」と驚く。とにかくも塹壕のシーンが異様に長く、しかもガッツリ作り込まれている。これはもう作り込むしかないから、いやはや参ったというしかない。
さらに役者を見ていると、目の前をずーーっとカメラが動いているのに、そちらのほうを一切見ない。カメラを見ずに、ずーーっと緊張感ある芝居をし続けている。その集中力の凄さとか、台詞よく覚えてるなぁとか……。
あとカメラマンも大変な映画で……。役者のタイミングが一個でもズレたらリテイク、カメラの向ける方向を一回でも間違えたらリテイク……というのがワンショット映画の大変なところ。これだけの長尺で、全員のタイミングを合わせての撮影……よくぞ作り込んだなぁ……。
でも注意深く見ていると、「カメラマンの通り道」が見えてくる。例えば前半の鉄条網を抜けるシーン、画面の右手に人一人分入れそうな空間が空いている。
問題なのはその直後のシーンで、大きな水たまりの上を、カメラがすーっと抜けていく。あそこでカメラがクレーンに切り替わるのだけど、どこで切り替わったのかよくわからなかった。
後半でも、水の中に飛び込むシーンで、実際には撮影不可能な位置から撮影してしまっている場面があって、これはいったい……? と見ていて首をひねる。見ているだけではトリックの全容が掴みきれない。舞台裏を知りたくなる作品だ。
オブジェクトの側を通過する時に切り替えがあったことはなんとなく察するのだが、詳しい仕組みがまったくわからない。魔術のような映画だった。
物語はある伝令を知らせるために、決死の覚悟で戦場を走り抜けた男を描いている。その地獄巡りっぷりが凄まじい。ワンカット撮影だからこそ生まれた異様な緊張感。カットを切り返したりしないから、役者と同じくらいの視界で、敵がどこから撃ってきているのか、とか考えながら見てしまう。とにかくも恐い。その緊張から解放される結末があまりにも秀逸で、素晴らしい。
ドラマの組み立ては、まずは「多くの人々のために!」という使命感ではなく、ごくパーソナルなところで、「デヴォンシャー連隊にいる兄を救うために!」という動機でスタートする。ウィリアムは消極的で、使命感を持っていなかった。それが半ばから本当の使命感に変わり、命がけの伝令を果たそうというドラマに代わっていく。
これはジョゼフ・キャンベルがいうところの「冒険の召命」という手法で、どんな物語でも英雄は最初、必ず一度使命を拒否する……というのがある。主人公である英雄にとって、その使命が自分にとってどういう価値のあるものなのか、が物語冒頭において定められていない。
だから『1917』でもはじまりは渋々と承諾し、その後、使命の意味を理解し、それを達成するために命をかけようとする。こういった戦争映画でも、物語の基本原則をきちんと守られている。『1917』は全編ワンショット映画というかなり特殊な構成の映画だが、本質的にはそれ以外のいろんな作品と変わらないということがわかる。
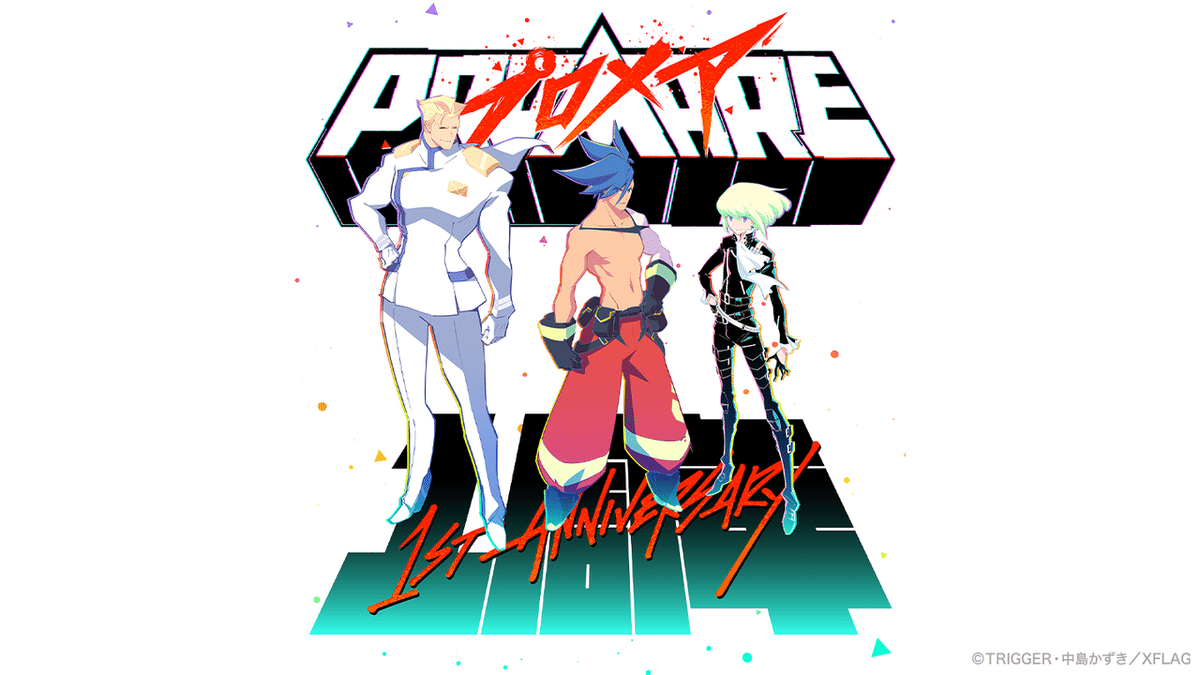
プロメア
TRIGGER作品といえば……で「うん、これこれ」っと言いたくなる、イメージ通りの作品。一応、デジタル+手書き作画の作品なのだが、見ていてもどこがデジタルでどれが手書き作画なのか……見始めた最初は区別しながら見ていたが、物語に意識が入っていくとそういう区別をせずに見入ってしまった。要するに、それだけデジタルの出来がいい、ということ。
アニメーションについてだが、なんと3コマ作画。秒間8枚しか作画されていない。
これはビックリな話で、劇場アニメーションとしての豪華さやテレビアニメーションとの違いを表現しようと思ったら、まず作画のコマ数を増やす。滑らかなアニメーションを見せて、劇場アニメならではの豪華さや、凄みを出していくものなのだけど、なんと秒8枚作画。CG映画なのに秒8枚作画。しかも、明らかに潤沢な予算があるのにも関わらず、3コマ作画にこだわっている。
要するにここがTRIGGERのコダワリで、TRIGGERはよくあるアニメーションとは違い、とことん外連味を優先した絵でアニメーションを表現する。細かく分解すると、これ変だよ、という絵でも堂々と入れて、それがアニメーションとして連なった時の見栄えを優先する。つまり、本当は繋がっていない絵の連続でアニメーションを作っちゃう。
言ってしまえば、ある意味デタラメな作りだけど、それが映像としてできあがった時のなんともいえない痛快感。はっちゃけた感じ。とにかくも気持ちいい。TRIGGERでしかできない芸みたいなもんだね。
『プロメア』ではこの、もう全編いかにもなTRIGGERらしいアニメーションで構成され、1秒でも飽きないように作られているし、1コマたりとも退屈な絵が入っていない。そういう強い絵で構成されたアニメーションを見ていると、だんだん「ああ、美しいな」という気分にもなってくる。確かにフルコマ作画はまったくないが、画面の構成やアクションの壮絶な動きで、劇場アニメーションらしい凄みを表現している。アプローチの方法が普通とだいぶ違うんだ。
TRIGGER作品……というか「キルラキル組」のチームは(今石組と呼んだほうがいいかも)、いわゆる「撮影効果」というものをほぼ使用しない。例えばufotable作品では作画後にふんだんに撮影効果を使い、奥行き感やエフェクトを一杯盛り込み、それで画面の奥行きやリアリティを表現している。(なぜufotableを例に挙げたかというと、ufoが業界で一番良い仕事をしていると思ってるから)
でもキルラキル組はこういうデジタルエフェクトを使わずに、作画であることにこだわっている。
『プロメア』という作品の場合は炎の表現。炎の作画表現が、まずいってぜんぜんリアリティがない。リアリズムに一切基づかずに、作品独自のシンボリックな絵で表現されている。火の粉の表現とか三角形で表現され、この三角形が飛び散る様……というのがなかなか格好いい。『キルラキル』では発光を十文字の作画が手書きで表現され、それが作品独自のらしさを作っていたが、それをさらに追い込んだ、という感じだ。
炎の表現が自然主義的なリアリティがまったくなく、作画生理だけで表現され、その作画生理でしかないものが画面全体を覆う。要するに放火魔と消化チームの戦いの物語だが、炎表現とキャラクターが絡み合う画面がやたらと格好いい。見ていると、なるほど、こういう画面表現をしたかったために、この設定を考えついたんだな……みたいに思ってしまう(実際はどういうプロセスで企画が進んだかわからいけども)。ここで私が「アニメーションが美しい」と感じた理由。格好いいを通り越して、美しさを感じてしまったんだ。
それで、発火能力を持った人々が最終的には動力源にされてしまう……という物語だが。見ていて、「ああ、なるほど!」と私はかなり大きなショックだった。フィクションの世界、様々な炎系能力を持った人々がいたが、どうして誰もこの発想に至らなかったのか! 炎系能力はエネルギー問題と結びつけられるじゃないか!
で、私は映画を見ながら、後半はちょっと別のことを考え始めていて……。フィクションの世界に出てくる「異能」をもうちょっと定義づけし直すべきじゃないか、ということを考え始めていて。この発想を、自分の作品に取り入れてみようか……。誰も『プロメア』をパクったとは言わんだろうし。
お話については、非常にわかりやすい。「ああ、この人が黒幕だろうな」と思った人が黒幕。期待を裏切らない。物語が世界観の奥行きを作るためのものではなく、作画の生理を活かすための舞台作りでしかない。物語自体がオマケってこと。2時間の映画だとそれで充分なのだけど、『キルラキル』のような2クールという長尺で組み立てられる物語と較べるとずいぶん薄く感じるのが惜しいところ。映画を見終わった後、Amazonのレビューを読んでみたが、作画に興味がない人には退屈だったらしく……まあ、物語の興味がある、という人が見るとそうなるわな。「物語はさておき」という作品を志向したわけだから、仕方ない。

アメリカン・ファクトリー
Netflixドキュメンタリー。
私は一日の隙間時間にドキュメンタリーを視聴している。一日10分~20分ほどで、音量も絞って、毎日少しずつ視聴する……という鑑賞方法を採っている。これも、空き時間の有効活用だ。そういうわけで、時間を取って、ガッツリ見ているわけではない。
こんな感じでドキュメンタリーはいくつか視聴したのだが、その中でも紹介したい作品がこれ、『アメリカン・ファクトリー』。
2008年、オハイオ州のとある自動車工場は閉鎖された。これによって、1万人が失業。多くの人たちが収入のアテを失い、貯金を取り崩す生活に陥り、家をなくした人もいた。
それから3年後、中国企業フーヤオ(福耀)がオハイオ州に進出してくる。元自動車工場だった廃墟を買い取り、自動車のガラスを製造する工場を操業する。
もしかしたら都会っ子は「工場が閉鎖したんだったら、別のところに勤めればいいじゃない」と軽く考えるかも知れない。でも、舞台となっているような小さな街で、1万人が即座に別の仕事に就けるわけがない。それだけの求人があるわけがない。
ついでに言うと、都会であっても1万人の失業者に即座に仕事を与えるなんて無理。
私の想像だけど……もしかすると舞台になっている街は、大きな工場があって、そこでの仕事や収入を求めて人々が集まり、発展した……みたいな街だったんじゃないかな。
とにかくも大きな工場が一つ閉鎖しただけで、街は1万人の失業者を抱えることとなってしまった。
そうした最中にやってきたフーヤオはどれだけ人々の救いになったか。職場へ行ってみると、機材は変わっているが、3年前自分たちが勤めていた工場。建物の形自体は一緒。そういう光景を見て、労働者がいかに感動したか。
ところが、いよいよ操業という時が来て、セレモニーの舞台上で、会長のとある発言がアメリカ人労働者をざわつかせる。「労働組合は作らせない」と発言したのだ。つまり、労働者側に権利を与えない。
中国側の意見によると、労働組合なんてものがあると労働者側が権利を主張し、工場での仕事を妨害するという。利益優先をしたい経営者側にとってすれば、労働組合なんていらねーという。
工場での仕事が始まると、次から次へと問題が持ち上がる。まず給料は以前の半分。労働の内容は極めて単調な上に、長時間労働。労働者達は次第に鬱っぽくもなるし、労働災害……つまり仕事中の事故による怪我が続出。
さらにフーヤオは中国人を大量に送り込んでくるのだが、中国人は無茶な指示ばかりする。例えば、フォークリフトに荷物を2つ載せて運べ、と。もし積み荷が崩落したら? そもそもフォークリフトの重量制限を超えてないか? 中国人はそんなのお構いなしで、効率優先だ、と指示を出してくる。
労働者達の鬱憤が次第に溜まっていき、工場内ストライキが始まってしまう。
一度、アメリカ人労働者達を中国本国のフーヤオに招待する場面がある。ここの場面が凄まじい。
中国本国のフーヤオはもっと巨大で、映像を見た感じ、どうやら工場内に住宅街も作ってしまっている感じ。街そのものが一つの工場みたいになっている。車でどこまで走ってもフーヤオ領地……みたいな感じ。
そこでの労働環境がトンデモなかった。こんな台詞が出てくる。
「君たちは週に2回も休日があるだろう? 僕たちは月に1~2回しか休日がない。楽勝だ」
アメリカと中国では労働文化が違いすぎる。えらい昔に、日本の自動車企業がアメリカに進出し、しかし労働文化の違いから軋轢が生まれるという映画があったが……。
タイトルはなんだっけな、と調べるとロン・ハワード監督の『ガン・ホー』が出てきた。予告編も見つからないので、これだったかはちょっとわからないのだが。こちらの映画では最終的にアメリカ人労働者たちは日本人労働者の繊細な物作りを理解し、団結していくというエンターテインメント作品になっていた。
ところが『アメリカン・ファクトリー』ではそういうわけにはいかない。アメリカと中国では埋められない谷が深すぎる。
中国企業の世界進出は今回の一件だけではなく、世界中で起きている現象。それがどんな問題を生み出しているのか。その一端を知るよいドキュメンタリーだと思うので、オススメしておこう。
いいなと思ったら応援しよう!

