
【デジタル版】とのしょう野生鳥獣新聞 第一号(2025年1月)
小豆島 土庄町 地域おこし協力隊 農業振興担当の稲葉(イナバ)です。野生鳥獣と共存していくための情報発信をしていく新聞を発行していこうと思います。
補足:この新聞は小豆島 土庄町で月1で発行されている町の広報誌に折込み、全戸配布してます。同じ小豆島の小豆島町民、瀬戸内海圏に住む方々、日本国内の中山間地などで野生鳥獣との共存を模索している方々にも読んで頂きたいと思い、デジタル版として編集し直し、再発行したものです。
データ、写真、イラスト等、輪転機印刷ではキレイに出力できない箇所も、カラーで見やすくしています。
「補足」と書かれた箇所は、デジタル版のみで追加した記述となります!
●ご挨拶
なぜ私たちは野生鳥獣と向き合わなければならないのか、どのように向き合うのかを考えていくためにも、土庄町の住民の方々と一緒に学んで行きたいと思い、情報発信していくことにしました。
第一号のテーマは「イノシシ」。
●小豆島のイノシシ生息数?
近年、土庄町でも集落に出没するイノシシが多いなと思う方がいらっしゃると思います。農業被害だけでなく、石垣が崩されたとか、車でぶつかりそうになりヒヤッとしたなど。
そもそも小豆島にどのくらい生息しているかご存知でしょうか?
実は野生動物の正確な生息数を把握することは非常に困難です。それぞれの地域で、対象とする動物の生態学的な情報などを用いて数学的な計算で推定されます。
ここでは、まずイノシシの捕獲頭数から見てみましょう。図1は、香川県本土部と小豆郡で捕獲されたイノシシの2011年からの個体数変化です。県本土部でも島でも、ある年以降から急速に捕獲数が増えています。

1990年〜2022年に狩猟及び有害鳥獣駆除で捕獲された イノシシ個体数の経年変化.
(香川県データ※1を改変)
ご存じの方も多いと思いますが、過去、島には「猪鹿垣(ししがき)」というイノシシやシカによる農作物被害を防ぐ石垣が島内にあちこちに築かれていました。つまり、石垣を作る大変な労力に見合うほど、イノシシやシカがたくさんいて、被害があったと想像できます。
しかし、近年までは小豆島にイノシシはいませんでした。香川県のデータ※1を見ると(右下の図1)、1990年以前は香川県と徳島県・愛媛県の県境のみで生息確認されており、1990年代に入り香川県内を北上、分布域が拡大し、2008年には荘内半島、翌年に小豆島で報告されたと書かれています。

((香川県データ※1から転載)
さて、イノシシの推定生息数については、香川県では5年ごとに行う「特定鳥獣管理計画※2」の中に記載があり、令和2年度(2020年度)末時点の香川県(小豆郡を除く)の生息数は約4万頭(50%信頼区間2万〜5.5万頭)という推定がなされています。これはこの年の香川県内の総捕獲頭数の約4倍に当たります。
2022年の小豆郡管内全体での捕獲頭数は、約2,700頭※2 であり、少なくともその数倍の頭数が森の中に生息していると想像できます。
どうやって島に渡ってきたのか?
島には海を泳いできたようです。YouTubeで検索すると、瀬戸内海の海を泳ぎ、他の島に渡ろうとしているイノシシ動画が複数見つかりますし、島の知人からは、海から上陸しようとしているイノシシに海岸で遭遇したという経験談も聞きました。
●イノシシの生態 ※3, 4
イノシシは牛の仲間(偶蹄目)に属する蹄を持つ動物の一種です。世界に十数種類が分布し、日本の「イノシシ」はそのうちの1種です。
イノシシは1年に1回、3〜5月頃に約4頭出産します。生まれた仔は、身体の模様からウリボウと呼ばれますが、この模様は3ヶ月ほどで消失します。メスの大半は生後1.5歳、栄養状態の良い個体は生後1年までに性成熟するようです。
繁殖期は12月終わりから3月頃で、この時期の繁殖に失敗したメスは再発情し、秋頃出産する場合があるため、早冬にも時々ウリボウを見ることがあります。
社会単位は、子供を連れた成メスの母系的グループ、単独成オスまたはメス、生殖に参加しない若齢オスのグループの3タイプとされ、基本的には定住と移動を繰り返すため、縄張りは持たないと言われています。
イノシシは夜行性の動物と言われますが、人間を避けるため早朝や夜に行動していて、実は日中にも活発に活動します。そして、行動域はその場所の食べ物量と関係して大きく変動します。
食性としては植物を主とした雑食性ですが、季節変化は大きく、特に晩夏〜秋期はミミズや昆虫の幼虫などの動物質も多くなるようです。
行動や生態については、まだまだ分からないことが多い動物のため、これから研究者や専門家の研究結果を学んだり、自分の観察結果などの最新情報も発信していきたいと思います。

最高に素敵なイラスト、ありがとうございます!
【引用文献】※より学びたい方は是非参照ください!
※1 香川県イノシシ適正管理計画 (特定鳥獣保護管理計画) 平成 24 年3月(2012) 香川県.
※2 イノシシ第二種特定鳥獣管理計画 第5期計画 (変更) 令和5年7月(2023) 香川県.
※3 第二種特定鳥獣管理計画作成のためのガイドライン(イノシシ編) 改定版 2021年3月(2021) 環境省.
※4 野生鳥獣被害防止マニュアル【総合対策編】(2023) 野生鳥獣被害防止マニュアル総合対策編企画編集委員会/農林水産省.
特集 イノシシ防除を考える。
- 研修会参加レポート -
11月14日に香川県による鳥獣被害対策指導能力養成研修会に出席しました。講師は香川県農業経営課 主任専門指導員の矢木 聖敏さん。普段は農業者との密接な活動を行い、併せて国の農作物野生鳥獣被害対策アドバイザーとして活躍する大ベテランです。
今後、土庄町で鳥獣害対策に役立つと考える、私が感じた4つのポイントをレポートします。
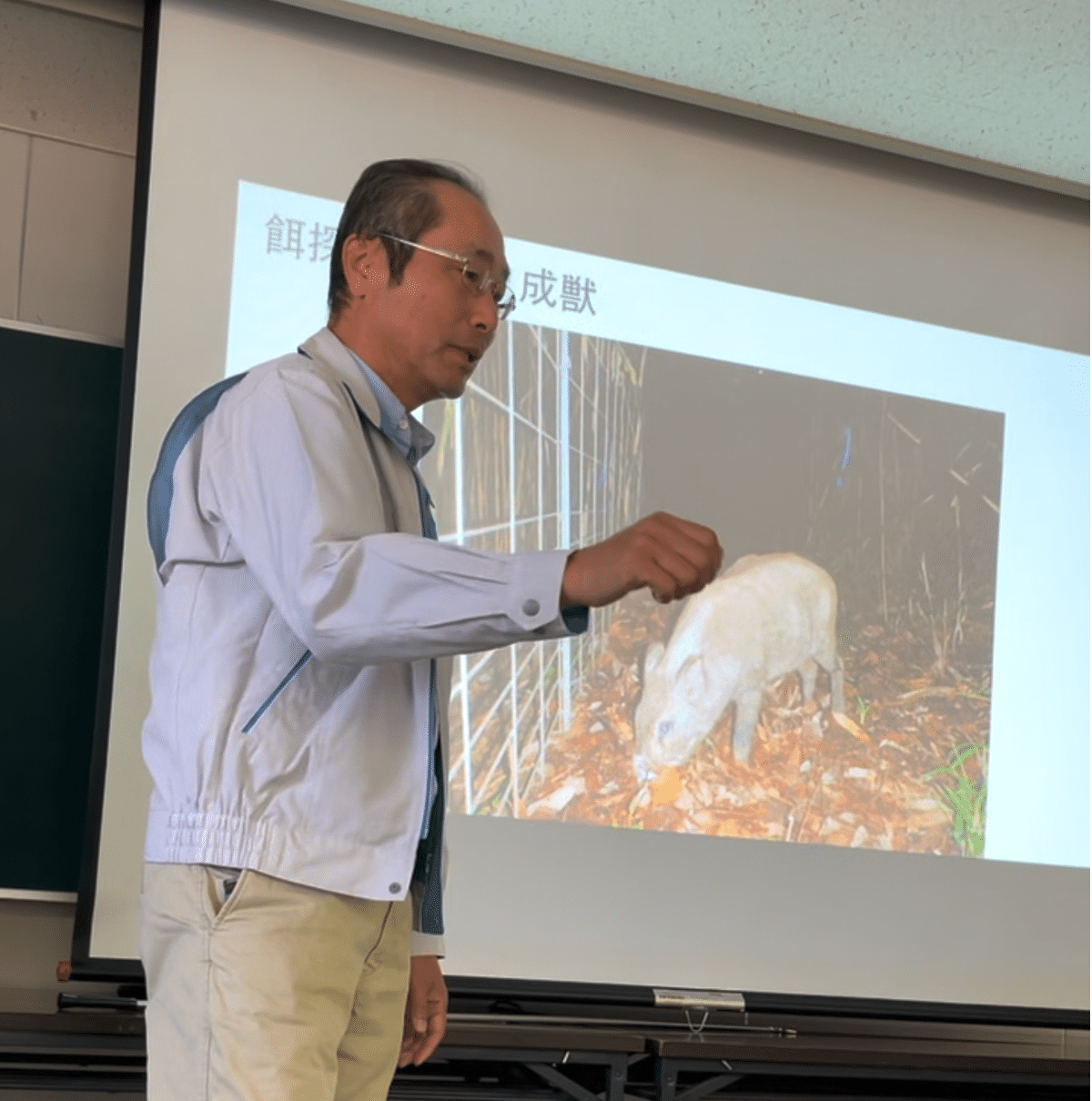
1) イノシシを知り、防除方法を検討する
イノシシがなぜ私の畑に来る? どうやって入ってくる? なぜ集落に頻繁に出てくる?
そういう原因を明らかにするためにはイノシシを知り、行動の意味を考え、その上で行動予測しながら適切な防除対策を行う、という基本的な考え方の大切さを学びました。
2) 誰がイノシシのことを考えるのか?
農業被害対策だけでみれば、鳥獣被害対策の主役は農家となりますが、鳥獣被害をもう少し大きい視点でみると農業だけの問題ではなくなります。農家や狩猟者を含む住民、行政、専門家など様々な立場のヒトが、それぞれでできることを連携して行わないとなりません。
土庄町でも鳥獣の出没は当たり前の時代となりました。動物の行動を変える【物理的防除など】、野生鳥獣を取り巻く環境を変える【残渣の処理、緩衝帯設置等】、そして大切なことは野生鳥獣に関わるヒトの意識を変える【集落の課題を自分ごと化するなど】、継続的に取り組むためには、「なぜ対策をしなければならないのか?」を集落の住民が考え、共有していくことが重要であると学びました。
3) 地域にあった防除対策を適切に施工する
ワイヤーメッシュ柵の効果的な設置方法についての実地研修もありました。適切な方法で設置された柵は、防除効果が優れていますが、設置計画が適切でない、適切な施工がされていない場合は、柵があっても侵入します。「柵を設置したのにイノシシが入ってくる!」という原因の多くがこの点にあります。
講師から①ワイヤーメッシュ柵の選定、②柵の設置場所の選定と設置計画、③具体的設置方法、について指導がありました。上記1)でもお伝えしましたが、イノシシの行動を知ると、より正しい設置方法の意味が分かります。イノシシは跳躍能力が非常に高いのですが、実際は地面を掘り、柵の下から侵入しようとします。研修では特に
◉柵の設置する地面を少し堀り、柵下部を地面に埋めること、
◉柵と柵を連結する際には、最下部の連結が重要で1段目か2段目を結線すること、
◉人が出入りする柵扉の確実な設置固定方法などを、体験しました。
なお、ワイヤーメッシュ柵や電気柵の詳しい設置方法は、別に整理してお伝えできるようにします!

せっかく柵を設置しても、設置方法に誤りがあれば役に立たない。

イノシシはを飛び越えるよりも、柵の下をなんとか潜ろうとするため、
柵の下部の設置方法を特に注意する必要がある。
1)柵を設置する地面を5〜10センチ程度掘り、柵下部を地面に埋めること
2)柵と柵の連結では、特に柵下部の一番下から1段目か2段目を結線すること

ワイヤーメッシュ柵設置を行いました。
4)総合的な対策が必要な理由
講師からは、それぞれの施策を連携していくことが大切で、どれか一つだけに偏っても防除はできない、捕獲しているから大丈夫、と思うのではなく、「①近寄らせない(緩衝帯の整備)」と「②入らせない(侵入防止柵設置)」対策と合わせて「③増やさない(残渣の処分)」という3つの取組を適切に行なった上で、初めて捕獲対策(=③増やさない)の効果が出ると強調されていました。改めて【総合的な防除対策】として検討し実施することの、その大切さを感じました。
コラム 目から鱗
-電気柵の電気は消さない-
電気柵は、電線に触れさせることで強い刺激で侵入防除する方法。ではイノシシはどのように感電するのでしょう?
実は、イノシシは見かけないものを警戒し、鼻で触れて探索します。この際に感電し「痛い!」という記憶が作られ、以降の侵入をためらいます。体毛が厚いイノシシは身体が触れても感電しません。だから鼻で触れさせて「痛い!」と最初に学習させることが非常に重要です。
しかし日中電気を切ることが多いですよね?「痛い!」を学習せず、一度でも「ここは入れる」と思ったイノシシは、もう電線を警戒しないため、鼻で電線に触れることなく身体を電線の下に入れて畑に侵入します。これを経験すると、【電気が流していても感電することなく畑に侵入】してしまうそうです。
だから、電気柵は、「常に電気は流す」、「電気が流れるようにメンテナンスをする」ことが非常に重要なんですね。
-被害を増やさないためにできること-
矢木講師が強調されていたのは、田畑、そして集落に近づけさせないために何ができるか?です。
イノシシなどの野生動物による食害対策は、収穫前の田畑で行うことが多いですが、実は収穫期が終わった田畑でも、例えば「ひこばえ(二番穂)」や「農作物の残渣」があると、その田畑を大変魅力的な食べ物がある場所と認識してしまいます。
香川県では、長年ひこばえを放置してしたことで、収穫後の農地も、食べ物がある場所と認識させてしまい、その後の被害が拡大したと言うことでした。
農家にとって収穫が終わっても、まだ多くの作業が残ってます。その中で余計な耕うん等の作業をする余裕がないことは十二分に理解しているが、中長期的にみて獣害対策するためには「残渣を作らない」重要性を、集落ごとに考えてほしいとおっしゃっていたことが印象的でした。
★★ 編集後記 ★★
※ 発刊にあたり、調査や資料提供など多数の方々にご協力していただきました。感謝とともに、引き続きのご協力、何卒よろしくお願いします!
※ 農業振興担当に着任した7月以降、農作業のお手伝いをしながらさまざまな農家さんからたくさんのことを勉強させていただいています。その中で、手塩にかけた作物が収穫間際に野生動物に食べられてしまう悔しさや怒り、諦めを、自分ごととして感じるようになりました。学びながら考えて行動し、提案をしていく一貫として、新聞発行していきたいと思います。
※ 一緒に考えたり、勉強したい!と思われた方は、ぜひ稲葉に声を掛けてください。ご意見ご感想もお待ちしてます!
★★ デジタル版編集後記 ★★
※ デジタル版として再編集しました! カラーになること、図表などが見やすくなること、何よりも素晴らしい内澤旬子さんに提供いただいたイラストをお魅せできること!が嬉しいです。
※ 小豆島土庄町の住民だけではなく、広く一般にも知っていただきたいし、同じようにご苦労されている他地域の方とも繋がりたいので、ぜひご意見ご感想をお待ちしています〜〜
