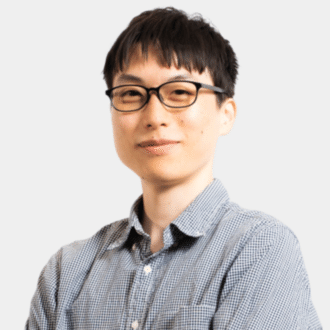集団の中で自分が何とかしなくてはと思えないと頑張れないのです。
数年前、自分にとって初めての国際論文を投稿した後、査読対応に迫られているときに、准教授からこう言われたことがある。
「自分にとっての最初の1報が重要だ。最初の1報さえ出してしまえば、心的プレッシャーがある程度無くなって、その次以降の論文がかなり書きやすくなる。お前は諦めが早いところがあるから、ここはなんとか粘って頑張った方がいい。」
その助言を受けて、何とか査読対応の締め切りに間に合わせてレビュアーへの返事を返し、結果的には無事にその論文はアクセプトされることになった。
一方で、この助言を受けて私が少し引っかかっていたのは、「お前は諦めが早いところがあるから」、という言葉だ。
そう言われた自分は、「あ、自分って諦めが早い人間だったのか」と思って、本当に自分は諦めが早い人間なのか、そう思われたのはなぜだろうか、と考えた。
自分としては、これまで「諦めが早い人間だ」という明確な意識は無かった。
しかし、よくよく自分の人生を振り返れば、確かに周りから見れば諦めたり、力を抜いていると思われてもおかしくないだろうな、と思われるところはあったかもしれない。
私という人間の特性を表すときによく使う言葉に、「省エネ人間」という言葉がある。自分としてはそれなりに頑張っているつもりだが、傍から見ると本気を出しているように見えないらしい。
しかしその一方で、「まだやれることはある」と考えて必死に頭を回転させた過去の自分もいたことを自覚している。それは、子育て団体で一緒に活動する子どもたちを連れて行ったキャンプ中に台風に見舞われたときや、急な予定変更や欠員が出たときに、それを切り抜けるために最善を尽くそうと考えていたことがあるからである。
こうして、「諦めが早い」自分と、「まだやれることはある」と思う自分の両方が存在することがわかったとき、それぞれを私なりに分析してみると、以下のようになった。
つまり、前者の「諦めが早い」自分が発動するのは、自分自身だけにしか関わらない物事に取り組んでいるときであり、「まだやれることはある」と思う自分が発動するのは、集団の一員として役割を担っていたり、リーダーとして意思決定をしなければならなかったりするときである、ということである。
そのように考えると、やはり自分は、自分だけのためには頑張れない人なのだ、という説が濃厚だ。そもそも自分自身に欲が無いし、欲望を満たしたいという強烈な感情も無い。むしろ、自分が本来の力を発揮できるのは、集団の中で重要な役割を担っているときだと思う。
この集団のために自分が何とかしなきゃ、と思えないと、自分は頑張れないみたいだ。
いいなと思ったら応援しよう!