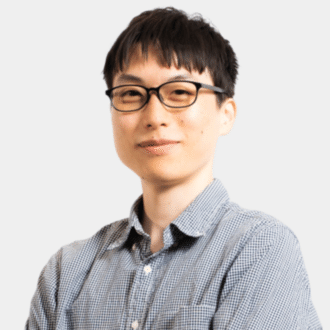幸福に生きるための努力。
昨日、以下の主旨のようなことを書いたつもりだ。
「本当は、人間には(その人にとっての)生きる意味などないが、確率論的に考えると『生きる意味はある』と思って生きた方が幸福に生きられる可能性が高いのではないか」
過去から現在までの古今東西の宗教学・神学・哲学書の類を洗えば、これと似た結論や、逆に全く異なる結論に出会う可能性もあるが、私はこの暫定解に辿り着いてある程度の納得感を得ている。「人間が生きる意味」について自分なりに問うて、自分なりに色々な書籍を読みながら考えて、自分なりに納得する解を得た結果だ。
どんな暫定解を出すにしろ、おそらく大事なことは、こうした「生きること」「生きる意味」などについて、ある程度自分の頭で考えるという経験をすることなのではないかと思う。なぜなら、それがある種「人間らしさ」の1つのかたちだと思うからだ。
現代社会においては、それを実現するためのハードルも比較的低くなってきているのでは、と思う。この多量情報社会と一定程度の生活水準社会においては、「人間の生きる意味には一般解がない」のようなことを頭で理解すること自体はそんなに大変ではない。多くの人にとっては、何とか一定程度の生活水準を維持しながら、言葉によって書き残された過去の叡智やそれを元にした様々な言説に触れるためのチャンネルを持ち、考える時間をつくることくらいはある程度できるのではないだろうか。
確かに、それを実際にやるかどうかの違いはあるし、例えば本当に経済的に困窮している人々にとってはそんな余裕はない!という声も聞こえてきそうだが、一旦そういうことにさせてほしい。なぜなら、より本質的な問題はその後にやってくるからだ。
その問題とは、仮に人生に意味がないとわかったとして、「それでも生きていかねばならない」ということだ。
ここで、本当に生きて「いかねばならない(義務的)」のか?と言われたら、必ずしもそうでないかもしれない。「意味がないなら今すぐ命を絶てばよい。どうせあらゆる人間はいつかは死ぬのだ。それが早いか遅いかだけの違いである」と言える可能性もある。
しかし、(私も含めて)多くの人にとって死ぬことはそれなりに怖いことだと思う。相当追い詰められていなければ、容易に取れる選択肢ではない。となると、やはり体感的には「(いつか死ぬまでは)生きていかねばならない」という感覚になるだろう。
そういう中で、「『生きる意味はある』と思って生きる」ことはそれなりに大変なことだと私は思う。特に、何かを確信することができない私のような思索的な人間にとっては、『生きる意味はある』と確信すること自体がまず難しい。その上で、それを信じられるよう意識しながら生き続けることはもっと難しい。
だから、冒頭述べた生き方を実現するには相当な努力が必要だ。誰に何を言われたとしても、自分が生きた過去と今現在を参照しても特にその意味が思い当たらなくても、これから先の未来にその意味が見つかる保障が全くなくても、自分にはきっと生まれた意味があると信じる努力をして生き続けることが、幸福に近づく道なのかもしれない。
いいなと思ったら応援しよう!