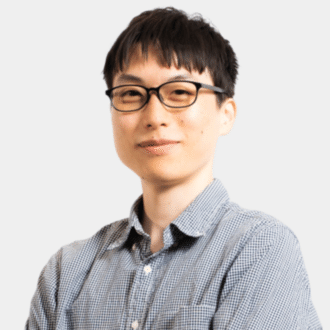課題発見力が生き方を形づくる。
自分が現在教育分野に関心を持っているのは、おそらくそこになんとなくの課題が見えているからだ。しかし、それが本当に自分という人間にとって最も重要なテーマなのか?と言われると、まだ確信は持てない。しかし、教育分野には間違いなく課題があるし、それは形を変えながらそこにあり続けるだろう。なぜなら、人間が生きていくはずの社会の側はどんどんと形を変えて変化し、人間側はそれらへの対応を常に迫られるからである。
これからの時代に求められる力は何かと問われたとき、1つ確かなのは、単に知識やスキルを持っていることよりも、「課題を発見しそれを適切に(言語によって)定義する力」=「課題発見力」 のほうが重要になるということだ。特にAIが台頭する時代においては、既存の知識を知っていること、その知識を活用すること以上に、「どのような課題を解決すべきか」を見極めることが問われると思う。さらに言えば、「どの分野に身を置いたとしても、その分野における課題を発見し、より良い状態を目指してアクションを起こせる力」が必要なのではないかと思う。
「課題発見力」とは、端的に言えば「いつ、どこで、誰が、何を、どのように困っているのか?」を把握し、それを適切に言語化する力だと思う。この力のベースには、「自分の置かれた状況を理解し、その社会的な位置付けを整理する力」や「他者の気持ちや立場を想像する力」が不可欠になるだろう。
とはいえ、課題発見力をつけるには、まずは自分自身の好奇心と興味関心に従ってどんどん進む「探究的な学び」が有効そうだ。また、「自分は何に困っているか?」「社会との不整合点をどのように感じているか?」という問いを突き詰めるのも有効かもしれない。それらを発信し、周囲からの共感を得ることができれば、その課題には一定の社会的ニーズがある可能性がある。こうした取り組みを経て「課題発見力」を鍛えていけば、自然に社会の中での役割も定まっていくのではないかと思う。
いずれにしても、大事なのは「自分はこの分野で何をするべきか?」と自問し、見つけた課題の解決に向けて自分の能力と情熱で迫ることだろう。「課題発見力」は、単なるスキルではなく、「生き方を形づくる力」そのものなのかもしれない。
いいなと思ったら応援しよう!