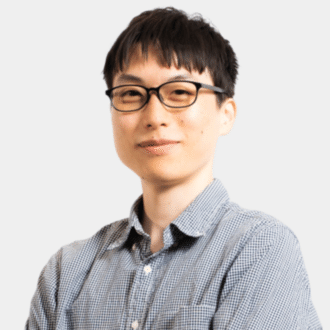「頼る」を覚える。
人望のある人とはどんな人だろうか。
少なくとも、自分自身はまだまだ人望がある人間であるとは到底思えない。確かに一定程度信頼していただいている人は多いと思うが、それが人望の域にまでは到達していない気がする。「信頼できる」ことは、「人望がある」ことの必要条件ではあるが、十分条件ではない。
「人望がある人」には「信頼できる」以外にもいくつかの特徴があると私は考えている。そのうち、ここで特に取り上げたいのは「人を頼るのが上手(自分一人で抱え込まず、人を巻き込める)」であるという特徴だ。
先日も書いたように、今の私に足りないのは「人を適切に頼る」ことだと考えている。確かに自分の力で何でもできることの良さもあるのだが、それによって失っていることにも目を向ける必要がある。
もし自力で取り組むことを選べば、自分の理想の通りのアウトプットが得られるから、良く言えば「想定通り」である。しかし、それは悪く言えば「想定通りでしかない」。
もし自分でやればできることをあえて誰かにお願いするとしたら、そこには「期待通りのアウトプットが出るかどうかわからない」という不確かさが生まれる。しかし、この不確かさは「自分では想定できなかった良い結果が生まれる」可能性をも秘めている。
つまり、「頼ること」は、単に「できないことをやってもらう」ことではない。むしろ、自分ができることでもあえて他者にお願いし、その結果として自分の予想の範疇を超える可能性に価値を見出す行為であるとも考えられる。「頼る」ことを覚えるには、この不確かさに対して向き合う気持ちが必要だ。
また、「自分にとっての理想」のハードルが高いことも課題の1つである。それが「自分がやったほうがいい」という発想を生み、人に任せる経験そのものが少なくなる傾向を生む。結果として、「人に頼ることによる成功体験」が少ないから、頼ることに対しての心理的な抵抗が無くならない。この点を克服するには、意識的に「人に頼る⇒任せてみる⇒意外とうまくいく」という成功体験を重ねることが大事だ。
さらに、「頼る」ことを実践するには、自分が「仕事を生み出す存在」になる必要がある。世の中の多くの仕事というのは、基本的に「誰かのやりたいことを代わりにやってあげること」によって成り立っている。これが成立するには、まず「やりたいこと」が無ければならない。それを自分自身が生成する必要があるのだ。
仕事を生み出す人は「他者に役割を与える人」 であり、「他者にとってのやるべきことを与える人」でもある。このスタンスが、「人を頼ること」を生み出す。
こうして他者のやるべきことを生み出せる人こそが、「人を頼るのが上手」な人であり、すなわち「人望のある人」なのではないだろうか。「人を頼ること」によって、ある種周りの人々の「やりがい」「生きがい」のようなものを生み出せる人こそが、人望のある人なのではないだろうか。
いいなと思ったら応援しよう!