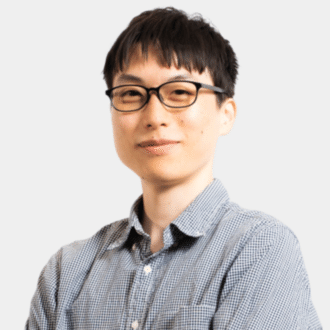自己解決能力の弊害。
先日、感情が欠落した人間として、自分が心からの感謝ができている人間なのかどうかが疑わしいことについて書いた。そういう自分はどこから生まれたのだろうか?と考えると、端的に言えば「困った経験が少ない」からかもしれないと思った。他者からの支えや助け、贈与に対して、どこか鈍感な自分がいるような気がする。
ふと、学部生のときに研究室の先輩から言われた言葉を思い出した。
「ともや君は自己解決能力が高いから…(略)」
そのときは何気なく聞き流したが、今振り返ると、その言葉の持つ意味を考えざるを得なくなってきた。
自己解決能力が高いことは、確かに生きる上での1つの武器になる。自分で問題を処理できる人間は、他者に頼らずとも前に進める。すると、他者には「ある程度できる人だ」という認識が広がり、期待が大きくなる。他者に頼らずにその期待に応えるためには、自分が力をつける必要がある。その力が身につくと自力でできる範囲が広がり、他者からの「できる人だ」という認識がさらに強化される。過去の私はこの成長ループをベースに、さまざまな人々との関係性の中で少しずつ成長してきたように感じる。
(もちろん、他者に全く頼らなかったわけではないし、助けられたことも大いにあるし、書籍や過去の偉人たちの言葉に救われたこともある。ここで言いたいのは、あくまで「身の回りの人々」の助けを「自分から」借りることが相対的に少なかった、ということだ。)
その一方で、この成功モデルに囚われてしまうと、身の回りの人々を頼るのが下手になる、という側面がある。「自分でやれることは自分でやる」ことが当たり前になると、助けを求めるという選択肢が消えてしまうのだ。もし、助けられる経験がもっとあれば、身の回りの人々への感謝の念も自然と浮かぶのかもしれない。
実際、人は何かの目的に向かって進むとき、必ず自分の手に負えないことに直面する。そして、その瞬間にこそ、他者の力を借りる必要が生じる。だとすると、自分が人を頼れないのは、そもそも「他者の力を借りざるを得ないほどの目標」を設定していないからなのではないか?
本当に達成したいこと。どうしても手に入れたいもの。そういう強い欲望や執着を持ち、それに向かって遠くの目標を立てたとき、初めて「自分ひとりでは限界がある」と認識できるのかもしれない。そして、その過程で誰かに助けられる経験を重ねていけば、他者に対する感謝も自然と生まれるのではないか。
また、自分自身が「見返りを求めずに(感謝されることもなく)何かをすること」に慣れすぎているのも一因かもしれない。自分以外の誰かのために動くことが当たり前になっていると、他者が同じように動いていることに対して感謝を伝えるという感覚が徐々に薄れてしまうのではないか。
と、こうして文章にしていくと、どこか上から目線なことを言っている気がしてきてしまった。そういう意図はないのだけど、この感覚を言葉にするのは難しい。感謝とは本来、意識して湧き起こすものではなく、自然に生じるものだ。それが自分の中で希薄だと感じるならば、きっとまだ自分には何か足りないものがあるのだろう。それが何なのかを探るために、もっと人を頼り、もっと助けられる経験をしていくことが、今の自分に必要なのかもしれない。
いいなと思ったら応援しよう!