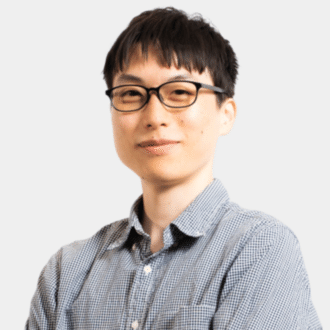役に立つことが全てではない。
先日、自分の「志」が一体何なのかを知るためのワークに取り組む機会があった。自分は合理的か情緒的か、情熱的か冷静か、のような分析を元に自分の性質の解像度を上げていき、そこから自分の人生にとってしっくりくる「動詞」を選び、そこに目的や方法論を肉付けしていくような形だ。
数ある動詞の中で私が相対的に最もしっくりくると考えて選んだ動詞は、「役に立つ」だった。そのときはあまり時間が無かったけれども、後からよくよく考え直してみても、自分にとってはそれなりに重要な要素だと感じる。
この「役に立つ」の感覚は、最近の自分が考えていた「生きる意味」みたいなところとも関わってくると感じたので、とりあえず考えたことを書きならべてみたいと思う。
シンプルな言葉で表現すると、私にとっての「意味がある」とは「役に立つ」だったのではないか、と思えてきた。確かに、自分自身が何かの役に立つ存在であれるかどうかは、自分にとって結構大事なことな気がする。自分がそこにいる意味、もっと言えば「生きる意味」も、自分が何かの役に立つかどうかを元に判断していたかもしれない。
「役に立つ」とは言っても、Pragmatism(実用主義)的な感覚とはまたちょっと違う気はする。単に結果が良ければそれ以外の部分の重要度は低いという意味ではなく、役に立っているかどうかと、それを支える根拠や思想も含めて大事だと思っている気がする。
この「役に立つ」=「意味がある」という感覚は、現状はあくまで自分自身にのみ向くものであって、他者に対してはあまりそう思わない。これが必要以上に他者に向いてしまうと、やや危険な考え方になると思う。それは、その他者を「何かの役に立たなければそこにいる意味はない」と判定してしまうおそれがあるからだ。
自分自身に向いているこの「(何かの)役に立つことではじめて、自分に(生きる)意味が生じる」という感覚とはうまく付き合っていく必要性を感じている。もし、今の自分のように五体満足で特に通常生活に支障なく何らかの役に立てていることを実感できる状態から、そうでない状態に陥ったとき、上記の価値観のままではより罪悪感に苦しむことになるだろう。究極的には「そこにいるだけで良い」という形で肯定できればいいのかもしれない。それが本当の「自己愛」でもある気がする。
私は以前、「愛すること」とは「意味を与えること」である、と書いたことがある。その意味をもう一度問い直すと、無意識で「(意味がないものに後から)意味を与える」という感覚で書いていたかもしれないことに気づいた。つまり、暗黙の裡に「あらゆる事物の中には、意味のあるもの(役に立つもの)と意味のないもの(と役に立たないもの)がある」「一見すると意味のないものに対して、積極的に意味を与える行為が『愛』である」と考えていたことになる。
これも、よく考えれば少し傲慢な考え方だったかもしれない。私の判断に関わらずあらゆる事物には意味がある、という信念があっても良いはずだ。私はその信念があり得ることに気づけていなかった。
「役に立つ」を是とする私の感覚も、この世界に数多ある価値観の1つに過ぎないということをきちんと認識する必要があるだろう。
いいなと思ったら応援しよう!