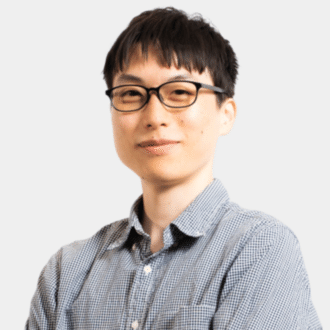本能的な危機感から始まる学び。
久しぶりに大学生協の本屋ゾーンに行ったら、平積みされていた複数の書籍に目が留まった。特に印象に残ったのは「年収443万円 安すぎる国の絶望的な生活」「高学歴難民」の2冊だ。
タイトルから想像されるように、いずれもあまりハッピーな話題の書籍ではない。しかし、その他の数ある本の中からこれが今自分の目に留まったということは、自分もそれに対して何らかの問題意識を持っていることの表れだろう、と思うことにしている。
中身を少々立ち読みしてみると、いずれもタイトルの通り、現代日本社会において支援の目からこぼれがちな人々の生活事例が具体的に書かれていて、何とも言えない複雑な気持ちになった。特に後者の「高学歴難民」については、自分自身が博士の学位を持ちつつも今後のキャリアのビジョンがあまり見えていない状況に照らして、到底他人事とは思えなかった。あまりに内容に引き込まれてしまい、つい珍しく長時間の立ち読みをしてしまった。
最近は読書をする時間があまり意識的に取れていない実感があるので、生活習慣の中に改めて組み込んでいかなければと思っているところだが、こうして興味関心が引き込まれたそのままの勢いでガッと読んでいけると、よりインプットしやすいだろうなと思ったりする。
冒頭の「目に留まる本」の話に戻ると、やはり「自分ごと」だと思える本は目に留まりやすいなと思う。それも、私の場合は特に「自分にネガティブな影響がある」「自分への攻撃になる」という情報は目や耳に入りやすいし、そのまま積極的に調べようという気持ちが向きやすい実感がある。
今の仕事としての研究においてあまり調査の気力が湧かないのは、そういう「自分にとって直接的にネガティブな情報」ではないからかもしれない。元々は好奇心からいろいろなことを勉強したりはしていたのだけど、それよりも圧倒的に「不安」「恐怖」のような感情からの方が自分の知的活動へのエネルギーを出すことができるタイプだということが最近やっとわかってきた。「自分に何らかの形で(ネガティブな)影響を与えるものを検知する繊細さ」を持ち合わせてはいるようだ。
今取り組んでいる研究でそのように感じられていないということは、自分の研究そのものにアイデンティティを持てていない可能性がある。「これは自分の大事な研究テーマだ」という思いがあれば、それに関係する情報(特に、自分の研究にネガティブな影響を与え得る「競合の研究」や「異なる学説」などの情報)は目や耳に入りやすいはずだが、そうなっていないのが正直なところだ。
好奇心による学びが上手くいかないのなら、本能的な危機感から学びを深める方が私にとっては良さそうだ。
いいなと思ったら応援しよう!