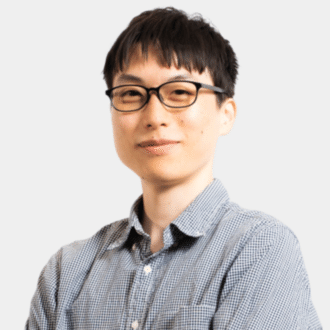もっと早く知りたかったお金の話。
私は自分の誕生日がクリスマスと正月の間にあることもあって、幼い頃はクリスマスプレゼントと誕生日プレゼントを一緒にされがちだった。これについて当時の私がどう思っていたかは正直覚えていないが、今現在の私は特に嫌な思い出とは思っていない。それは、両親の立場からすればその方が合理的だし、そもそも私には大した物欲がなかったと思うからだ。
私が小学校高学年になる頃にはサンタさんがいないことがわかって、それから以降は両親や親戚からのクリスマスプレゼントや誕生日プレゼントは主に現金や図書カードになった。加えて、正月にはお年玉ももらえるので、年末年始に親戚一同が集まる期間は私にとってサラリーマンのボーナスのようなものだった。
これが私としてはありがたかった。それは、現金としてもらうことで欲しいモノを自分で買えるからではなく、モノが増えないからである。私はモノを徹底的に実用主義的にみる人間なので、生活の中で使えるものは徹底的に使うし、不要だと思ったものは容赦なくクローゼットの奥底にしまわれる(さすがに捨てることまではしないが、それがプレゼントを贈った側への慰めになっているのかは正直わからない)。
特に中学生以降の私はそもそも欲しいものもそんなにないし、もし必要なものが出てきたら自分で選んで買った方が良かったのだ。ある程度年齢を重ねた自分にとっては、プレゼントを現金や図書カードとして頂いて、大事に貯蓄・保管しておく方がむしろ喜びが大きかったのである。
そういう過去を振り返って今の自分がどう思っているかというと、このお金たちをもっと有効に使う方法は無かっただろうか、ということだ。というのも、この数年でお金というものについてきちんと勉強した結果、ただお金を眠らせておくことの圧倒的無意味さに気づくことができたからである。
そういうお金の保有のしかたやお金の使い方について、幼い頃の私に教えてくれた大人は一人もいなかった。おそらく彼らには悪気があったわけではなく、そういうことを教える発想がそもそも無かったのだろう。
私はそういう人たちを決して憎んでいるわけではなく、そういう部分は適切に反面教師にして、自分の子どもたちの世代には教えるべきことを教えた方がいいだろうと思っている。例えば、単にお金を渡すだけではなく、その貯め方・使い方・増やし方を教えるとか、そういう「方法論」も含めて教えることで、子どもたちは自分たちの世代よりも先に進むことができるのだ。
これはいわゆる、「魚を与えずに釣り方を教える」的な考え方だ。人に何かを与えるときは、それそのものをただ与えるのではなく、どうすればそれが得られるのか、自分たちでそれを実践しながら生きていけるような方法論も含めて教えるべきだろう。
さらに、もっと根本的なことを言えば、お金とは何なのか、その役割や重要性も含めて伝えるべきだろう。お金の運用方法がわかっていたとしても、「なぜお金は大事なのか」という問いに自分なりの解を持っていなければ意味がない。
少なくとも自分の子どもには、時が来たらそういう話ができるように、しっかり学んでおこうと思う。
いいなと思ったら応援しよう!