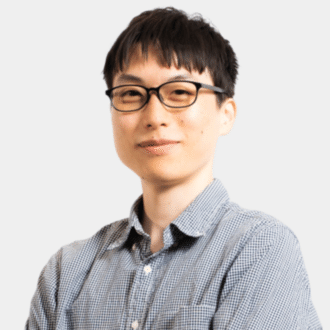退屈への向き合い方を会得できそうなのです。
「暇と退屈の倫理学」という本を読んだ。
素晴らしい本だった。今の私が抱えているこの何とも言語化しにくいモヤモヤについて、明快な言葉と論理で説明してくれている本だった。
そもそもこの本を手に取ったのは、自分の中から何かに取り組みたいという潜在的なエネルギーがなかなか湧いてこず、仕事をしているから暇ではないのだけど、暇なような退屈なような時間の過ごし方をすることが長く続いていたからだ。
そのモヤモヤが反映された記事が、直前の記事だ(なんとも頭の中がグルグルしている状態を感じさせる文章である)。
そんな中で、たまたま本屋を歩いていて目に留まったのが本書だった。
本書は、タイトルにある「暇」や「退屈」といった言葉の意味だけでなく、人間はいつから退屈しているのか、人間が生きることと暇であることや退屈することはどのように関係するか、などについて、多様な分野の視点から記載してあり、まず読み物として面白い。
そして、肝心の「退屈とどう向き合うべきか?」という問いについても、過去の哲学者たちの思考を借り、批判的に検討しつつ著者なりの見解を示しており、深い学びを得ることができた。
本書の結論部には「以下の結論だけを読んでも幻滅するだろう」と断った上で結論の記載があったので、ここではその結論のみを羅列することは敢えて避けるが、本書の狙いの1つであるところの「暇と退屈の倫理学」の一歩を踏み出すこと、すなわち、退屈な人生をどう生きていくか、について考えることを始めることができたと思っている。
私が漠然と抱えていたモヤモヤは人間がよく陥る状態の1つであり、まさに私が人間として生きていることの証左でもあった。
この状態を脱するためには、日常的なものをもっと「楽しむ」ことが必要だった。
「楽しむ」と言っても、実は楽しむことは容易ではなく、一定の訓練を必要とするものだ。例えば、食事を楽しむにしても、まずは食器の使い方や口や舌などの身体の器官の使い方を習得しなければならないし、口に入れたものを適切に味わい楽しむにはその味覚に意識的になる訓練が必要だ。こうした訓練を踏んだ上で初めて食事を「楽しむ」ことができるのである。
これは、食事のみに留まらず、人間が文化として作り上げてきた多くの物事に当てはまる。さまざまな物事に対して自分自身を楽しませることができるような訓練、これが必要だったのだ。
この認識に到達したからと言って、私のこのモヤモヤが今すぐに無くなるわけでは当然ない。なぜなら、それは人間が生きるにあたっていつでも抱えうるものだからだ。これから先の人生でもきっと、同じような瞬間が何度も訪れるだろう。
しかしそのときには本書の内容と結論を思い出し、また歩みを始められるかもしれない、と思った。
私の中で、2024年下半期のNo.1の1冊になりそうだ。
いいなと思ったら応援しよう!