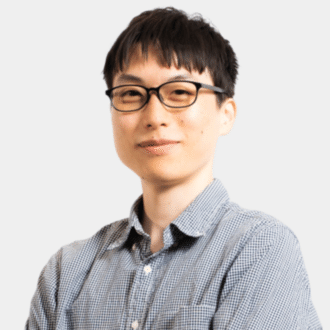歌舞伎と現代的価値観の融合。
絶賛「やったことないことリスト」に1つ1つ取り組んでみようキャンペーン中だ。
その中の1つに書いてあった「歌舞伎を観に行く」について、なんと最近たまたまその機会を得ることになった。とある筋から、チケットの譲り先を探しているというご連絡をいただいたのだ。何かしら宣言してみると、引き寄せる何かがあるのかもしれない。
というわけで先日、実際に銀座の歌舞伎座に人生で初めて行ってきた。この2月、歌舞伎座では「松竹創業百三十周年・猿若祭二月大歌舞伎」の真っ最中であり、私が頂いたチケットはそのうちのとある日の昼公演の分だった。
歌舞伎座の中に入り座席の前に辿り着くと、そこは上手側(舞台向かって右側)で、舞台がかなり見やすい位置にあるグレードの高い席だった。これを無料で譲り受けるのは逆に申し訳ないくらいだ。後方を見上げると3階席まであり、1階席の両サイドにはVIP席のような特別な席も設けられていた。調べたところによると「桟敷(さじき)席」と呼ばれるもので、畳敷きの床に座椅子が据えられ、足元は掘りごたつ式になっていて、ゆったりと観劇できる環境が整っていた。
歌舞伎座内では開演前に音声ガイドを借りることができた。上演前や幕間には今日の演目や歌舞伎の関連知識についてのアナウンスが流れており、上演中には今何が行われているのか、舞台上の役者の動きに合わせて良きよころで解説が入るので、非常に勉強になった。
今回観ることができた演目は3つで、前半の2幕がそれぞれ短尺の古典作品、後半の2幕は2幕で1作品の創作歌舞伎だった。
1つ目の演目は「鞘當(さやあて)」で、とある豪傑とそのライバルの色男がすれ違いざまに刀の鞘が当たることによって喧嘩になり、それを止めに入った女が、鞘を交換することで事態を収拾しようとする、というストーリーだ。
2つ目の演目は「醍醐の花見」で、太閤秀吉が開いた宴の一幕を描いたものである。秀吉の正妻や忠臣・前田利家などの家臣たちも登場して酒を楽しみながら踊りを披露し、最後には秀吉の跡継ぎ・秀頼が登場して豊臣家の安泰を祝う、というものだ。
これら2つの古典作品からは、ならではのゆっくりとした時間の流れを感じた。セリフの一つ一つがすごく時間をかけて語られるという特徴に加え、登場からしばらくずっと笠で顔を隠した状態でセリフを語り合い、キメのシーンでやっと初めて笠を取って顔を見せる、という演出には観客を引き込む効果があるような気がした。
2作品を終えて少し長めの幕間があくので、ここでお弁当を食べた。歌舞伎座の大きな特徴の1つが、客席で食事を楽しめることだろう。多くの近代劇場ホールのほとんどはホール内での飲食禁止を定めているが、ある意味これが昔から続く1つの文化なのだよなと思った。また、幕間の時間では舞台上に立派な垂れ幕がかわるがわる現れ、スポンサーの紹介があった。歌舞伎の商業的な側面も感じ取ることができた。
そして、いよいよメインの演目「きらら浮世伝~版元・蔦屋重三郎 魁申し候~」だ。これは、江戸時代中期に活躍した版元・蔦屋重三郎を主人公とした物語で、今年のNHK大河ドラマでも同様の題材が取り扱われているようだ。版元とは当時のエンタメプロデューサーのようなものであり、絵師や戯作家を支援し、彼らの作品を世に送り出す役割を担う立場のことである。
舞台は江戸中期の吉原。重三郎は吉原に出入りする本屋として働いていたが、とあるきっかけで気鋭の絵師・歌麿と出会う。自信家だった歌麿は一度重三郎とぶつかるが、やがて彼の才能を認め、共に名を世に轟かせるためタッグを組むことを決める。時代の渦に巻き込まれながらも己の生き方を貫く重三郎の生き様を描いた作品だ。
こちらは前半の古典作品とは打って変わり、私の印象としては「現代的時代物創作歌舞伎」とでも言えるような作品で、大変面白かった。時代物でありながら、通常の舞台演劇と似たようなセリフの言い回しとスピード感で進んでいくと共に、劇中音楽は三味線や箏の音色をベースにしながらも、ストリングスなども使用されて現代風の雰囲気が感じられた。
また、江戸時代を描いてはいるものの、作品のテーマは「自分の【好き】を追求し圧力に屈せず生きていく」という、まさに現代的価値観と通底するものを感じた。重三郎が自分はクリエイターの才能はないことを悟りながらも、才能あるクリエイターたちを支援し、時流の厳しさに負けずに「面白い」を世に届ける立場として闘うリーダーシップと生き様が描かれ、特に、幕府の規制をかいくぐる作戦を語りクリエイターたちを鼓舞するシーンは感動的であった。
今回の歌舞伎鑑賞は、古典から創作まで幅広い演目を楽しむことができ、大変満足度が高かった。特に「きらら浮世伝」は現代にも通じるテーマを扱っていることが意外でもあったが、そういう「古典芸能」と「現代的価値観」をいかに融合させるか、という、この現代において歌舞伎を創っている方々の試行錯誤をも感じさせるものだった。
いいなと思ったら応援しよう!