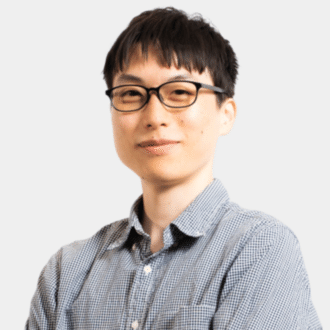コンテンツの質にこだわる。
私はこれまでに通算1000本以上の記事を書いてきた。実数としては今回の記事で1069本になるようだが、その実感はあまりない。文字数としては、大体1本の記事で900~1200字程度書いていることが多いので、仮に記事1本あたり1000文字とすると、そのまま桁数が増えて約107万字を書いてきたことになる。
これがどういう数字かというと、文庫本1冊あたりの文字数が約10万字らしいので、その10倍だ。10冊も本が出せるほどに文章を書いてきたと考えると、なかなかの蓄積を感じて少しの自信になる。
それだけの数の記事を書いていると、自分の書いた文章に手ごたえがあるときとそうでないときがあることもよくわかるようになる。その手ごたえを感じるための指標としては、リアクション(スキ数)が良いかどうかという観点と、自分がうまく書けたかどうかという観点の2つがある。
前者について言えば、noteを始めた当初も今も、ただ自分が考えていることをWeb上に垂れ流しているだけだと思っているので、記事へのリアクションに一喜一憂しているわけではない(いつもスキを押してくださっている方々には感謝である)。しかし、スキ数が伸びる記事とそうでない記事があるという実感はあって、それがなぜなのか、それぞれの記事で何が違うのかはまだよくわからない。分析したいと思って考えてみたこともあるが、まだ分析しきれていない。
noteは文字メディアであるが、動画メディアであるYouTubeでも再生回数について同様の事情を持っているだろう。YouTuberの方たちがよく語っている様子を見聞きするに、どの動画の再生回数が伸びるかどうかは自分自身の予想とは異なることが多いようだ。私のnoteにおいてもそれと同様の傾向は確かにあって、なぜこの記事が読まれたりスキが押されているのだろう、と思ったりすることもある。
しかし個人的には、noteの場合は比較的、自分として「良く書けたなぁ」と思う記事はそれなりにリアクションが良いように感じている。一方で、自分でもあまり自信が無かったり、生煮えの状態で終わっている文章は当然リアクションが芳しくない(そんな記事がほとんどである)。YouTubeなどの動画の再生回数に比べると、文章に関しては想定とのブレが少ない気がする。
その理由の私なりの仮説としては、サムネやタイトルから直感的に観る観ないを判定する動画の類よりも、比較的ゆっくりと時間をかけて楽しまれる傾向がある文章の方が、中身のコンテンツの質そのものが重視されるからではないかと思う。
だから、釣りタイトルのついたよくわからない内容の謎文章よりも、良質な内容を備えてしっかりと読ませる文章の方が、より正当に評価されやすいのだ。
そう考えると、これからも玉石混交はあれど、より良い文章が書けるように少し意識的になりながら毎日更新を継続してみようか、という気持ちにもなる。改めて頑張ってみます。
いいなと思ったら応援しよう!