
ロングセラーの本たち - ビジネスにおける知的生産術
以前自宅の蔵書を整理をしていて出てきた、ビジネスにおける「思考法」や「文書作成」など、「知的生産術」に関連する本をまとめてみた。
あくまでも個人的な興味と趣味による選択である。
しかも、かなり古いものばかりなので、現在入手できないものも多々あるのであしからず。
情報を集め、整理・分析し、問題・課題を考える。
あるいはアイデアを出し、結果を表現する。
ビジネスの現場をはじめとして、あらゆる場面で必要となる基本的な技術やノウハウを、体系的に整理し身につけるのに役立った本たちである。
最近は、AIの急速な発達により、かなりの部分を任せることもできるようになってきている。
しかしながら、その成果物の真偽や出来栄えなどを評価・判断するには、やはり自分で考える力、判断する力が不可欠でもある。
今回取り上げたのは、その際に役立つであろう(私にとっては実際に役立った)書籍たちである。
結構な数があり、今は手に入らないような、かなり古い本がほとんどではあるが、つらつらと列挙してみた。
----- 1.思考の整理学 -----

ちくま文庫 思考の整理学
外山 滋比古【著】
筑摩書房
1986年4月発売のロングセラー
自分の頭で考え、自力で飛翔するためのヒントが詰まった学術エッセイ。
アイデアが軽やかに離陸し、思考がのびのびと大空を駆けるには?
独自の思考のエッセンスを開示し、考えることの楽しさを満喫させてくれる。
【目次】
グライダー/不幸な逆説/朝飯前/醗酵/寝させる/カクテル/エディターシップ/触媒/アナロジー/セレンディピティ/情報の“メタ”化/スクラップ/カード・ノート/つんどく法/手帖とノート/メタ・ノート/整理/忘却のさまざま/時の試錬/すてる/とにかく書いてみる/テーマと題名/ホメテヤラネバ/しゃべる/談笑の間/垣根を越えて/三上・三中/知恵/ことわざの世界/第一次的表現/既知・未知/拡散と収斂/コンピューター
----- 2.「知」のソフトウェア -----

講談社現代新書 「知」のソフトウェア
立花隆【著】
講談社
1984年3月発売のベストセラー
知的生産を行うには何が必要か?
オリジナル情報を重視し、情報の意味を読む。ジャーナリズムの最前線で活躍をつづける著者が、体験から編みだした考え方と技法の数々。
【目次】
1.情報のインプット&アウトプット
2.新聞情報の整理と活用
3.雑誌情報の整理について
4.情報検索とコンピュータ
5.入門書から専門書まで
6.官庁情報と企業情報
7.「聞き取り取材」の心得
8.アウトプットと無意識の効用
9.コンテ型と閃き型
10.材料メモ・年表・チャート
11.文章表現の技法
12.懐疑の精神
----- 3.考える技術・書く技術 -----

講談社現代新書 考える技術・書く技術
板坂元【著】
講談社
1992年12発売の知る人ぞ知る名著
類似のタイトルの書籍がいくつか存在する。
すぐれた文章を書くための、一連の知的作業の技術やコツ。目のつけどころや発想法、材料のあつめ方や整理術、構成力や説得術などなど、現代人必読の知的実用の書。
【目次】
I.頭のウォームアップ
II.視点
III.読書
IV.整理
V.発想
VI.説得
VII.仕上げ
VIII.まとめ
----- 4.調べる技術・書く技術 -----

講談社現代新書 調べる技術・書く技術
野村 進【著】
講談社
2008年4月発売
第一線のジャーナリストがすべて明かす、プロの「知的生産術」。
テーマの選び方、資料収集法、取材の実際から原稿完成までを丁寧に教える。
【目次】
第1章 テーマを決める
第2章 資料を集める
第3章 人に会う
第4章 話を聞く
第5章 原稿を書く
第6章 人物を書く
第7章 事件を書く
第8章 体験を書く
----- 5.「超」整理法 -----

中公新書 「超」整理法 ― 情報検索と発想の新システム
野口 悠紀雄【著】
中央公論新社
1993年11月発売のベストセラー
知的活動の生産性を高める方法論。情報洪水の中で、書類や資料を保存し検索するため、「整理は分類」という伝統的な考えを覆し、「時間軸検索」という発想を提案。
【目次】
序章 あなたの整理法はまちがっている
第1章 紙と戦う「超」整理法
第2章 パソコンによる「超」整理法
第3章 整理法の一般理論
第4章 アイディア製造システム
終章 高度知識社会に向けて
----- 6.ライト、ついてますか -----

ライト、ついてますか ― 問題発見の人間学
ゴース,ドナルド・G./ワインバーグ,ジェラルド・M.【著】
木村 泉【訳】
共立出版
1987年10月発売のロングセラー
問題は解くより発見する方がずっと難しく、ずっと面白い。
実人生において活かすべき問題発見の人間姿勢をエッセイ風に描く。ワインバーグとその仲間たちの〈計算機の人間学〉の本。
【目次】
第1部 何が問題か?
(問題は何なのか?;問題を抱えているのは誰か?;キミの問題の本質は何か?;「何がまずいか」をどう決めるか?;まずいのは何か?;そのために、何ができるか?;問題とは、望まれた事柄と認識された事柄の間の相違だ;幻の問題は本物の問題)
第2部 問題は何なのか?
第3部 問題は本当のところ何か?
(すべての解答は次の問題の出所;結論に飛びつくな、だが第一印象を無視するな;新しい視点は必ず新しい不適合を作り出す)
第4部 それは誰の問題か?
第5部 それはどこからきたか?
第6部 われわれはそれをほんとうに解きたいか?

----- 7.水平思考の世界 -----

ブルーバックス 水平思考の世界 - 電算機時代のための創造的思考法
エドワード・デ・ボノ【著】
白井実【訳】
講談社
1983年7月発売のベストセラー。
自分のカラを破れ! 現代のようなコンピュータ時代にこそ、人間の創造的機能が大いに発揮されなければならない。なぜならば新しいアイデアを生み、新しい角度からものをみる頭脳、能力が、進歩成長の原動力となっているからである。「水平思考とは、問題解決のために、"想像力ゲーム"を意識的に使うことである。つまり、直線的なロジックでは見落とされてしまう新しいアプローチをみつけることである。
【目次】
まえがき
1 垂直思考と水平思考
2 アイデアを生み出す法
3 古いアイデアの支配
4 水平思考の視覚的訓練
5 水平思考のさまざまなアプローチ
6 新しいアイデアを阻む垂直思考
7 アイデアを生むチャンスの利用
8 水平思考の具体例
9 水平思考によらないマイナス
10 水平思考の応用と展開
要約
※2015年11月、きこ書房より、藤島 みさ子【訳】
「水平思考の世界 ― 固定観念がはずれる創造的思考法」が、
「半世紀読み継がれているアイデアのバイブル」として発売されている。

----- 8.問題発見力と解決力 -----

日経ビジネス人文庫 ビジネススクールで身につける 問題発見力と解決力
小林裕亨/永禮弘之【著】
日経BPM(日本経済新聞出版本部)
2006年4月発売
ビジネスでは課題は与えられない。過去のやり方も通用しない。だから取り組む課題を自ら見つけ(=問題発見力)、解決策を立案し実践する(=解決力)能力が必要だ。豊富な事例と各章のポイントを図表化したまとめにより、どの階層のビジネスマンでも理解しやすいように配慮されている。
【目次】
[基本編]
第1章 組織における問題発見と解決の難しさ
第2章 問題発見力と解決力を高める思考・行動様式
第3章 問題解決請負人への道
[視点編]
第4章 顧客視点で見る
第5章 プロセスと数字を「見える化」する
[問題発見力編]
第6章 問題をどう見つけるか
第7章 目標を設定する
[問題解決力編]
第8章 DMAIC問題解決法を身につける
第9章 プロジェクトリーダーのスキル
第10章 実践研修でおぼえる問題解決の定石
----- 9.課題解決の技術 -----

ポケットサイズのノウハウ・ドゥハウ
課題解決の技術 ― 「5段階思考法」がビジネスの勝敗を決める!
野口 吉昭【編】
HRインスティテュート【著】
PHP研究所
2002年11月発売
仕事ができる人の思考ステップ/ロジカルシンキングと仮説検証の思考法で、ビジネス課題をいかに克服するかを、図表を交えて解説。本書のノウハウを知れば、どんな課題にも対応でき、鬼に金棒。
【目次】
総論 課題解決の技術
(問題と課題は違う;問題がわからなければ課題も解決策もわからない ほか)
技術1 仮説検証サイクルを回す
(仮説とは何か;なぜ仮説が必要か ほか)
技術2 情報収集力&分析力
(情報にはどのようなものがあるか;どういうときにどんな情報が必要か ほか)
技術3 ロジカルシンキング
(ロジカルシンキングとは何か;ロジカルシンキングの3つの体系 ほか)
技術4 課題構造化力&構成化力
(構造化はなぜ必要か;ロジカルシンキングの課題構造化力&構成化力のパターン ほか)
技術5 解決策創造力
(ビジョンとは何か;ビジョンの2つの種類 ほか)
----- 10.QCからの発想 -----
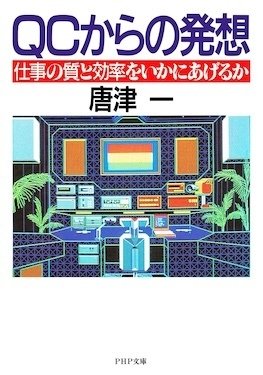
PHP文庫 QCからの発想 - 仕事の質と効率をいかにあげるか
唐津一【著】
PHP研究所
1987年4月発売
品質管理の向上にすぐれた業績を残した者に贈られるデミング賞を受賞した著者が、仕事の改善の着眼ポイント、問題解決の手順などをやさしく解説。サービス業をはじめ、あらゆる分野に応用できるQCのノウハウを説いた書。
【目次】
第1章 推理小説よりおもしろいドキュメンタリー?
第2章 赤信号みんなで渡ればこわくない?
第3章 かけ声だけでは火は消せない?
第4章 守るも攻めるも知恵しだい?
第5章 未利用資源はQCで開拓できる?
----- 11.成川式文章の書き方 -----

成川式 文章の書き方 ― ちょっとした技術でだれでも上達できる (改訂版)
成川 豊彦【著】
PHP研究所
1998年3月発売
表記法、避けるべき表現や文法の知識など、文章についての項目を細かく分解して説明。よい文章の法則がわかり、仕事を進めるにあたって求められる最低限の文章力が得られる。
【目次】
第1章 文章上達のための心構え
第2章 ちょっとした文章作法でみるみる上達
第3章 文章上達「べからず」集
第4章 注意すべき文章表記法
第5章 しっかり覚えよう!文法編
----- 12.「超」文章法 -----

中公新書 「超」文章法
野口 悠紀雄【著】
中央公論新社
2002年10月発売
これまでの文章読本が扱ってこなかった問題への答がここにある。伝えたいメッセージを確実に伝え、読み手を説得するには。論点をどう提示するか。説得力を強めるために比喩や引用をどう用いるか。わかりやすい文章にするためのコツは。読み手に興味を持ってもらうには・・・。
【目次】
メッセージこそ重要だ
骨組みを作る(内容面のプロット;形式面の構成)
筋力増強―説得力を強める
化粧する(わかりにくい文章と闘う;一〇〇回でも推敲する)
始めればできる
----- 13.情報デザイン入門 -----

平凡社新書 情報デザイン入門 ― インターネット時代の表現術
渡辺 保史【著】
平凡社
2001年7月発売
すべての人が表現者になるインターネット時代に求められている画期的デザイン論。
形のない「知識」や「情報」を「デザイン」するとはどういうことか?「情報デザイン」とは、ものと人、人と人との新しい関係を作ることだ。本棚の整理から手帳、地図、時計、そして地域社会の活性化、・・・あらゆるものが、「情報デザイン」の対象である。
いきいきとした例を数多く挙げることによって「情報デザイン」という概念がカバーする範囲の驚くべき広さに気づかせてくれる。情報デザインの実践の立場からかかれた好適の入門書。
【目次】
第1章 情報に「まとまり」をつける
―本棚整理からウェブサイトの構築まで
第2章 見えない空間の地図を描く
―速度の地図からネットの地図まで
第3章 時間で変化する情報をデザインする
―スケジュール管理から地域のフィールドワークまで
第4章 よりわかりやすく、使いやすく
―道具とインターフェイスのデザイン
第5章 環境と身体をめぐる情報デザイン
―生きている世界を実感するデザイン
第6章 社会に開かれていく情報デザイン
―コミュニティをめぐる関係のデザイン
あとがき
当時は最先端あるいは革新的な考え方や手法であっても、今はもう使えそうもないものもいくらかはある。
しかし、今でも十二分に通用する事柄が多く書かれているように思う。
実際、ここで取り上げた本の多くは、ロングセラーであり、改版をしながら現在でも流通しているものもみうけられる。
興味がある人は、(もし入手できたなら)読んでみるのも良いかもしれない。

