
新たなテーマと総合ディレクターご紹介
2025年は、2年にいちどの国際芸術祭「東京ビエンナーレ」の開催年です。秋の季節に、都内各地でさまざまなアート展示やプロジェクト、関連イベントが繰り広げられる予定です。ここでは今回のテーマと総合ディレクターをご紹介します。ぜひ、今年のビエンナーレにもご期待ください。
編集・文:内田伸一
総合テーマは「いっしょに散歩しませんか?」
2025年の総合テーマは「いっしょに散歩しませんか?」。なぜ散歩なのか?についても、下記のステートメントが発表されています。
東京のまちを歩いていると、⽬的地に向かって⾜早に移動する⼈がとても多く感じます。互いに無関⼼で、困っていることや⼩さな苦しみにも気づかずにいる。都会のその距離感が気楽、という⼈もいるでしょう。⼈と真正⾯から向き合うのはエネルギーを要することでもあるから。
でも、そんな諦念をこえて、私たちをゆるやかに優しくつなぐ⽅法はないのでしょうか。アートに、その⼒はないのでしょうか。東京ビエンナーレ2025のテーマは、「いっしょに散歩しませんか?」です。肩を並べて歩けば、たとえ無⾔でも、そこに、ゆるやかなつながりが⽣まれます。⽬的なくゆったり歩けば、視点が⾃由になり、気づかなかった景⾊が⾒えてきます。
本芸術祭においてアートとは、散歩の過程で出会い、⽣まれる、すべてのできことです。いっしょに歩く⼈たちの関係性を創造的に変えたり、知らなかったこと・知っていたことに気づいたり、何が⼼と⾝体の妨げになっているかを知ったり、 精神的に寄り添うことができたり、ひとりであってもひとりではないと感じたり。誰でも。何度でも。⼼と⾝体でいっしょに散歩する新しいかたちのビエンナーレ、はじまります。
東京ビエンナーレ2020/2021では「見なれぬ景色へ ―純粋×切実×逸脱」。
東京ビエンナーレ2023では「リンケージ つながりをつくる」。これまでの開催回におけるテーマとの重なりも、上のステートメントのあちこちにも感じられます。たとえば「気づかなかった景⾊」「ゆるやかなつながり」など。

壁画はO JUN《絵と目》(2021年、有楽町)
撮影:ただ(ゆかい) クリエイティブ・ディレクション:佐藤直樹
東京ビエンナーレのテーマは、各回が切り離された内容(たとえばその時々の社会的トレンドを反映したキーワードなど)ではなく、過去回の積み重ねと発展形であるとも思います。共通するのは「アーティストと市民がともに東京を再発見・再創造すること」ではないでしょうか。これは、まちなかを舞台に市民でつくる「東京の地場に発する国際芸術祭」ならではとも言え、私も東京に暮らす一人として、そこに可能性を感じて関わっています。
「お互いに見つめ合うことではなく、一緒に同じ方向を見つめること」について書いたのはサン=テグジュペリですが、誰かと散歩することはそうした感覚も連想させます。互いの目に映るものはそれぞれでしょう。でもだからこそ、ともにまちを歩くことで始まる再発見や再創造の共有可能性がある。そこでアーティスト、地域の人々、参加者のやりたいことが交わり、新しい挑戦が生まれることを楽しみにしています。
「東京ビエンナーレ2025」 3人の総合ディレクター
続いては、「東京ビエンナーレ2025」の総合ディレクターをご紹介します。今回は3人のディレクターの協働体制となります。
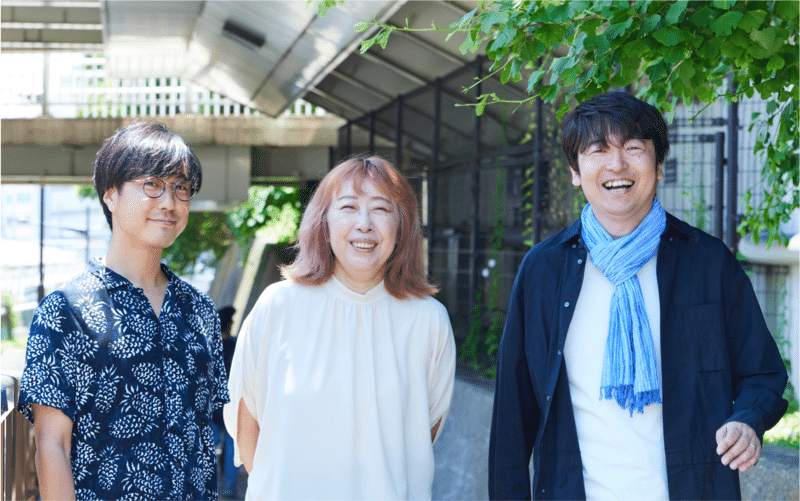
⻄原珉ディレクターは、前回2023年にはアーティストの中村政人と共に共同総合ディレクターを務めました。90年代から中村政人と村上隆の「中村と村上」展や、若き小沢剛や会田誠らが参加した「fo(u)rtunes」展に携わるなど活躍。後にロサンゼルスに渡るとソーシャルワーカー・臨床心理療法士の経験を積み、2018年に帰国しました。
「東京ビエンナーレ2023」ではそうした彼女ならではの視点とネットワークが、国内外のアーティストをつないだ企画「東京のための処方」などに結実しました。今回も、アートとレジリエンス(回復力)、ケアなどをめぐる豊かな経験をもつ彼女がどのような芸術祭をつくるのか、ご期待ください。
プロフィール
1990年代の現代美術シーンで活動後、渡⽶。ロサンゼルスでソーシャルワ
ーカー兼臨床⼼理療法⼠として働く。⼼理療法を⾏うほか、シニア施設、DVシェルターなどでアートプロジェクトを実施。2018年帰国。アートとレジリエンスに関わる活動を⾏う。東京ビエンナーレ2023総合ディレクター、東京藝術⼤学 美術学部先端芸術表現科 准教授。2024年より、秋⽥市⽂化創造館館⻑。
並河進ディレクターは、コピーライター・ 詩⼈・プログラマーの肩書きをもつ、芸術祭のディレクターとしては珍しい(新しい)人かもしれません。前回2023年には芸術祭と人々の接点をつくるコミュニケーション・ディレクターを担当。新聞に大きく掲載された芸術祭マップや、まちなかの屋外ビジョンを活かしたプロジェクトも手がけました。
ソーシャルデザイン、コピーライティングの仕事をしながら、詩とプログラミングによる作品も発表しています。⼈⼯知能との共作詩をつくるなどテクノロジーと創造性についての関心も高く、「一見すると無機質にみえるものに、ストーリーを見出すことが好き」との言葉通り、2023年のビエンナーレでは失われゆく建築や都市の記憶を扱うプロジェクト「Not Lost Tokyo」を牽引しました。そうした視点は今回も発揮されるでしょう。
プロフィール
1973年⽣まれ。dentsu Japan エグゼクティブ・クリエイティブディレクター。東京藝術⼤学芸術未来研究場 アート&ビジネス領域 客員教授。ソーシャルデザイナー、コピーライターとしての仕事の傍ら、詩とプログラミングによる作品を発表し続ける。展覧会に、詩展「little stones in panic forest」(⼭陽堂ギャラリー)、⼈⼯知能との共作による詩展「わたしAとわたしB」(Impact HUB Tokyo)などがある。『ハッピーバースデイ3.11』(⾶⿃新社)他著書多数。
服部浩之ディレクターは、新たに東京ビエンナーレに加わった頼もしいキュレーターです。建築を学んだのち、青森公立大学国際芸術センター青森[ACAC]などでキュレーターとして活躍。担当した第58回ヴェネチア・ビエンナーレ⽇本館展⽰「Cosmo-Eggs | 宇宙の卵」(2019年)は、美術家、作曲家、人類学者、建築家という異分野アーティストの協働を通じて、さまざまな「共存」「共生」をテーマに構成した展示を手がけました。
この試みでは「共同体」ならぬ「共異体」という言葉も語られていました。これは異なる価値観や時間軸の共存を考えさせる言葉で、彼自身も公共性、コモンズ、横断性といったキーワードで、協働によるプロジェクトに取り組み続けており、東京ビエンナーレに新しい風を吹き込んでくれそうです。
プロフィール
2006年早稲⽥⼤学⼤学院修了(建築学)。公共性・コモンズ・横断性を
キーワードに様々な地域で活動を展開するなかで異なる領域の応答関係に関⼼をもち、協働を軸にしたプロジェクトを展開する。近年の活動に、第58回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展⽇本館展⽰「Cosmo-Eggs | 宇宙の卵」(2019年)、「200年をたがやす」(2021年、秋⽥市⽂化創造館)。2021年より東京藝術⼤学准教授。2024年より、⻘森公⽴⼤学 国際芸術センター⻘
森 [ACAC]館⻑。
散歩のはじまり「東京ビエンナーレ2025 プレアクション」
実は「散歩」はもう始まっています。さる2024年秋には「東京ビエンナーレ2025 プレアクション」が開催され、上野エリア、東京駅・日本橋エリア、水道橋エリアで先行するアートプロジェクトやツアーが開催されました。

また今年に入ってからも、今回のテーマにちなんでフィールドワークや特別講義を行うプロジェクト「散歩大学」が1月30日にスタートしました。これらのレポートや、秋の本開催に向け走り出す各プロジェクトの詳細も、次回以降ご紹介していきたいと思います。ぜひ楽しみにお待ちください。
