
PRODUCER Q&A Session 1:なぜWeb3でゲームを出すことを選んだのですか?
ユーザーの皆様からいただいた質問に、プロデューサーのNAOKIが答える企画、「PRODUCER Q&A」のコーナー。今回は6つの質問にお答えしました。
Q1: 自己紹介とご自身のWeb3文脈を教えてください

OSU!TOKYO BEASTのNAOKIです。
そうですね、非常に正直にお話しすると、私はこれまでずっとWeb2のソーシャルゲームを作ったり、プロデューサーとして関わってきました。Web3に本格的に触れたり研究し始めたのは、このTOKYO BEASTの開発が始まってからです。本格的に取り組み始めたのは2年ほど前からですね。
Q2: どうしてWeb2ゲームとしてリリースする力があるのに、Web3に焦点を当てることにしたのですか? 多くのNFTプロジェクトは価値を失い、99%は無価値です。特に多くの人がNFTプロジェクトは詐欺だと考えているにもかかわらず、どうしてWeb3でリリースすることを選択するのでしょうか?

いい質問ですね。
多くのタイトルが無価値だという厳しいご意見を頂いていますけど、そうですね、多分大きく2つあって。
1つは、TOKYOBESTを開発し始めたときのきっかけでもあるんですけれども、やっぱりAxie Infinityとか、STEPNとか、ああいうWeb3の本当に巨大なタイトルが出てきて、ビジネス的にも、これからその業界が伸びていきそうだし、すごく規模感が出せそうなニオイがしたというのが1つ。
そして、もう1つは、僕らプロのWeb2ゲームの開発チームの技術に、Web3の技術が重なることで、よりゲームが面白くなるというか、ゲームだけじゃなくて本当に総合的なエンターテインメント体験みたいなものを作ることができそうだなっていう未来が見えて。
おっしゃるとおり、結構、急いで作ったなって印象のタイトルとか、本当にこう、運営側がもしくはそこに関わってきているユーザーたちが、基本はお金儲けのことだけを考えているタイトルっていうのもやっぱり多いなとは思ってるんですけど、僕らはそういうタイトルとは違って。
本当にWeb3があったからできる面白さとかユーザー体験みたいなものを本当に真剣に追い求めて作ってますし、ものづくりに対して、これは大げさかもしれないですけど、世界のどのweb3タイトルと比べても、一番真剣に取り組んでいるなという自負はあるので、そこを楽しみにしてもらえたらなと思っています。
Q3: Web3要素がからむことで、さらにエンタメ性が上がるという発言がありましたが、Web2だけでは実現できない楽しさがあるということですか?

そうですね。うちのタイトルでいうと、具体的にホワイトペーパーとか読んでくださっている方はご存じだと思うんですが、やっぱりベッティングがあったりとか。あと、NFTがオーナーとして、いわゆるゲームプレーヤーではないけど、オーナーとしてこのタイトルに関われたりとかっていうところが、絶対Web2だけではできなかった部分ですね。
ちょっと言い方がアレですけど、やっぱりお金がかかると、何事も熱くなれるっていうのも絶対あると思いますし、間違いなく、自分たちがWeb2の中だけでやろうと思ったらできなかったことっていうのが、今回のWeb3の技術によって、表現することができるようになるだろうなというふうに思っています。
Q4: どうして現在web2領域でも成功しているweb3タイトルがないと考えてますか?一部のNFTプロジェクトは立ち上げ時に成功しているように見えても、結局Web2 ユーザーが本当に一緒にプレイできるゲームはありません。

なるほど。今まで出てきたタイトルが、Web2ユーザーさんはプレーはできるんだけど、結局、うまくプレーが成り立ったことがない、それがなぜだと考えているかっていうことですよね。
これも2つですかね…。1つは、やっぱりそもそもWeb2ユーザーさんにとっての、参入ハードルというか、スタートハードルがやっぱり高いタイトルが多いですよね、Web3ゲームって。
それは例えば、本当に分かりやすい例で言うと、そもそもウォレットがないと遊べないとか、NFTを買わないとできませんとか、そもそもトークンってなんぞみたいな話とか、詳しい人じゃないと全然分からないような知識とか、前提が必要なタイトルさんっていうものがやっぱり多いと思うので。
そういう意味で、やりたいんだけど分かんないなとか、やってみたんだけど結局そういう難しい話があってやめちゃうみたいな、そういうパターンが一つあるかなと。
もう1つは、結局「Web3タイトルである意味があるか」という部分があると思います。Web2のユーザーさんからして「Web3のタイトルをやる意味があるか」みたいなのが結構あるなと思ってて。
本当に既存のWeb2ゲームに取って付けたように、アイテムがNFTになりますとか、ただ独自に発行しているトークンがありますとか、そういう話だとWeb2のユーザーさんからするとそもそもそのゲームをやる意味ってあんまりなくて。それに似たもともと自分が好きな有名なタイトルとか、普通にWeb2ユーザーのユーザーがWeb2のユーザーだけで遊んでいるタイトルをやればいいじゃんそれで終わっちゃうじゃんっていうのが、やっぱり普通の考え方だと思っています。
なので僕らは、Web2のユーザーさんも結局、Web3があるから、Web2文脈でもゲームが面白いよねっていうふうに作らなきゃいけないと思っていて。
本当の意味でWeb2とWeb3の融合みたいなところに向き合って作られるタイトルが少ないっていうのが、Web2とWeb3が共存できたタイトルが少ない原因というか、課題の1つなのかなと思います。僕らはすごく本気でそこにチャレンジをしているという状況ですね。
Q5: TOKYO BEASTはNFT PROXY MODELが特徴的ですが、このモデルがあることによって、web2ユーザーへ起こる変化で大きなものを教えてください
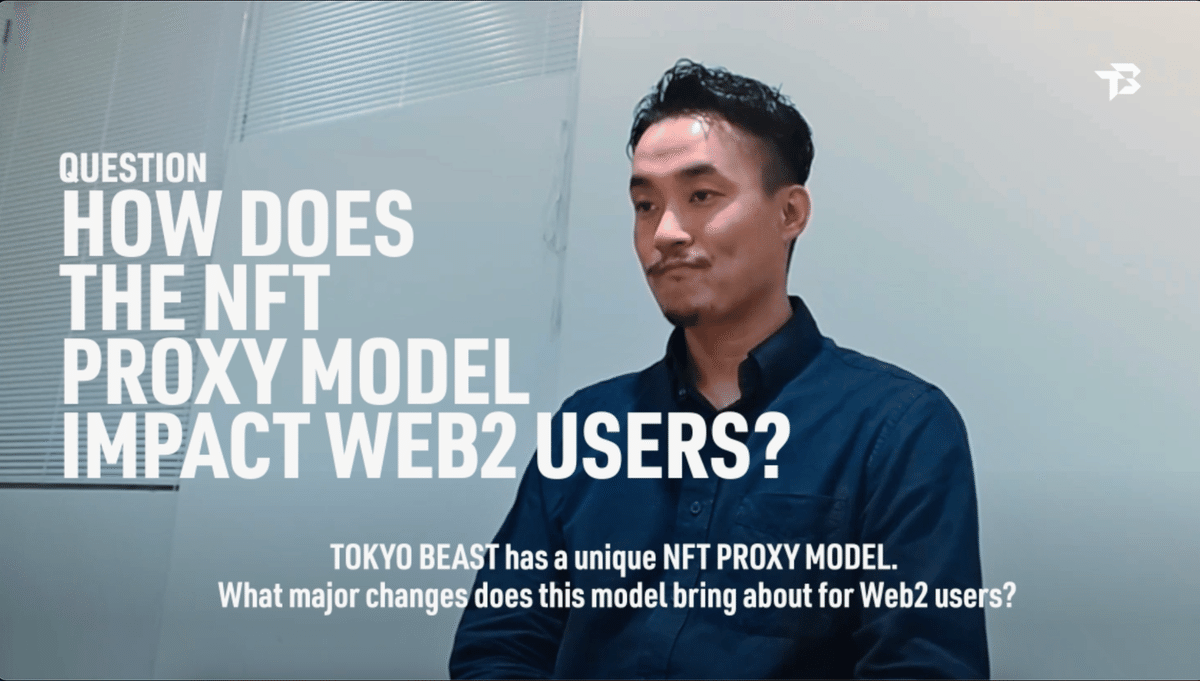
NFT PROXY MODELとは、TOKYO BEASTにおける独自のシステムで、ゲームプレイヤーがNFTホルダーの持っているBEAST NFTのコピーデータであるPROXY BEASTを使ってゲームを楽しむことができる仕組み。このモデルにより、プレイヤーは直接NFTを購入しなくてもゲームに参加することができ、NFTの初期購入に伴うハードルを下げることで、Web2ユーザーにも参加しやすく設計されています。また、NFTの発行数を抑えることができるため、NFTホルダーにとっても有意義な体験が提供されます。
NFT PROXY MODELって、僕らのゲームにとってすごい重要な仕組みで。
Web2ユーザーの参入に関してはとても大きな意味を持つモデルです。
TOKYO BEASTをプレイする際に、今までのWeb2タイトルと同じようなフローで遊べるというのが一番の利点で、普通にApp StoreとかGooglePlayからアプリをダウンロードしてきて、普通にフリープレーでゲームができるというのが担保されます。要はNFT持ってないとゲームできないよとか、ウォレット接続しないとゲームできないよとか、トークンで買わないとプレイできないよっていうのを、一切なくしました。
Web2ユーザーさんって、Web3のことが分かんない人がほとんどだと思っているので、Web3に関しても、「なんかNFTは聞いたことあるけど、なんだろう?」ぐらいの人も全然いると思うので、そういう人たちも、単純にまず普通にこう「なんか面白そうだからやってみようかな」となった時に、スムーズにプレーできる。今までのweb2ゲームと変わらずに、スムーズにそのままゲームに入ってこれるっていうのが、実現できている、実現するための仕組みっていうのが、NFTプロキシモデルのポイントでもあったりします。
モデルの話になると長くなっちゃうんですけど、そういうハードルを完全になくしてるっていうのが一点いいところですね。
ついでに答えるんですが、NFT PROXY MODELって、Web3のユーザーさんにとっても、NFTの価値担保という観点でもすごく意味があって。
まあ要はNFT PROXY MODELって、NFTの本体を持っているユーザーさんと、そのNFTのコピーデータがゲームのほうで生成されて、ゲームのユーザーさんはそのコピーデータを使ってゲームがプレイできるっていう仕組みになっているので、例えば、これがNFTを持っていないとゲームできないよってなると、NFTはもう本当にユーザーさんを集めるためには、無尽蔵に発行し続けなきゃいけないと。
そうするとやっぱりどうしても、NFTって発行すれば発行するほど、価値が下がりやすくなってしまう。なので、NFT PROXY MODELを使えば、NFTはある程度数を絞って価値を担保しながらも、ゲームをプレイするユーザーさんの数は無制限に広げられることができ、NFTの価値担保と多大なユーザー数の両方担保できるっていうのも、このNFT PROXY MODELの一個の特徴だったりします。なので、Web2だけでなく、Web3のNFTホルダーの方々にとってもすごく重要な仕組みになってくるかなというふうに考えてます。
Q6: BEAST NFT HolderはNFTの情報を自由に更新できるのが面白いと思いました。このモデルを採用することでどのような未来のコミュニティー体験を目指しているのでしょうか。

要は、NFTホルダーが、BEASTの強化とか、ブリードとか育成できるみたいなところがどうコミュニティーにつながるかということですよね。そこのポイントだけでいうと、ちょっと面白そうだなと思っている形が、BEAST1体に対してオーナーさんって1人なんですよ。なんですけど、そのBEAST自体をゲームの中で使っているプレイヤーさんがたくさんいるっていう構図になっていくので、そのオーナーさんとそのオーナーさんが持ってるBEASTを使ってプレーしているプレイヤーさんたちのコミュニティーみたいなものが発生してくる可能性があるなと思っていて、それは結構面白いなと。むしろぜひそういうのを作っていってほしいなと思ってます。
実際そこでどういうコミュニケーションが生まれるかっていう話のイメージでいうと。例えば、BEAST自体のパラメーターとか、スキルとか、ブリードとかっていうのは、このオーナーさんにしかできないことで、ゲーム側でプレーしているプレイヤーさんたちがオーナーさんに多分、オーダーを出すんですよね。もっとこういうパラメーターにしてくれたら、強くなるとか、使いやすくなるとか、今のゲームのバトルの環境的には、ここもちょっとこういうふうにしてもらったほうがより強いBEASTになると思うみたいな、それをオーナーさんが頑張って、BASE側でBEASTのパラメーターを調整したりとか、いわゆる、強化育成みたいなことを、頑張っていくみたいな未来があるんじゃないかなと思っていて、それは一つ、楽しみだなと思っています。
今回のプロデューサーQ&Aはここまで!
次回の更新も、お見逃しなく。
