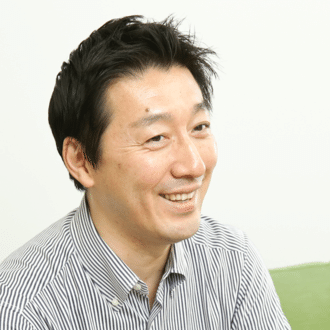嵐の大野智さんへの悪質デマ問題に学ぶ、悪質なデマや誹謗中傷を減らすための唯一の選択肢
嵐の大野智さんに対する虚偽のデマを投稿、拡散した人物やサイトに対して、STARTO ENTERTAINMENT(以下、STARTO社)が発信者開示請求などの法的措置を進め、一部インターネットサイトを閉鎖するなどの成果を上げたと発表したことが大きな注目を集めています。
これは、もともとXで炎上系インフルエンサーが、未確定情報としつつも、嵐の大野智さんが逮捕されたらしい、という趣旨の投稿を行ったことが発端となった騒動です。
11月28日に投稿されたこのデマ投稿は、あっという間にX上で拡散。
伝聞で聞いた人の一部が、それを信じてさらに投稿を繰り返したり、記事化するというデマのスパイラルが発生したため、STARTO社が11月30日付で「看過できない虚偽の記事とそれに伴うSNS投稿について、法的措置をとる」と宣言する展開となりました。
◤ 名誉毀損記事と一部のSNS投稿に対するお知らせ ◢
— STARTO ENTERTAINMENT(Corporate) (@Lets_starto) November 30, 2024
当社契約タレントへの、看過できない虚偽の記事とそれに伴うSNS投稿について、法的措置をとることをお知らせします。
詳細は以下をご確認ください。https://t.co/opPZyHMVVv
STARTO社が騒動発生直後に「法的措置をとる」ことを表明したことは、驚きを持って受け止められ、こうしたSTARTO社の迅速な動きに対し、発端となった投稿を行った炎上系インフルエンサーは、即座に一連の投稿を削除し、関係者への謝罪投稿を行う展開になりました。
今回のSTARTO社の発表は、この11月30日に開始した法的措置の途中経過を報告するもので、権利侵害投稿7件に対し通信会社が特定されたため、通信会社に契約者情報の開示請求を行ったことを発表したものとなります。
実はこうしたSTARTO社の姿勢は、今後組織が悪質なデマや誹謗中傷から社員や関係者を守る為にポイントになると考えられますので、ご紹介したいと思います。
怒りを呼ぶデマ投稿をお金にする「レイジベイティング」
従来、一般人によるネット上の虚偽投稿に対しては、「法的措置を検討する」というポーズを取る企業は多くても、実際に法的措置まで踏み切る企業は少なかったのが現実だと思います。
これは訴訟費用が見合わないという問題もありますが、企業や組織が一般人の誹謗中傷に対する法的措置を取るという行為を、やりすぎではないかと考える人がまだ多かった面も影響していると考えられます。
象徴的なのは、オリンピックのたびにオリンピック選手への誹謗中傷が問題になるものの、協会や選手が積極的な法的措置を取っていないと見られることです。
ただ、もはや状況は明らかに変わってしまいました。
一般人の憶測の投稿であっても、X上でたくさんのリポストが集まれば、おすすめのタイムラインに表示されることによって、話題が一気にXのトレンド入りすることも珍しくない時代になっています。
最も重要な変化と言えるのが、Xが収益化プログラムを用意したことにより、そうした憶測の投稿によって他の人の怒りを煽り、注目を集めることで収益をあげる「レイジベイティング」と呼ばれるような手法が流行するようになってしまっている点です。
実は、炎上系インフルエンサーと呼ばれる人達は、以前は主に唯一収益化が可能なSNSだったYouTubeを中心に活動していました。
ただ、ある程度YouTube側の迷惑YouTuber対策や、炎上系YouTuberの代表的存在だったガーシー氏の逮捕により、落ち着きを見せていると言われています。
しかし、Xの収益化プログラムの登場により、活動の場が拡がりを見せてしまったことで、あらためて炎上系インフルエンサーの存在感を増す結果となっていることがポイントと言えます。
さらに、アメリカでトランプ大統領が就任し、ツイッターを買収して「対戦型SNS」であるXに変貌させたマスク氏が要職に就いたり、メタ社がファクトチェックの廃止を宣言するなど、大手プラットフォームが「言論の自由」の名の下に検閲を廃止していく流れがあることを踏まえると、こうした「レイジベイティング」の手法は、今後収まることはなく増加していく可能性が高いと考えられるのです。
1つの憶測投稿事件が炎上件数の減少に
一方で、実はこうした炎上系インフルエンサーの憶測による投稿や、炎上の拡散行為は、法的措置によって減らすことができることが証明されつつあります。
象徴的なのは、昨年5月に発生した星野源さんに対してデマによる誹謗中傷が発生した問題です。
この問題も、今回の大野智さんの問題と同じように、炎上系インフルエンサーが、匿名ではあるものの星野源さんを想像させる形で、不倫とそのもみ消しについての噂を拡散することで発生しました。
この投稿を行った滝沢ガレソ氏がXのフォロワーが270万人を越えるインフルエンサーだったこともあり、この憶測投稿は1.5億回以上も表示され大きく拡散、アミューズ側が迅速に否定して「法的措置を検討」と宣言する結果になったことを覚えている方は少なくないと思います。
最終的にこの騒動は、9月になってようやく滝沢ガレソ氏が投稿を削除し、謝罪する形で決着することになります。
興味深いのは、実はこの騒動の後、滝沢ガレソ氏が炎上ネタを取り上げる方針を変更したことによって、日本での炎上発生件数が減少したという分析結果が出ている点です。

上記は、デジタル・クライシス総合研究所が作成している「デジタル・クライシス白書2025」に掲載されている2024年の炎上発生件数のグラフです。
5月以降明らかに炎上件数が減少していることが良く分かると思いますが、この減少要因の1つに、前述の騒動によって滝沢ガレソ氏の投稿方針が変わったことが影響しているとデジタル・クライシス総合研究所が分析しているのです。
筆者は、このデジタル・クライシス総合研究所のアドバイザーもさせて頂いている関係で、このグラフを少し早めに拝見しましたが、ここまで明確に件数が減少していることに驚いたのが正直なところです。
法的措置を行うことが悪質なデマ抑制の唯一の選択肢
ただ、ここから学べるのは、現在の憶測投稿に基づく炎上拡散の増加に対しては、断固たる法的措置を取る姿勢が、明らかに効果をもたらすということです。
多くの炎上系インフルエンサーは、若くしてフォロワーが増えた結果、法的リスクなどをあまり分からないまま影響力を持ってしまったケースが往々にして存在します。
また、多くの駆け出しの炎上系インフルエンサーは、他の影響力の大きな炎上系インフルエンサーの投稿姿勢を見て真似するのが一般的です。
そういう意味で、今回のSTARTO社や昨年のアミューズのように、明確に法的問題がある投稿に対しては、法的措置を取っていくことによって、影響力の高い炎上系インフルエンサーも、駆け出しの炎上系インフルエンサーも、法的リスクのある投稿を自重するようになっていく可能性が明確になっているわけです。
最近は一般的に理解されるようになってきていますが、炎上に加担する人や誹謗中傷に加担する人というのは実は40万人に1人など非常に少数で、少人数が大量の投稿を行うことによって炎上状態を作り出していることも少なくないと言われています。

炎上の起点となるような投稿をする人や、誹謗中傷の投稿をする人は、放置されていれば放置されているほど、慢心して過激化し、より過激な投稿をするようになるリスクがあるとも言えます。
これまでは、誹謗中傷に対する罰則も甘く、「ネット上の投稿ぐらいで訴訟するなんて」と考える人が少なくなかったことが、こうした過激な投稿を放置してきてしまった面があることは間違いないでしょう。
しかし、ネット上の悪質なデマやそれによる誹謗中傷が、多くの人の心を傷つけ、時には人の命を奪う結果になってしまうことも明確になりつつあります。
今後はプラットフォーム側が、アメリカでの政治的方針転換により、そうした過激な投稿の削除やアカウントの凍結を行わなくなっていくことを考えると、もはや法的措置を取ることこそが悪質なデマや、無益な炎上発生を抑制するための唯一の選択肢と言えるかもしれません。
当然、一般人やアーティスト個人がそういった対応を行うことは現実問題として難しいと考えられますので、今後はSTARTO社やアミューズのように、事務所や会社、オリンピック選手のようなスポーツの場合には協会などが、悪質なデマや誹謗中傷に対する断固とした法的措置を組織的に実施し、組織に所属する個人を守る姿勢を見せていくことが求められるように思います。
この記事は2025年2月1日Yahooニュース寄稿記事の全文転載です。
なお、今日13時からの雑談部屋「ミライカフェ」では、このあたりの話題も皆さんと雑談できればと思っています。
タイミングが合う方は是非ご参加下さい。
今日の雑談部屋「ミライカフェ」は、13時開始です。
— 徳力 基彦(tokuriki) (@tokuriki) February 2, 2025
タイミング合う方は是非ご参加ください。
日本のアーティストの海外展開とか誹謗中傷対策とか(#ミライカフェ)https://t.co/8kYB5na8sw
いいなと思ったら応援しよう!