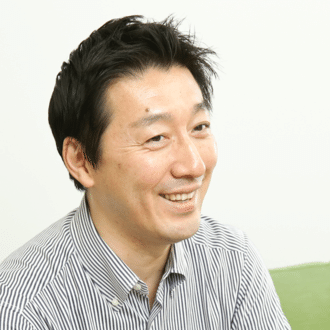Netflixは、なぜ日本で成功することができたのか。
Netflixの日本発コンテンツの勢いが止まりません。
Netflixといえば今月、流行語大賞で『地面師たち』のセリフ「もうええでしょう」がトップテン入りしたかと思えば、日本国内の会員数が1000万を突破していたことを発表して注目されました。
その上、今度は「アジアン・アカデミー・クリエイティブ・アワード」で日本発Netflix作品が5部門受賞の快挙を成し遂げたというニュースが入ってきました。
特に大きなニュースと言えるのが、映画『シティーハンター』が最優秀作品賞に加えて、主演を務めた鈴木亮平さんが日本人初となる最優秀コメディ部門主演俳優賞と最優秀主演男優賞をダブル受賞され、3冠を達成されたことでしょう。
今年はまさに、日本発のNetflix作品の躍進の年だったと言えると思います。
一方、ここで振り返っておきたいのは「なぜNetflixは日本で成功することができたのか?」という問いです。
資金力が成功の秘密?
日本の映像関係者の方に、この問いを投げかけると「Netflixには膨大な資金力があるから」という答える方は少なくないと思います。
ただ、実はこの答えは必ずしも正解とは言えません。
あえて厳しい言葉を選ぶとすれば、日本の映像関係者がそう考えている限り、Netflixの成功の答えを見つけることができない、ということが言えるかもしれません。
もちろん、Netflixには世界に2億8000万以上の会員がおり、年間のコンテンツ投資額は2兆円を優に超えると言われていますから、日本企業が束になってもかなわない資金力があるのは事実です。

ただ、そのNetflixも2015年9月に日本に参入してから3年間は、なかなか会員数が増えない厳しい時期がありました。
Netflixで日本コンテンツを統括する坂本和隆氏によると、その頃はアメリカからは日本の実写コンテンツが本当に必要なのか、懐疑的な見方も少なくなかったとのことです。
筆者自身も、当時のNetflixは、『ストレンジャー・シングス』のようなハリウッド制作のドラマや映画を視聴するためのサービスだと思い込んでいたのを良く覚えています。
ただ日本は世界の中でも、際だってハリウッドの映画がヒットしなくなっている国です。
もし、Netflixが日本の実写コンテンツに注力しないままだったら、実は現在ほどNetflixは日本で話題にならなかったでしょうし、現在のように会員数を増やすことができなかった可能性は高いと考えられるのです。
『全裸監督』の成功がNetflixのイメージを変える
その雰囲気を一変させたのが2019年に配信が開始された『全裸監督』でした。
この作品を視聴したことがない方には、アダルトビデオの帝王と呼ばれた村西とおる監督を題材にしている関係で、「コンプラ的に地上波では放送できないドラマ」という印象が強いかもしれません。
ただ、当時業界でこの作品が注目されたのは、そのアダルトビデオをテーマにしているという文脈だけでなく、ドラマとしてのクオリティや完成度の高さゆえでした。
現在Netflixでプロデューサーとして『シティーハンター』や『地面師たち』を大ヒットに導いた髙橋信一さんも、当時前職の映画の撮影現場でスタッフ全員が『全裸監督』の話をしていて、こんな作品が日本でつくれるのかと驚き、自分でも作りたいと思ったことがNetflixに転職したきっかけだったと話されています。
ただ、この作品は簡単に生み出されたわけではなく、生み出されるまでに様々なハードルがあったようです。
2019年以前を知るNetflix関係者は「坂本さんの粘り勝ちだった」という言葉を使っていました。
世界に比べるとなかなか会員数も伸びず、世界に広がるヒット作品もなかなか生まれていなかった日本市場において、本当に日本発のNetflixオリジナル作品を作る必要があるのかどうか懐疑的な見方が多ければ、『全裸監督』のような作品作りを継続することが難しい状況になることは容易に想像できます。
Netflix全体として資金力があっても、それを日本の実写コンテンツに投資するかどうかは全く別の話なのです。
しかし、坂本さんはその状況でも諦めずに、 『全裸監督』のような日本発の実写作品作りの可能性や重要性を信じて、熱意を持って周囲の説得にあたっていたそうです。
会員500万突破のきっかけに
結果的に『全裸監督』が成功を収めたことで、日本国内の映像関係者からのNetflixの印象も大きく変わり、Netflix社内における日本の実写コンテンツに対する印象も大きく変わり、Netflixの日本における存在感も大きく変わることになります。
その後Netflixは2019年の年末には嵐のドキュメンタリーを配信開始。
さらなる会員数の増加に弾みをつけます。
そして、翌年2020年にはコロナ禍の影響もあり、会員数はさらに増加、2020年の9月には1年で200万もの会員増を達成し、会員数が500万を突破したことを発表するのです。
ある意味では、コロナ禍の前に『全裸監督』が生まれていなければ、その後のNetflixの日本における快進撃はなかったかもしれないとも言えるのです。
その後、日本発のNetflix作品は、2020年の『今際の国のアリス』のヒットなどもあり、着実にその存在感を増していくことになります。
ここでポイントとなるのが、Netflixにおける日本作品への投資は、こうした1つずつの成功があるからこそ、徐々に投資額が上がってきているという点です。
今回『シティハンター』が3冠を受賞した「アジアン・アカデミー・クリエイティブ・アワード」では、Netflixの『幽☆遊☆白書」が日本作品としては史上初となる最優秀視覚効果賞に輝いていますが、『幽☆遊☆白書」がその受賞に値する規模のVFX投資ができたのは、それまでの日本発作品の成功があったからと言えるわけです。
つまり、Netflixが日本発作品で投資や成功の規模を上げることができているのは、『全裸監督』の頃から1つずつ成功を積み上げながら、作品にかけられる金額を増やすことができているからということです。
Netflixの日本発作品が成功し、Netflixが日本で1000万会員を突破する成功を収めることができたのは、単純にNetflixに膨大な資金力があるからではなく、Netflixの坂本さんや髙橋さんのような日本チームが、地道に1つずつ成功を積み上げて日本発作品の可能性を証明してきているから、と考えるべきなのです。
リスクを取らせてくれる企業文化
筆者が、坂本和隆さんに「これからライバルも日本の実写作品に注力してくると思いますが、その際のNetflixの強みって何ですか?」と質問させていただいたところ、非常に興味深かったのが「Netflixはリスクを取らせてくれる会社」と回答されていた点です。

実際に、Netflixがリスクを取らせてくれる会社だからこそ、2019年までの日本市場で苦戦していたNetflixにおいても、坂本和隆さんの熱意が『全裸監督』のような作品を生み出すことにつながったと言えるわけです。
逆に言うと、これから日本のテレビ局や映画会社に問われるのは、「Netflix同様に自分達はリスクを取れるか?」という問いになるでしょう。
これまで日本の映像業界は、日本市場だけを対象に、ある程度予算を抑え、ある程度日本人にウケるコンテンツを作るというスタイルを確立してしまっていました。
ただ、Netflixで坂本さんや髙橋さんが証明してくれているのは、日本発コンテンツもリスクを取ってしっかりと投資をすれば、世界に通用するということです。
「アジアン・アカデミー・クリエイティブ・アワード」でシティーハンターが三冠を獲得したように、これからNetflixの日本発の実写作品の活躍がさらに世界に拡がっていくことは間違いないでしょう。
このNetflixの成功が、日本の映像業界全体にも拡がっていくかどうかは、各社がリスクを取って必要な投資を行っていけるかどうかにかかっているのかもしれません。
この記事は2024年12月8日Yahooニュース寄稿記事の全文転載です。
今日13時からの雑談部屋「ミライカフェ」では、皆さんとこのあたりの話題を雑談できればと考えています。
タイミングが合う方は是非ご参加下さい。
月曜日の雑談部屋「ミライカフェ」は、13時開始です。
— 徳力 基彦(tokuriki) (@tokuriki) December 8, 2024
タイミングが合う方は是非ご参加ください。
Netflixの強さの秘訣とか、注目点とか(#ミライカフェ)https://t.co/y1RcfCifIx
いいなと思ったら応援しよう!