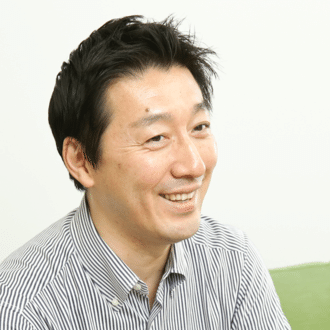私たちは、なぜまだ「ポケモンGO」を続けているのか
この記事は2018年11月17日に東洋経済オンラインに寄稿した記事を転載したものです。
「ポケモンGO」が一大ムーブメントを巻き起こした2016年7月から、もう2年以上が経過しました。
私自身は、ポケモンGOのサービス開始から、ほぼ毎日のようにアプリを起動し、ポケモンゲットにいそしんでいる人間ですが、おかげで「徳力さん、まだポケモンGOやっているんですか?」と聞かれる機会も増えました。
私と同じようにポケモンGO生活を続けている人にはわかってもらえると思いますが、その質問をされること自体が、正直ちょっと寂しくなったり、ちょっとイラッとしたりします。
そこで、今日はこの場を借りて、ポケモンGOについての誤解を解く機会をいただければと思います。
ポケモンGOをやっている人にしかわからない説明になりますが、私の現在のトレーナーレベルは39。とっくに最高レベルの40に到達している本当のガチの人に比べると遅いペースですが、たまにプレイしている人からするとガチ側の人に見えるかな、ぐらいの立場です。
ポケモンGOについては、プレイを日々続けている人と、続けていない人で、見えている世界感がまったく違う、まさにパラレルワールドのような世界だと思います。
2年前、「ポケGOに迫り始めた『流行語大賞病』のワナ」(2016年9月4日配信)という記事を書きましたが、ポケモンGOにおいては、サービス開始時のブームがあまりに大きかったことの反動から、いわゆる最初のたまごっち現象のように、一時的ブームに見えやすいという問題がそもそもあります。
実際にGoogleトレンドで「ポケモンGO」のグラフを見てみると、最初のブームがあまりに大きすぎてその後に沈静化したように見えてしまうのは事実です。

でも、これは最初の山があまりに大きすぎただけです。
実は、世界のスマホアプリのアプリ内売上高ランキングでは、ポケモンGOは引き続きトップ5の座を守り続けており、多くの人がプレイを続けていることがわかります。
ただ、ポケモンGOをほとんどプレイしてない人からすると、ポケモンGOは「スマホゲーム」の1つであり、ゲームなんだから一定期間はまっても、普通はクリアしたり、飽きたりしたら次のゲームに移るもの、というのが常識でしょう。
しかも、言葉を選ばずに言うと、いわゆる狭い意味でのポケモンGOのゲーム性は高くありません。
ちょっとだけポケモンGOをプレイした人からすると、ボール投げてポケモンをつかまえるだけの大して面白くもないゲームに、なんでそんなに長いことはまっていられるのかわからないと思っている人も多いでしょう。
そういう人からすると
「なんで(スマホゲームの1つでしかない)ポケモンGOをまだやってるの?」 とか
「なんで(大して面白くもないゲームだった)ポケモンGOをまだやってるの?」
という質問が出てしまう気持ちもわからなくはありません。
ただ、そういう方が間違っているのは、ポケモンGOを通常のゲームと同じものとして取り扱っている点にあります。
あくまで個人的意見と断りますが、私がいまだにポケモンGOを続けている理由は、下記の3点にあります。
■歩くのが、ちょっぴり楽しくなる
■遠くに行くのが、ちょっぴり楽しくなる
■ヒマな時間が、ちょっぴり楽しくなる
順番にご説明しましょう。
■歩くのが、ちょっぴり楽しくなる
個人的にいちばん大きいのがこれです。
ポケモンGOでは、一定の距離を歩くと卵からポケモンが生まれるという要素があります。卵の種類によって、2km、5km、7km、10kmとあるんですが。
やっぱり卵が割れると嬉しいんですよね。
要は歩数計です。
通常の歩数計とか歩数カウントアプリとかだと、歩数や歩いた距離は測定してくれるものの、特にメリットはないですよね。
それがポケモンGOでは、ポケモンがゲットできます。
いや、ポケモンGOをやっていない人からすると「だからどうした?」という話になるのは間違いないんですが、このちょっぴり楽しくなる、というのがポイントです。
どうせ毎日歩いているんだったら、ポケモンGOを歩数計的に使うほうが、歩くのがちょっぴり楽しくなるんです。
自宅と会社の往復も、ちょっと駅から遠いお客さんへの訪問も。
今までは退屈な移動時間でしかなかったのが、ちょっぴりだけ楽しくなるんです。
せっかく、ちょっぴり楽しくなるんだから、やめる理由がないんですよね。
「歩数計まだ使ってるの?」なんて、あまり言わないと思います。その人の勝手だし、歩数を測ること自体は習慣化してしまえばやめることではないですから。
■遠くに行くのが、ちょっぴり楽しくなる
上の理由と似ていますが、こちらは歩く距離の話ではなく、いろんな場所に行く時の話です。
私自身は超インドア派で、外出は基本的に嫌いです。
できることなら家でずっとゴロゴロしていたいタイプです。
ただ、当然仕事や、子どもたちとの外出で、普段とは違うところに出かけることがあるわけですが、ポケモンGOがあると、そんな外出がちょっぴり楽しくなります。
「ひょっとしたら、まだ手に入れてないポケモンをそこなら見つけられるかも」という期待を持ってしまいます。
特にポケモンGOには、ポケコインというポイントを得るためにジムという特定の場所の陣取り合戦のような要素があるのですが、これが基本的には地方のほうが敵が少なく、ポイントが得やすい傾向にあります。
そうすると、今までは地方とかに行くのが超面倒で仕方なかったのが、ちょっぴり楽しくなったりするわけです。
これまた、せっかくちょっぴり楽しくなるんだから、やめる理由がないんです。面倒な遠出を少し楽しくしてくれる要素は、ほかに比較する対象がありません。
■ヒマな時間が、ちょっぴり楽しくなる
すでに紹介した2つの理由と似ていますが、これは歩いてもいないし、遠くにも行かない時の話です。
たとえば、満員電車の中とか、大行列の待ち時間とか。これはちょっと特殊な話ですが、ポケモンGOにはPokémon GO Plus(以下、GO Plus)という専用端末があります。
スマホと連動して動作するポケベル(若い人にはかえってわからないかもしれませんが……)みたいな端末です。通常ポケモンGOはスマホのアプリを開いてプレイをしますが、このGO Plusがあると、アプリを開かなくても、ポケモンやスポットに反応して振動してくれます。
そうしたら、このGO Plusのボタンを押せば、ポケモンやアイテムをゲットできるわけです。このGO Plusがあると、一日中ポケモンGOのアプリを開いてポケモンやスポットを探す必要はなくなります。
ブルっときたらボタンを押すだけ。ポケモンGOをやってない人からすると意味がわからないと思いますが、とにかくこれがあるだけで、日々の隙間時間がちょっぴり楽しくなるわけです。
ある意味、パブロフの犬状態。もはや、この振動が長いこと来ないと不安になるレベルです。
と言うと、ドン引きされてしまうかもしれませんが。でも、くどいようですが、ちょっぴり楽しくなるから、やめる理由がないんです。
これが、もしGO Plusがなく、つねにスマホのゲームを占有するアプリしかなかったら、私もおそらくどこかで飽きてやめていたと思います。でも、GO Plusがあるとやめる理由がないんです。
極端な話、スマホではほかのスマホゲームやっていても、GO PlusがあればポケモンGOがプレイできてしまうのです。
上記の3点に、いわゆる「ゲーム」として中毒性が高いとか、今までプレイした中で「史上最高のゲーム」で、まだこれ以上のものが出てこないからこれをプレイし続けている、というような「ゲーム」視点での理由が出てこないのがポイントです。
これ以外にも、私の場合は土日に子どもたちとポケモンGOを楽しむ時に、平日の移動時間でたまったアイテムが生きてくるので、子どもに褒めてもらえる、という別の理由もあったりしますが。
とにかくポケモンGOが大きく誤解されているのは、いわゆる「ゲーム」という言葉がもたらす印象でしょう。
実際、ポケモンGOは位置情報を活用したゲーム、と表現されることが多いですが、ポケモンGOを開発しているナイアンティックが提供しているのは、正確には位置情報とゲーム要素を組み合わせたサービス、と理解するほうが正しいように思います。
もちろんゲームとしてガッツリのめり込む人もいます。
私の周辺にも信じられないほど、ポケモンGOのために長い距離を歩いたり、ポケモンGOのために、いろんなスポット巡りをしていたりする人もいます。
一方で歩数計代わりに使いつ続けている人もいれば、知らない土地で手持ち無沙汰になった時の隙間時間を埋めるためのエンタメ要素としてたまに使っている人もいるわけです。
だからこそ、子どもだけでなく、私たちのようなビジネスマンや、シニアの世代も含めてポケモンGOが長く愛されていると言えるでしょう。
さらにポケモンGOはサービス開始時から、継続して機能が追加され続けています。
本来のポケモンの重要な要素である、友達とのポケモン交換が実装されたのは、まだつい数カ月前のことです。毎月のようにイベントが開催されるなど新しい要素が追加され、歩数計と比べれば、楽しく続けやすいサービスなのは間違いありません。
ナイアンティックはポケモンGO以外に、「イングレス」というゲームも提供していますし、来年には「ハリー・ポッター」が始まることが決まっています。今後もこのリアルワールドゲームと呼ばれているカテゴリにはさまざまな変化が起こることでしょう。
この記事は2018年11月17日に東洋経済オンラインに寄稿した記事を転載したものです。
いいなと思ったら応援しよう!