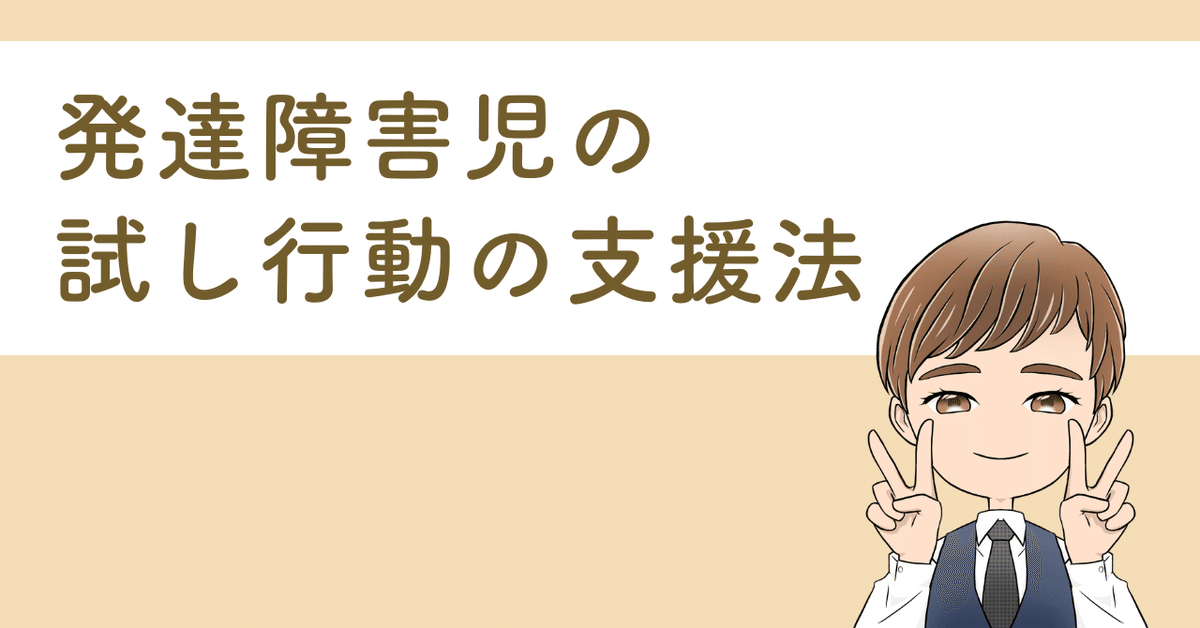
発達障害児の試し行動の支援法
みなさん、こんにちは。
特別支援学校の先生のしんちゃんです。
今回は『発達障害児の試し行動』をテーマに書いていきますね。
こちらは有料記事になります。
教育公務員特例法第17条『教職員の兼業』において、県教委の認可を得ています。
先生や保護者の方は、子どもの試し行動に悩んだ人が多いのではないでしょうか?
僕は知的障害・自閉症学級の担任をしていますが、常に悩んでいることでもあります。例えば、こういった行動がありますよね。
・人に手を出す
・自分の思いや感情を過剰に表現し、周囲の注意を引こうとする
・故意におもちゃを投げたり壊したりする
・走ってはいけないところで走り回る
こいった試し行動が続くと、先生や保護者の方は気持ちに余裕がなくなり、つい怒ってしまうこともあると思います。実際、僕もそうでしたから…
ですが、悩んでいても解説にはならない。職場の先生からのアドバイス、書籍等から学んだこと、実践して成功したことを書いて行きますね。
試し行動と愛着形成
試し行動は、「リミットテスティング」とも呼ばれています。職場では聞いたことのない言葉でした。
これは、わざと良くない行動をして、相手が「何をどこまですると、どのような反応があるのか」、「どこまでであれば、許されるのか」を確かめるための行動ということです。
具体例を挙げると…
・授業中に教師の指示を無視する。
・大人の指示に耳を貸さず、自分の意見を通そうとする
・強い言葉で相手を罵倒する
子どもが小さいうちは、先生や保護者など大人に対して試し行動をすることが多いです。これは、愛着形成をするための成長過程で見られることがあります。
愛着形成がされることで、信頼関係を築きながら愛情を得ることができ、感情が豊かになったり社会性を高めたりすることができます。
そのため、愛着形成が今後の成長過程において非常に重要になってきます。幼少期に適切な愛着形成ができないと、感情のコントロールやストレスへの耐性が身につかなかったり、大人になった時にメンタル面に大きな影響が出てきたりすることがあります。
試し行動をする理由
子どもが試し行動をする理由は複数ありますが、試し行動は「自分が愛されているか」、「どこまで許されるのか」を確認することが目的です。
試し行動は、自分が受け入れられるかどうかを大人の対応で確認します。
①大人の愛情を確認するため
子どもは大人がどれほど自分を愛してくれているのかを知りたいと感じることが多いです。これは、愛着形成ができていない子ほど強い傾向にあります。
例えば、親が仕事で遅くなる日が増えたり、妹・弟が生まれたりすると、以前よりかまってもらう機会が少なくなることで愛情を感じる時間が減少し、不安に感じることがあります。
そして、自己肯定感を取り戻すために、試し行動に出ることがあります。常日頃から子どもに愛情が伝わるような声がけをするようにし、愛情を示す時間を持つことが重要です。
②相手のことを知りたいから
子どもが知らないの人に試し行動をする一因として、相手の本質を理解しようとすることがあります。子どもは新しい人間関係の中で、相手が自分をどの程度受け入れてくれるのか、またどのような限度があるのかを把握しようとします。
例えば、初めての保育園や学校で、新しい先生や友達との出会いの場面がわかりやすく、このような場面で、子どもは自らの行動が受け入れられる範囲や適切な距離感を見つけるため、故意にルールを破ったり言い訳をしたりする「試し行動」に出ることがあります。
③環境の変化で不安やストレスを感じているから
試し行動は、新しい状況や環境に対する対応の一環として行われることがあり、新しい状況や環境への適応が難しい場合、子供は不安を払拭するために試し行動を取ることがあります。
例えば、親が多忙で急にかまえなくなる、家族構成に変化があった、転校や引っ越しなどによる生活環境や家庭環境の変化があります。
ここから先は
¥ 200
Amazonギフトカード5,000円分が当たる
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
