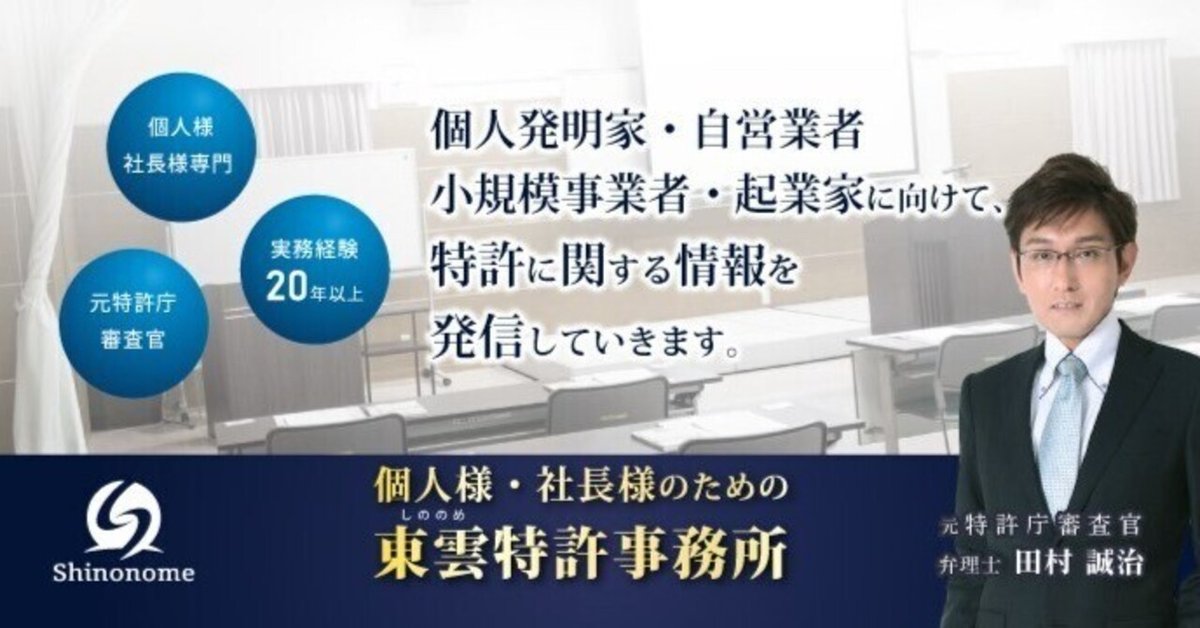
「2つの課題を解決する」発明の特許出願書類のストーリーについて【リライト版】
(Q)わたしの発明はとても良いものです。
従来のモノと比べて、2つの効果(効果1、効果2)があります。
【発明が解決しようとする課題】の部分は、どう書けばいいでしょう。
これに対応して、2つの課題を書かなくてはいけませんか?
つまり、従来のモノは、
✔効果1が得られなかったという課題
✔効果2が得られなかったという課題
の2つを書く必要がありますか?
(A)2つ書いてもいいですし、1つだけを書いてもいいです。
なお、2つの効果があるケースでは、気を付けることがあります。
<解説>
発明とは、従来の技術に課題があり、それを解決するための手段です。
発明の創作の場面では、一般には、課題は一つでしょう。
ただ、発明を創作したら、結果的に、
✔他の効果もあった(他の課題も解決していた)
こういうことは、よくあります。
ちなみに、「課題」は「効果」の裏返しと考えることができます。
この場合、複数の課題を、記載しても構いません。
■ありふれた課題について
ただ、課題は、審査官が発明を認定するために非常に重要な部分です。
複数の課題の中にありふれた課題(例えば、コスト削減、省エネなど)
→そのありふれた課題は記載しなくても構いません。
というより、むしろ記載しない方がいいかも知れません。
複数の課題のうち、
✔もっとも特異な課題が際立つような書き方
をした方がよろしいと思います。
斬新な課題の発見は、発明の特許性を主張するのに効果的だからです。
ありふれた効果は、出願書類の他の部分に記載することができます。
なお、複数の効果があるというケースでは、気を付ける点があります。
■複数の効果がある場合に気を付けるべき点
1つの構成で、複数の効果が得られるのでしたら、問題ありません。
しかし、
✔効果1を得るための構成1
✔効果2を得るための構成2
が異なる場合があります。
この場合、検討が必要です。つまり、
✔構成1だけ(または構成2だけ)で一つの発明を構成する場合がある
この場合、構成1と構成2を「両方必須の構成」としてはいけません。
特許の権利範囲が非常に狭くなります。
つまり、構成1、2が両方必須の発明に対して、特許されたとします。
あなたが独占できるのは、構成1、2が両方ともある発明だけです。
他者(他社)は、
✔構成1だけがあるもの
✔構成2だけがあるもの
は、この特許とは無関係に、製造販売等できることになります。
このような特許では、価値が半減します。
(特に、構成1だけまたは構成2だけで、十分な効果がある場合)
■以上をまとめると
✔構成1が特異な課題を解決、構成2がありふれた課題を解決
✔構成1だけで、発明が成立するとします
発明の特定の仕方として、例えば、
✔構成1だけの発明(いわゆる独立項)
✔構成1+構成2の発明(いわゆる従属項)
の2つを特許として請求することができます。
そして、課題は、構成1についてだけ触れればいいことになります。
<元記事>
【Q&A】2つの課題を解決する発明の特許出願書類のストーリーについて(2015年06月17日執筆)
<関連記事>当ブログのリライトについて
特許の過去記事をリライトします&YouTubeも【1文1行ブログ】
●YouTubeで音声でもご覧いただけます
●元ブログ(+αの情報あり)
https://www.tokkyoblog.com/archives/89035016.html
********************************
【PR】個人様・社長様に特化&元特許審査官が運営する特許事務所!
「おすすめの特許事務所」「おすすめの弁理士」を目指します!
そんな東雲特許事務所(しののめ特許事務所)へのお問い合わせは、
お気軽にこちらからどうぞ!
https://www.patande.com/お問い合わせ/
(↑お問い合わせフォームが開くだけですのでご安心ください。)
********************************
