
新任教員紹介/稲垣秀人 「声なき声」のメディアになる
この4月から、特任講師としてコミュニケーション学部に着任した、稲垣秀人です。
「情報システムとメディア制作システムの設計・構築・運用」「Webプログラミングとマルチメディアによる情報表現」「映像・音声・画像等のメディア制作」そして「社会・思想・メディアコミュニケーション分野の研究」と、様々な領域のあれこれを手がけてきましたが、ある程度は(脱線多し)一貫した関心に基づいて実践や研究を行ってきたつもりです。
その関心とは、生きてゆく上で様々な困難を抱えている人々、無理解や偏見に苦しんでいる人々、不当な扱いを受けている人々、自らの困難な状況を打開しようと行動する人々から学び、そうした状況を理解し、原因理由について考えるということです。さらに、そうした人々の声を通して、社会の諸問題を、様々なメディアや肉声を通して伝える、あるいは当事者が自らの問題を発信・発言することを支援するということです。そして、こうした周縁から、あるいは周縁とさえ扱われないような側からの、社会に向けたコミュニケーションのありようについて、考えるということです。
制作に携わった作品例としては、20年前に、日中の学生・社会人と一緒に、『中華学校の日本人』『狂牛病騒動』等、日中の相互理解のために、日本の習慣やイベント、社会問題、中国に関わる事柄についてのドキュメンタリー映像を、日中2カ国語で制作(人民日報ウェブ日本版で配信)。

10年前には、練馬市民と当時の職場である武蔵大学社会学部の教員・学生とともに、CATVで放映したドキュメンタリーシリーズを協働して制作しました。作品は現在公開されていませんが、『地方の時代映像祭』での以下の受賞記録が公開されています。『私は風船爆弾を作っていた−小岩昌子の戦後64年−』、『練馬駐屯地で見たものは-自衛隊はフレンドリ-?-』。
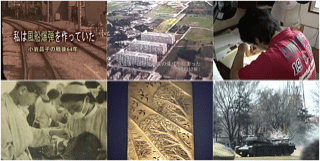
現在は、SOSを心に抱えた少女や若い女性たちと支援者をつなげ、彼女たちの支援を行っている一般社団法人が企画した、支援者に必要な知識・情報を届ける映像シリーズの撮影と映像編集を担当しています。
研究については、これまで高等教育での情報・メディア表現教育に関する実践論文が主でしたが、昨年、「日本」の視覚メディアがどのように発展してきたのか、つまり「大文字の日本史」という物語が回収しないような歴史的事実への関心をもとに、幻灯(プロジェクターの祖先)が国産化される以前の、東京での外国人、アメリカ在住日本人による幻灯上映に関して、『明治初期の東京における幻燈上映とその背景:社会史の観点から』という論文を昨年執筆しました。
最後に、担当している授業を簡単に紹介。ドキュメンタリー制作を目的とした「メディアデザインワークショップ」では、前期〜夏休みにかけて「コロナと私」あるいは「コロナと私たち」という各自のセルフドキュメンタリー制作に取り組んでいます。コロナ禍での生活と以前の生活との違い/変わらないこと、困難なこと/新たに見つけた楽しみ等を率直に伝えて欲しいとお願いしています。また、セルフドキュメンタリーとは、私たちにとって「あたりまえ」である「現在=今ここ」について見つめ直すこと、その「あたりまえ」は私個人の小さな歴史であると同時に社会の歴史でもあり、私たちの過去そして未来へと繋がるような時代の歴史でもあると説明しています。
「社会分析ワークショップ」では、『データでよみとく 外国人”依存”ニッポン』という新書、大学生であれば1日で読める文章を1学期かけて、不案内な語句の意味は全て調べる、関連するデータや取り上げられているものと類似した事例を丹念に調べる、文章の意味を正確に読みとるというように「丁寧」に読んでいます。受講生には「日本」と「外国人」という視点からだけではなく、「外国人」の立場、つまり皆さんが当事者である「外国人」であればどう考えるのか?という視点からも読んで欲しいとお願いしています。
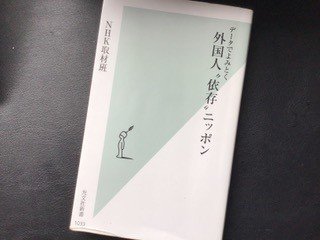
新入生と同じく、コロナ禍でいきなりの1年生生活が始まってしまいましたが、教職員の方々や受講生にいろいろ助けてもらって、何とか前期を乗り切れそうです。皆さんに感謝しています。

曽祖母のアルバムから見つけた、曽祖母の弟の結婚式写真。彼女は多くの写真にキャプションを書き込んでいて、この写真には以下の記述がありました。「善之さんの結婚式、善之さんが設計した朝鮮神宮にて」。朝鮮神宮は、日本統治下時代に京城(現在の韓国の首都ソウル)に建てられていた神社。公的な記録には善之さんの設計という事実は残されていないのですが、朝鮮総督府の建築技師だった彼が、何らかの形で関わったのか、関わってはいないのか。。。日本統治下時代の朝鮮支配と「日本としての朝鮮」、韓国における統治下時代の建築の保存(彼が設計した建物は韓国に現存)、家族の「歴史」の記録と記憶等、見るたびに色々考えさせられます。
