
縄文楽検定(初級)第13回16.17.18 火焔型土器の特徴、鉄分の量と色調、雪の降る理由
第16回 縄文楽検定 初級受験
試験日:2024年3月3日(日)
試験まであと17日‼︎
今日も過去問解いていきます😊
【16】

火焔型土器を特徴づけているこの部分(写真)は何と呼ばれている?
a)鶏冠状突起
b)袋状突起
c)眼鏡状突起
d)橋状突起
答: a)鶏冠状突起
鶏のトサカにに似ていることから、鶏冠状突起あるいは鶏頭冠と呼んでいる。
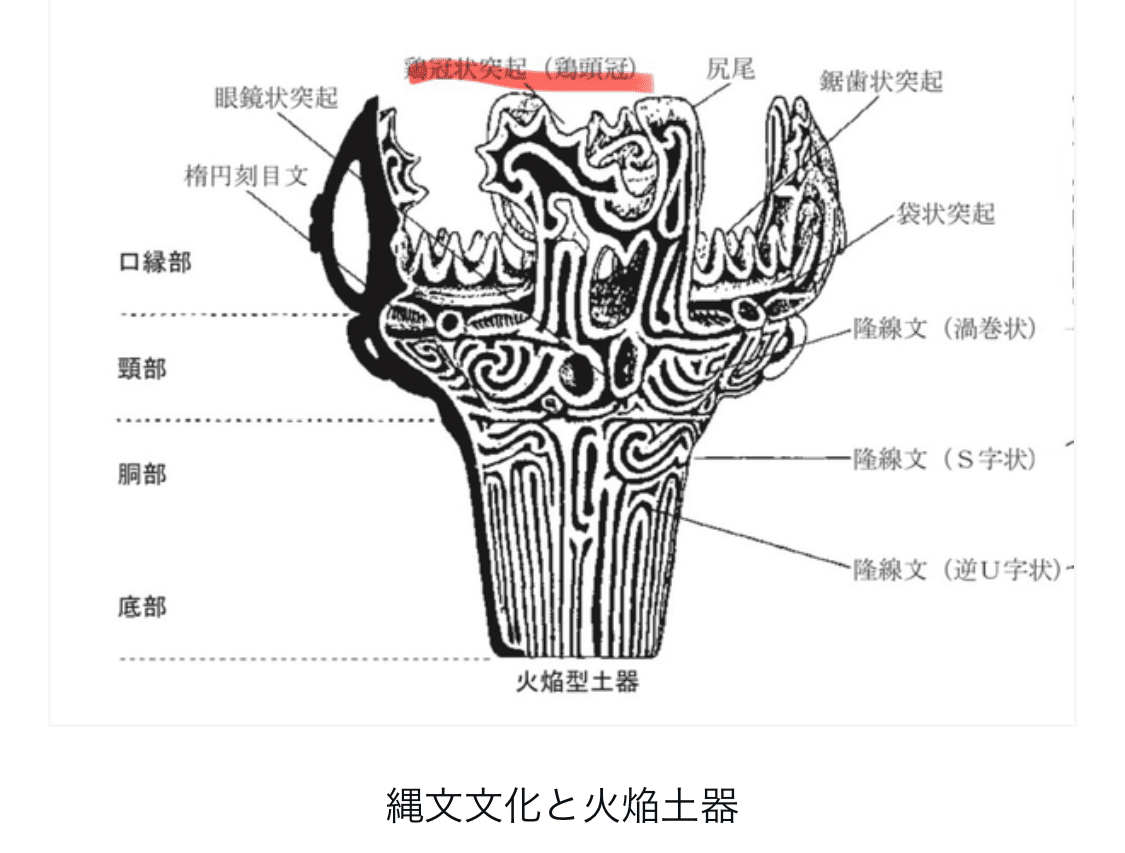
【17】
火焔型土器の色調に関わるとされる、鉄分の量と色の組み合わせで正しいものは?
a)赤色系ー鉄分:少
b)黒褐色系ー鉄分:多
c)白色系ー鉄分:少
d)黒褐色系ー鉄分:少
答: c)白色系ー鉄分:少
・火焔型土器の色調:赤色系、白色系
・土器の胎土に鉄分多い→赤い
少ない→白く 焼き上がる。


【18】
およそ8千年前に信濃川流域に雪が多く降るようになったのはなぜ?
a)信濃川流域の人口が減ったから
b)日本海の気圧が上昇したから
c)氷河期が終わり間氷期になったから
d)日本海に対馬海流が流れ込んだから
答: d)日本海に対馬海流が流れ込んだから
暖流の対馬海流の流入によって、日本海の海水面が上昇し、ここに大陸からの季節風が吹き込む事により、この地域が豪雪地帯になったと考えられている。

いいなと思ったら応援しよう!

