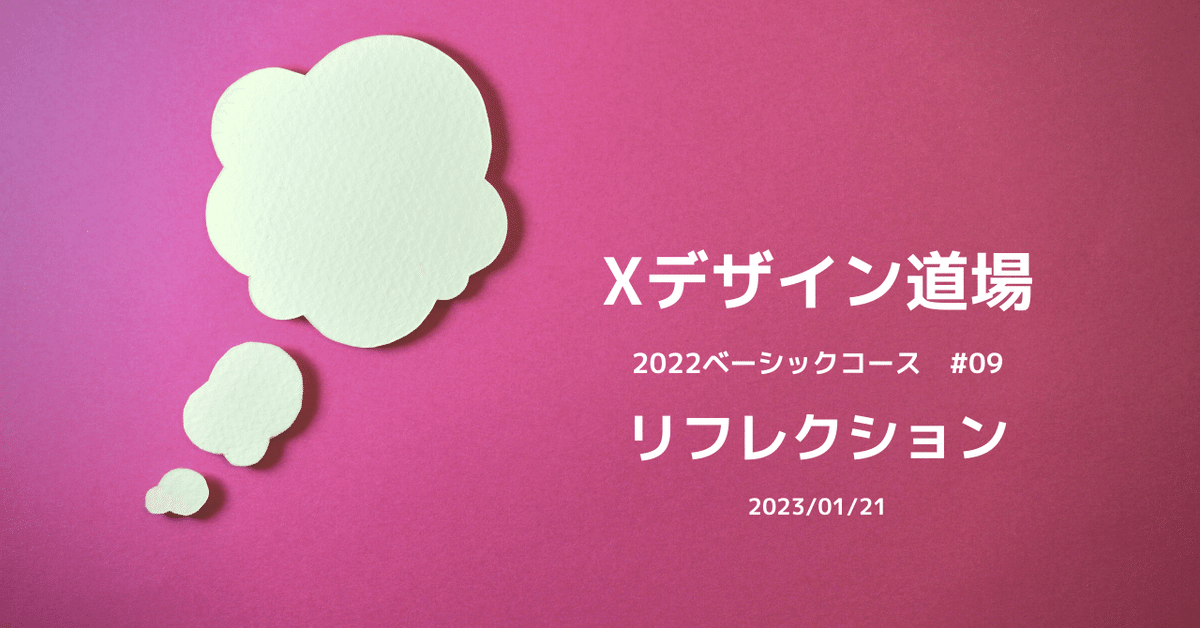
Xデザイン学校|リフレクション:#09 ユーザー評価と発表準備
明けましておめでとうございます。
去年の5月から、UXデザイン知見強化のためにXデザイン学校ベーシックコースを受講しています。早いもので、次回はいよいよ発表を残すのみということで、今回はグループワーク中心の作業となりました。
インタビューって難しい!
今回、うちのチームは講義終了後1時間ほど浅野先生から直接ご指導を頂いたのですが、気付かされた事は
インタビューのターゲットを間違えている
的を射た質問が出来ていない
そもそも、提案予定のビジネスモデルの方向性自体に問題があった(汗)事はさて置き、全く価値のないインタビューをしていた…ということが浮き彫りに。なので、以降のフェーズがガタガタ。。
リサーチもそうですが、ユーザーインタビューがしっかり出来ていないと、全てが水の泡となってしまうことを、この段階になって改めて思い知らされました。序盤の段階ではチームで共有し合っていたはずの「未来像」に関しても、ビジネスモデルを何度かピボットするうち完全に見失っていましたし、情けないことに穴だらけの提案となってしまっていたのです。
質問設計のコツ
幸い先生からヒントを授かることが出来たので、チームで話し合った結果、来月の発表までに急きょインタビューをし直して資料も再構成することに。
その前に改めて、ユーザーインタビュー設計について再確認してみます。
本来ユーザーインタビューの設計フェーズは、綿密な計画と相当の時間を要するはずですが、今回は限られた時間内で出来るだけ、ユーザーのニーズを引出すための設計を行わなくてはなりません。
見出そうとしている「テーマ」に専念し定義する。
インタビューイーが答えやすいよう細分化する。
バイアスのかかる質問をしない。
過去の体験談に沿う質問をする。
思い当たるのはこのへんですが、一番やらかしてしまいそうなのは3ですね…
修正前「夜にネットショッピングすることが多いですか?」
修正後「どんな時間にネットショッピングすることが多いですか?」
例えユーザーの回答に見当が付くような質問でも、必ず予想通りの答えが返って来るという確証はありません。結論を急ぐのではなく、なるべく先入観の無い回答を得るため、真っ新な気持ちで臨める質問をする必要がある。
インタビューの際の心得として良く聞くのは
出来るだけ多く
出来るだけ深く
出来るだけ多様に
あくまでもインタビューは次のステップへの「材料集め」。そのためには出来るだけ多くの情報を渡す必要があるため、インタビューイーからより多く発話が見込めそうな質問こそが望ましいのでしょう。
次回はいよいよ最終発表。。
残り時間もあと僅かですが、何とか形にして行きたいと思います!
いいなと思ったら応援しよう!

