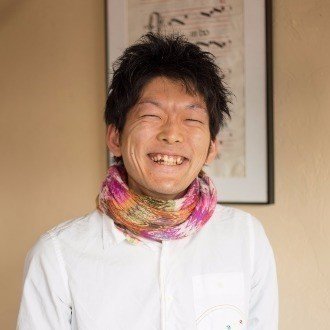Designship2021を見て印象に残ったこと
Designship2021(※)のアーカイブ動画を見た。
※ Designship(デザインシップ)……“物語の力で「デザイン」の壁を越える。” がコンセプトの、業界の壁を越えた、日本最大級のデザインカンファレンス。
2日分、十数時間ある動画を、1.5〜2倍速にして1日かけて見た。
感じたことや気づきをnoteにまとめたいのだけど、まだ消化不良なところがあるので、ひとまず、印象に残っているところを断片的に書いてみる。
深澤 直人 今デザインにできること
一人目のスピーカーにして、一番メモを取ったセッションでもある。
デザインっていうのは、形とか色とか、あるいは、美しいとか、そういうだけの概念ではなくて。人間と物と環境の関係性を、読み解いて、そこに正しい立場を作っていく、ということがデザインだと思っています。
デザインは問題を解決することと思っている人も少なくないだろうが、デザインは何を問題とするのかの定義を見出すものであり、それに対応した最適解を導き出すことでもある。
答えを出すことがクリエイションではなく、何が問題なのかを的確に考えることが我々(デザイナー)がやらなければならないこと。
株式会社モリサワ 阪本 圭太郎
フォントが物語の“声”となる
書体は目で感じる声
株式会社イチバンセン一級建築士事務所 代表取締役 川西 康之
公共デザインの領域を超えて
過ごし方のデザイン、時間のデザインの話。セッションを聞いていて、鉄道業界が抱える問題や背景がわかり、デザインで課題解決をしているな、と感じた。
WEST EXPRESS 銀河、乗ってみたい。
株式会社サイバーエージェント 宮崎 慎也
「キャリアの罠」にすべてハマったクリエイターの、罠脱出の極意
わたしのことなので、この先も都度つど罠(わな)にはまるでしょう。でも事前に知っていれば、様々な罠に対処できます。これからも、必ず罠にはまることを前提に、「いま何の罠にはまってるのかな」と思いながら、自分のキャリアを自由に描いていきたいなと思います。
デザイナーとしてキャリアを歩むなかで躓くことを「罠(わな)」といい。罠にはまることを前提にして、キャリアを描き実践していく。
「いま自分がどういう状況にいて、なぜ上手くいっていないか」を客観的に言語化する。この考え方はすごく参考になるなと思った。
HI(NY) 代表・クリエイティブディレクター
渡邊デルーカ 瞳ㅤ 小山田 育
日本の次世代デザイナーの働き方
私たちにとってデザインをするっていうことは、5つのステップがあって
1. クライアントをよく観察する
2. 課題や問題点や強みを見極める
3. オーディエンスや時代、市場を考慮して
4. 問題を解決する方法を柔軟にクリエイティブに考え出して
5. ビジュアル化して伝わる形に落とし込む
このすべてを合わせて、デザインをすると考えています。
でも日本では、この最後のビジュアル化するだけを(デザインと)指していることがあって、どうしても小手先の印象がある。
* * *
ちょっと長くなってきたので、今日はここまでに。どのセッションもめっちゃ面白かったです!
いいなと思ったら応援しよう!