
パーム油は体に悪い「隠れた」植物油、トランス脂肪酸の代わりにはなりません
日本人が2番目に多く摂っている油がパーム油です。
パーム油は、一体どういう脂質なのか
どういう食品に含まれているのか
体にどういう悪影響があるのか
以上の点に関して解説します。
(記事の文末に動画を貼っています)
2番目に多く摂っている油?
まず、下のグラフをご覧下さい。

2014年、日本の植物油別消費量を示しています。
もっとも多いのが菜種油、
2番目にパーム油、
3番目が大豆油です。
この3つで約8割を占めています。
が、多くの人にとって、意外なデータではないでしょうか。
菜種油は、キャノーラ油という商品でお馴染みです。
大豆油は、サラダ油の主要な原料です。
しかし、パーム油は、家庭用食用油では見かけません。
加工食品の原材料表示を見ても「パーム油」は見当たりません。
パーム油は、何の食品に含まれているのでしょうか。
私たちは、何からパーム油を“知らず知らず”摂っているのでしょうか。
パーム油が“隠れている”食品
その一つは、加工食品です。
加工食品の原材料表示を見ると、パーム油の文字は見かけません。
しかし、
「植物油」「植物油脂」「加工油脂」
の表記を至る所で発見することができます。
この
「植物油」「植物油脂」「加工油脂」
の中に、かなり高い確率でパーム油が含まれています。
日本では複数の植物油を混合使用した場合、その一つ一つを表示する義務はありません。
「植物油」「植物油脂」「加工油脂」
などの一括表示が認められています。
つまり、油の内容は全く分かりません。
言ってみれば、ブラックボックスです。
では、パーム油が使用されている代表的な加工食品を挙げると、
カップ麺
レトルト食品
パン
ドーナツ
クッキー
ケーキ
チョコレート
ポテトチップ
ポテトフライ
アイスクリーム
など、あらゆる商品に及びます。
もう一つ、私たちがパーム油を摂取しているのは、飲食店とテイクアウトです。
飲食店とテイクアウトで提供するものには、原材料表示の義務そのものがないので、使っている油の確認しようがありません。
トランス脂肪酸の消費量が減ると・・・
そして、近年パーム油を使う機会が増えている原因の一つが、トランス脂肪酸です。
マーガリン、ショートニング、ホイップクリームに代表されるトランス脂肪酸は、植物油に水素を添加した人工的な油です。
多量に摂取すると、心筋梗塞などの冠動脈疾患をはじめ、あらゆる生活習慣病のリスクが高くなります。
このことを、多くの消費者が知るところとなってきました。
それに対して、ファストフードなど飲食店や食品業界が、トランス脂肪酸の低減に取り組むようになります。
それ自体は悪いことではないのですが、トランス脂肪酸が減った代わりに増えたのがパーム油です。

知らず知らずのうちに消費者は「隠れた植物油」であるパーム油を、年間で平均4kg も摂っています。
パーム油の正体は? どんな油?
パーム油は、熱帯地域で栽培するアブラヤシの果肉を絞った油です。
インドネシアとマレーシアで、世界生産量の8割以上を占めます。

融点が高い飽和脂肪酸が約半分含まれることから、植物油であるのに常温でも固体であるという脂質です。
飽和脂肪酸の特長である、酸化に強いというメリットはあります。
精製する前の栄養素は、βカロテン、ビタミンEが豊富です。
βカロテンの量は、グラム当たりニンジンの15倍もあります。
さらに、原料が安く、食感がなめらかで口溶けもいい、という生産者の側からすれば、いいこと尽くめの油とも言えます。
一見すると健康そうな油だが
このパーム油も、近年さまざまな面から、健康被害が相次いでいる「危ない油」との指摘が目立っています。
パーム油には、血糖値を下げるインスリンの働きを妨げる作用があり、糖尿病のリスクを上げる。
大量摂取すると、動脈硬化や心疾患の罹患率が高くなる。
また、動物実験によると、遺伝毒性発ガン性(細胞のDNAを傷つけて遺伝子変異をもたらすことによるガン)、生殖毒性、神経毒性があることが認められています。
さらに、熱帯地域からの長距離輸送に使用される酸化防止剤BHA(ブチルヒドロキシアニソール)は、ラットの実験で胃ガンを発症させた、という事実もあります。
トランス脂肪酸の代替にはならない
このことから、
「人工的な油であるトランス脂肪酸を、天然の植物油であるパーム油に代えれば安全」
とは言えなくなりました。
これを裏付けるように、
農林水産省のHP 「トランス脂肪酸の低減」のページには、
「米国農務省(USDA)は、食品事業者にとってパーム油は、トランス脂肪酸の健康的な代替油脂にはならない、とする研究報告を公表しています」
と、5年前に出版された『隠れ油という大問題』という本に書かれていました。
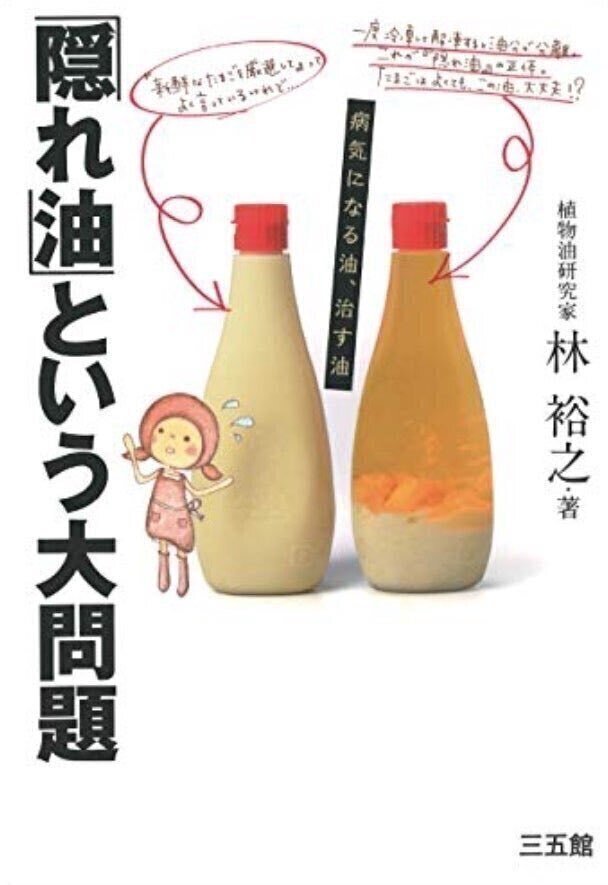
ところが、確認のため農水省のHPをチェックしてみると、現在は削除されています。
何か、大人の事情があったのでしょう。
決して、安全性が確認されたわけではありません。
難しいですが、対策です
「植物油」「植物油脂」「加工油脂」
の表記がある加工食品、及びパーム油を使っていると思われる飲食店やテイクアウトのメニューを食べない、のが理想です。
しかし、現代の食生活でそれらを完全になくすのは現実的ではありません。
少しでも減らすことが大切です。
そのためにも、まずはパーム油に関して正しい知識を持ってください。
まとめ
日本の植物油別消費量では、菜種油に次いで2番目に多いのが、パーム油です。
パーム油は、加工食品の
「植物油」「植物油脂」「加工油脂」
の中、
飲食店とテイクアウトで提供される食べ物に「隠れた植物油」として入っています。
パーム油の疑われる有害性は、以下の通りです。
・糖尿病のリスク
・動脈硬化や心疾患のリスク
・遺伝毒性発ガンのリスク
・生殖毒性や神経毒性のリスク
・酸化防止剤BHAによる胃ガンのリスク
このことから、パーム油はトランス脂肪酸の安全な代替油だとは言えません。
対策としては、
「植物油」「植物油脂」「加工油脂」
の表記がある加工食品、または飲食店やテイクアウトの食品の摂取を少しでも減らすことが大切です。
この記事の内容については動画もアップしています。
合わせてご覧ください。
