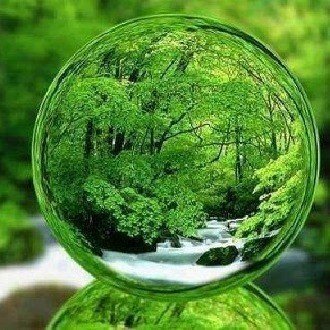【英日対訳】記念転載「私の家族は強制収容された。ムスリムを同じ目に遭わせてはならない」ジョージ・タケイ氏|米ワシントンポスト(2016.11.18) #dayofremembrance
はじめに
2016年11月18日、初代『スタートレック』で『Mr.カトー』を演じた俳優のジョージ・タケイ(George Takei)さんが日系人の強制収容についてワシントンポストに寄稿。当時のトランプ政権で「ムスリムに同じ事をしないでほしい」と訴えました。「合衆国は日系アメリカ人を強制収容したことについて謝罪したが、本当に過ちから学んだのか」――自身も日系アメリカ人で幼い頃に強制収容を経験したタケイ氏は、発足間もないトランプ新政権の姿勢に対する警鐘をこう鳴らしました。
マイノリティが感じている危機感はここまで現実的だったのです。
A Trump surrogate argued the internment was "precedent" for a national Muslim registry. I could not stay silent. https://t.co/uTUHkNXLLb
— George Takei (@GeorgeTakei) November 18, 2016
「トランプの分身が日系アメリカ人の強制収容を『先例』だと主張した。私は、黙っていることができなかった。」
それから4年後の2021年2月19日、今度は発足して間もないバイデン新政権が、日系人収容を「米国史で最も恥ずべき時代だった(one of the most shameful periods in American history)」と改めて謝罪。
1942年2月19日、当時のルーズベルト大統領が署名した日系人強制収容の根拠になった大統領令署名から79年目の19日、バイデン新大統領は声明を発表し「”we reaffirm the Federal government’s formal apology to Japanese Americans for the suffering inflicted by these policies”(これらの政策によってもたらされた苦しみに対して、連邦政府が日系アメリカ人に公式に謝罪することを再確認する。)」と改めて謝罪しました。
1940年代当時、この大統領令により、日系アメリカ人は国際法上の「敵性外国人(enemey alien)」であると見なされ、12万人もの人びとが全米各地で数年間に及んで強制収容されました。この「敵性外国人」のレッテルは、その46年後の1988年にレーガン大統領が過ちを認めて公式に謝罪するまで、ずっと残り続けたのです。レーガン氏と党派は違えど、バイデン大統領はその「正のレガシー」を正式に受け継いだといえるでしょう。
2016年当時、Tumblr版では、タケイ氏の寄稿文がかなりの長文だったため、適時に間に合わせるため急ごしらえの訳文のみを掲載しましたが、あらためて政権が変わり、今回の声明の発表を受けて、当時危機感を持っていた人びとから安堵の声がもれたことを受け、記念に英日併記で掲載します。
ソース
2016年11月18日付, ワシントンポスト紙、オピニオン欄寄稿
本編
George Takei: They interned my family. Don’t let them do it to Muslims.
ジョージ・タケイ氏「私の家族は強制収容された。ムスリムを同じ目に遭わせてはならない」
The United States apologized for locking up Japanese Americans. Have we learned nothing?
合衆国は日系アメリカ人を強制収容したことについて謝罪したが、本当に過ちから学んだのだろうか?
November 18, 2016
2016年11月18日
There is dangerous talk these days by those who have the ear of some at the highest levels of government. Earlier this week, Carl Higbie, an outspoken Trump surrogate and co-chair of Great America PAC, gave an interview with Megyn Kelly of Fox News.
ここ数日、政府最上層の情報に接することができる人物から危険な発言がなされている。今週のはじめ、FOXニュースでは、トランプの腹心と公言して憚らない『グレート・アメリカ』政治活動委員会 (PAC) 共同会長のカール・ヒグビー (Carl Higbie) がメグィン・ケリー (Megyn Kelly) のインタビューに応えた。
They were discussing the notion of a national Muslim registry, a controversial part of the Trump administration’s national security plans, when Higbie dropped a bombshell: “We did it during World War II with Japanese, which, you know, call it what you will,” he said.
話題がトランプ政権の掲げる安全保障政策の一つで物議を呼んでいる「全米ムスリム登録制」という考え方の話に及んだときに、ヒグビーが爆弾発言を行った。
「二次大戦のとき日本人に対して行ったあれだ。それをどう呼ぶかは勝手だが (“We did it during World War II with Japanese, which, you know, call it what you will,”)」
Was he really citing the Japanese American internment, Kelly wanted to know, as grounds for treating Muslims the same way today? Higbie responded that he wasn’t saying we should return to putting people in camps. But then he added, “There is precedent for it.”
ケリーは、彼が現代においてムスリムを同様に扱う根拠として、日系アメリカ人を強制収容したことを引き合いに出したのか、確認しようとした。
するとヒグビーは、人びとを強制収容する政策に戻るという訳ではないと言いつつ、「そういう先例があった (“There is precedent for it") 」と言っているだけだと付け加えた。 (参考報道)
Stop and consider these words.
ここで立ち止まって、よくこの言葉の意味を考えてみよう。
The internment was a dark chapter of American history, in which 120,000 people, including me and my family, lost our homes, our livelihoods, and our freedoms because we happened to look like the people who bombed Pearl Harbor.
強制収容はアメリカの暗黒史のひとつだった。私や私の家族を含む12万もの人が、家を失い、生活を失い、自由を失った。ただ私たちが真珠湾を爆撃した人びとに似ているという理由だけで。
Higbie speaks of the internment in the abstract, as a “precedent” or a policy, ignoring the true human tragedy that occurred.
ヒグビーは強制収容を抽象的な「先例」あるいは、政策だったとしているが、そこで起きた人間の悲劇をまったく無視してしまっている。
I was just a child of 5 when we were forced at gunpoint from our home and sent first to live in a horse stable at a local race track, a family of five crammed into a single smelly stall. It was a devastating blow to my parents, who had worked so hard to buy a house and raise a family in Los Angeles.
私たち一家が銃口を突き付けられて家から強制退去させられたとき、私はまだ5歳の子どもだった。まず送られたのは、近くの競馬場の馬屋で、5人家族が狭くて臭い仕切りの中に収められた。(参考文献)やっとの思いでロスで家を買い、家族を養っていた両親は激しく打ちのめされた。
After several weeks, they sent us much farther away, 1,000 miles to the east by rail car, the blinds of our train cars pulled for our own protection, they said.
その数週間後、私たちは、今度は列車を使って東へ千マイル (約1600キロ) ほど離れたところへと送られた。列車の車両には、私たちを守るためだとして、目隠しがされた。
We disembarked in the fetid swamps of Arkansas at the Rohwer Relocation Center.
私たちは悪臭を放つアルカンソーの沼地で下車させられ、ロウア―日系人移転収容所(Rohwer Relocation Center) へと収容された。
Really, it was a prison: Armed guards looked down upon us from sentry towers; their guns pointed inward at us; searchlights lit pathways at night.
収容所はまさに「刑務所」だった。監視塔からは武装した警備員が私たちを見下ろし、私たちの方向に銃口を向けているのだ。夜には施設内の小道がすべてサーチライトに照らされた。
We understood. We were not to leave.
私たちは理解した。ここを離れることはできないのだと。
My parents did their best to make life seem normal. As a child, I very readily accepted our new circumstance and adjusted to it.
両親はなるべく普通の生活をしているよう振る舞うのに必死だった。子どもだった私は、すぐにこの新しい状況を受け入れ、順応した。
As far as I was concerned, it was normal to line up to use the common latrine, or to eat wretched grub in a common mess hall, prisoners in our own country.
私からすれば、共用の便所を使うことは「日常」だったし、ひどく粗末な食べ物を共用の軍用食堂で食べることも「日常」だった。
私たちは自分の国で捕虜となったのだ。
It was normal for us to share a single small barrack with no privacy whatsoever. And it was normal to stand each day in our makeshift classroom, reciting the words to the Pledge of Allegiance, “With liberty and justice for all,” as I looked past the U.S. flag out the window, the barbed wire of the camp just visible behind it.
狭いバラックを全員で共用して、まったくプライバシーがなくても、それが「日常」だった。そして間に合わせの教室で、『忠誠の誓い』を何度も暗唱して、「万民のための自由と正義を備え」と謳いながら、ふと窓の外をみやると、星条旗のすぐ後ろには収容キャンプの鉄格子が見えていた。
Not until I was older did I understand the irony of those words and the injustice that had been visited on so many of us.
私はもう少し大人になるまで、この言葉がどれほど皮肉に満ちていて、いかに私たちの多くが不正義にさらされてきたかを理解できなかった。
As I studied civics and government in school, I came to see the internment as an assault not only upon an entire group of Americans, but upon the Constitution itself — how its guarantees of due process and equal protection had been decimated by forces of fear and prejudice unleashed by unscrupulous politicians.
大学で公民権や民主的統治について学んだとき、強制収容がアメリカ人の集団を害する行為であるだけでなく、合衆国憲法そのものを害する行為であることがわかった。法のデュープロセスや平等な保護という保障が、いかにして無思慮な政治家たちの解き放った恐怖や偏見という力により圧殺されたかということを。(参考)
It had been a Democratic administration at the time, under Franklin D. Roosevelt, that had ordered us to the camps, proving that demagoguery and race-baiting knows no party.
時の政権はフランクリン・D・ルーズベルトの民主党政権だったが、彼らは私たちを強制収容所へと追いやり、デマによる扇動や人種差別的な言動を行うことに党派は関係ないことを示した。
It took decades for the United States to own up to what it had done and officially apologize for the internment, offering symbolic monetary reparations to the survivors.
合衆国が過去の過ちを認め、強制収容について公式に謝罪し、象徴的な贖罪の行為として生存者らに補償金を支払ったのは、数十年後のことだった。(参考)
I donated my own check to the Japanese American National Museum, whose mission, like mine, has been to help ensure the mistakes of the past are never repeated. That is why these words by Higbie, which ominously are representative of much of the current thinking in the incoming administration, have reopened very old and very deep wounds.
私は、日系アメリカ人国立博物館 (Japanese American National Museum) に政府のその小切手を全額寄付した。その使命が、私同様、過去の過ちを二度と繰り返さないことにあったからだ。だからこそ、ヒグビーの言葉は、次期政権の考え方を不気味に言い表しているといえ、とても古く、とても深い傷口を再び抉りだしたといえるのである。
This was not the first time the Trump camp had raised the internment.
トランプ界隈が強制収容に言及したのはこれが初めてではない。
When he did so before, it wasn’t as the historical warning it should be, but as a precedent for what might yet come. In late 2015, during the presidential primary, Trump actually went on the record with Time magazine stating that he did not know whether he would have supported or opposed the internment. “I would have had to be there at the time to tell you, to give you a proper answer,” he said.
以前トランプが語ったとき、彼は歴史的警鐘としてそれを語ったのではなく、今後実現し得る「先例」として語った。2015年後半に予備選を戦っていたとき、トランプはタイム誌の取材に対し、公式な発言として、強制収容の方針を支持したか反対したかわからないと述べたのである。
「その時代のその場にいないと、きちんとした回答は返せない」 “I would have had to be there at the time to tell you, to give you a proper answer,”
He argued that FDR was “one of the most highly respected presidents,” and that what he was suggesting was “no different from FDR.” Trump hedged his response with a nod to the horror of the camps, but tellingly did not disavow them: “I certainly hate the concept of it. But I would have had to be there at the time to give you a proper answer.”
トランプはルーズベルトを「もっとも敬愛される大統領の一人だ (“one of the most highly respected presidents,”)」としつつ、彼が提案しているそれは「ルーズベルトのそれと変わらない (“no different from FDR”)」ことを確認した。強制収容所の恐怖についてトランプは頷くだけだけだったが明確に拒絶することはしなかった。
「その考え方は嫌悪するが、その時代のその場にいないときちんと答えられない (“I certainly hate the concept of it. But I would have had to be there at the time to give you a proper answer.”) 」
Higbie similarly has kept open the specter of the camps, in one breath stating that he does not favor the idea, but in the very next noting, “We have to protect America first.” Indeed, in a follow-up interview with the New York Times, Higbie doubled down on the unthinkable: “There is historical, factual precedent to do things [that] are not politically popular and sometimes not right, in the interest of national security.”
ヒグビーも同様に、強制収容の恐怖の再来に含みを残した表現に終始した。そのような考えは「好ましくない」としながら、同じ発言の中で「第一にアメリカを守らなければならない」と言って憚らない。実際、ニューヨークタイムズが行ったフォローアップインタビューの中でヒグビーは、”あってはならないこと”を敢えて念押しした。
「国家安全保障のために、政治的に不評な、または【時に正しくないこと】を行うという歴史的な、かつ、事実としての先例は存在する (“There is historical, factual precedent to do things [that] are not politically popular and sometimes not right, in the interest of national security.”) 」
Let us all be clear:
ここでハッキリさせておこうではないか。
“National security” must never again be permitted to justify wholesale denial of constitutional rights and protections.
「国家安全保障」の名の下に憲法上の庇護や権利が一緒くたに否定されるということは、二度と再びあってはならないと。
If it is freedom and our way of life that we fight for, our first obligation is to ensure that our own government adheres to those principles. Without that, we are no better than our enemies.
合衆国は、自由とわれわれの生き方を維持するために戦ってきたのであり、われわれ市民の第一の義務は、われわれの政府がこの原則に準ずることを保障することにあると。それなくしては、われわれの「敵」とそう変わりはなくなってしまうと。
Let us also agree that ethnic or religious discrimination cannot be justified by calls for greater security.
また、より安全な社会につながるからという主張の下に、民族的・宗教的に差別を行うことは正当化され得ないと。
During World War II, the government argued that military authorities could not distinguish between alleged enemy elements and peaceful, patriotic Japanese Americans. It concluded, therefore, that all those of Japanese descent, including American citizens, should be presumed guilty and held without charge, trial or legal recourse, in many cases for years.
二次大戦中、合衆国政府は、軍当局には敵性分子と平和的で愛国的な日系アメリカ人を見分けられないと主張した。したがって、日系移民は、アメリカ市民を含めすべて有罪と推定し、起訴無し、あるいは裁判または法手続き無しの勾留も可能とされた。場合によっては、何年もの間も。
The very same arguments echo today, on the assumption that a handful of presumed radical elements within the Muslim community necessitates draconian measures against the whole, all in the name of national security.
これと同じ主張が今日この時代に繰り返されている。ムスリム・コミュニティに内在すると「想定される」ごくわずかな過激と「思われる」分子のために、すべてのムスリムに対して、国家安全保障の名の下に、過酷な措置を施す必要があるという風に。
It begins with profiling and with registries, but as Trump and Higbie have made clear, once the safety of the country is at stake, all safeguards are off. In their world, national security justifies actions that are “sometimes not right,” and no one really can guarantee where it will end.
これはまずはプロファイリングや登録制から始まるが、トランプやヒグビーが明らかにしたように、国家の安全保障が脅かされていると判断されたら、すべての保障は撤廃される。彼らの世界では、「時に正しくない」ことを国家安全保障の名の下に行うことは正当化されるのであり、その判断がいつ終わるかなど誰にもわからないのであるから。
We cannot permit this invidious thinking, discredited by history at the cost of so much misery and suffering by innocents, to take root once again in America, let alone in the White House.
多くの罪なき人びとの受難と苦悩という犠牲に立って、歴史的に否定されたこのような不当な考え方が、ホワイトハウスの中に芽吹くことは言うに及ばす、このような考え方がアメリカに根を張ることを見過ごすことはできない。
The stigmatization, separation and labeling of our fellow humans based on race or religion has never led to a more secure world. But it has too often led to one where the most vulnerable pay the highest price.
人種や信仰によってわれわれと同じ人類に汚名を着せ、非難し、分離することが、より安全な世界へとつながったことなどない。むしろほぼ常に、もっともか弱い者たちがもっとも高い代償を払うという忌むべき世界を生み出してきた。
The Constitution and the government exist in large measure to protect against the excesses of democracies. This is particularly salient when, in an atmosphere of fear or mistrust, one group is singled out and vilified, as Japanese Americans were during World War II and as Muslim Americans are today.
憲法や政府というものは、その大意として、民主主義の暴走を抑止するために存在する。これはとくに、恐怖や不信が蔓延る環境の中で、いち集団が選り分けられ中傷されるような状況。すなわち、二次大戦中の日系アメリカ人や、現代のムスリム系アメリカ人が経験しているような状況の中でこそ突出すべき特長である。
How terrible it is to contemplate, once again, that the government itself might once more be the very instrument of terror and division. That cannot happen again. We cannot allow it.
いま再び、政府が恐怖と分断の源となり得るということを、思い悩まなければならないとは、なんという悲惨な現状なのか。
もう二度とあのようなことはあってはならない。
二度とあのようなことを見過ごしてはならない。
ジョージ・タケイ氏の当日のツイート
Today is the Day of Remembrance. On this day in 1942, FDR signed Executive Order 9066, which led to the incarceration of 120,000 Japanese Americans living on the West Coast. We lost our jobs, our homes, and our freedom. We #NeverForget today, so that it can #NeverAgain happen.
— George Takei (@GeorgeTakei) February 19, 2021
「今日は『追憶の日』。1942年のこの日、ルーズベルトは大統領令9066号に署名。西海岸に住む12万人の日系米国人が強制収容された。我々は職を失い、家を失い、そして自由を失った。このような日が二度と起きないために、我々はこの日を永遠に忘れない。 #NeverForget #NeverAgain 」
訳者あとがき
長いので別扱いとして「訳者あとがき」をあげました。語り尽くせぬ思いがありますが、取り敢えずこんなところで留めておきます。https://t.co/RdkUWoraDi
— 💫T.Katsumi #StayHome🏠 (@tkatsumi06j) November 22, 2016
訳者あとがき──ジョージ・タケイ氏の寄稿オピニオン記事を訳して
ジョージ・タケイ氏は、私がFacebookでフォローしている数少ない著名人。ゲイであることをカミングアウトしながら、ゲイの権利にかぎらない政治的主張を忌憚なく発するタケイ氏は、人間として尊敬に値する人物だと思っている。
とは言いながらも、初代『スタートレック』のTVシリーズでミスター・スールー(日本名「ミスター・カトー」)を演じていた彼の事、他のドラマ等で典型的な武闘派の”東洋人師匠”や”東洋人実業家”という日本人像を演じてきた彼のことを、実は私はほとんど知らなかった。
今回の寄稿文は、タケイ氏のポストの中でも異例の「ステートメント」だったからすぐに目を引いた。短いコメントはよく見かけたが、寄稿記事というのは初めて見た。後になってわかったが、この記事に前後して彼はひじょうに活発に執筆活動を展開していた。このTED動画の存在も後から知った。
実は私はタケイ氏を「日本人」とも「日系人」とも思ったことがない。「アメリカ人」だと思ってきた。仮に日系だとしても、遠い昔の移民くらいに思っていた。だが御年79歳と知り、今回の記事で日本人の両親の間に生まれたと知り、それほど遠い昔の移民ではないことがわかった。
そして、強制収容を経験した日系アメリカ人であったこと、今回初めて認識しながら、タケイ氏のメッセージを翻訳した。まだ表題とパンチラインしか読んでいないうちから、翻訳する価値のあるものだと確信していた。ただ当初は訴えの内容を勘違いしていた。
そこを @TrinityNYC さんに指摘され、あらためて読み進めながら翻訳作業を進めた。何度も呟いてきたが、私にとっては翻訳こそが最大の精読行為なのである。読み進める(作業を進める)うちに、活動家としてのジョージ・タケイ氏の姿が自分にも見えてきた。
わたしも自分で訳そうと思っていたところですが訳されるならどうぞ。。本文のポイントは在米マイノリティの扱い云々よりも、彼のような米国人でも「公的な制度」として差別を受ける、それが今また繰り返されようとしているその恐ろしさです。
— TrinityNYC (@TrinityNYC) November 21, 2016
そしてタケイ氏が訴えようとしている内容を理解した。さすが @TrinityNYC さんはよく理解していた。彼は単にムスリムの人たちがかつての日系アメリカ人と同じ受難の日々を送らないようにしてほしいと訴えているのではなかった。だから表題を変えた。
タケイ氏は、アメリカ市民の使命として、二度と再び、あのような思いを他民族・他人種・他宗教の人びとにさせてはならないと、古参の活動家として"アメリカの同胞"に檄を飛ばしたのだ。でもそれを知った時、やはり私は思った。やはりタケイ氏は、「日本人」でも「日系人」でもない。「アメリカ人」だと。
いま話題のTED動画でタケイ氏は、なぜ日系アメリカ人として強制収容され、祖国に裏切られながらも祖国を愛し続けるのかを訴えた。それは彼が合衆国憲法の掲げる理想、合衆国の民主主義が目指す理想を愛してやまないからだ。そのことが、今回のメッセージにも滲み出ている。
だからこそ、怒るのだ。憤るのだ。思い悩むのだ。「こんな国は(私の愛する)アメリカではない」と。日本に帰国後21年も暮らしながらも、残りの23年を海外で過ごした私も日本について同じ思いを抱えるから、この愛国心はよくわかる。
ただ、私はタケイ氏のように、生まれてから今に至るまでずっと同じ場所に留まったことがない。だから、彼のロス、カリフォルニアという州、そしてアメリカという国に対する熱情は、私のそれなどととは比べようもないだろう。まして彼は、日系アメリカ人として文化の橋渡しも行ってきたのだから。
私も翻訳や通訳を通じて、そういう「橋渡し」をしたいと思って生きてきた。アメリカの大学の卒業式で父に託されたのは、「世界の架け橋になってほしい」という願いだった。だから私は、タケイ氏のような、「同じ異邦人のために翻訳」という橋渡しの作業を続ける。
それが私の屋号「BALÉS」が意味するところである。
祖国を愛してやまないタケイ氏の思い、愛するが故に理想を追い求める姿勢、単なる幼少の不幸な生い立ちではなく、彼が「日系」として虐げられながらも、愛し続けてきたアメリカの理想が危機に瀕していること。もしそのことが訳文から伝わるようになっていたら、訳者として本懐である。
いいなと思ったら応援しよう!