
「問いの時代」がやってくる: TOI Magazine 001
TOI Magazineは、哲学対話プログラム「Think Out!」を運営するTOIが土曜日の朝にお届けする、「問い」と「対話」の可能性を深掘りする不定期のニュースレターです。
vol.001 - Contents
・Preface|「問いの時代」がやってくる
・Documentary|TOIの実践 2019→2020
・Postface|問いと対話における「ととのう」を探して
◯

text by matsuishi(TOI)
「問うことは、なぜいま新鮮に思えるのか?」
これは、昨年の5月にThink Out!のβ版を実施した際、参加者のひとりから出していただいた問いだ。そう問われてみて、確かに「問うこと」自体は別に新しくも何ともないな、とハッとさせられたことを憶えている。
人類の歴史を振り返っても、哲学対話の元祖といえるソクラテスとプラトンの対話なんて、まさに問うことの連続である。あるいはそこまで遡らなくても、自分の幼少時代を思い出すだけでもいい。「なぜ?」と問うことは、言葉を覚え始めた赤ちゃんの専売特許みたいなものだ。
ではなぜ、我々TOIはいまこの時代に「問うこと」をあらためて掲げ、活動を始めたのか。
それは、いまこの時代に生きる人々が抱えるさまざまな課題には、問うこと、そしてそれによって思考し、対話を始めることこそが有効だと考えているからだ。
現代の課題。ひとつひとつ挙げていけばキリがない。難民やテロ、気候変動といった「社会の課題」から、将来不安やスマホ依存といった「個人の課題」まで、数限りなく存在する。
そんな「課題だらけ」の世界で生きていくために必要なこと。それが、「自分の頭で考えること」、そしてそれをうながす装置としての「問い」である。
■ 思考停止は社会も人生も貧しくする。
このことは、いちど裏返して考えてみるとわかりやすい。つまり、「自分の頭で考えなくなること」、思考停止である。
思考には、受動的思考と能動的思考の2種類あるといえる。「自分の頭で考える」とは能動的思考であり、反対に「条件反射的に考える」のが受動的思考だ。
そして、いまの社会に溢れているのが、この受動的思考を増長させる装置の数々である。
代表的なのが広告だ。生活者に強い刺激を与え、嫌でも商品やサービスのことを頭に浮かべ、記憶させようとする。電車に乗っても街を歩いていてもSpotifyを聴いていても、この日本、とりわけ東京では広告を目(耳)にしない日はない。
教育だってそうだ。学校の試験に出される問題は、必ず「正解」を求める。正解がない問題など出したら収拾がつかなくなるからだ。そしてそんな問題ばかり解いていると、問題が出されれば自動的に正解を探そうとする頭になる。しかし問題が出されなければ考えないから、これこそ受動的思考だ。
これは、筆者自身が最も痛感している問題だ。筆者は、小学3年生の時点でわけもわからないまま受験勉強を開始し、そのまま大学に入学するまでよくわからないままそれを続けた。10年近いこの期間が人間として成長する上でもっとも重要なフェーズであることは言うまでもない。その期間を受験勉強漬けになって生きてきた結果、正真正銘の「受験脳」が完成した。
人生には無数の可能性がある。それなのに、どこかで「正解」を求めようとする。そして、自ら選択肢を限定してしまう。仕事をしていても同じだ。もっと自由に発想し、失敗を恐れず挑戦すればいい。しかし、安全な方、安全な方へと「逃げて」しまう。社会人になってから、いかに自分の頭が貧しい思考しかできないかを痛感し、強く後悔したのは時既に遅しである。
■ 答えなんてない。考えなければ、未来はない。
一昔前の社会であれば、それでもよかったかもしれない。共通して目指すべきゴールがあり、それが文字通りの「正解」だった。そうでない可能性など、考える必要もなかった。
しかしいまは、それでは通用しない。いままでのやり方が通用せず、決まった正解など存在しないから、常にそうでない可能性を考え、失敗を恐れず行動に移していく必要があるのだ。
受験勉強によって受動的思考に特化した脳になってしまったのは、おそらく筆者に限らないだろう。受験勉強というのは、ほぼ例外なく子どもを「受動的思考しかできない大人」へと育てるようにできているからだ。
こうして、自ら問題を見出し、解決しようとする人が少数派となった。問題は与えられるものであり、与えられなければ問題は存在しないに等しい。これがいかに世論を操りたい政治家や広告会社にとって都合がいい事態か、決して想像に難くない。日本という国がじりじりと貧しくなっていっている理由がここにはある。
■ もう一度、問うことからはじめよう。
だからこそいま、問うことが必要なのだ。3歳児だった頃そうしていたように、世界のあらゆる事象に対して、なぜ?と問うてみよう。正解などない、答えなどないという前提に立ち、あらゆるものを疑い、自分の頭でゼロから考えてみよう。
哲学対話は、いつも必ず問うことからはじめる。それも、答えが明らかでない問いであればあるほどいい。そしてその問いをもとに、他者と自由に対話しながら、当初想像もしなかったアイデアが生まれ、考えが深まっていく。
そうしたなかで自分なりの「答え(=気づき)」を見い出す人もいれば、そうでない人もいる。どちらがいいというわけではない。大切なのは、答えのない問いを考え続けること。すぐにどこかで聞いたような「正解」に飛びつかないこと。
誰もが問いを持ち続け、考えることをやめない社会。そんな理想的な社会の状態を「ウェル・シンキング(Well-Thinking)」と名付け、TOIの理念として位置づけた。
もしもそんな社会が実現すれば、TOIが活動する必要はなくなる。その日が来るまで、問い、考え、対話する場を提供し続けること。これが、私たちの生きるこの世界を良くするために我々にできる、小さいけれど確かな抵抗なのだ。
問いが世界を変える時代は、もうすぐそこまで来ている。
◯

text by tagai(TOI)
■ TOIの発足
こんにちは。TOIのタガイです。2019年7月から毎月1回、吉祥寺のバツヨンビルで哲学対話プログラム「Think Out!」を開催しています。
「ウェル・シンキングな社会の実現」を理念とする我々TOIが、Think Out!をはじめとしてこの1年でどんなことに取り組み、どんな示唆を得られたのか、2020年代へと突入する節目であるこのタイミングで、簡単に振り返りたいと思います。
もともと友人であるマツイシに誘われて様々な哲学対話に参加していた我々は、2019年4月、「自分たちでも哲学対話をやってみよう」と決意します。発足にあたって考えたことはこちらにまとめましたが、哲学対話をもっといろんな人に参加してもらいたい、という考えからはじめてみることにしました。
■ 月に1回、合計6回のThink Out!を開催
トライアルを経て6月に募集を開始した第1回は『考える』をテーマに実施。「本当に申し込んでくれる人はいるんだろうか」という不安をよそに9名の方にご参加いただき、盛況のうちに終えることができました。
以降、異なるテーマで実施してきた各回についてはnoteでレポートを公開していますので、よろしければご覧ください。
vol.001|2019.7.20開催|テーマ「考える」
▶ 「現在感じていることは、過去に考えてきたことが決めている」(Think Out! vol.001 レポート)
vol.002|2019.8.24開催|テーマ「生きる」
▶ 「生きるとは何か」を考えることから、「生きる力」は生まれる――Think Out! vol.002 レポート
vol.003|2019.9.28開催|テーマ「自由」
▶ 自由は、どこまで可能だろうか?――Think Out!003レポート
vol.004|2019.10.22開催|テーマ「幸せ」
▶ 幸せは再現可能か?――Think Out!004レポート
vol.005|2019.11.23開催|テーマ「本音」
▶ 本音は必要か?――Think Out!005レポート
vol.006|2019.12.21開催|テーマ「価値」
▶ 価値を一言で表すと?――Think Out!006レポート
■ 参加してくださった方は総勢53名!
今年実施したThink Out!に参加してくださった方は合計53名。そのうち2名の方は6回のうち4回も参加してくださいました。本当に、ありがとうございます。毎回みなさんから頂く感想のひとつひとつが、ThinkOut!の改善につながっています。
アンケートでいただいた感想の言葉を一部抜粋してご紹介します。
・思考の幅が広がる感じがする
・全く異なる視点を知ることができる
・人の考えを聞くことで、自身の偏った考え方を変えられると感じた
・短い時間でも人って変わるのだなと思った
・やわらかい雰囲気があって自然と他の方の話に耳を傾けられた
・いろいろな人の感覚、体験を通じて、自分自身がとても豊かになった
こうして声をいただくみなさん、毎回ご参加いただくみなさん、そして今この文章を読まれている読者のみなさんの存在が、活動をはじめたばかりの私たちにとっては大きな励みであり、活動の意義をより確かなものにし、そしてこの活動の先にきっとよりよい世の中があるはずだ、という希望を抱かせています。
みなさんが、このTOIの創成期を目にしたことを誇れる時がくるよう、この先も活動を継続、そして発展させて参ります。
■ 実験と改善
そんなみなさんの存在を励みに、Think Out!に加えていくつかの試みに挑戦しました。
【オンライン】
・Twitter|「今日の問い」
https://twitter.com/thinkoutinside
毎朝7時に、botによる「問い」の発信をしています。朝、通勤時や通学時に問いに触れて、その日を「考える一日」になるきっかけをつくります。
・note|イベントレポート発信
https://note.com/thinkoutinside
TOIが実施するさまざまなイベントは、参加できなかった方にもエッセンスを体験できるよう、運営メンバーがレポートを執筆しています。
・note|イベントレポートの民主化「TOI アンバサダープログラム」
運営メンバーの視点からだけでなく、参加者の方の視点からもTOIのイベントを追体験していただけるよう、参加者の方に有志でレポートを執筆いただく試みを始めました。
▶ vol.005 by オヤマさん https://note.com/thinkoutinside/n/n8a1fd8788f8b
▶ vol.006 by クラユキさん https://note.com/thinkoutinside/n/n835deba61f61
・Podcast|耳で聴く哲学対話「Think Out! on Air」 by TOIラジオhttps://anchor.fm/toiradio/
Think Out!に参加されたことがない方にさらに臨場感ある疑似体験をしていただくために、毎回のレポートに加え、10月からはPodcastをはじめました。
【オフライン】
・店舗|「問いが見つかる本棚」出店@ブックマンションhttps://note.com/thinkoutinside/n/nb1e0ff1d2375
Think Out!を開催しているバツヨンビルの地下1Fには、様々な店主が本棚を構えるブックマンションがあるのですが、そちらにTOIも棚を出店しています。毎回のThink Out!のテーマに合わせた選書をしており、それぞれの本にはその本から得られる「問い」がしおりになって挟まっています。
・店舗|選書のオープン化:「問いの循環」
「問いが見つかる本棚」に展開する本をThink Out!参加者の方から募集する施策を始めました。すでに3名以上の方が本を持参くださっていて、陳列してまもなく売れた本も。
・イベント|ABD読書会「問いと対話の研究会」実施https://note.com/thinkoutinside/n/n6ce83b905b80
Think Out!の体験をより深いものにするために、問いや対話に関する資料をABD(アクティブ・ブック・ダイアローグ)形式で読み込むイベント「問いと対話の研究会」を試験的に開催しました。
・イベント|Think Out!で価格自由の実験
https://note.com/thinkoutinside/n/n7ba1d035897f
2019年最後のThink Out!は『価値』をテーマに実施。テーマに関連した試みとして、参加者の方に会場費を決めて頂く形を取り入れてみました。
・セミナー|企業研修として実施
Think Out!のプログラムを応用して、企業向けに研修プログラムを実施しました。互いに初めての人どうしが対話をするThink Out!とは異なり、普段一緒に働く社員どうしでひとつのテーマを深める試みでしたが、「いつもと違う新鮮な視点で同僚を見ることができて発見があった」といった満足の声が多く寄せられました。
■ 2020年も新しい試みに挑戦します。
1|TOI Magazine発刊
今回の創刊号を皮切りに、これからも不定期で発刊して参ります。コンセプトは「問いと対話の可能性を深堀りするニュースレター」。これまでお届けしてきた各種レポートに加えて、メルマガならではのオリジナルコンテンツもお届けする予定です。ご登録はこちらから。
2|TOI Member募集
これまで創業メンバーであるタガイ 、マツイシ、きのしの3名で運営をしてきたTOIですが、2020年は新メンバーを加えてさらに活動を拡大していきます。まずはアンバサダーとして何回か部分的にご協力いただき、その後メンバーとして企画にも関わっていただきます。ご興味ある方はthinkoutinside@gmail.comまでご連絡ください。
3|企業や学校での研修プログラム提供開始
活動を続けるなかで、企業や教育関係の方からご相談をいただくようになりました。2020年は、プログラムとして企業内研修や教育研修を積極的に提供していきます。こちらも、ご興味のある企業関係者(経営者や人事担当者など)や教育関係者(学校の先生など)の方がいらっしゃいましたら、thinkoutinside@gmail.comまでご連絡ください。
◯
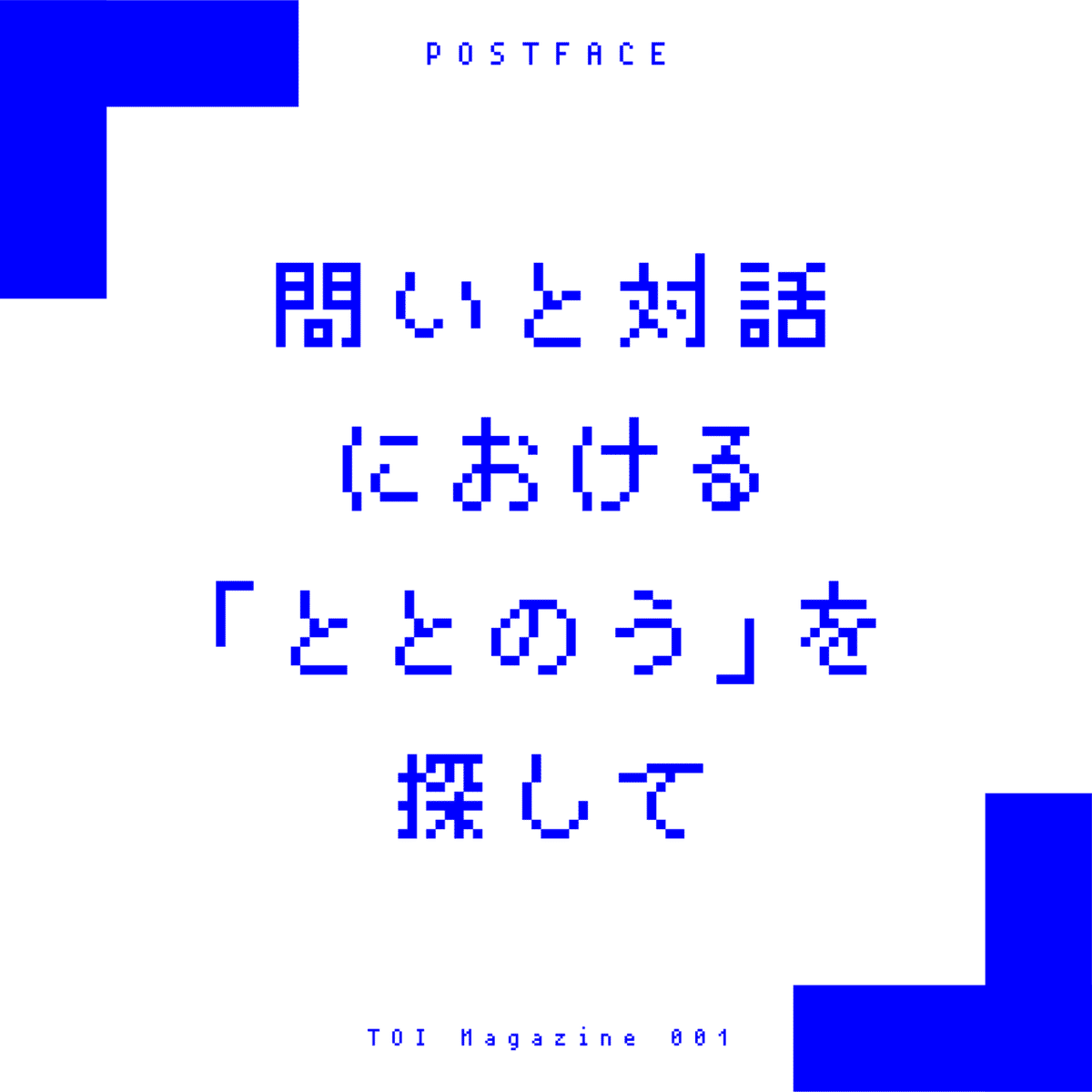
text by tagai(TOI)
Think Out!の取り組みを始めてから常につきまとってきたのが、その魅力を伝える難しさである。約2時間の対話を終えた後に生まれる独特の高揚感や満足感は、なかなか言葉では表しにくい。
Think Out!でやっていることを簡単に説明するなら、「答えのないテーマについて参加者が問いを持ち寄り、4人1組ほどのテーブルでルールに則って対話をする。それを30分を2回繰り返す。」ということなのだが、大抵の人はその説明だけを聞くと「?」といった表情をする。いったいそれの何が面白いんだ、といった反応である。
しかしひとたび参加をして体験をしてみると、初めての参加者ほどその感覚に感動する人が多い。先日も、対話が終わった後のチェックアウト(簡単な感想共有)でこう述べていた人がいた。「初めて参加してみましたが、すごい爽快感に包まれていて気持ちがいいです。まさに“頭のワークアウト”という感じです」。それを聞いていた私はもちろん、他の参加者の方も「うんうん、そうだよね」という感じでうなずいていた。
そこには、体験した人にしかわからない感覚が存在する。
この体験を伝える難しさは、サウナの魅力を伝える難しさに似ている。サウナも、やっていることだけを説明すると「80〜100度の部屋に裸で入り、何分か経ったら水風呂に入る」ということになるのだが、それだけだと「何が楽しいのだ?」となるだろう。
しかしひとたびサウナにより得られる独特の高揚感を体験すると、なんともくせになる。私自身、6−7年前にその作法を体得し、独特の高揚感を体験してから定期的にサウナへ通っている(ちなみに私のルーティーンはサウナ5分→水風呂を3回繰り返し最後に水風呂→湯船という流れ)。
サウナもまた、体験しないとわからない感覚が存在するということだ。
サウナ業界は近年その感覚を「ととのう」という言葉で説明している。この「ととのう」という言葉自体はサウナブロガーの「濡れ頭巾ちゃん」という方が提唱したものだそうで、2011年には既にその言葉が使われていた(https://ameblo.jp/spasaunalove/entry-11087164266.html)。しかし、この言葉自体が今のように至るところで聞くようになったのは2019年に入ってからだと思う。事実、私がサウナへ通い始めた6−7年前はこのサウナ後の独特の高揚感を説明する言葉が見当たらなかったと記憶している。
試しにGoogle Trendで調べてみると、「サウナ」という言葉は2019年9月に2004年からの間で最も検索されており、昨年がサウナブームとなった年であることがわかる。2015年からモーニングで連載されていた漫画『サ道』のドラマ化(テレビ東京)も影響として大きいだろう。

そして「ととのう」という言葉を調べるとさらに顕著に傾向が出ていて、2018年10月に突如山ができたあと、2019年10月にそれを超える形で検索されている。2018年の「ととのう」という言葉の認知がひとつのきっかけになって、2019年のサウナブームが生まれたと捉えることもできるのではないだろうか。

このサウナブームから我々が学ぶことは多い。体験しないとわからない感覚を「ととのう」という言葉で形容し、広げたサウナ業界。現在、哲学対話においてこの「ととのう」にあたる言葉は存在していないはずだ。その感覚を的確に表現する言葉は何か。そして、その言葉をどのように広げていくことができるのか。
サウナ同様に体験しないとわからないThink Out!の魅力を伝えるべく、2020年も私たちTOIはさらに活動を広げて参ります。本年もTOIの活動にご期待ください。
◯
TOI Magazine第1号、いかがでしたでしょうか。お読みいただいてのご感想をハッシュタグ「#toimagazine」をつけてツイートしていただけると、執筆者一同とても喜びます。ご意見などもぜひ。最新情報はTwitterで配信していますので、よろしければチェックしてみてください。
Copyright © TOI 2020, all rights reserved.
いいなと思ったら応援しよう!

