
新時代のワンダを描く、忘れられた意欲作「スカーレット・ウィッチ (2015)」
ここ最近は何でもかんでも実写化して「あんなキャラが映画に出るの!?」と思うことにも慣れてきたマーベル作品だけど、中でもここ数年で飛び抜けてぶっ飛んでいた企画が、アガサ・ハークネスを主人公にしたテレビドラマ「アガサ・オール・アロング」だろう。
アガサ・ハークネス自体は「ワンダヴィジョン」に登場しているけど、そんなスピンオフのスピンオフみたいな企画を、しかも正直お世辞にも人気があるとは言えないようなアガサ・ハークネスを題材にしたドラマなんて本当にうまくいくのか…と、ファンダム全体が結構困惑していたような気がする。

ところがどっこい、これが意外にも面白く、サプライズもいっぱいでするする見れるような怪作だった。近頃は「マーベルの実写化作品は質が落ちた」なんてことが囁かれるけど、こういうキャラもしっかり魅力を掴んで面白い話を作られるとやっぱりマーベルはすごいんだなと思い知らされる。まだまだMCUの未来は明るそうだ。
その一方で、僕はコミック読者として一つ驚いたことがあった。それはこのドラマが、ジェームズ・ロビンソン著作の「スカーレット・ウィッチ (2015)」を設定のベースに使っていること。自分はかなり楽しく読んでいた作品でかなり意欲的な設定を導入したんだけれど、その後の作品でほとんど拾われることなく今まで来てしまっているので、てっきり「もう公式にも忘れ去られてしまっているのか…」と思っていたところだった。それが突然、実写化という晴れ舞台で持ち上げられたのだからこれまた相当なサプライズだ。
今回はこの物語の魅力を、当時のスカーレット・ウィッチというキャラクターの状況を踏まえて書いていきたい。

2010年代前半は、スカーレット・ウィッチとクイックシルバーにとっては激動の時代だった。それまで双子はX-MENの宿敵マグニートーの子供という設定だったが、大型クロスオーバー「アベンジャーズ&X-MEN:アクシス」にて、実は2人の実父はマグニートーではないことが判明し、それどころかそもそもミュータントですらないことになってしまう。この設定の急な転換にはいろいろ裏事情があるようで、ディズニーがアベンジャーズの実写映画に双子を出すに当たって「X-MENの映画化権は20世紀フォックスが持っているから、ミュータントという設定をそのまま使うわけにいかない!」という都合で、映画はもちろん余計なことにコミックでの設定もねじ曲げたというのが通説。この頃のマーベルはとにかく実写映画を盛り上げるために訳のわからんことをいっぱいやっていたけど、特にスカーレット・ウィッチとクイックシルバーはその被害に直撃したとも言える。
そんな波瀾万丈な双子の映画デビューから数ヶ月後に始まったシリーズこそ、今回紹介する「スカーレット・ウィッチ」である。本作は約20年ぶりのワンダの個人シリーズとなるが、これまでキャラの根幹だった「マグニートーの娘」設定は当然使えない。そんな中で、ロビンソンはワンダのもう一つのルーツ「母親の正体」に注目することにした。
実はワンダとピエトロは東欧の出身で、中でもラマという少数民族の生まれであるという設定があった。その出自故に差別を受け、かつ怪しい能力を持つということで化け物扱いされながら、2人は身を寄せ合って少年時代を生き抜いてきた。ロビンソンが注目したのはこれまであまり語られなかったその設定で、ワンダは自身のアイデンティティを再び掴むために自分の母親の正体を探ることになる。その過程で、アガサのドラマにも登場する「魔女の道」へと踏み入り、時空を超えて母親と対面するのだ。

ワンダの母の正体は魔女であり、先代の「スカーレット・ウィッチ」だった。そう、これまでワンダが思いつきで名乗っていたと思っていたスカーレット・ウィッチの二つ名は、実は世代ごとに受け継がれていた称号だったのだ。
魔法そのものを救う壮大な闘いの中、ワンダは自身の母と確かに心を通わせる。世代を超えて受け継がれてきた魔女の力、そして「スカーレット・ウィッチ」の称号は、魔法使いとしてのワンダの側面をより強く強調させるとともに、彼女の印象を「マグニートーの娘」から「スカーレット・ウィッチの座を受け継ぎし者」へと確かに変化させた。度重なるいざこざの結果めちゃくちゃになっていたワンダのアイデンティティを、作家のジェームズ・ロビンソンは新しい形で復活させようと尽力したのだ。
同時に、ロビンソンはこれまでいなかったスカーレット・ウィッチの宿敵として「エメラルド・ウォーロック」というキャラクターを作り上げた。スカーレットやエメラルドという言葉からわかるように、ロビンソンは「魔法は色と深く関わりがあり、多くの魔女や魔法使いはさまざまな色を用いた称号を名乗る」という設定を導入した。彼ら以外にも日本人の「葵・マスター(マジで英語もAoi Master)」なるキャラクターが登場した。「アガサ・オール・アロング」でも登場した、母から受け継いだ魔法で警官として闘う香港人のキャラ、アリス・ウー・ガリバーは髪を特徴的なオレンジに染めている。

僕はこの設定めちゃくちゃ好きで、色という縛りがあるだけで色んなキャラの世界観が繋がって見えるし、その癖色なんてほぼ無限にあるんだからいっぱいキャラを出しても別に枯渇することもない。うまくいけばDCの「グリーン・ランタン」みたいな独創的な世界観を作れるんじゃないか。
これまで「アベンジャーズのそんなに目立たない人」みたいなイメージだったスカーレット・ウィッチも、新たな宿敵が生まれたことでより派手な物語を描けるかもしれない。この作品は、スカーレット・ウィッチというキャラクターをより深く描くため、新しいアイデンティティとともに今後の土台となる設定を作ろうと、とにかく意欲的に新しいアイデアを出し続けた。

設定はあったけどあまり注目されていなかったワンダの側面や、全く新しいアイデアまで次々に取り入れていき、とにかく新しい時代のスカーレット・ウィッチ像を作り上げようと意欲的に取り組んでいた本作だけど、結果はというと…正直そこまでうまくいかなかったように思える。
本作は15号で打ち切り。この号数自体はそこそこ長く続いている方だし、特にこの時期のマーベルはやたらめったら打ち切りと新シリーズ刊行を繰り返していた時期なので、5号や6号で打ち切られた短命シリーズもごまんとある中、ここまで長く続けられたのはかなり頑張ったと思う。しかし、シリーズの最後の最後で「実はワンダの母を殺したのは彼女の真の父親その人」という衝撃的な事実が明かされ、その父親の正体は愚か、その事実をワンダが知ることもなく物語が終わっていった様子を見ると「本当はまだ描きたい物語があったんだろうな…」と思ってしまう。
せっかく頑張って練り上げた「色」の設定や、ワンダの新たな宿敵エメラルド・ウォーロックも、本作の後再び姿を現すことは依然無いままだ。そもそもこのシリーズの後、スカーレット・ウィッチ単体主人公のコミックが次に連載されるのは8年後。そもそもワンダの物語を再び深く描く機会すらほとんどなかったはずだ。
そもそも魔法とは割となんでもありなもの。ライターごとに解釈も変わるためか、魔法系キャラはどうも固定の設定が根付きにくいような気がする。ワンダも皮肉なことに、自分の使う力の特性に翻弄されてしまったというところだろうか。
そんなわけで、ジェームズ・ロビンソンが生み出した斬新なアイデアは長らく埋もれてしまっていた…そう「アガサ・オール・アロング」が配信されるまでは。
知っての通りMCUでのワンダはもう死亡してしまっているし、今回のドラマはワンダではなくアガサが主人公だ。しかしコミックでもなかなか素材の少ない「魔女」という題材を実写化作品で扱うにあたって、マーベルはついにこの「スカーレット・ウィッチ」のアイデアを掘り返した。物語の主題となる「魔女の道」や、「緑」を纏った主人公の宿敵、そして魅力的なサブキャラ「アリス」の登場…本作がジェームズ・ロビンソンのアイデアから着想を得ていることは疑いようが無い。実写化作品は普通のコミックよりも多くの人の注目を集めるし、「アガサ・オール・アロング」で日の目を浴びたアイデアが多くのファンの共通認識として今後定着していく可能性は十分にあるだろう。実写化によってミュータントというアイデンティティを奪われた末に生まれたこの新時代のスカーレット・ウィッチは、奇しくも再び実写化作品によって第二のチャンスを与えられたのだ。
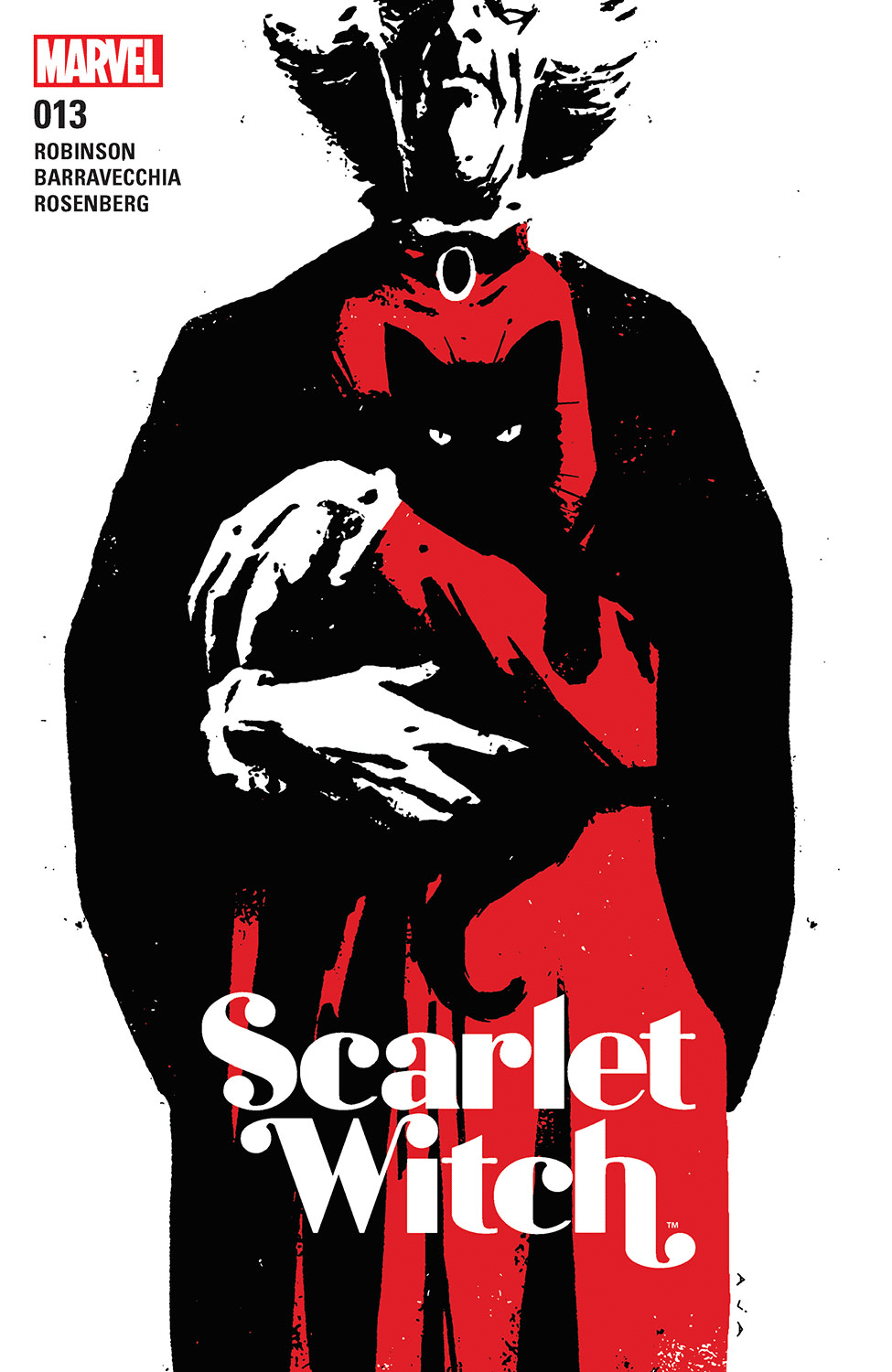
今作は決して有名な作品ではないし、生み出された数々のアイデアも爪痕を残したとはとても言いづらい。それでもワンダ・マキシモフの根幹が揺るいでいた激動の時代の中、確かにそこに新しいキャラクター像を作り上げようとしていた本作が僕は大好きだ。来るかもわからないいつかの話だけど、ワンダの父親の正体が明かされるその日を待ちながらスカーレット・ウィッチの物語を追い続けたい。
