
全オリジナル・アルバム FromワーストToベスト(第35回) ボブ・ディラン その3 10〜1位
どうも。
では、FromワーストToベスト、ボブ・ディラン。いよいよトップ10。

エントリーするアルバムはこんな感じですが、そうそうたるアルバムばかりですよね。
では、早速10位から行きましょう。
10.Nashville Skyline (1969 US#3 UK#1)

第10位は1969年発表の「Nashville Skyline」。ディランが終始、鼻にかかった謎の歌声で歌い続ける唯一のアルバムとしても有名ですが、これ、ディランの中でのルーツ志向、レイドバック系のアルバムの中では一番好きですね。もっともカントリー・ミュージックを強く念頭においたものであり、枯れ具合も郷愁を誘う詫びげなエモーションでも、歴代のディラン作品の中でも屈指のものがあります。シングル・ヒットした「Lay Lady Day」もいいんですけど、とりわけ、カントリー界の”マン・イン・ブラック”、ジョニー・キャッシュとの共演となった「北国の少女」での領有並び立ったカリスマ性がいいですね。
9.Oh Mercy (1989 US#30 UK#6)

そして9位に「Oh Mercy」。80年代に入り、長らく「絶不調」と呼ばれていたディランの放った起死回生のアルバムですね。これまで普通に80sの進んだテクノロジーのスタジオで当たり前のように録音していたディランが鬼才ダニエル・ラノワをプロデュースに迎えた途端、がらんとしたスタジオの中、ディレイをかけたギターだけが蜃気楼のように揺れる緊迫した空気の中、ディランがこれまでに聴いたこともなかったようなしゃがれ声でうなりながら歌う。ディランが迎えた中でももっとも大きな変化となったこのアルバム。これが一時的なものになるのか否かがこの当時だけではまだわからなかったものでしたが、このダークでゴシックな路線が結果的に新たな時代のはじまりだったことは8年後に証明されることになります。今となってはいわば「変化の前段階」ですが、「Ring Them Bells」「Man In The Black Coat」あたりは今聴いても光りますね。
8.Another Side Of Bob Dylan (1964 US#43 UK#8)

8位は「Another Side Of Bob Dylan」。1964年に発表の4枚目ですね。その前作と前々作でかなりのプロテスト・シンガーと見なされたディランが、そのイメージに一石を投じた、よりパーソナルで穏やかなアルバムですね。それで当時、批評家の一部から「社会から離れた」と批判も受けたようなんですけど、それによって言葉に意味がなくなるどころかラブソングひとつとっても畳み掛ける言葉でユーモアと率直かつ赤裸々な気持ちをしっかり表現できています。そして、それに伴って起こったのかどうかは定かではないんですが、メロディがかなり柔和になって聴きやすいんですよね。ここから「All I Really Wanna Do」「悲しきベイブ」が長いことディランの定番曲になっていることでもそれは明らかです。そして、やっぱり「My Back Pages」での「昨日の僕より今日は若いぜ」の名フレーズですよね。既存のイメージを恐れず、人々の予想をかいくぐりながら果敢に生きていく。デヴィッド・ボウイでいうところの「Changes」のような自己アイデンティティの宣言のようだし、それがはじまるのはやはりこの地点だと僕は思ってます。
7.Time Out Of Mind (1997 US#10 UK#10)
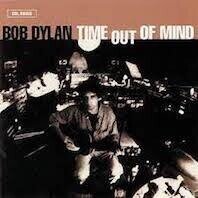
そして7位に「Time Out Of Mind」。現在に至るまでの、「現役での最強アーティストとしてのディラン」が正式に幕を開けたアルバムが、彼が56歳のときに出した今作ですよね。アイデアそのものは「Oh Mercy」で見せたものと同じものではあるんですけど、ダニエル・ラノワのほどこすドローンとディレイのサイケデリックな魔術というか、ダークでゴシックな音の揺らぎが広い空間美を伴って現出した、圧倒的な音像になってますね。この頃って、時代的にはマッシヴ・アタックとかポーティスヘッドのようなトリップホップもかなり人気あったものですけど、この不穏な重々しさ、ポーティスヘッドに近いものを感じさせるなと、リアルタイムで思っていたものです。もう、これが出てからでさえも25年近く経とうとしてますけど、「Love Sick」や「Not Dark Yet」のゆっくりとドシリとくる緊迫感溢れるヘヴィなグルーヴ感は今聴いてもかなり新鮮です。音の刺激そのものを優先して欲するタイプの人なら、これ、もっと上位だったかもしれないですね。
6.Blonde On Blonde (1966 US#9 UK#3)

そして6位に1966年の大作「ブロンド・オン・ブロンド」です。「おいおい、なんだよ。それが1位じゃないのかよ!」という声が聞こえてきそうで怖くはあるんですが、これがこの位置にあるのはこのアルバムが嫌いだからではありません。もちろん素晴らしいアルバムです。単純に僕の中で、これよりも優先したい同等に素晴らしいアルバムがあった。ただ、それだけのことです。そんな本作はいわゆるフォークロックに開眼したディランがサウンドの幅をフォークからロックンロールからソウルから、25歳の若さの勢いを持って拡大していったときです。「雨の日の女」「我が道を行く」「女のように」。どれをとっても名曲です。いきおいで作った造語的な文章も炸裂してます。のちにクラッシュの「ロンドン・コーリング」がこれと比べられる事があることもわかります。ただ、スマッシング・パンプキンズでいうところの「メロンコリー」より「サイアミーズ・ドリーム」の方が好きなのと同じ理屈で、僕はもう1枚の曲数シンプルな方が好き。それだけのことです。
5.Love And Theft (2001 US#5 UK#3)
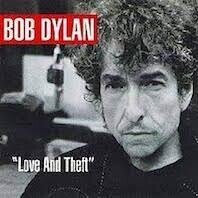
そして5位に「Love And Theft」。「Time Out Of Mind」からの「円熟して、さらに進化した今日のディラン」の中では、これが最高峰ですね。これ、聞いた時、ビックリしましたもんね。「Time〜」で生んだゴシックかつ歪んだ音像を残しつつ、ここでディランが展開したのはライブラリーのように無尽蔵なアメリカン・ミュージックの歴史のようなめくるめくサウンド展開ですね。フォーク、カントリー、ブルーズといった次元ではないです。第二次大戦前のショー・チューンから、ジャズ・ギターをフィーチャーしたバラードまで。ディラン、このとき還暦でしたけど、彼の60年の人生で培った深遠すぎる音楽への造詣を一気に吐き出したかのような誰にも到達できないアメリカ伝統音楽の深みがここにあります。骨太ロックンロールの「Honest With Me」や、古のロマンティシズムへ誘う「Po' Boy」あたりは近年のディランのライブでも定番曲になってます。
4.The Freewheelin' Bob Dylan (1962 US#22 UK#1)

そして4位に「Freewheelin' Bob Dylan」。「反骨のフォークの闘士」としてディランが注目を浴びた最初のアルバムです。このときまだディラン、21歳ですよ。僕でさえ生まれる10年近く前の作品ではありますけど、「人として認められるのにどれくらい時間がかかるの。答えは風が知るだけ」でおなじみの「風に吹かれて」を筆頭に、キューバ危機やそれに伴う核戦争の恐怖を汚染された雨に託して歌った「激しい雨が降る」、国民の意思の届かぬところで戦争を企む政治家たちへの怒りを歌った「戦争の親玉」。こういったプロテスト・ソングが60年を経た現在でも全く古びず強い説得力を持地続けています。これらの曲はおそらく、「人類の教訓」としてずっと歌い継がれるでしょうし、忘れられたら怖いものだと思います。あと、それとは別に、この当時のガールフレンドのスージーとのジャケ写。寒空の中で若い二人が片寄せあって歩く愛と希望と活力にあふれた写真もこれまたタイムレスです。
3.Bringing It All Back Home (1965 US#6 UK#1)

3位は「Bringing It All Back Home」。これまた重要なアルバムですね。ディランが、この当時のフォーク界の「ロックなんて子供の音楽」というあざけりをものともせず、そこにある新たな可能性を信じてエレキギターを手にしたアルバムなんですけど、そうした、その当時としては大胆な英断を行う時期というのはやはり音楽創作的にも勢いがあるものでして、多数の名曲を吐き出すように量産してます。前のめりなリズムに乗りながら韻を思いつくままに叩きつけた「サブタレニアン・ホームシック・ブルース」からはじまって、ディラン流エレクトリック・ブルーズの「マギーズ・ファーム」。リリースの同年にザ・バーズにカバーされフォーク・ロック初の全米1位となったミステリアスな「ミスター・タンブリンマン」、そして今日まで無数のカバーを生んでいる「大丈夫だよ、血を流しているだけだから」という奇妙な皮肉のタイトルの「イッツ・オーライト・マ」、さらに「イッツ・オール・オーヴァー・ナウ・ベイビー・ブルー」まで。他人に歌い継がれている曲の多さではこれが一番のような気もしますね。
2.Blood On The Tracks (1975 US#1 UK#4)

2位は「血の轍」。これも、ディランの名作というだけのみならず、ロック史全体でのオールタイムで必ず入ってくるアルバムですね。しかも、わりとそれ、ここ20年くらいの傾向だと思います。だから日本のディラン・ファンで以前は「そうなの?」という反応もあったんですけど、最近は若い人にも人気ですね。これはディランが妻のサラと別れた傷心アルバムとしてことのほか有名ではあるのですが、そうした気持ちのコントローウのできない、理屈にならない感情的な時期だからこそ、より本音が生々しく生まれるもの。その瞬間をとらえた作品なんですが、このときのメロディと言葉のセンスが絶妙ですね。これは前も書いたんですけど、「天国の扉」以降、ディランのメロディ・メイカーとしての才が冴えてる状態にあったのがひとつあると思うんですけど、思いついたフレーズもやぱり「ブルーにこんがらがって」なんて表現はどうやったら思いつくのかわからないですね。うまくいかない恋愛を「ちょっとした運命のひとひねり(Simple Twist Of Fate)」と呼んでみる感じとか「イディオット・ウインド」とかも語感がすごくいい。タイミングとメロディと言葉のケミストリーがここまで噛み合った作品も、ディランの人生の中でないような気がします。
1.Highway 61 Revisited (1965 US#3 UK#4)
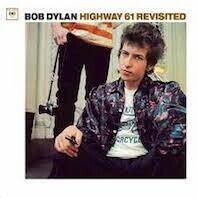
そして1位はやっぱりこれですね。「追憶のハイウェイ61」。これ、一部のディラン・ファンに言わせると、ビートルズの「サージェント・ペパーズ」同様、これを1位にするのはイケてないようなんです。「ブロンド・オン・ブロンド」を1位にすべきだと。たしかに、彼の音楽的資質の爆発を考えるにそっちの方が適切なのかもしれません。でも、「ブロンド・オン・ブロンド」がどうやったところで手に入らないものがここにはあります。それはやっぱり「ライク・ア・ローリング・ストーン」。ディラン最大の代表曲がキャリアのトップを争う名盤に入っている以上、それはやっぱりトップなのです。それだけじゃないですね。マイク・ブルームフィールドを筆頭としたエレキ編成のバックバンドとのケミストリーとグルーヴ感でも今作は群を抜いているし、「やせっぽちのバラード」「クイーン・ジェーン」「廃墟の町」といった曲でのストーリー・テリングとキャラクター設定も巧みだし、さらに、やはりタイトル曲で、彼自身の人生の象徴とも言える「ハイウェイ」を持ち出してきていること。これだけの要素があれば、これが1位で僕は十分有効だと思いますけどね。
