
沢田太陽の2020年7月〜9月のアルバム10選
どうも。
では、3ヶ月に一度の、毎度の企画、行きましょう。7月から9月にかけてのアルバム10選。
この3カ月、好きなアルバム、すごく多かったですが、こんな風にまりました!

はい。なかなか力作揃いだと、選んでて僕も思いました。では、ランダムにざっと語って行きましょう。

Folklore/Taylor Swift
まずは、一番目立つものからいきましょう。テイラー・スウィフトの「Folklore」。これはひとつの歴史的なアルバムのような気がしますよ。2010年代以降、最大のポップスターのテイラーが、彼女の本来持っていたカントリー、フォークの路線に、ザ・ナショナルやボニー・ヴェアといったUSインディ・ロックの精鋭たちときわめて鋭角的なセンスと共に表現した。しかもそれが、コロナのパンデミックという、地球上の多くの人が苦味を味わい、後年まで忘れられない辛い時期にあった多くの人たちのハートに届いたわけですからね。後述しますが、パンデミックの期間中、僕は必ずしも「内省のとき」とは思ってはいないのですが、そのセオリーに叶う実は唯一のアルバムでしたよね。プラス、テイラーにとっては、ポップ化が空回りつつあったタイミングで自身を取り戻すいいきっかけにもなって。「1989」とかでなく、これでグラミー取るんだったら文句はなかったですね。

Inner Song/Kelly Lee Owens
今回は意外にも、テイラーと、このケリー・リー・オーウェンズしか女性選んでないんですね。これは自分でも、少し意外でした。ただ、このウェールズ出身の女性エレクトロ・シンガーソングライターのセカンド・アルバムは、サウンド・クリエイターとしてかなりのものだと思います。彼女の場合、「歌があってトラック」ではなく、元がアンビエントっぽい浮遊感漂うエレクトロ・アーティストで、歌はあくまで彼女自身のセルフ・フィーチャリングなんですけど、すご立体性、鋭角性、叙情性の三拍子が揃った絶妙な電子音の上に、か細い喉から精一杯紡ぎされるエアリーでささやくようなハイトーン・ヴォイスが溶けていくさまがなんとも美しいです。

The Ascension/Sufjan Stevens
続いてはリリースされたばかりですね。スフィアン・スティーヴンスの最新作。もうUSインディではすっかり大物SSWになってる彼には、すでに幾多の名作があります。その中で本作は、僕が聞く限り、最高傑作ではないと思います。やはり僕自身が彼にどうしても期待するのは、優美に入り組んだ華麗かつ透明感あふれるバロック・ポップであり、今回のような、これまでも時折展開していたエレクトロ・サウンドではないから。ただ、それでも今回のアルバムが耳をひきつけてやまないのは、先行トラックでいち早く話題を呼んでいた大曲「アメリカ」での「アメリカに対してやったことを僕にやってこないで」に象徴される、心から愛した祖国アメリカに対しての徹底した幻滅ぶり。「君のビデオゲームなんてやるつもりはないんだ」「何に対しても信念を失ってしまった」・・。わかりやすく平易に語られた心からの失望の念が、繊細ながらもいつも以上にエモーショナルな熱唱にもつながっていたりもして。そして、これは、ラナ・デル・レイの昨年の大傑作「Norman Fucking Rockwell」にも通じる流れでもあると思います。

A Celebration Of Endings/Biffy Clyro
ただ、もう今回は、「こんなのいつ以来だろう?」ってくらい、思い切りバンドだらけですね。自分でも驚いています。まずはビフィ・クライロ3枚目の全英1位アルバムから。彼らの場合、「グランジ以降」のバンドとして2000年代からイギリスでは批評、人気共に昔から高いバンドですけど、これまでに試したことのなかったリフだとか、間合いの使い方が本当にうまいですね。それがゆえに、大きくサウンドの方向性を変えているわけでもないのに、マンネリ感が全くでない。今回もそんな彼らの、「剛の中の柔」の部分がすごく端的に現れた作品だと思います。あと、サイモン・ニールの声がどことなくピーター・ゲイブリエル似なのも、普通のラウドロック・バンドに聞こえない一つの大きな理由かなと、今回聞いて思いました。

Imploding The Mirage/The Killers
続いてはザ・キラーズの、もう、これは復活作と言ってもよい会心作ですよ!いやあ、デビューのときからの長年のファンとしては本当に嬉しいというか。2010年代に入ってから、ビッグになりすぎたバンドにブランドン自身が戸惑ってサウンド自体が守りに入ったままビッグになっていたところがあったんですけど、これ、前にも書きましたけど、今、ここで改めて、彼らの基本である「グラマラス・インディ・ロックンロール」の基本に立ち返りましたよね。ブランドンのソロで展開していた、カントリー、フォークのテイストももらさずにここで注入することで、独自のシンセ・ポップ・サウンドにさらに深みが増したし、ワイズブラッドのゲスト参加のような趣味の良さも随所に見せているし。やはりここは、ギタリストのデイヴの抜けた危機感とか、ブランドンの奥さんのうつ病とか、そうした苦境が、バンドとしての行き詰まりを結果的に打破させる力として働いたかと思います。

Ultra Mono/Idles
そして、ここからはUKロック怒涛の4連発ですよ!まずはじめは、出たばかりのアイドルズのアルバム。2018年の「Joy As An Act Of Resistance」、あのアルバムはUKロックを再生させる契機となった非常に大きなアルバムと僕は捉えています。洗練を拒むかのような猪突猛進のロックンロールに無骨を絵に描いたようなヴォーカル、歯に絹着せないま正直すぎる物言い。ここ数年のロックが忘れていた何かを思い出させたこのアルバムは、イギリスでロックの存在感を今一度思い出させたことに大きな意味があったと思っているし、実際、あのあとから、タイプは違えど、それぞれにUKロックのバンドたちが各々自己主張し始めたような気がしてるし。7月からUKチャートのロック勢の活躍素晴らしかったんですけど、この素敵な3カ月を、このアルバムが見事にシメました。正直、今作の場合、「Mr.Motivator」「Grounds」といった先行シングル曲のインパクトほど光った他の曲が少なくはあったし、多くのレヴューで指摘されている「労働党の政治集会みたいだ」とアジテーションしすぎる歌詞が批判もされています。ただ、だからといって前作で彼らが示した、直線的なだけでないエッジィなグルーヴも、獰猛な攻撃性も微塵も失われたどころか、良くなった音質で逆説的にに強調してたりもして。このアルバムも文句なしの初登場1位のようですけど、もうカリスマとしての足場もしっかり固めることもできています。下手にかみつくだけ無駄というものです。
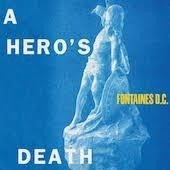
A Hero's Death/Fontaines DC
続いては7月上旬、これも大きな話題になりましたね。アイルランドはダブリン期待の大器、フォンテーンズDCの2枚めのアルバム。先述のアイドルズ、シェイム、そして彼らの3バンドが「新世代ポストパンク・トリオ」なんて言われてロックの再興を期待されていたわけですけど、順調に成長してます。このアルバムも、テイラー・スウィフトのアナログ販売さえ行われなければ初登場1位だったわけですからね。彼らはもう、出てきたときから個性は完成され尽くしてましたけどね。それはグリアン・チャッテンの覚醒しきった表面のクールさの中に潜むエモーションだったり、ギター・リフの切れ味や、ストロークスのファヴリシオを彷彿とさせる空間の隙間を活かしたドラムのリズムに、時折アイリッシュ・フォークを漂わせる歌心だったりするんですが、今回は、彼らのサウンド・フォーマットをザ・フォールからジョイ・ディヴィジョンに移行させたかのような、よりシリアスでダークなサウンドの方向で彼らのシグネチャー・サウンドを発展させた感じがありますね。グリアン、アレックス・ターナー以来のカリスマになれる風格、漂ってます。

Sex,Death & Infinite Void/Creeper
ただ、個人的には、そのフォンテーンズと同じ日にリリースされ、全英初登場で5位に突如として入ってきたクリーパーのこのアルバムの方が好きなんですよねえ。このアルバム、僕には嬉しい衝撃でした。このバンドのことは2017年くらいから知ってて、その頃は「ゴス系エモ」といった趣でAFIとかマイ・ケミカル・ロマンスのフォロワーのイメージでした。曲もそれっぽくて、時折メタルっぽくもなったりして。それが、3年たった今作では、フロントマンのウィル・グールドの風貌が、それまでのジョーイ・ラモーンみたいな野暮ったい感じから、手に花を持った貴公子風の風貌にメイクオーバーし、曲もボウイ、というより90sの半ば頃のスエードを彷彿とさせる、流麗なストリングスとグラム・ロックのたおやかさをより前面に出し、ポップ・パンク的な子供っぽさが一気に後退。より本格派に一気に成長しました。しかもウイル、ルックス的にもかなり美形なんですが、ヴォーカルのロウとハイを巧みに操れるかなりレンジの広いシンガーでもあるので、曲にダイナミズムもつけやすいんですよね。今作は、そうした彼らの潜在能力が一気に開花した大出世作となっています。本当はこれを、ジャケ写大枠の作品にしようかと最後まで迷うほど、気に入っていました。

Zeros/Declan McKenna
そのクリーパーとどっちを大きい写真に選ぼうかすごく迷った末にこっちにしたのがデクラン・マッケンナのセカンド・アルバム。これも、本当に全く期待していなかっただけに驚きました。前作のときはまだ彼、ティーンエイジャーで、「ソロでもインディ・ロックが好きな人」として聴いたデビュー作は、まだ声がひ弱で全体的に基礎体力がまだ根本的にないなという印象だったんですけど、21歳になってからのこのアルバムの急成長には驚きましたね。「ソロシンガー」という肩書がもったいなさすぎるくらい、近年、稀に見るギターの切れ味の鋭いロック・アルバムですね。彼自身がかなり腕の立つギタリストのようなんですが、コンビを組んでる女性ギタリストのイザベル・トーレスとの絡みが90s中期のレディオヘッドみたいな瞬間があるんですよね。曲調もボウイのグラム期とニュー・ウェイヴ期を絶妙に折衷した、先人から技を盗むにしても、その組み合わせ方が絶妙というか。彼の基礎的なソングライティング能力が高いものだから、ミックスしても全くぶれないというか。あと、「Beautiful Faces」「Be An Astronaut」「Daniel YOu're Still A Child」「Rapture」と、アンセミックなサビの書ける強みもあるし。このアルバムで一躍全英2位まで上がってきましたけど、「次は全英1位」とかの次元じゃなくて、もっと大きな目標目指して躍進してほしいですね。

Shore/Fleet Foxes
UKロック怒涛の3ヶ月ではあったんだけど、でも、ベストとなると、やっぱ、これかな。フリート・フォクシーズの「Shore」。このバンドに関して言えば、もう、オリジナリティに関して言えば、デビューのときからとにかく圧倒的だと思っていまして。フォーク・ロックを、「ペット・サウンズ」のサイケデリアと、フィル・スペクターの「ウォール・オブ・サウンズ」のヴォーカル・エコーで表現したかのような。もう一聴して彼らとわかる、決定的な個性が早いうちから確立されていたものです。その後も、決して嫌なわけではありません。ただ、同じ時期に出てきたボニーヴェアが頭良すぎてテクノロジーと共に曲が暗号みたいに変化したほど極端ではないにせよ、フリート・フォクシーズも2017年の前作「Crack Up」で「フォーク・ロック内プログレ」みたいなすごい構造のアルバム作ってね。「すごい!」とその才能に驚きはするんだけど、だけど、「わかるけど、何回も聞きたいとは思わない」感じに正直、なっていたところがありました。。そこに行くと、このアルバムは、久しぶりにフリート・フォクシーズらしい、素の曲の良さが、胸にスーッと染み込んでいくような、そんな快感をデビュ―作以来に与えてくれましたね。やっぱり、ロビン・ペックノルド、メロディメイカーとしては絶品ですね。今回は実質、彼のソロ作に近いという言われ方をしますが、どこかこういう「素描」的な作品を僕も望んでいたところがあったのかもしれません。
あと、南米居住者としては、ブラジル現在最高のインディ・バンド、オ・テルノのチム・ベルナルデスと共演したり、チリの軍事クーデターと戦った不屈のフォークシンガー、ヴィクトル・ハラへのリスペクトが捧げられていたり、南米からの影響も垣間見せたりしているところも嬉しいところです。
