
80年代と00年代にSpotifyとグローバル・チャートが欲しかった!
どうも。
こないだ紹介した
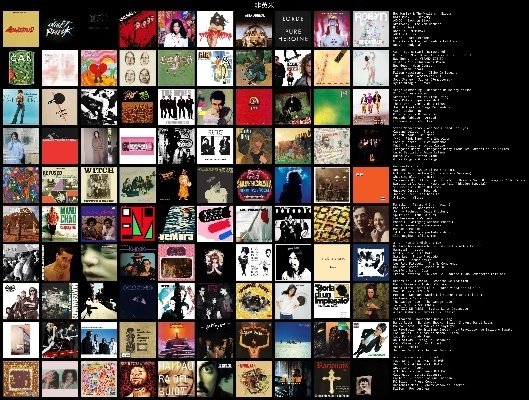
非英米の100枚アルバム・リスト、好評で嬉しいです。
以前から「非英語圏」だったり「ラテン・アメリカ・ロック・ベスト」とか、そういう企画をちょこちょこと発表していくうちにこなれてきてるんでしょうね。発表する内容が洗練されてきているような気が自分でもしています。
今日はちょっと自分のルーツ的な話をしておこうかと思います。
僕の場合は特定のジャンルってあまり興味がなくてですね。小学生のときの影響で、「自分で曲書いて、自分のバンド持ってるような人を優先的好きだ」というのはあるんですけど、そこから先は緩いというか、「いろんなものが混ざってる感じ」が好きですね。
というのは、僕の中学のときに受けた影響がありまして。それはやっぱり
80年代のMTVですよねえ。この時代、とりわけ80年代の前半から半ばにかけて何したかというと、「国境を超えた音楽を伝えていた」んですよね。
もちろんこんな風にイギリスのアイドル性の強いアーティスト流行らせたというのもあるんですけど、なにもイギリスだけじゃなくて
こういう風にオーストラリアからもヒットが届いてたし
ドイツからのヒットも知ることが出来たし
さらに北欧からのヒットもわかったんですから。
もっと言えば
こういう曲を通じて南アフリカ共和国のアパルトヘイトの問題を知ることも出来たし
アフリカ音楽を体感することも出来ました。
流行りが自然と世界向いてたからどんどん外向きになっていけたというか。知れるものなら色々知りたかったですもん。
だから、今、自分がSpotifyのグローバル・チャートを眺めるに「あのときにこれが欲しかった!」とすごく思いますもん!
もちろんあの時代に世界のあらゆるのが拾えていたわけではありません。ただ、チャートで紹介こそはされなかったもののあの時って世界中の至るところでロックの台頭が起こっていてですね
共産独裁国家が終わりつつあったソレンやポーランド、ユーゴスラビアでロックで逸材がすごく出てきてたんですよね。
その一方で
南米では逆に、右翼軍事政権の終わったアルゼンチンやブラジル、チリでロックのムーブメントですからね。特にスペイン語圏はスペインやメキシコとも繋がって動きがすごくでかくなったんですよね。
こういう時代にこそ、こうしたことをリアルタイムに知りたかったものです。今、別の10代を追体験しているところですね。
ただ、その後の90sのワールド・ミュージック・ブームが好きだったかと言えば、あれはすごく嫌いだったんです(笑)。
あの時期になると、「流行り」ではなく、マニアの人が「知らないといけない」みたいな教条的な上から目線で押さえつけたような感じがすごく嫌で。しかも80sのときの流行りより明らかにその地域固有の土着性を愛してこそ本物みたいに主張する人がいてですね。そりゃ、地域を理解するのは大切ですけど、でもその論法って「日本人なら演歌だろ、やっぱ」みたいなものと変わらないし、実際、沖縄民謡とか川内音頭を煽る人、いましたしね。僕としては逆に、地域ごとに住む若い人たちが作る今どきのポップ・ミュージックの方が断然聞きたいわけで文化人類学の研究をしたい訳じゃなかった。僕が聴きたかったのは、地域ごとにある同時代の若い人の息吹だったのに。そういうのが無視された気がして嫌でしたね、あの頃は。
あと、どんなに市場開放してマーケットとしてでかかろうが、あの当時のアジアン・ポップスは我慢ならなかったです。だってレベルが高いとはお世辞にも思えなかったから。特に香港ポップスですね。Jポップ以前の歌謡曲のカバーが多かった上に、モダン演歌みたいなアレンジのものが多くて。中国のロックがマインドの面で共感は出来つつも音楽で聴く気になるかと言われれば難しかったし。あと韓国もKポップ以前でトロットが韓国ポップスのイメージの時期ありましたしね。ソテジは衝撃でそれ以降に変わりましたけどね。でも、まだ日本との差が大きすぎて聴く理由が見いだせなかったですね。
そして、忘れちゃいけない。2000sもかなり音楽的に多様な時代だったんですよね。このときはグローバルというより、アメリカの音楽界が過去になく多様化した時代でしたけど。
だって
ヒップホップとR&Bがメインストリームで一番面白かった時代だった上に
アイドル大全盛で
ロックでヒット曲がでて
アダルトもののポップも売れてたし
女性アーティストでカントリーの売り上げのけたがメチャクチャ上がっててたし
空前のラテンブームがあったし
エレクトロも良質な曲が売れてたし
イギリスに目を向ければ2ステップがあり
イギリス国内では大きなバンドブームがあったんですから。
僕はこれらを
スカパーにあったチャンネルVって香港とかオーストラリアで強かったチャンネルで見てました。そこで音楽の多様さに衝撃を受けたんですね。前にスティーブ・アルビニの記事で「本物のインディとかにこだわろうとしていた自分が小さく感じた」と書きましたが背後にこれがあったのです。
惜しむらくは当時これらが各ジャンルごとに分断して聴かれていたことです。これは非常にもったいなかったし、もっと言えば失敗です。これを当たり前の感覚として聴いていれば音楽聴く柔軟性、間違いなく上がってたのに。10sになってインディ・ロック聴く人が急にヒップホップやアイドル嬉々として聴き始めましたけど、僕は正直な話、この時期ほど面白いとは思わないので「何を今さら」感は本音言えば今もあります(笑)。
そして20sは
Kポップがワールドワイドなヒットとなり
プエルトリコからスペインからメキシコからスペイン語による世界ヒットが生まれ
男性カントリーがバカうれし、それがSpotifyのグローバル・チャートを通じて世界の人に一般認知されてるでしょ。すごいことだと思います。
これが20年周期で起きてるのも偶然ではないですね。意味があることだと思ってます。
