
特集・1969年(第6回) 50年前より今の方がカッコいい名盤12選
どうも。
クエンティン・タランティーノの新作「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド」。この特集も、あと、2回、もしくは3回で終わりますが、今回はですね、「1969年当時よりも、後の評価の方が結果的に高くなってしまった名盤」。これを取り上げてみたいと思います。
1969年って、独特の空気があるからそこにハマると紹介しやすいものではあるんですが、この年のすごいところって、そのリアルタイムにそこまで時代に合致しなかったタイプの作品にも名盤が多いことなんですよね。そういうアルバムを12枚集めて紹介したいと思います。
では、まずはこれから行きましょう。
Kick Out The Jams/MC 5

まず最初はMC5の「kick Out The Jams」。パンク・ロックの元祖ともよばれているデトロイトのガレージ・ロックンロールのライヴ盤でのデビュー・アルバムです。これ、極左政党の党大会でのライブなんですよね。その時点で、同じカウンターでも、その当時の左寄りの人の中でトレンドだったヒッピーの人たちの求めるノリよりもより過激だったわけです。そういうこともあり、全米アルバム・チャートでの最高位は30位。前回、前々回で紹介したアーティストは軒並み英か米でのチャートのトップ10アクトばかりだったのでそれに比べると注目度は低かったと言わざるをえません。ただ、そんな彼らの破天荒でノイズまみれのロックンロールは、この8年後くらいにパンク・ムーヴメントの中で輝くことになります。
The Stooges/The Stooges

続いてこちらもMC5と同系統のバンドを。MC5がデトロイトなので彼らもデトロイトと思われがちですが、同じミシガン州でもアン・アーバーという街出身のストゥージズ。フロントマンは当時22歳だったイギー・ポップです。MC5のイメージが破天荒の暴れん坊なら、こちらは、外面も激しいんだけど、むしろ内面狂気の熾烈で、混沌としたサイケデリアが渦を巻くイメージですね。あと、この当時から、イギーの、熱いながらもどこか覚醒した佇まいにはすでにカリスマ性があります。今聞いてもタイムレスにカッコいい名盤なんですが、ただ、当時の商業的展開はあまりに弱く全米最高106位。この当時の彼らの実態を伝えるライブ映像の類もほとんどありません。あまりに早すぎた存在ゆえでしょうね。
Velvet Underground/Velvet Underground

60年代後半、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドの存在は、「裏のまた裏」のカルチャーを求める人たちのカリスマだったのかな、と言う気がします。カリフォルニアで沸き起こるヒッピーたちの大人たちへの反抗を、対岸のニューヨークから冷静に見つめ、基本お坊ちゃんたちが多かったヒッピーたちの目線の届かない、裏社会に生きる人たちの現実を歌っていたのが彼らでした。そんな彼らの、これは3枚目のアルバム。上のストゥージズのアルバムのプロデューサーでもある前衛芸術肌のジョン・ケールが脱退してルー・リード主体のアルバムになったんですが、前作までのフィードバック・ノイズは影を潜めましたが、穏やかなる”歌”のアルバムで、その後のインディ・ギターロックのある系譜を作った作品でもあります。これも全米最高197位と、同時代の中では脚光を浴びていませんでした。
Trout Mask Replica/Captain Beefheart

続いてはLAが生んだ鬼才中の鬼才、キャプテン・ビーフハート。とにかくこの魚面のジャケ写からして普通じゃないことは一目瞭然なんですけど、「これ、曲の断片では??」ともおぼしき細切れの曲の大群が、ドス黒いブルースとギザギザの切り裂きエレキギターとともに襲ってくる感じですね。彼はフランク・ザッパの幼馴染としても知られているんですけど、音楽理論の天才だったザッパが全てを計算して譜面に起こして変態音楽を作っていたのに対し、譜面の読めないキャプテンは自分から沸き起こる内面衝動を口移しでミュージシャンに伝えて、直感的野生を表現していたと言います。そんな彼の作品の中でもこれは群を抜いてルール無用の自由な作品です。そうした作品ゆえ、チャートヒットには本来縁がなさそうなんですが、イギリスではこれが21位まで上がっていたりします。ただ、半世紀経とうが、ここまで自由な初期衝動はなかなか耳にすることがないですね。
Happy Sad/Tim Buckley
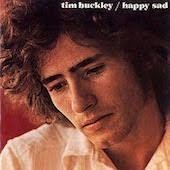
続いて紹介するのはティム・バックリー。かのジェフ・バックリーのお父さんで、ジェフが3歳の時にでたティムのサード・アルバムがコレです。彼はLAのフォークシンガーだったんですが、その後、息子ジェフが後年に渡って伝説にした、あの驚異的な声域、あれが父からの遺伝であったことは、ティムのアルバムを聞けばすぐに分かることです。感情が高ぶった時に、果てしなく伸びることになる高音。それはこのアルバムでも聞けます。さらに言えば、本作で彼はフォークにジャズのエッセンスを加えた、より即興性の高い音楽を展開してまして、そこにより生々しい声の蠢きを耳にすることができます。ただ、息子ジェフがその天賦の才能を商業的に活かせぬまま世に去ったのと同様、このアルバムはこの当時チャートインせず、さらに1975年に死去してしまいます。また、上のMC5、ストゥージズもそうですが、ティムも所属したエレクトラというレーベルは、この当時最高の才能をいくつも抱えながら、ドアーズしか成功しなかった早すぎたレーベルでもありました。
Illuminations/Buffy Sainte Mary
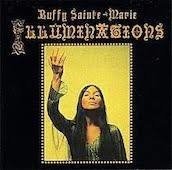
続いてはバッフィ・セント・メリー。この人は60年代初頭から活動するプロテスト系のフォークシンガーで、ジョーン・バエスあたりと同じ時期の人ですが、ジョーンが音楽の世界を超えた政治活動家だったようにこの人も活動家で、それはFBIからブラック・リストに加えられていたほどで、さらに基本カバーがメインだったジョーンに対して、バフィはほとんど自作曲でした。なぜ、ここまで知名度に差がついてしまったのかはいまひとつ定かではないのですが、とにかく過小評価されている女性フォークシンガーです。彼女には、プロテストの方面ではのちにドノヴァンがカバーした「Universal Soldier」という、「世界中の日人たちが愛国心を叫んで戦争に参加する」とどぎつい皮肉を披露してますが、このアルバムは彼女なりにロック化したアルバムです。ただ、一旦ロック化してしまった後の振れ幅が非常に大きなアルバムで、そのギターのファズのかかり方から、呪術的なグルーヴから、そして喉にチョップでも当てながら歌ったのかと思いたくなる彼女のスタッカートの効き過ぎた声の揺らぎから、サイケデリアが闇なる方向に向かった不思議なアルバムです。リアルタイムでチャート・ヒットはしていませんが、これはカルト作として長らく語られてまして、ピッチフォークが選ぶ60年代の名盤でも100位入りしてます。
Five Leaves Left/Nick Drake
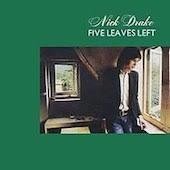
続いてはイギリスが生んだ伝説のフォークシンガー、ニック・ドレイク、行きましょう。よく「内省的」なる言葉がシンガーソングライターを称する際に使われますが、この人ほど、その言葉が似合う人はその後も50年もいません。とにかく、その、耳をそばだてないと聞き逃してまうんじゃないかと思って気持ちを集中して聴きたくなってしまう消え入るようなスモーキーな歌声と、極限まで憂に富ませたストリングス・アレンジ。これがとにかくあまりにも美しいですね。あと、自然の描写を多用した田園風景が見えるような歌詞描写の中に息づくロマンティシズムも麗しいものがあります。暗い曲も確かに多いですが、キラキラした希望のあるラヴソングもかなり光るものがあります。彼は3枚の疑いようのない傑作を生みながらも商業的には全く成功せず、1973年に世を去りますが、その後作品は伝説化し、内省フォークシンガーの代名詞として今日に至ります。この人の場合、動く映像すら残されていないから、尚更です。よく、彼を意識した作品は耳にしますが、これに近づいたものは聞いたことがないですね。
Scott 4/Scott Walker

続いてはこれもカルト名盤ですね。「Scott 4」。彼のことあ追悼記事を今年書いたばかりですが、かつてはその麗しの低いバリトン・ヴォイスと甘いマスクで女の子たちを虜にしたアイドルだったんですが、そんな彼が、このアルバム以降、急速に偉大なクリエイターとか化していきます。もともと、ストリングスとオーケストレーションを多用した、ロック時代では異色の存在(しかもそれでアイドル)だった彼ですが、このアルバムからはそこにサイケデリックなニュアンスが強くなり、歌詞も宗教や戦争などに踏み込んだシリアスで観念的な内容が目立つようになりますが、このアルバムはスコットの美声の響きと、その実験性、そしてメロディの完成度の美しさのバランスが絶妙な均衡で取れた最高傑作ですね。80年代以降は実験性を強め、晩年の作品は心して聞かないとついていくのも大変にもなったりするのですが、これほど尊い「アイドル脱皮作」もそう存在するものではないですね。
The Guilded Palace Of Sin/The Flying Burrito Brothers

続いてはフライング・ブリトー・ブラザーズ。これはこの前の年にバーズに加入し、「カントリー・ロックのパイオニア」と今日まで謳われる「ロデオの恋人」を作って脱退したグラム・パーソンズが、そのヴィジョンをより明確化すべく作ったカントリー・ロックバンドです。よく「カントリー・ロック」とか「オルタナ・カントリー」とかっていうと、「カントリー風味のロック」と誤解する人がいるのですが、違います。アメリカの伝統音楽であるカントリーを、ロック以降の音楽の味付けで再解釈したのがカントリー・ロックです。グラムはそれをバーズに続いて自分のバンドでも実践しますが、それはスティール・ギターにかけたファズだとか、ソウル・ミュージックのグルーヴ感だとか、反体制的なヒッピーの心情とか、旧来のカントリーが避けてきたものであり。そうしてルーツ・ミュージックを統括し、現在にアップデイトさせたのが彼らです。グラムもニック・ドレイク同様、1973年に夭折しますが、こうした手法はのちのウィルコだったり、去年のケイシー・マスグレイヴスのアルバムなどで脈々と続いています。これも全米最高は164位。
Dusty In Memphis/Dusty Springfield

続いてはダスティ・スプリングフィールド。彼女はミニスカートでおなじみのスウィンギング・ロンドンの時代のイギリスの女の子シンガーでしたけど、そうしたガールシンガーの中でも歌唱力はずば抜けていて、より本格的なソウル・ミュージックを志向すべく、本場メンフィスまで飛んでレコーディングしたのがこのアルバムです。ここからは当時、「Son Of A Preacher Man」が全米トップ10のヒットとなり、未だによく懐メロで耳にしますが、せいぜいそれがヒットしただけでアルバムとしては全米最高99位。長らく語られるようなものではありませんでした。なぜか。やはり、それはこの当時「ソウルといえば黒人のもの」というイメージがあっただろうし、「女性アーティストはシングル・アーティスト」とみなされ、アルバムでなかなか聞かれなかった風習的な差別をもろに食らったからでしょうね。あと、ジャンル的にどのシーンに食い込ませるのが適切かも見えにくいしね。でも、今となっては、その「枠へのはまらなさ」こそが魅力で普遍化していると思うんですけどね。今や立派な60sソウルの大名盤です。
Moondance/Van Morrison

続いてはヴァン・モリソン、行きましょう。この人は本当に息の長いあーてぃすとで、70歳を超えた現在でも新作が出ればそれなりに大きく扱われるし、ロマンス映画の中での曲の使用頻度もすごく高い(90sから00sは特に)人なんですけど、そうなるまでは長らくカルト・アーティストの扱いだったもので、音楽的評価はいつも高いのに、商業的にそこまで大きくならない人でもありました。このアルバムはそんな彼が、60sのブリティッシュ・ビートの名バンド、ゼムを解散させた後、ソロに転じて3枚目のアルバムです。この一つ前の「アストラル・ウィークス」も名盤選で頻繁に選ばれますが、アイリッシュ・フォークのテイストが強い、彼のアイリッシュとしてのイメージと結びつけやすいそのアルバムも傑作ですが、よりジャズとブルースの色合いを強めた、より白人なりのソウル・ミュージックを追求したこのアルバムもかなりの傑作で、そのあとの彼のキャリを考えると、軸足はむしろこちらにあるようにも感じられます。これは実は割とヒットはしていていますが、それでも全米29位の全英32位。ただ、寿命は非常に長い作品です。
Monster Movie/Can

最後に紹介するのはドイツの鬼才、カンのアルバムで。昨年、「非ロック圏の101枚のロック・アルバム」という企画をやった際にも書きましたが、ドイツという国は民謡ベースのシュラーゲルという伝統音楽が強い影響でロックが流行るのが遅れたんですね。ただ、いざ、独自のロックが登場してくると、これまで英米ではやっていたものとは全く捉え方が違う独自のものが生まれてきました。人々はそれを「クラウト・ロック」とも呼んだんですが、その代表格こそカンです。彼らが斬新だったところって、これまでだったら、基本、「曲」というものが先にあって、そこにリズムやグルーヴが後からついていくものだったのに、彼らの場合、ミニマルなグルーヴが先にあって、そこにメロディが乗っていくパターンですね。だから、うねりの大きな長尺のグルーヴの中で雄大に曲を展開させることができるんですよね。その意味でロックのスケール感をかなり大きくしてくれたバンドだし、のちのレディオヘッドあたりを聞いてもその断片的な影響は十分感じられるものです。これは日本人ヴォーカリスト、ダモ鈴木の入る前の作品ですが、ダモ時代の名作群とともに聴いていただきたい名作ですね。
・・と、こんな感じになりました。
次回は、全英チャートの後、「1969年の映画やテレビ文化」についてやります!というか、もうそろそろタランティーノの新作も見ます。
