
全オリジナル・アルバム FromワーストToベスト(第32回) デヴィッド・ボウイ その2 10位〜1位
どうも。

昨日に引き続いて、デヴィッド・ボウイの没後5年にちなんだFtomワーストToベスト。思えば、この企画がはじまったのは彼と同じ年になくなったプリンスからでした。
では、早速10位からいきましょう。
10.The Man Who Sold The World (1970 UK#21 US#105)

10位は「The Man Who Sold The World」。「世界を売った男」。ボウイがスキャンダラスなロックスターとしてのイメージを世界に向けて打ち出すのはこの2年後になりますが、そのアイデンティティ形成はもう、ここから出来始めてますね。ひとつはこのアルバム・カバーに象徴される両性具有の概念ですね。1970年当時でここまで出来た例、まだほとんどない頃ですからね。そして、グラムロック・サウンドの萌芽ですよね。このアルバムから、妖艶にして豪快なミック・ロンソンの放つ音塊がボウイ・サウンドを支配するようになります。この当時の彼のプレイってすごく「剛と柔」のバランスが絶妙に取れてて、まだフォーク・ロックの流れからの影響下の強かった長尺のボウイ・ナンバーにおいて、その物語の流れに沿うように、時にあでやかにソロを決め、ときに攻撃的なアタックとなるリフを繰り出す。ことミックのプレイに関して言えば、タイトル曲や「円軌道の幅」「ブラック・カントリー・ロック」はベストプレイですね。ちょうどこの頃はライバル、マーク・ボランもレスポールを手に、いい意味で猥雑で荒唐無稽、刹那的で爽快なブギーをTレックスで始めた頃。ロックの一つの時代のはじまりでしたね。
9.Let's Dance (1983 UK#1 US#4)

9位は「レッツ・ダンス」。ボウイにとって、世間一般での最大のヒット作です。タイトル曲を筆頭に世界のどこでも売れました。あの当時、MTVに端を発したデュラン・デュランやカルチャー・クラブなどの第2次ブリティッシュ・インヴェージョンとも呼ばれた時代でしたが、このアルバムでのボウイはその親玉の貫禄もありました。70sのアルバムに比べイノヴェーティヴな感じがなくポップでわかりやすいサウンドであったがゆえにボウイ・ファンのあいだでは長年「嫌わないといけないアルバム」のように言われてもきました。ただなあ。もう没後5年にもなるのにいまだにそういう風にこのアルバムを揶揄し続けるのは僕は正直ナンセンスだと思うんですよね。ポップだったとしても、楽曲のつかみの点においてはこのアルバムがダントツであることはたしか。さらにいえば、ナイル・ロジャースのプロデュースに当時のブルーズ・ロックの新生スティーヴィー・レイ・ヴォーンのギター、ナイルのシックでの盟友の名ドラマー、トニー・トンプソンによるねちっこいグルーヴ感は僕は「ヤング・アメリカンズ」以上のR&Bの体得をボウイが出来た瞬間だとさえ思います。全米1位になったタイトル曲は言うまでもなく、「モダン・ラヴ」が「汚れた血」や「フランシス・ハ」、「キャット・ピープル」が「イングローリアス・バスターズ」に使用されるなど、その後の映画での引用などを通じてポップ・カルチャーに残り続けている点でもポイントは高いです。
8.The Next Day (2013 UK#1 US#2)

8位は「ザ・ネクスト・デイ」。ボウイが2016年に亡くなったとき、みんなこの次の遺作のことばかり話していましたが、あの死があそこまで大きく注目されたのは、その前作にあたる、10年ぶりの復活作となったこのアルバムが大ヒットし、アーティストとしての勢いがついていた最中だったことを決して忘れてはいけません。それくらい、このアルバムは充実作でした。2013年の彼の誕生日の日にバラード「Where Are We Now」で何の前触れもなく突然復活したときは本当に驚きましたけど、10年経とうが、彼が「hours」のときから続けていた、「自身が古くから培ってきたソングライティング・アイデンティティへの回帰路線」は中断を経ても続けられ、「Heathen」のツアーのときからの馴染みのメンバーで、ひねりとエッジと円熟と哀愁溢れる彼なりのロックンロールをここでも届けてくれました。「基本、HeathenやRealityと同じタイプのアルバムなのに、何で今回、評論家、こんなに絶賛するんだろう」と当時思いもしましたけど、やはり今聞いても、その路線の中で曲の練りが抜群ですね。「Where Are We Now」や「Valentine's Day」「The Stars(Are Out Tonight)」はやはり末期ボウイを代表する名曲だとも思いますしね。
7.Blackstar (2016 UK#1 US#1)

そして7位に遺作の「ブラックスター」です。これは2016年の1月8日、彼の誕生日に出て、その「21世紀型ジャズ」に進化したボウイ・サウンドに驚いていた矢先に、その2日後にまさかの逝去となりました。僕の場合はあの日、起きてパソコンを立ち上げて、いきなり速報ニュースで一瞬だけ目に飛び込んできて、「ん?今、変なこと言ってなかった?」となって確認した結果、呆然。その日は、1日、しのげるかどうか、すごく不安だったものです。ただ、その死が他のどのアーティストの訃報よりも結果的にドラマティックになったのは、やはりこのアルバムの存在があったからこそだと思います。死のニュースが入る前からメディアはすでに大絶賛し、ここから彼の新しい時代がはじまると確信したかのような感じでしたからね。そんな力作を手土産に宇宙に帰っていったわけですからね。そして、これは僕自身もボウイの才能を過小評価していたことが証明された瞬間でもありました。「イノヴェーターとしての務めは終わり、自分自身の培ってきたもので勝負」。「hours」から「The Next Day」でボウイは15年にわたりそれを実践し、アーティストとして鮮やかに復活しました。でも、ボウイの中ではもう一度イヴェーターになりたかったんだろうな。それが、最後に、ボウイが少年時代に音楽の基礎を作るきっかけとなったジャズを元に行われたということは、ボウイ自身にとっても本望だったんじゃないのかな。そんなことも当時、いろいろ考えました。そのジャズを背景とし、死の匂いが漂う荘厳な瞬間とその緊迫感は何度も聞きたくはないものの圧倒的なのは言うまでもありません。ただ、それがひと段落ついた際に、80sのときのような親しみやすいメロディでお別れのあいさつのように「I Can't Give Everything Away」で締める救いのある余韻がすごく彼らしく、愛さずにはいられません。
6.Alladin Sane (1973 UK#1 US#17)
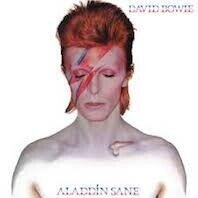
6位は「アラジン・セイン」。いわゆるグラム・ロック黄金期を代表するアルバムですよね。今となっては、このときの稲妻メイクが一人歩きして有名になっているような気もします。このアルバムはもう、ダイナミックな、ボウイ史上、もっともワイルドにロックンロールしたアルバムですね。これまでのボウイって、リフでグイグイ押すよりはまず曲の世界そのものがあって要所でノイジーなギターで華麗に演出するパターンだったんですが、アメリカ・ツアーでの影響でよりオーディエンスを掴むやり方を学んだからなのか、ここではリフでグイグイ押す、前のめりなロックンロールで勝負してますね。そのテの曲の中ではやはり「ジーン・ジニー」「Watch That Man」「Panic In Detroit」「Cracked Actor」あたりは不可欠なロックンロールですね。あとストーンズの「夜をぶっとばせ」には、この次の出るカバー作「Pin Ups」を予感させるものがあります。とはいえ、ちょっと引いたピアノやサックス、ストリングスなどをフィーチャーしたミディアム〜スロウでも秀逸な曲も多くアルバムのタイトル曲や「Drive In Saturday 」「Lady Grinning Soul」もやはりいい。エンターテインされたロック・アルバムとしてはある意味これが一番かもしれません。
5.Scary Monsters (1980 UK#1 US#12)

5位は「スケアリー・モンスターズ」。僕が思うに、今日まで世間一般が受け取る、あるいは音楽的に受け継がれているボウイのイメージって、このアルバムのことなんじゃないかな、とよく思います。それゆえにランキングも高くしたんですよね。いわゆるグラム・ロック黄金期では、すごくボウイの理解がV系のそれに近い一面的な理解に終わってすごく古く感じられます。やっぱ、もう少し後の、ちょっとひねりのあるニュー・ウェイヴ通過したロックのイメージが今日のボウイのそれかと思うんですけど、それでいうと、まさにこのアルバムなんですよね。このアルバムはいわゆる「ベルリン三部作」の後に出たアルバムなんですけど、あの3枚、さらに言ってしまえば同時期に手がけたイギー・ポップの「Idiot」や「Lust For Life」、あそこで得たエレクトロやフリーキーなギターのトーンなどの実験の成果をわかりやすくまとめたのがこのアルバムだと思います。その結果、「Ashes To Ashes」や「Fashion」のような今も人気のボウイ・クラシックも生まれたわけですけど、つかみのリフのコード感とか、すごく変なのにそれがうまくポップにまとまっているというか。そのことは特にキャリアの晩年に成功した「Heathen」〜「The Next Day」でもより色濃く出た気もするし。その意味で「もっともボウイらしい」一作だと思います。
4.Low (1977 UK#2 US#11)

残り4枚。僕の気持ちとしては、ここから先、正直な話、みんな1位でもいいくらいなんですが、あえて順位をつけると4位が「ロウ」です。これはベルリン三部作の1作目です。「ヤング・アメリカンズ」ではアメリカにわたりソウル・ミュージックのマナーを身につけていたボウイでしたが、ここからの3枚はドイツに拠点を構え、この頃、もっとも実験的だったクラフトワークやタンジェリン・ドリームに代表されるエレクトロ・ミュージックに接近することになります。この当時、ドイツのクラウト・ロックの世界でこそシンセサイザーを使ったエレクトロなサウンドは珍しくなかったものの、使い方そのものがまだかなり実験的で、ポップな方面での使用がまだ咀嚼されていない頃でしたからね。そこをボウイは3枚かけて、それをいかにロック流に咀嚼しています。A面の歌ものでも、これまでにないちょっと無機質でヒリヒリした音質で「Speed Of Life 」「Breaking Glass」「Be My Wife」そして彼の代表曲のひとつである「Sound And Vision」。このあたりはロックのテイストを残しながら後のシンセポップへのヒントにもなっているんですが、圧巻はやはりB面ですね。「Warszawa」をはじめとした、盤一面をすべてシンセサイザーのインストだけで固めるという、この当時のロックではmeasure・アーティストでは誰もやってなかった大胆な手法をとって。しかも、ここでのアンビエントなエレクトロ・サウンドがときを経ても全く古びれてないのが驚きです。機材自体は間違いなく今となっては古いものなのに。本当に先進的なものは時代をも超えると思ってるんですけど、これはまちがいないですね。A面の曲が、このつぎの「ヒーローズ」の完成度と匹敵すれば、文句なしにこれが1位でした。
3.The Rise And Fall Of Ziggy Stardust From Mars (1972 UK#5 US#21)

そして、3位に「ジギー・スターダスト」です。これが1位ではありません。というか、僕、思うんですけど、ボウイにとって今後、これが彼にとっての「サージェント・ペパーズ」になりそうな予感がしてます。ちょっと、「最高傑作」の基準として古くなりつつあるというか。やっぱり、いきおい、手法が「アリーナ・ロックの見本」(それはかっこいい見本ですけど)みたいのになりつつあって、ボウイがキャリアをかけて進めた音楽的な進化みたいなものが、このアルバムからどうしても見えにくく、その意味でちょっと古臭く聞こえてしまうからなんですよね。ただ、それでも、このアルバムが輝きを放っているのは、そのコンセプトの巧みさがゆえですよね。宇宙からやってきたロックスターが、「5年間」という期間内に地球をロックスターとして混乱させ、世を去っていくというストーリー性の中に、ボウイが音楽だけでない、文学、映画、アート、ファッションなどを含めた総合芸術の中で何をやっていきたいのかの並ならぬ決意が感じられますしね。しかも「宇宙から」というのが「Space Oddity」のトム大佐からのつながりみたいでいいじゃないですか。華麗なるロックンロールとしてもタイトル曲に、「Moonage Daydream」「Starman」、そして「Rockn Roll Suicide」と名曲そろいでもあるし。その意味で文句はありません。ただ、彼が他の作品でやってることが素晴らしすぎるだけのことです。
2.Station To Station (1976 UK#5 US#3)
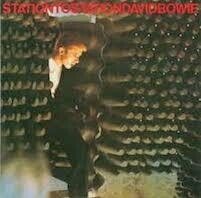
そして2位に「Station To Station」。これは近年、再評価が本当に著しいアルバムですよね。そのきっかけは、ボウイ自身がこのアルバムがフェイヴァリットだと語ったことにもあるんですけど、実際の話、このアルバムには、ボウイのあらゆる意味での良さが6曲という、限られた曲数の中でぎっしりと凝縮しているためです。これ、それまでのイメージ的には、「プラスチック・ソウルとベルリン三部作のあいだの作品」という中途半端なイメージ持たれていたかもしれないんですが、それで片付けられるアルバムではないし、プラスチック・ソウルよりははるかに濃く、三部作のテイストもしっかり表現できているところが一挙両得なんですよね。まず、冒頭の10分を超えるタイトル曲で、もうベルリン三部作を予想させるクラフトワークへの接近があって、この1曲の存在だけでかなり光る上に、「Golden Years」「TVC15」といった「ヤング・アメリカンズ」以上に光るボウイ流ソウルの名曲がある。そしてボウイ流ファンクの6分に及ぶ名曲の「Stay」。この曲にもアメリカとベルリンの両方の流儀の良いとこ取りを感じさせるスリリングな展開があるし、さらにラストはニナ・シモンの名曲「Wild Is The Wind」の非常に目ざといカバー。ニナ・シモンといえば、60sの公民権運動の時代にジャズの立場から黒人の自由・解放を歌ってきたことで知られ、それはむしろ21世紀になってからさらに強く評価されるようにもなってきているんですけど、そんな彼女の反骨精神が最高潮に乗ってたアルバムのタイトル曲を選んでこの時期にカバーしていることが光りますね。クラフトワークといいニナ・シモンといい、ボウイの音楽的な目利きの良さが非常に光るアルバムです。この路線あたりは、ダイレクトなロックンロールの評価が少し停滞してるときあたりになればなるほど評価の上がる作品ではないかと僕は思っています。
1.Hunky Dory (1971 UK#3 US#57)

そして1位はこれです。「ハンキー・ドリー」!これに関しては昔から一番好きなアルバムで、動かしようがないですね。これは「ジギー・スターダスト」の一作前のアルバムになるんですけど、これ、なにが良いかって、歌詞なんですよね。これは自身がこの後に作り出すキャラ「ジギー・スターダスト」の前の、変身前のデヴィッド・ジョーンズの素顔がここにある感じがして。その「変身宣言」とも言える「Changes」をはじめ、自身がアーティスト活動上、敬愛するアンディ・ウォホールとボブ・ディランに関して歌うことで自身のアーティストとしてのアイデンティティを改めて確認する。とりわけ、精神分裂症の兄テリーに捧げたの曲とも、ゲイ・アンセムとも言われるラストの「The Bewlay Brothers」も、真相はともかく後に自分のペンネームに使うほど思い入れの曲でもあり。あと、ソングライティングの起伏もこれ、とにかく素晴らしいです。このアルバム最大の代表曲で、先にヒットした「Space Oddity」同様、宇宙への想像を換気させるシュールレアリスティックな名曲「Life On Mars?」のストリングスはボウイ史上のみならず70sのロック全体で見てもドラマティックで美しい曲だし、2000年代に同名のバンドを生んだ小曲「Kooks」の牧歌性、「Life On Mars?」に負けない流麗さとサビの哀愁溢れるボウイの歌唱が胸を打つ「Quicksand」、そしてきたるべきグラムでの黄金時代を予感させる豪快な「Queen Bitch」まで、収録11曲の表情と個性が豊か。生身のボウイのもっともリアルな部分が詰まった傑作だと思いますね。
