
愛し君へ
君と出会った意味を考えてみることがある。
けどそれは、「意味がない」ことも選択肢に入れている、ということに気が付いた。
だから、僕は考えるのをやめた。
「ねー、聞いてる?」

君が横からそう尋ねる。少し怒ったような声で。
「ごめんごめん、ちょっと考え事をしてたんだ」
「もー!また考え事?」
まさか「君のことを考えていた」だなんて、恥ずかしくて言えたもんじゃない。
「…拗ねた顔も可愛いよ?」
「ちょっと~、それはずるいよ~」

…あ、笑った。照れ笑いというやつだ。
やっぱり君には、笑顔が一番似合う。
_____________
君がパンを好きだと知っていたから、今日のドライブの目的地はとっくに決まっている。
「ね~ね~、どこ行くの~?」

「…まだ内緒。着いたらわかるよ」
「え~、気になるなぁ~」
そんな純粋で素直な所も可愛い。
到着すればきっと大喜びするはずだ。その光景を思い浮かべていると運転に集中できなくなりそうだ。危ない危ない。
お目当てのパン屋に到着し、何も知らない彼女を連れて車を降りる。サプライズの瞬間のワクワクはいつ味わってもたまらない。
が、僕の視界に真っ先に飛び込んできたのは
【本日 臨時休業のお知らせ】
と、書かれた看板だった。
「う、嘘だろ…」
僕にとって、思いもよらないサプライズだった。
「ここ、何屋さん?」
まだ状況を理解していない彼女がそう尋ねる。
「パン屋…なんだけど。おかしいな、ちゃんと調べたはずなのに…」
「えー!パン屋!」
「ほんとにごめん。まさか臨時休業になってるとは思わなくて…」
せっかく彼女を喜ばせるつもりが、こんな形で頓挫するとは思わず、僕はわかりやすく意気消沈していた。
「なんで謝るの?」
でも彼女は、落ち込んだ様子を少しも見せない。
「今日はたまたまお休みだったけど、また別の日に来ればいーじゃん!」

そう言って笑った。まるで僕を励ましてくれているかのように。
「で、でも…」
「いーの!これでまたドライブする予定できたね!へへへ」
「そう…だね。次は気をつ…」
「じゃあ~、今日はどこ行こっか?私はね~」
ポジティブで、自由で、優しくて。そんな彼女も、やっぱり好きだ。
_____________
そんな彼女にも、テンションが低い日だってある。
「ねえ~、退屈だよ~~ぅ」
今日の天気は生憎と雨。家の中でのんびり過ごす時間も僕は嫌いじゃない。
が、彼女にとっては物足りない時間のようだ。
「今日はさすがに出かけられないよ。まあ、たまには家でゆっくりするのもいいでしょ」
「やることないもん~…暇!暇なの~」
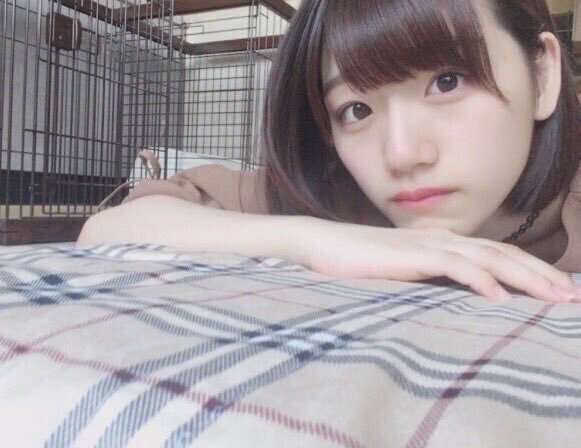
そう言いながら、床に突っ伏して足をバタバタさせている。
まったく。わがままにも困ったものだ。
「とりあえず、お昼にしよっか。僕が作るからさ。何食べたい?」
「麻婆豆腐~~~~~~!とびっきり辛いやつ~~~~~~~!」
激辛料理が大のお気に入りな彼女と一緒にいるせいで、僕は何度も辛いものに悶絶してきた。おかげで耐性が付いた、とも言えるが。
「まだ~?」
「もう少し待って~」
「まぁだぁ~?」

キッチンからちらっと覗くと、まるで子供のようなぷく顔をしている彼女が見える。もう少し見ていたい気もするのだが。
「できたよ~」
「わーい!いっただっきまーす!」

よほどお腹を空かせていたのか、出すやいなや彼女は料理に飛びついた。どんな欲にも素直だ。
「どう?辛い?」
「け、結構…辛い~…でも美味し~~~~!」
「よかった。喜んでくれたなら作った甲斐があったよ」
いっぱい食べる君が、好きだ。
雨の日もたちまち明るくなる。
______________
「うるさいな!悪いのはそっちだろ!」
「違うもん!私じゃないもん!ばーか!もう知らないっ」

ぽろぽろと涙をこぼしながら、彼女はそのまま奥の部屋に引きこもった。
きっかけはしょうもないことだが、僕の苛立ちは収まりそうにない。
玄関のドアをわざと勢いよく開けて、外へと飛び出した。もうすっかり陽も落ちて、肌寒い。
外の風を感じている間に、火照っていた僕の心も落ち着きを取り戻す。
「…謝らなきゃな」
戻ろうと振り向くと、ガチャ、と音がしてドアが開いた。
「…やっぱりここにいたんだね」

彼女の方もすっかり泣き止んではいたが、まだ目が若干うるうるしているようだ。
「……ごめん。僕が悪かった。」
「…ううん。私こそ、ごめんね?」
そう言ってお互いに顔を見合わせると、さっきの喧嘩も馬鹿馬鹿しく思えて笑ってしまった。
「…中に入ろっか。うう~…寒いねぇ~…」
体を震わせながら彼女が言う。もうすっかり秋も終わりそうだ。
と、その時。
肩になにか触れたような気がして、僕はもう一度外の方を振り返った。
「……!雪だ……!」
「えっ!雪!?」
彼女が勢いよく外へ飛び出してきた。危うく押し倒されるところだったが。
「わあ~…!ほんとだ!」
子供のように純粋な目をした彼女は、雪にくぎ付けだった。僕はといえば、その嬉しそうな横顔だけで十分だった。
また一つ、僕たちの過ごす季節が重なっていく。
______________
「ねえねえ」
「ん?」
ある日の帰り道。
「私たちが巡り合ったのって、すっごい偶然だと思わない?」
彼女が突然そんなことを言いだしたから、僕は言葉に詰まってしまった。
まるで、僕がついこの間考えていたことを見透かされたみたいだ。
「急にどうしたんだよ」
「今ね!ふと思ったの!」

彼女の方からそんな話を聞くと、なんとなく不安になってしまう。
今にも僕の目の前から消えてしまうのではないか。それくらい、いつでも明るい彼女の存在を、必要以上に儚いものだと思い込んでいる自分がいる。
「…そうか。出会えたことに感謝だよ。ありがとう」
「うふふ。私こそ、ありがとうだよ」
「……あ、それだけ?」
「え?なんで?」
……まあ、彼女がその言葉以上の意味を含ませているとは、到底思えなかったのだが。
「い、いや…特に意味はないけど。急だなと思って」
「んん~~~?怪しいぞ~~~?」

そう言いながら急接近してくる彼女に、ドキッとしてしまう。もう何度も見ている顔のはずなのに。
「な、な、なんにもないって!」
「ほんとに~~?嘘はだめだよ~~?」
タジタジになりながらも、僕はちょっとだけ安心していた。彼女はやっぱりいつも通りの彼女だ。
「まああえて言うなら……僕たちの出会いは『偶然』じゃなくて、『必然』だったんじゃないかな、って思うな」
「ひ…ひつぜん?」
……漢字が苦手な所は直りそうにない。
「たまたまじゃなくて、出会うべくして出会った、ってことだよ」
「お~~、なんかかっこいいねえ」
「これからもよろしく、ね。この先に何があるのか、全然わからないけどさ」
そんな感傷的なことを言ってはみたけど、あまり心配する必要はなさそうだ。
だって、
「大丈夫だよ!」

「未来はいつだって、味方だもん!」
僕の隣には、いつも彼女がいるから。
