
「ワタクシは」
手元の手帳のスケジュール欄を見ると、次の予定は30分後だった。
さっきコンビニで買ったおにぎりをお茶で流し込み、駅へ歩く速度を少しだけ上げた。

夏に着るスーツほど煩わしいものはない。額の汗をハンカチでぬぐいながら、冷房のよく効いた車両に乗り込む。
大学4年目の夏。こんなにせわしなく行動するのは新鮮だが、苦労もひとしおだ。
_______________
電車を降り、エスカレーターに乗ると、後ろからトントン、と肩を叩かれた。
振り向くと、
「あ、やっぱそうだ」

見覚えのある顔と目が合い、慌てて耳につけていたイヤフォンを外す。
「渡邉…?なにしてんの?こんなところで」
「ん、面接だよ。…そっちも、スーツってことは面接でしょ?」
そういえば、渡邉もワイシャツにスカート、手には黒い鞄を持っている。
「そ、そうだよ」
「ってかさ、もしかして…」
と言って彼女から告げられた企業名は、数分後に面接を受けるまさにその企業だった。僕は急に自信をなくしてしまった。
同じ学科とはいえ、かたや同期の中ではトップの成績で、社交的で容姿も整っている彼女と、ごくごく平凡でなんの取柄もない僕とでは、比べるまでもない差がある。
_______________
「……多分、ここもだめだな」
外はどんよりと曇り空だったが、それにも負けず劣らず僕の心も曇っていた。
周りの友人たちが内々定をもらっていく中、僕はと言えばからっきしだった。焦りはしないが、気分は良くない。
と、朝と同じように不意に肩を叩かれた。
「おつかれさま~」

「…びっくりした。面接終わったの?」
「そ!ついさっきね。そっちも終わったところでしょ?」
「…まあね。二重の意味で」
「そんなこと言って~、笑えないよ?」
上手くいったのだろうか、渡邉は意気揚々としているように見えた。
空も僕も暗いせいか、彼女だけやけに光っているように感じてしまう。
「この後は?まだなにか用事ある?」
「…いや、今日はもう何もないよ」
「そーなんだ!じゃあさ、ちょっとカフェにでも行かない?」
「え、ええ?まあいいけど…」
急な話に戸惑いつつも、断る理由もない。最も、今までこうして誘われたことがあるわけではないが。
蒸し暑さがますます強くなってきた。
_______________

今まで2人きりで話すことはあまりなかったが、他愛のない会話で意外と盛り上がった。
4年生になってからというもの、周りは皆就職活動に熱心で会う機会も少ない。こうして久しぶりに会うとほっとする。
「こんな暑いのに堅苦しい格好させられてさ、たまったもんじゃないよね~」
「ほんとな。ここ最近ずっと同じ格好だし、服とか買ってないや」
「バイトは?今何もしてないの?」
「今は週2だね。どうしても交通費とかでお金かかるし」
文字通り「汗水垂らして」稼いではいるが、一向に来年の進路は決まりそうにない。このままだと、今のバイト先にずっとお世話になることになりそうだ。
「…渡邉ってまだ就活続けてるのか?」
「え!そりゃそーじゃん!今日だってそのために面接したし」

正直その返事は、僕にとって意外なものだった。
「そっか。とっくに1つや2つくらい、内々定貰ってると思ってたよ」
その言葉の意味が果たして本音なのか、それとも僻みなのか、僕自身にすらわからない。
だが渡邉は、それには答えず黙って微笑んだ。
_______________
いつの間にか外は雨模様だった。
鞄に入れておいた折りたたみ傘のことを思い出したのと同時に、渡邉が不意に話し始めた。
「うちさ」
「やめようかな、って思ってるんだよね。就活」

「…?」
「就活をやめる」のは簡単だ。内々定を貰って満足すれば、それ以上続ける必要はない。当たり前のことだ。「なんだ、やっぱりもう決まってたのか」と少しがっかりした。
が、その心の声が聞こえたかのように、
「どこか決まったわけじゃないよ。ただ…もういいかなって。ほんとにそれだけ」
「えっと…それってどういうことだよ?」
その続きを促すかのように、気づけば僕はそう聞き返していた。僕は一体何を期待しているのだろう。
「まあ…言っちゃえばお休み、みたいな。疲れちゃったから」
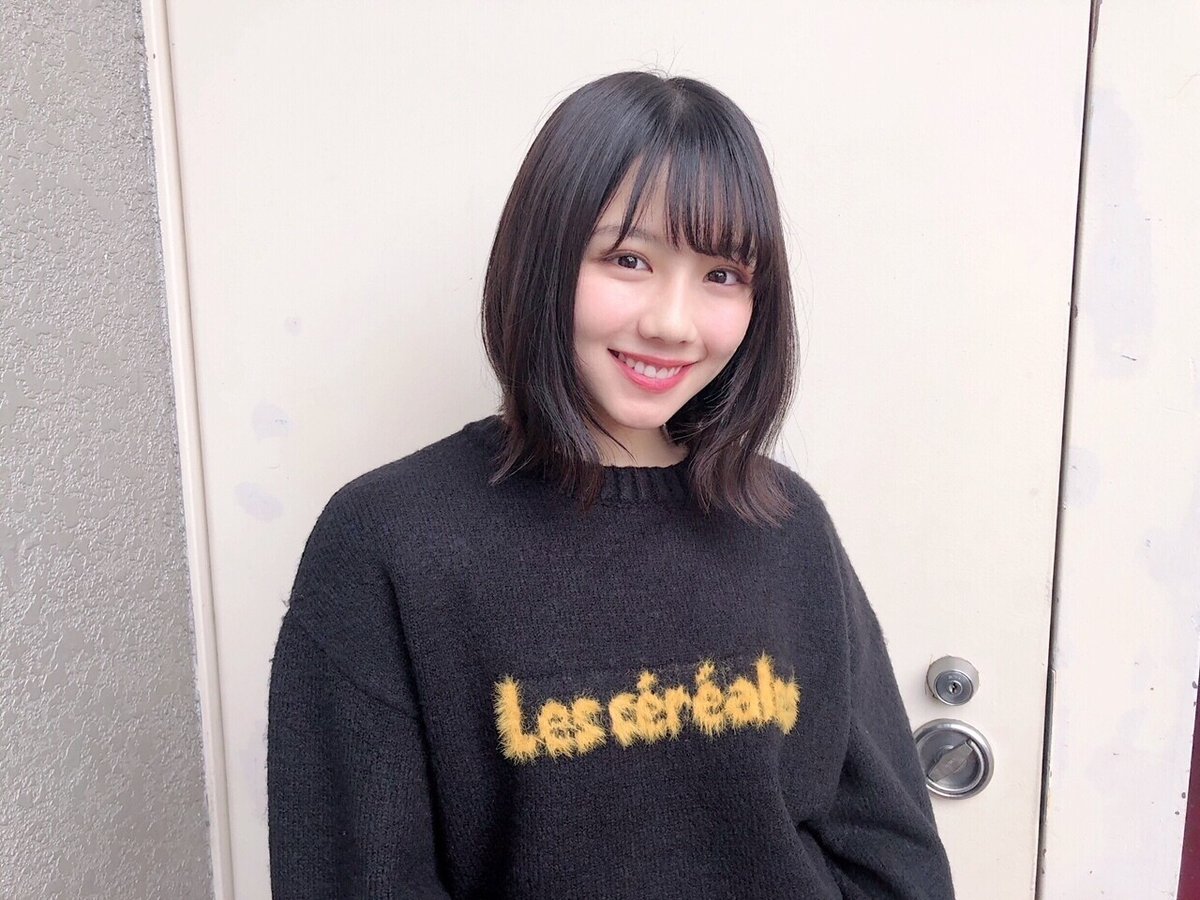
「…なんだよ、それ」
渡邉は笑顔だったが、僕は全く腑に落ちなかった。
「そうやって逃げるのかよ」
「まとも」な将来のために、数少ない学生時代の経験を捻り出し、相手の懐になんとか潜り込もうと必死になってる自分が馬鹿みたいだった。
「逃げるのって、良くないことなの?」

その真剣な眼差しから、冗談を言っているわけではないことは伝わった。
いや…逃げるのがだめなわけじゃない。
「そうじゃない…けど…」
彼女のような人間が「逃げ」を選ぶのなら、僕には一体何が残されているのだろう。
暗闇の中でもがき続ける僕に、どんな救いがあるというのか。
「やりたいことやらないと、人生損じゃん。無理して何かを続けるの、私にはできないな~」
「僕が無理してる、って言いたいのか?それ」
少し頭に来て、思わず荒い語調になってしまう。
「無理してるの?逆に」
「な…!」
「あ、雨止んだね。そろそろ出よっか」
僕が何か言う前に、彼女は何事もなかったかのように席を立った。
確かに彼女の言う通り、雨は止んでいた。どんよりとした雲だけは、まだ残っていた。
_______________
去年買ったはずのチノパンは、久しぶりに履くと、心なしか腰回りに少し余裕が生まれた気がする。
ジャケットを羽織り、駅までの道を歩く。
予定よりも1本早い電車に乗ることができ、気持ちにも少し余裕が生まれる。平日の午前ということもあり、車内の人もまばらだ。
ホームに降りると、後ろからトントン、と肩を叩かれた。
前にもこんなことがあったような気がして、今度はすぐに振り向いた。
「あ、やっぱりそうだ」

「やっぱ、渡邉だったか」
以前と違うのは、お互いに私服だということだろう。
「大学行くんでしょ?」
「そう。教授にちょっと用事が、ね」
お互いに何も言わず、僕らは並んで歩き出した。
鬱陶しいほど生い茂っていた緑たちも、すっかり枯れ落ちて裸の枝だけが目立つ。
しばらく黙って歩いていたが、渡邉が口を開いた。
「就活、どうなった?」
「…会社は決まったよ。内定式も出たし」
「えー!よかったじゃん!」

他人のことでこんなに嬉しそうな顔ができる彼女が羨ましい。
ふと、最後に渡邉と会った日のことを思い出した。
忘れもしない、蒸し暑いあの曇り空の日だ。
「…お前は?どうなったの?」
「ん?私?」
渡邉はそう返事をすると、なにか確信を持っているかのような表情で
「まぁ、ちょっとね。まだ秘密」
とだけ答えた。
_______________
「あー…またこんな時間か…」
自宅のドアに手をかける時、思わず声が漏れた。中に入り、部屋の電気とテレビをつける。
あと1時間ほどで日付が変わる。テレビには、よくある恋愛物の深夜ドラマが映し出されていた。
疲れた体をソファに預け、惰性で画面を眺めていると、
『あ、やっぱそうだ』
聞き覚えのある声が聞こえた気がしてはっとする。しかし、一体どこからだろう。
『うん、じゃあ、またね~』
この部屋から声が聞こえたとすると、選択肢は1つしかない。
何気なしに付けていたテレビを、今度は集中して見てみた。

ほんの一瞬だったが、そこに映っていたのは紛れもなく渡邉だった。
「あいつ…嘘だろ」
気づけば僕は、手元のスマホで彼女の連絡先を探していた。
深夜だったが、意外にも渡邉はすぐに電話に出た。
「久しぶり~。こんな時間にどしたの?」
「テレビ、見たよ。びっくりした」
多くは伝えなかったが、渡邉も理解したようで、
「あ…バレちゃった?ほんとちょっとだけどね、出番」
その声がなんだか嬉しそうだった。
まさかこんな形で、渡邉が一体何を決意していたか知ることになるとは、夢にも思っていなかった。
「やりたいこと、ってこれだったんだな」
あの日、渡邉を責めてしまったことが恥ずかしくなった。それなのに、彼女はこう続けた。
「そう。でも、まだこれからだよ。これから私、もっとがんばるから。
…そっちもさ、がんばってね」
色々な感情が混じり、僕はすぐに返事ができなかった。
「…あ、ああ」
ふと目頭が熱くなるのを感じ、また言葉に詰まる。
「じゃあ…またね。私、明日はまたオーディションなんだ」
「そか…急にごめん。おやすみ」
電話を切った後、あの日の渡邉の声と、その表情がふっとよぎった。
『やりたいことやらないと、人生損じゃん』
この暮らしに慣れてから考えもしなかった。いや、就活に飲み込まれたあの頃から、既に忘れていたのかもしれない。
ボールペンを手に取り、筆を走らせる。
迷いも、不安もなかった。
_______________
「…それで、今お前らにこうやって話してるってわけ」
「なんか、結構壮大な話っすね!」
「いや…そうか?」
金曜日の夜ということもあり、店内は賑やかだ。1週間の疲労や不満を、アルコールで帳消しにする。これも大事な時間だと思う。
後輩たちの前で自分の経歴を話すのも、もう何も抵抗はない。
「先輩、すごいな〜。それで今は、やりたいこと叶えてるってことですもんね!」
「まあな、だからお前も、やりたいことがあるならそれに向かって進んだ方がいいぞ。道は絶対開けるから」
そう言いながら、頭上のテレビの画面をちらっ、と見た。
『私、絶対諦めないよ!がんばるから!』

僕にできることは、才能ある彼女にも負けないくらい努力し続けることだ。
それこそが、誰もが与えられた一番の才能だから。
