
ドルフロ『回帰定理』感想──正統派国際謀略小説にして異端派美少女ゲーム
ドールズフロントライン大型イベント『回帰定理』の感想です。
記事前半はネタバレなしです。
ついに『回帰定理』がやってきた。渋いおじさん二人がでかく描かれたラシュモア山みたいなキービジュアルは大陸鯖での実装時にも話題になっていたが、そんな『回帰定理』が日本にも上陸した。初期の頃のノリとはだいぶ離れて「暗い・重い・ややこしい」の三拍子揃ったストーリーを展開しているドルフロだが、今回のシナリオは素直に面白かった。話としてはあまり進んでいないけど、ちゃんと盛り上がる場面があったし、思いがけない話が掘り下げられたり、それでいて悲惨すぎた前回とは対照的に救いのある描き方がされていたりなど、個人的にも嬉しいポイントが多かった。

最近のドルフロの展開はほんとうに面白いのでもっと読まれてほしいんだけど、どうもファン層がマニアックなところに固定されてしまっていて、ライトなファンのひとが少ない気がする。内容が重いからライト層のひとがけっこう抜けてしまったのかもしれない。ストーリーに関しても、ドルフロのシナリオはかなりクセがあって、そこを意識して読まないとけっこうストレスを受ける。
ただ、最近はゲームの難易度もそこそこだし、ストーリーもコツを掴めば読めるようになるので、ライト層のひとにも優しい環境になってきているのではないかと思う。ドルフロのシナリオを読むときに気をつけなくてはいけないのは、
・細かいプロットの整合性を気にしないこと
(登場人物の動きとかを真面目に考えだすと狂う)
・謎めいた会話に深入りしないこと
(現段階の読者の情報では理解できない会話が多いのでそこはスルーする)
・言葉尻を捉えて伏線探しをしないこと
(本物の伏線と、単にシナリオ・翻訳が"怪レい"せいで伏線っぽくなっているところの判別が困難だから)
……といったあたりである。要するに、細かいことは気にせずに、その場のテンションに任せて読むのがいちばん良い。あと人形の名前は覚えられなくてもなんとかなる。まあ世界観設定とかはそれなりにしっかり構築されているので、そのへんはいちおうちゃんと読むわけだけど、それはまた別の話だ。
以下、ネタバレあり感想。

前回『鏡像論』でRPK-16が言い放った「私から言わせれば、人形にはどうしても補えない欠陥があります。私たちは本物の痛み、苦しみ、悲しみを理解できず、そして快楽という概念もありません。ましてや生と死など尚更理解できないでしょう。勝利はいつも人間の物ですが、死はいつも人形が担っています。けれども、結局最後に死ぬ権利があるのは、人間だけなのです」という言葉が、『回帰定理』も重要になってくる。
グリフィン基地襲撃により、多くの人形たちが決死の戦いを強いられる場面だ。人形はメンタルサーバーさえあれば何度でも修復できるが、バックアップのない状態で破壊されるとその記憶が引き継がれず”死ぬ”ということは、以前から描かれていた。さらに今回はメンタルサーバーそのものが危機に瀕し、破壊されそうになっている。人形たちは二重の意味で「死」と対峙させられている。
決戦に挑む前、人形たちは己の思い出の品々と最後の分かれをする。身を挺して戦火に飛び込んでいったトカレフとウェルロッドMkⅡは戦いの中でディラン・トマスの詩を叫ぶ。かれらの行動は死を目前にした生き物の意地そのものだ。人形にも「死」がありうるというのはドルフロがずっと投げかけているテーマのひとつだが、『回帰定理』ではRPK-16の言葉に反論するかのように、人形が感情むき出しで「死」に立ち向かう姿が描かれている。

一方で、RPK-16の言葉は皮肉にも真実を言い当ててもいる。『回帰定理』のラストで、襲撃を受けたヘリアンとクルーガーは焼け跡で再起を誓い、ライトの葬式で物語は幕を閉じる。この戦いで死んでいったのはライトだけではなかった。しかしひとまずの勝利を祝い、死者を悼む場面が与えられたのは、けっきょく人間たちであったのだ。「最後に死ぬ権利があるのは、人間だけなのです」という彼女の言葉が、図らずもまた反復されるかたちになっている。
とはいえ、ヘリアンたちはメンタルサーバーを守り抜き、生き残った人形たちとともに歩みを進める。指揮官も反逆小隊のコアを引き継いで次の戦いに向かう。RPK-16の語るニヒルな世界とは必ずしも同じではない。そこに希望がある。
クルーガー「もうグリフィンはないかもしれない。だが、一番大事なものは守れた。」
ヘリアン「はい。」
ヘリアンは頷くと、立ち上がろうとするクルーガーを支えた。そして静かに目を閉じ、心の中で祈り始める。
ヘリアン「十年も経てば、お別れの時が来ます。ですが、私は常にあなたと共にいます。たとえこの肉体が朽ち果てても、私の魂はいつまでも、あなたの傍に。」
二人に続いて、人形たちも徐々に周囲に集まり、同じように夕日に向かって、かつて自分たちの家だった場所に、最後の敬礼をした。
以下、各キャラについて。
今まで何を考えているのかほとんどわからなかったサーについては、だんだんわかってきた気がする。オーベルシュタインとの静かな舌戦でサーの本領が垣間見えた。グリフィン&クルーガーは”知”を司っている政治家・暗躍気質のサーと、”武”を司っているバリバリ武闘派のクルーガーで成り立っているんだなあというのがよくわかる展開だった。
サーとオーベルシュタインがキービジュアルに使われていたのは、ドルフロがこれからも政治を正面からやっていくぞ!という意思表示なんだろうな。実際、政治家同士のやり合いって国際謀略ものとしては避けて通れない要素だろうし。奇しくもドイツとロシアが主戦場でゼリンスキーまで出てくるという完全に「時代」のコンテンツになってしまったドルフロだが、そういう真面目に軍事と政治の話をしようという姿勢は応援したい。
J君は『回帰定理』における主人公のひとりと言っても良いくらい活躍していた。目の前でモナを破壊されたり嘔吐したりさんざんな目に遭っていたけど、ネーレちゃんが有能だったのとモナもちゃんと生還できたのとでかなり救われた。このへんも『鏡像論』があまりに悲惨だったことの揺り戻しというか、対比を強く感じるところ。それにしてもJ君とモナとか、ネーレとミアみたいな人間&人形のバディもっと見たいね。

オーベルシュタインが未知数すぎて敵としての株がひたすら上がっているのに対して、パラデウス側はよくわからんというか、マジモンの政治家の悪意に比べると全体的に弱そうなんだよな。モリドーは悲しき過去が明かされるにつれて存在級位の凋落は避けられないし(というかウロボロスと似たようなもんじゃんと思ってしまう)、グリク、ブラメドあたりもなんか鉄血ボスみたいなキャラ付けなのであんまり脅威には感じられない。そういう意味で「お父様」を出さないまま引っ張ってるのは正しくて、そのおかげでパラデウスの株はぎりぎり保たれている感じ。
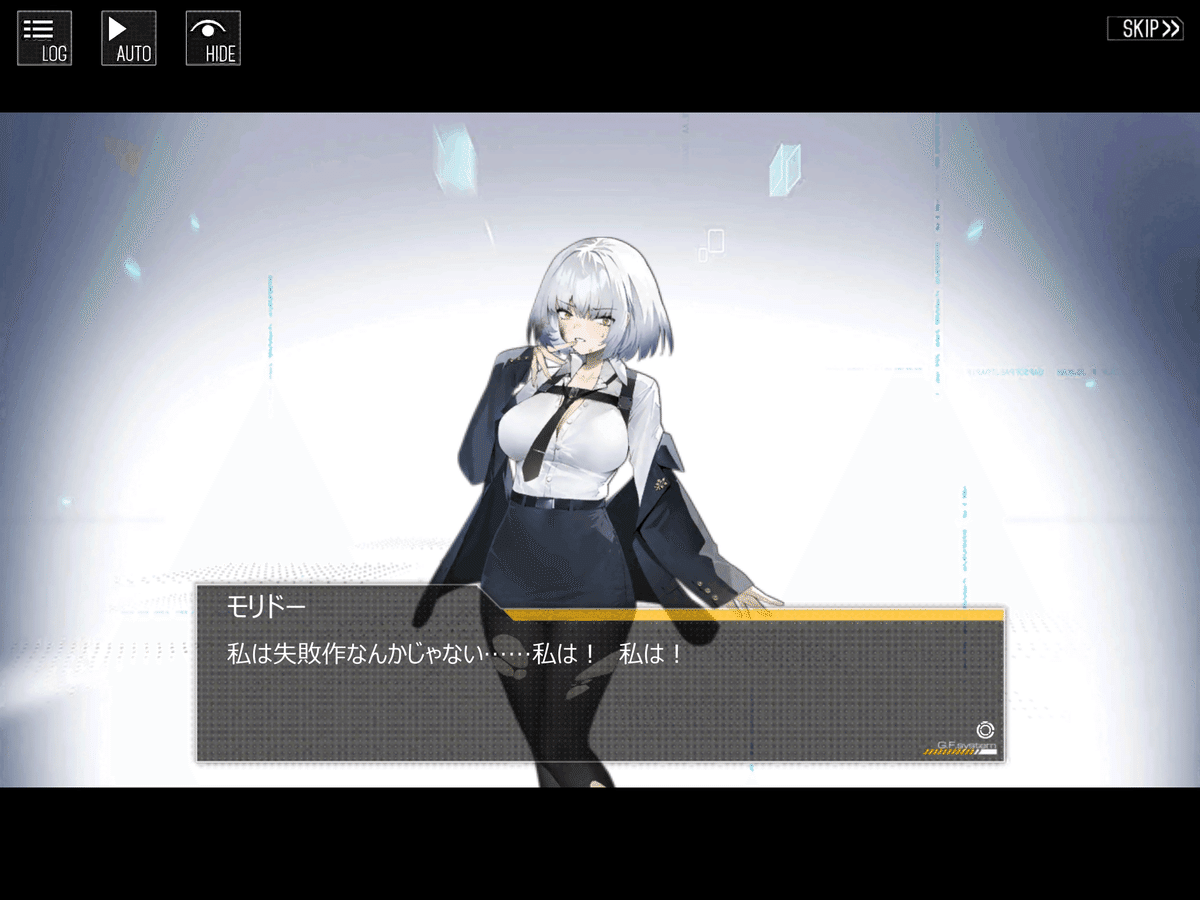
AR&404小隊については、全体的に安定感があって落ち着いて見ていられた。M4もM16もろくすっぽ説明しないまま勝手に出てきて勝手に帰っていくのはなんなんという感じだが……。ダンデライオンが相変わらずM4の真似をしてAR15にキレられるのはだんだん様式美になってきたな。M16が来る場面やSOPⅡの単独戦闘の場面はアガった。あと、ここぞというときに鉄血が助けてくれるのもベタだけど戦闘時の演出も含めてやっぱり嬉しいんだよな……。

それにしても『鏡像論』であれだけ布石が用意されていたパズル小隊が、
まったく出てこなかったのはなんなんだ。
ドルフロの好きなところのひとつは、引用や軽口を交えたコテコテに中二病っぽい会話をやってくれるところだ。『回帰定理』でのオーベルシュタインとサーの会話はいかにもって感じだし、プラトンやディラン・トマスを名前は出さずに引用するのとかもそうだ(まあ引用については既存の和訳を拝借しているから出典明記したほうがいいと思うが……)。そういう要素は本編のストーリーに直接寄与しているわけではないけど、物語のケレン味として必要だと思う。
最後にタイトルについて触れておこう。「回帰定理」とはフランスの数学者が導き出したものだが、本当にこの章のタイトルに相応しかったのだろうか。繰り返される戦争と再生の物語のタイトルには、むしろドイツの高名な哲学者の言葉──「永劫回帰」のほうがこの物語に相応しくはないだろうか。
